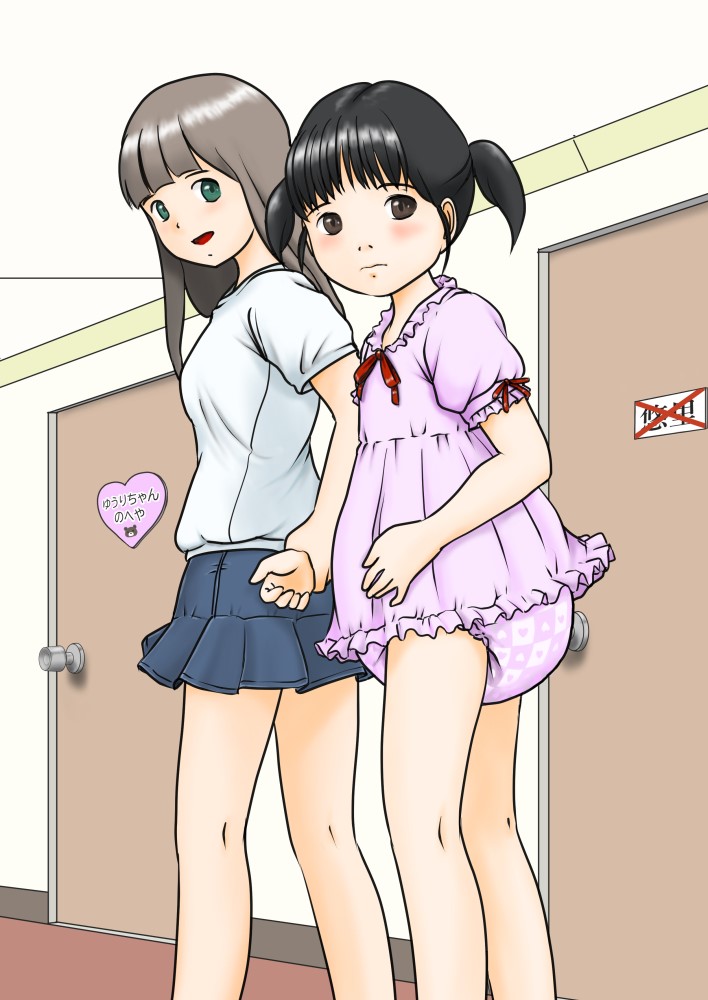|
ちょっと前に話したようなことがあって、久美お姉ちゃん、すっかり赤ちゃん返りしちゃって。ああ、ううん、しちゃってと言うか、私がさせちゃったわけだけど。
で、私としちゃ念願かなったのはいいけど、久美お姉ちゃんが赤ちゃん返りしてすぐの間は、(特に早苗ちゃんの頭の中で)家族の間柄というものが少しこんがらがっちゃったりしたんだ、うん。赤ちゃん返りの過程で、久美お姉ちゃん、早苗ちゃんのことを(仮の)お姉ちゃんだって認識しちゃうことがあって、それに合せて早苗ちゃんの方も久美お姉ちゃんのことを妹だって認識しちゃって。でも、自分よりもずっと体の大きな久美お姉ちゃんが自分の妹だなんて変だよね?という疑問も同時に幼心に抱いて、真剣に悩みだしちゃって。それに加えて、もうすぐママが赤ちゃんを産むってことを早苗ちゃんは知っている、知っているというか、その日が来るのを今か今かと心待ちにしている。それで、じゃ自分は久美ちゃんのお姉ちゃんなのか新しい赤ちゃんのお姉ちゃんなのか本当はどっちのお姉ちゃんなの?とかいう疑問まで抱え込んで、わけわかんなくなりかけていた。
だから私が助け船を出してあげなきゃいけなくなったんだけど、その助け船というのは、簡単に言えば、久美お姉ちゃんは私(そう、私。つまり、すっごい美人の朱美おばちゃん)の赤ちゃんになったんだよと説明してあげることだった。ま、私を親鳥に見立てての再刷り込み/リインプリンティングで久美お姉ちゃんを赤ちゃん返りさせちゃったわけだから、あながち間違った説明じゃないしね。で、その説明を聞いた早苗ちゃん、ちょっぴり不思議そうな顔をしながら、でも、にこっと笑って頷いてくれた。反則級に可愛い笑顔で。まだ高校生の私でも、早苗ちゃんにとっちゃ、おばちゃん(とっても美人の)なのは間違いない。ママには子供がいるんだから、ママの姉妹である朱美おばちゃんに子供がいても不思議じゃない。そんなふうに考えながら、自分がお手々をつないであげている間におむつをあててもらってすっかり自分よりも幼くなっちゃった(久美おばちゃん改め)久美ちゃんの顔を見て、久美ちゃんのこと、朱美おばちゃんの妹でもない、自分の妹でもない、朱美おばちゃんの子供で、自分よりも年下の手のかかる従妹だって思うようになったってわけだ。
ただ、早苗ちゃんが納得しても、普通だったら、お母さんと佳美お姉ちゃんが納得しないよね? まさか、高校三年生にもなる自分の娘/妹が赤ちゃん返りしちゃいましたって説明されて、はいそうですかと納得する母親&姉がいる筈ない。けど、うちのお母さんと上のお姉ちゃんは納得しちゃったんだな、これが。でも、そっか、考えてみれば、納得しても不思議じゃないかも。だって、前にも話したように、久美お姉ちゃんが生まれた時からずっと、佳美お姉ちゃんは久美お姉ちゃんを可愛がりまくりで。自分に子供ができた今も、その時の気持ちが残っていてもおかしくない。つか、感受性豊かな十一歳の頃に抱いた気持ちが消えちゃうわけがない。しかも、自分の愛娘である早苗ちゃん、丸っこくて愛嬌のある顔で、佳美お姉ちゃんや私なんかよりも、どっちかというと久美お姉ちゃんに似てるんだよ。だったら、久美お姉ちゃんが早苗ちゃんと自分を重ね合わせて佳美お姉ちゃんの愛情をシェアしてもらおうとしていたのと同じように、自分の愛情を早苗ちゃんを通して佳美お姉ちゃんが久美お姉ちゃんにも向けていたとしても、ちっとも変じゃない。それに、お母さんだって。佳美お姉ちゃんがかまいまくっていたせいで、お母さん、生まれてすぐの久美お姉ちゃんのお世話を殆どできなかった。そりゃ、楽は楽かもしれないけど、せっかく生まれた我が子への愛情を向ける先を見失っちゃって、不完全燃焼だったに違いない、お母さんの母性本能。で、久美お姉ちゃんの赤ちゃん返りが、そんなお母さんの母性本能に火をつけたとしたら? 早苗ちゃんという初孫を連れて我が家に帰ってきている佳美お姉ちゃんのお腹には、お母さんにとって二人目の孫がいる。目の前にいる孫と、まだ見ぬ孫。孫かわいさに気持ちがたぎっているお母さんの目の前で、十八年前には自分の手で可愛がることができなかった娘が(体は小さくなったわけじゃないけど、でも、本当の年齢から考えれば随分と小柄だし、童顔だし)赤ちゃん返りしちゃったら? 孫かわいさプラスまだまだ衰えない母性本能のダブルパワー。
結局、お母さんと佳美お姉ちゃんが揃って(赤ちゃん返りした)久美お姉ちゃんにメロメロになるのに、ちっとも時間はかからなかったというわけだ。
妹が生まれる前に可愛い『年下の従妹』ができて、可愛い妹がもっとずっと可愛くなって、昔は自分の手でお世話できなかった次女のお世話をやり直すことができるようになって、ようやく念願かなって久美お姉ちゃんを自分のものにできるようになって。早苗ちゃんにとっても、佳美お姉ちゃんにとっても、お母さんにとっても、私にとっても、みんなにとってWin−Winな結果になったと思っていいよね、久美お姉ちゃんを赤ちゃん返りさせちゃったこと。いや、ま、久美お姉ちゃん本人にとっちゃ大問題かもしれないけど、でも、いろいろ大変な生徒会長という職務からも受験勉強からも解放されて、しっかり者の妹におむつを取り替えてもらって心休めることができるんだから、やっぱり本人にとってもWinな環境だと思うんだよね、私としちゃ。
というような、ちょっと回りくどい経過説明なんてものを語ってから、いよいよ今回のエピソードに入るね。今回は久美お姉ちゃんのことがメインじゃなくて、ちょっと別の話題をね。
私が久美お姉ちゃんを私のものにするためにいろいろやっている時、実は、同じようなことをしている人が別にいたんだ。
それも、すごく身近に。
身近も身近、私の同級生で部活も同じ服飾文化研究部、でもって家は隣という、身近もいいところな女の子・須藤琴音こそが、私と同じような計画を立てて実行に移しているその人だった。
今回は、琴音が誰に何をしたのか、そのあたりのことを話そうと思う。
で、ついでだから言っておくんだけど、私も琴音も、ひとりで計画を練ってひりとで計画を実行したんじゃない。実は、私と琴音は共謀していた。そのへんの事情も話すからね、みんなに楽しんでほしいな。
*
それは、一学期の期末試験の最終日のこと。 ラスボスみたく最後にででんと待ち構えていた恐怖の数学の試験が終わってすぐ、琴音が私の席へやって来たところから話は始まる。
いつもにこにこしている琴音なのに、その時はなにか思い詰めたような、なんだか不機嫌そうな顔をしていたっけ。
「どしたん? 数学、そんなに難しかった?」
お気軽な顔で話しかけた私に向かって琴音ってば、地獄の番犬の唸り声もかくやというような低い声で
「朱美がお姉さんをしっかり見張っていないから、うちの悠里にぃがとんでもないことをしでかしそうになってるんだよ」
と言いがかりをつけてきて。
「え? なにそれ? ぜんぜん見えないんだけど?」
きょとんとした顔で訊き返す私。
あ、説明しとかなきゃいけないっけ。
悠里にぃというのは、琴音のお兄ちゃん。須藤悠里さん、十八歳。私たちと同じ高校の三年生で、しかも久美お姉ちゃんとクラスが一緒な上に、生徒会の筆頭副会長を務めていたりする。ちなみに、琴音の兄弟姉妹は悠里さんの他に、美音ちゃんという中学一年生の妹がいる。ただし、悠里さんも琴音も美音ちゃんも、お母さんは一緒なんだけど、お父さんは三人ともばらばらという、ちょっとばかりややこしい家庭事情があったりする。
琴音たちのお母さん、裕福な得意先の依頼を受けて宝石や珍しい雑貨を海外で買い付けてくる輸入商を個人で営んでいるというような行動力ばりばりの人で、並の男の人だったらすぐに圧倒されちゃって、ずっと一緒になんていられない。お母さん本人もそのことはよくわかっているから、普通の家庭を築こうだなんてことちっとも思っていなくて、その時その場で好意を抱いた男の人と束の間の逢瀬を楽しんじゃ、すぐに男の人を捨てちゃうというようなことを繰り返しているらしい。しかも、楽しむこと優先で、避妊のことなんてあまり意識にないとか。その結果として、みんなして父親が違う(なんだったら、自分の父親がどんな人なのかもわからない)三人の兄弟姉妹という境遇ができあがっちゃって。
それに加えて、美音ちゃんが生まれた後もお母さんの生活ぶりはまるで変わらなくて、自宅どころか国内にいることさえ殆どないという。ただ、ま、仕事も順調でお金はたっぷり稼いでいて、残された三人の子供が生活に困ることはないわけだけど、でも、自分のお父さんの顔も知らない上にお母さんがいない寂しさは三人ともひしひしと感じていて、それだもので、(父親はばらばらなんだけど)兄弟姉妹の結び付きというのが私なんかにはちょっと想像できないほど強くなっちゃって。ある意味、シスコンを拗らせまくっている私たち三姉妹とまるで同じ、いや、それ以上にシスコンとブラコンが拗れて絡み合いまくっている須藤家の兄弟姉妹だ。
しかも、しかも。それぞれのお父さんの遺伝子の影響なんだろうね、三人とも見た目がかなり異なっていて。あ、ううん、三人ともというのは違うかな。琴音と美音ちゃんは女の子ながら、凜とした細身で背が高くて、琴音が宝塚の男役、美音ちゃんが娘役みたいな感じで、どっちにしても『ハンサムさん』なのとは反対に、悠里さんの方は高校三年生の男の子としてはかなり小柄で(ひょっとしたら一六〇センチないかも?)全体に線が細くて丸っこい童顔で、妹たちの『ハンサムさん』とは程遠い『あどけなくて可愛らしい』感じがすっごく強くて、女の子二人と男の子とで、よくもまぁこれほどまでにと形容したくなるほど容姿とか雰囲気とかが正反対な兄弟姉妹に育ってしまっていた。ま、そのあたりも、私と佳美お姉ちゃんvs久美お姉ちゃんみたいな見た目の私たち三姉妹と似た感じかな。で、そんな見た目も関係しているのか、須藤家の兄弟姉妹の中で琴音が一番のしっかり者で、お母さんからの仕送りのお金をきちんと管理して、料理も洗濯も掃除もしっかりこなして、どこか頼りない長男・悠里さんの日常もすっかり管理しちゃって、健気にお母さんの代理ポジションにおさまって。
そんな琴音が私に言いがかりをつけてきた。
それも、琴音に言わせれば、「私が久美お姉ちゃんのことをしっかり見張っていない」せいで「悠里さんがとんでもないことをしでかしそうになっている」とかで。
「ま、これでも飲んで落ち着いて」
私は、休憩時間に学食の自販機で買っておいたフルーツオーレを琴音の目の前に差し出した。
じゅる。
紙パックにストローを突き刺してフルーツオーレを一口飲んで、少し表情を和らげて、琴音はこんなふうに付け加えた。
「悠里にぃってば、朱美のお姉さんに告る気になっちゃってるのよ。いつ告る気なのかまではわかんないけど、夏休み中に何度か予定が入っている生徒会役員の会合の日を狙っているんじゃないかと踏んでいるのよ、私としちゃ」
へ?
あの悠里さんが、あの久美お姉ちゃんに?
こ、告るだと?
私は思わず何度もまばたきを繰り返して、
あんぐりと口を開けてしまった。
そこへ琴音が
「ま、これでも飲んで落ち着いて」
とか言いながら紙パックを目の前に差し出すものだから、つい、ストローの先を咥えてしまう。
じゅる。
口の中いっぱいに広がるフルーツオーレの味と香り。
ああ、この甘酸っぱさこそ百合の味。
そっと目配せを交わしながら互いにほんのりピンクに頬を染め合う私と琴音。
――いや、そんなことしている場合じゃない。
琴音から聞かされた予想外の状況。
けど……けど、あれ?
なんていうか、うん、いや、ひょっとしたら、予想外なんかじゃないかも?
家は隣どうしで幼馴染みだし、同じ高校の同じクラスで同じ生徒会役員だし、なんとなく見た目も似た二人だし。
え? ひょっとしてひょっとしたら、お似合いの二人かも?
悠里さんと久美お姉ちゃんが手を繋いで歩いているところを想像してみる。
――いいじゃん。いけるじゃん。お似合いのカップルじゃん。
頭の中の二人、とってもお似合いだった。
ただし……ただし、だ。
どう想像を巡らせても高校生のカップルじゃない。二人揃って小柄で華奢で童顔で幼児体型で。高校の制服を着た二人が手を繋いでデートしている光景なんて、どんなに頑張っても想像できない。私の頭の中に浮かんだのは、ランドセルを背負ってお手々つないで仲良く通学路を歩く二人の姿だった。じゃなきゃ、スモック姿でリュックサックを背負って保育園の遠足の公園をきゃっきゃっ笑いながら歩く二人の姿。
なんて可愛らしくも神々しい幼児の二人連れ。
「ストローを咥えたまま、なんて顔してんのよ、朱美ってば!」
にへらと笑いながら妄想に没頭する私の頬をぴしゃりとやって紙パックを引き戻す琴音。
そうだった。
妄想にひたっている場合じゃない。
問題は、二人がお似合いかどうかなんかじゃない。
私の久美お姉ちゃんがかっ攫われそうになっているんだぞ。それも、琴音が愛してやまない悠里さんの手で。
駄目だ、なんとしても阻止しなきゃ!
私の顔がすっと引き締まる。
目の前には、同じように厳しく引き締まった表情を浮かべる琴音の顔。
おお、同士よ。
「ごめん、私がわるかった。私がさっさと久美お姉ちゃんを自分のものにしとけば悠里さんもお姉ちゃんに告ることなんてできないのに。私が久美お姉ちゃんをしっかり見張ってなかったのがいけないって責められても仕方ないよね」
君子豹変す。自分の過ちを悟った私はさっさと琴音に謝った。くっそ〜。こんなことになるなら、ちゃっちゃと久美お姉ちゃんを手籠めにしときゃよかった。んと、後悔先に立たずだ。昔の人は偉い。
「いや、ま、さっきのは私の八つ当たりも込みだから気にしないで。それよりも、シスコン朱美&ブラコン琴音のコンビとしちゃ、悠里にぃが告るの、絶対に邪魔しなきゃだよね。なにかいい方法はないかな」
唇を尖らせて琴音が言う。
「実は……実はね。私、前々からちょっとした計画を練っているんだけど……聞いてくれる?」
なに馬鹿なことをって笑われるかもしれない。なに訳のわかんないことをってどん引きされるかもしれない。なに変なことをって呆れられるかもしれない。けど、私は、かねてからねちねちと練っていた計画のことを琴音に話すことにした。私を親鳥に見立てた再刷込み/リインプリンティングによって久美お姉ちゃんの心を私が取り込んじゃう計画のことを。久美お姉ちゃんを赤ちゃん返りさせて私の言いなりにさせちゃう、あの計画のことを。
話し終えた時、琴音は笑わなかったし、どん引きもしなかったし、呆れもしなかった。 少しだけ何かを考えた後、どこか外国の血が混じっているのだろうか不思議な色の瞳に妖しい光を宿して、黙って頷くだけだった。
黙って頷いて、口元を奇妙に歪めて、上目遣いに私の顔を見るだけだった。
それで、私には充分だった。
私の突拍子もない計画に琴音は乗り気満々なんだ。私が計画を実行に移すのに合わせて、私の計画にヒントを得た琴音なりの計画を実行する気なんだ。たわわな胸元を見透かして、琴音の胸の内が私には手に取るように読んで取れた。
こうして、私たちの計画は始まることになったというわけだ。
久美お姉ちゃんを赤ちゃん返りさせて私の言いなりにさせちゃう計画と。
自分がいなきゃ何もできない無力な存在に悠里さんを堕としちゃう琴音の計画と。
*
さて、ここから舞台が琴音ん家に移るんだけど、どんなことになっているか、早速、様子を見てみようか。
そうと決まった後の琴音の行動は本当に素早かった。元から几帳面で決断も早い子だけど、目的がはっきりしたら尚いっそうで、お母さんの仕事仲間(特に、外国のちょっぴり怪しげなイヤーさんとか)の伝手を活かして、ちょっとばかり特殊な用途の薬をさっさと手に入れちゃった。そのへんの経緯、琴音は詳しく教えてくれたんだけど、その間、私は耳を塞いでいた。そうだ、聞いてないったら、断固聞いてないんだからね。そんな、後々面倒なことになるかもしれなやばそうな一件、私は一言も聞いていない。このお話を読んでくれているみなさんも知らなかったことにしておいた方が身のためだから、気をつけてほしい。だから、その特殊な薬の成分とか、琴音がその薬をどうやって手に入れたかということについて気にするのはやめておくべきだ。いいね? いい子のみんなとお姉さんの約束だよ?
でもって、夏休みに入ってすぐ、琴音は悠里さんにのませちゃったというわけだ、その薬を。
のませる方法? そんなの、簡単なことだ。だって、家事はみんな琴音がやっちゃうんだよ。料理だって、もちろん。ということは、悠里さんの食べる物とか飲む物とかに薬を混ぜちゃうのだって朝飯前のこと。いや、朝飯じゃなくて、琴音が薬を混ぜたのは夕食なんだけどね。
で、どんな効き目の薬なのかというと。
「悠里にぃ、悠里にぃってば。さっさと起きて朝ご飯食べちゃってよ。こっちは食器を洗った後、お洗濯もしなきゃいけないんだよ。夏休みだからっていつまでも寝てないで早く起きてよ」
夏休みに入って二日目の朝。ドアをどんどん叩きながら大声を出す琴音。
けど、ドアの向こうからの返事はない。
「悠里にぃ、ほら、早く起きてこなきゃ駄目じゃん。琴音ねぇが困ってるんだから、さっさと起きなさいよ」
少しだけ間を置いて二階の廊下に響き渡る美音ちゃんの声。琴音と同じようにドアを叩くんだけど、やっぱり返事はない。
しばらく待った後、琴音は美音ちゃんに向かってこくんと頷いてみせてから、ぐっとノブを掴んでドアを引き開けた。
部屋の奥、窓側の壁際にあるベッドの上には、こんもりした膨らみ。うん、悠里さんが夏用の薄手の毛布をひっかぶって寝ているんだな。ただし、眠っているんじゃないってことがすぐにわかる。だって、ドアを開ける時、床に落ちていた毛布の端を悠里さんが急いでつかんでベッドの上に引っ張り上げるのが見えたから。
「目が覚めているんだったら、さっさと起きてきてよ。ドアを開ける前に言ったこと、聞こえていたんでしょ!」
人の形に膨らんだ毛手に向かってわざときつい声で言う琴音。
「……ね、熱があるみたいなんだ。だから……だから、もう少し横になってるよ。……ご飯は昼に食べるから、そのままにしておいてよ」
少しだけ間があって、毛布の中からくぐもった声が聞こえる。元気のない悠里さんの声。でも、熱にうなされているような感じじゃなくて、なんていうか、なにか怯えているみたいな、なにか隠しているみたいな、そんな声。
「熱ですって? 大変じゃない! 期末試験の結果がもうひとつだったから夏休みの間に取り戻さなきゃって言っていたのに。体温計を取ってくるから、ほら、早く毛布から出て」
慌てた様子の琴音の声。でも、どこかわざとらしい。
「いや、いいよ。しばらく寝ていれば熱なんて下がるから、そっとしといてくれればそれでいいってば」
弱々しい声だけど、慌てた様子の悠里さん。
その時、毛布をひっかぶっているから悠里さんからは見えないけど、琴音と美音ちゃんは顔を見合わせて意味ありげに目配せし合っていた。
目配せして、せーので二人して両手を伸ばして毛布をひっぺがしちゃう。
「な、なに……」
なにすんだよと抗議の声をあげる暇もなかった。
ベッドにうずくまっている悠里さんの股間に二人揃って視線を向ける琴音と美音ちゃん。それだけじゃない。美音ちゃんてば、くんくんと鼻を鳴らしてみせたりなんかもしちゃう。
「汗にしちゃ濡れ方がひどいわよね、パジャマのあそこのところ?」
「なんだか、おしっこみたいな匂いがするんだけど?」
琴音と美音ちゃんが同時に首をかしげて悠里さんの顔を見おろした。
「……」
何も言えなくてベッドにうずくまったまま、ただ力なく首を振るだけの悠里さん。まるで、小っちゃい子がいやいやをしているみたいで、見ようによっちゃとても可愛い。
「頑張ってるからね、悠里にい、毎日毎日さ。生徒会のお仕事もそうだし、学年で十位以内の成績をキープしているのもそうだし、誰かが困っていたらとにかく後先考えずに助けようとするし。お父さんがいなくて、お母さんも滅多にお家にいなくて、だからあそこの子は駄目なんだって陰口たたかれないように、私たちが周囲から悪く言われないようにって、頑張ってくれているよね」
琴音、すっと膝を折って、ベッドの悠里さんと顔の高さを合せて、これ以上ないくらい優しい声で言う。
「頑張りすぎて疲れちゃったんでしょう? 来る日も来る日も頑張って、ずっとずっと気持ちを張り詰めて。もうこれ以上は頑張れないって時にようやく夏休みになってやっとのこと気持ちが休まって――私たちのために頑張り過ぎた反動だもん、仕方ないよ。気持ちも体も緩んじゃって、だけど、そんなの仕方ないよ」
琴音、自分がのませた薬が本当の原因だなんてことおくびにも出さず、しれっと誤魔化して、悠里さんの頬にそっと掌を押し当てる。
「……ぼ、僕は……」
「いいよ、何も言わなくて。あとのことは私と美音できちんとやっとくから、悠里にぃは何も気にしなくていいよ。ちょっと冷たくてちょっびり恥ずかしいかもしれないけど、我慢して、何もかも私たちにまかせてね」
「……でも……」
「悠里にぃは悠里にぃのできることをして私たちを守ってくれようとしている。だから、私と美音も私と美音にできことをして家族を守る。ま、そんな大袈裟に考えるようなことじゃないんだけどね。私や美音ができることっていったら、せいぜい家事くらいなものだし。でも、だからこそ、家事にかけちゃ一生懸命になるのよ、私も美音も。今は、その手始めとして、濡れたパジャマや下着やベッドパッドや毛布を洗濯して、マットレスを日当たりのいい所へ運んで乾かして、そんなことをしながら悠里にぃに朝ご飯を食べてもらう。それだけのことなんだけどね、私と美音にできるのは」
「……だけど、だって……」
「だけど、もしも、それじゃ気が済まないって悠里にぃが思うんだったら、一つだけ約束して。それで、みーんな、ちゃらにしちゃおうよ」
「約束……?」
「そんな心配そうな顔しないでよ、簡単なことなんだから。あのね、今みたいなことがあったら、つまり、おねしょしちゃったら、絶対に隠さないで私か美音に正直に話してほしいの。毛布にしたって、ベッドパッドにしたって、おしっこに濡れたまま放っておいたら大変なことになっちゃうのよ。そのくらい、悠里にぃもわかるでしょ。特にマットレスなんて、そうそう洗濯できるものじゃないんだから、バイ菌の巣になっちゃうかもしれないしさ。それに、早めに言ってもらえればさっさと綺麗にできるけど、後でわかったら余計な手間がかかっちゃうじゃない? 三年生の悠里にぃと違って私は夏休みの間も部活があるし、美音だって友達と勉強したり遊びに行ったりしなきゃいけないのに、余計な手間のせいで予定が狂っちゃうのは困るからさ。約束できるよね?」
「……わかった。そうするよ」
琴音と目を合わせないように顔を壁の方に向けながら弱々しく呟くように約束する悠里さん。
「いいわね、約束だからね。おねしょとかおもらしとかしちゃった時は絶対に隠さないで私か美音に教えるのよ。小っちゃい子じゃないんだから、できるよね?」
心ここにあらずといった様子の悠里さんは気づかなかったけど、琴音ったら、『おねしょ』とか『おもらし』とかいうところをわざと強調して、小っちゃい子じゃないんだからとか言いながらも、それこそ、まだ年端もゆかぬ小っちゃい子を相手にしているみたいな口調で言い聞かせる。まるで、これからも悠里さんがそんな粗相をしちゃうのがわかりきっているみたいな様子で(ま、実際『わかりきって』いるんだよね。だって、薬をこれからも毎日毎日のませるつもりなんだから)。
そんなことがあってしばらく後。
バスルームに隣接したランドリールームで、琴音と美音ちゃんがこんな会話を交わしていたわけで。
「すごいでしょ、あの薬の効き目」
「うん。高校三年生にもなって本当に悠里にぃがおねしょしちゃうだなんて、今でも信じらんないよ。おしっこの匂いがした時、叫びそうになっちゃったもん。……でも、お母さんの取引先さんと勝手に連絡取ったりして、琴音ねぇ、叱られちゃわない?」
「大丈夫よ。いずれ私がお母さんの仕事を継ぐことになっていて、高校に入った日から少しずつお母さんに紹介してもらって取引先さんとコンタクトを取っているんだから。今回のこともお母さんの了解を取ってあるから心配しないで。――ついでだから教えといてあげるけど、お母さん、かなり怪しい物も海外から取り寄せたりしているのよ。世の中には『好事家』って呼ばれる人たちがいてね、お金にあかせて世界中の珍しい物を集めたりしているんだけど、その中には、かなりやらしいことに使ったり、ちょっと人には言えないような物も混ざっているのよ。お金が有り余っている人たちって何を考えて何を楽しみにしているかわかったものじゃないわねって、お母さん、苦笑しながら、でも、ちょっぴり楽しそうに話してくれるのよ。それに、そんなちょっとヤバめの物の方がお金になるから、やめられないしって」
「へーえ、そうなんだ。なんとなくお母さんらしいよね、どんなことも後ろめたく思わないなんて。ま、私たちを養うためってこともあるんだろうから感謝しなきゃだけど」
「そうね、感謝しなきゃね。で、感謝ついでに、いずれは美音もお母さんの仕事を半分継いであげなさいね。私一人じゃ、とてもじゃないけどお母さんのお得意さんをみんな満足させるなんて無理だから。たぶん、美音が中学校の三年生になったらお母さんから話があると思うから、そのつもりでいなさいよ」
「うん、わかった。私も嫌いじゃないからね、そういうの。……ひょっとして、悠里にぃもお母さんのお仕事、手伝っているの?」
「ううん。お母さんの仕事の詳しいこと、悠里にぃは知らないわよ。あの子は真面目すぎて融通がきかないから、私の仕事を継ぐのは無理ね。だから、その分、あんたたち二人に期待しているのよってお母さん何度か言っていたから。たしかに融通がきかないし、性格的に押しが弱いから、あのお母さんの後継ぎは無理だって私も思うわ」
「言われてみれば、確かにそうか。悠里にぃだったら、その『好事家』って人たちに、怪しい品物の代わりにお持ち帰りされてオモチャにされちゃいそうだもんね」
「そういうこと。だから、私たち姉妹で悠里にぃを守ってあげなきゃいけないのよ。好事家さんたちに好き勝手されないように。――なのに悠里にぃったら、いっちょまえに女の子に告ろうだなんて考えちゃうだから。一応は長男だけど、本当は私たちが構ってあげなきゃ何一つ自分じゃできないお子ちゃまのくせに。お子ちゃまのくせして、私たちの手の中から飛び出そうとするなんて、そんなの、絶対に許さない。そうよね、美音?」
「いちいち確認しなくても、そんなの当り前じゃん。だから、そんな生意気なこと考えている悠里にぃにはお仕置きをしてあげなきゃね。お仕置きをしてあげて、自分が本当はどんなに無力なのか、たっぷり教えてあげなきゃ」
琴音が手配した薬によって強要されたおねしょのおしっこをたっぷり吸い込んだ悠里のパジャマやパンツを洗う洗濯機の音に混じって交わされる琴音と美音ちゃんの会話。
だけど、ランドリールームで妹たちがそんな会話を交わしているなんて、悠里さんには思いもつかない。
*
悠里さんのおねしょが始まって七日目の昼前。
それまで毎日おねしょの後片付けを甲斐甲斐しく続けてきた琴音が、ちょっと困った顔をして悠里さんに話しかけていた。
「あのね、こんなことを訊くのは気が引けるんだけど、やっぱり訊いておかなきゃいけなくて……なんていうかな、あのさ……まだ治りそうにない?」
琴音はあからさまには言わなかったけれど、何を訊かれているのか、悠里さんにも痛いほどわかって。でも、ちゃんとした原因がわからないんじゃ、どうしようもなくて。
「……ごめん。……まだ無理だと思う、多分……」
「そう。だったら、やっぱり、いろいろ考えなきゃいけないみたいね。――パジャマとか下着とかは洗濯すればそれでいいんだけど、ベッドのマットレスはそうはいかなくてね。眠る時、バスタオルを二枚重ねてお尻の下に敷いてもらっているんだけど、それでもマットレスまで濡れちゃって、その上、わりと分厚いやつだから少しお日様に当てたくらいじゃマットレスの中まで乾ききらなくて。このままだと中の素材とかスプリングとかに悪い影響が出ちゃうから、なんとかしなきゃなって」
「……」
「あの、だからね、いろいろ考えてみたんだ、マットレスを濡らさずにすむ方法。それで一つ思いついたことがあってね、その方法だと、マットレスだけじゃなくてパジャマや下着やベッドパッドも濡れずにすむから、洗濯を手伝ってくれている美音も少し楽になるかなって。ただ、悠里にぃ本人にも協力してもらわなきゃだし……どうかな、私の思いついた方法、試してみてもいい?」
「……いいも悪いも、僕のせいで二人に負担をかけているんだもの、何かいい方法があるなら、僕に相談なんてしなくていいから、試してみてよ。長男なのに妹二人に苦労かけてるなんて、どんな言い訳もできないんだから。だから、琴音にまかせるよ」
「いいの? うん、わかった、ありがとう。私はちっとも苦労だなんて思ってないけど、まだ中学校一年生の美音のことやマットレスのことなんかを考えると、やっぱりこのままじゃいけないって思って――ありがとう、わかってくれて。じゃ、準備しておくね。どんな方法かは、今夜、悠里にぃがお風呂から上がる時に説明する。だから、協力してね。その時になって気が変わらないよう、美音のためにもお願いね」
「……大丈夫だよ、そんな念押しなんてしなくても。迷惑をかけているのは僕なんだから」
目を伏せて力なく首を振る悠里さん。
そんな悠里さんの様子を窺う琴音の瞳には、教室の時と同じ妖しい光が宿っていた。
悠里さんと琴音のそんなやり取りがあった、その日の夜。
夕飯の後片付けを済ませてリビングルームでテレビを視ていた琴音と視音ちゃんの耳にインターフォンのコール音が聞こえた。
壁に掛かっているインターフォンのボタンを琴音が押すと、スピーカーからは
『寛いでいる最中にわるいんだけど、僕のパジャマと下着を持って来てもらえないかな。脱衣籠が見当たらないんだよ』
という、お風呂上がりで脱衣場にいる悠里さんの申し訳なさそうな声。
普段は自分で用意したパジャマと替えの下着を脱衣場まで持って行ってお風呂に入るんだけど、おねしょが始まってからは、悠里さんが入浴している間に、洗濯して真夏のお日様の光で乾かしたほこほこのパジャマと下着を琴音が脱衣籠に入れて脱衣場へ持って行くのが日課になっていた。でも、その日は、どうやらその脱衣籠が見当たらなくて、脱衣場からインターフォンで助けを求めてきたらしい。
「あ、ごめん。今夜から、いつものパジャマや下着じゃなくなったのよ。昼前に話した通り、ベッドのマットレスを濡らさずに済ませるためのパジャマと下着を用意してあるの。今からすぐに持って行くから、少しだけまっていて」
美音ちゃんに向かってにっと笑ってみせてから、助けを求める悠里さんに対してインターフォン越しに返事をする琴音、
待つほどもなく磨り硝子の戸が開いて、腰にタオルを巻いただけの悠里さんが待つ脱衣場に駆け付けた琴音と美音ちゃんだったけど、琴音、悠里さんの姿を見るなり
「駄目じゃない、悠里ったら。体にも髪にもまだ水滴が付いたままで。そんなじゃ体が冷えちゃうでしょ」
と言って、新しいバスタオルを悠里さんの体に押し当てる。
「いいよ、夏なんだから適当で」
腰にタオルだけという裸体を年頃の妹二人に見られて顔を赤らめながら後ずさる悠里さん。
この時、悠里さんは、琴音が自分のことを『悠里にぃ』ではなく『悠里』と呼び捨てにしたことに気がついていなかった。
「駄目よ、夏でも水滴が付いたままじゃ体が冷えちゃうよ。体が冷えたら余計におねしょしやすくなっちゃうんだから、ちゃんとしなきゃ。ほら、むずがらないでこっちに来なさいってば」
後ずさる悠里さんの肩を両手で掴んで自分の方に引き寄せる琴音。百六十センチあるかないかの悠里さんvs私とタメを張る身長の琴音。最初から結果は見えている。
「すぐに済むから、そのままおとなしくしているのよ。ほんと、手間のかかる子なんだから、悠里は」
髪の毛は根本から毛先へ向かってそっとバスタオルを滑らせるようにして、体はあまり強くバスタオルで擦らないようにして優しく悠里さんのお風呂上がりの面倒をみる琴音。
「はい、これ。今夜から悠里はこれを着ておねむだよ」
琴音が水滴を綺麗に拭き取った後、そう言って美音ちゃんが、両手に抱えて持ってきた脱衣籠を床に置いて、そこからつかみ上げたパジャマを悠里さんの目の前で広げてみせる。
でもそれは、薄いピンクの生地でできた、幼い女の子にお似合いのミニ丈のワンピースタイプのナイティだった。
「……?」
目の前に突きつけられた薄いピンクのミニ丈のナイティを見てきょとんとする悠里さん。
そんな悠里さんの耳許に
「おねしょとかおもらしとかしちゃった時は絶対に隠さないで私か美音に教えるのよ。小っちゃい子じゃないんだから、できるよね? ――最初のおねしょの日、そんな約束をしたこと、忘れてないよね?」
と、ぞくりとするような声で囁きかける。
「え……? ああ、うん、覚えているけど……」
きょとんとした顔のままそう答える悠里さん。
「いいわ。じゃ訊くけど、昨日の昼過ぎ、二時半ごろだったかな、大きな紙袋を持って慌てて家を出て行ったよね。なんとなく気になってこっそりつけてみたんだけど、コインランドリーに入って行ったよね? 違う?」
「あ……!」
琴音に言われて唇を震わせる悠里さん。
「ぴんときてね、急いで家に帰って悠里の部屋の椅子を調べてみたのよ。一応は拭き取ったんでしょうけど、まだ濡れていたわよ。それに、匂いもしたし」
「……」
「午後の勉強に取りかかったのはいいけど、お昼ご飯の後だったからうつらうつらして、机に突っ伏して、うたた眠りしちゃったんでしょ? それで、その間にしくじっちゃったのよね? 違う? ――昨日だけじゃないよね。今日も、そう。昼前と夕飯の時と、着ている物が違っていたものね」
「……」
夜眠っている間のおねしょだけでも惨めなのに、昼間もだなんて、惨めで恥ずかしくていたたまれなくて、とてもじゃないけど言えなかった。
だけど。
「約束、守れなかったね。小っちゃい子じゃないから守れる筈の約束、守れなかったね。だったら、小っちゃい子と同じだね」
「……」
顔を伏せて上目遣いに琴音の様子をちらちら窺うしかできない悠里さん。
「だから、悠里のこと、小っちゃい子として扱うことにしたの。だから、『悠里にぃ』じゃなくて『悠里』って呼び捨てにすることにしたの。だから、美音よりも下、美音の妹として扱うことにしたの」
「……」
「だから、美音が小学校の三年生だったか四年生だったかの頃のパジャマを着せてあげることにしたの。妹なんだから、お姉ちゃんのお下がりのパジャマを着せてもらってもちっとも変じゃないよね? ううん、大好きなお姉ちゃんのお下がりのパジャマを着せてもらえて嬉しいよね? おねしょの治らない小っちゃな妹だもん、憧れのしっかり者のお姉ちゃんからお下がりのパジャマを貰えて、すっごく嬉しいよね?」
「……」
「ついでだから、男の子の悠里のことを弟じゃなくて妹として扱うことにした理由も教えといてあげる。それはね、マットレスやパジャマを濡らさずにすませるための下着を身に着けるには、男の子のままじゃ都合がわるいからなのよ。――美音、パジャマは後でいいから、下着を用意してあげて。体が冷えてしくじっちゃったら可哀想だから」
「うん、わかった。悠里にお似合いの下着、お姉ちゃんがすぐに用意してあげるから、おとなしく待ってなさいね」
最初は琴音に、あとの方は悠里さんに向かってそう言った美音ちゃん、いったん広げたピンクのナイティを脱衣籠に戻すと、代わりに、柔らかそうな生地でできた『悠里にお似合いの下着』を取り出し、床にバスタオルをさっと広げて、その上にそっと置いて、なにやら準備を始めた。
「……そ、それって……」
美音ちゃんの手元に不安げな眼差しを向けていた悠里さんだったけど、しばらくして美音ちゃんが何の準備をしているのか察しがついて、うわずった声を漏らしちゃう。
「これが何だかわかったみたいね。そうだよ、おむつだよ。おねしょっ子の悠里にお似合いの下着だよ」
狼狽する悠里さんとは正反対に、澄ました顔の美音ちゃん。
そう。バスタオルの上に美音ちゃんが準備したのは、ピンクのチェック柄のおむつカバーと水玉模様の布おむつだった。ただ、おむつカバーは新しいんだけど、布おむつの方は、買ったばかりの新しいのじゃなさそう。
「これなら、パジャマもマットレスも濡らさずに済むからね。どう、柔らかくて肌触りのよさそうなおむつでしょ? 何度も何度も洗濯したおむつだから、とっても柔らなんだよ。うふふ、誰が使っていたおむつだと思う?」
目をそむけようとするんだけど、どうしてだかおむつから目を離せない悠里さん。
そんな悠里さんに届く琴音の笑い声。
「……」
「お隣ん家、一番上のお姉さんが里帰り出産で帰ってきているんだって。それで、そのお姉さんの子供、早苗ちゃんって名前なんだけど、早苗ちゃん、保育園の年少さんで、まだおむつ離れしてないらしくてね、これ、早苗ちゃんのおむつなんだよ」
唇を震わせるだけの悠里さんに、おむつの準備を終えてすっと立ち上がった美音ちゃんが面白そうに教えてあげる。
そこへ、こんなふうに付け加える琴音。
「今は美音ちゃんが使っているけど、元は、一番上のお姉さんが生まれた時にお隣のおばさんが愛情込めて自分で手縫いしたおむつなんだそうよ。我が子がすくすく育ってくれることを願いながら一針一針丁寧に仕立てたおむつ。それで、一番上のお姉さんが使わなくなった後は、久美さんや朱美が使ったおむつ。――そうよ、久美さんのお下がりのおむつなのよ、これは」
「……!」
何も言えなくて、浅い呼吸を繰り返すだけの悠里さん。
「悠里のおねしょのこと、うちのお母さんは外国にいるから相談できないでしょ。だからお隣のおばさんに相談して、いろいろ話しているうちに、おむつを貸してもらえることになったのよ。早苗ちゃんがまだおむつ離れしていないところに、もうすぐ二番目の孫が生まれるからって、昔のことを思い出しながら新しいおむつを仕立てていたんだけど、ちょっとした事情があって、思っていたよりもたくさんおむつが要ることになって、それで、すっごく頑張って縫い上げたんだよって、にこにこ笑いながら本当に嬉しそうに話してくれて。そんなわけで、おむつはたっぷりあるから、必要なだけ幾らでも貸してあげるから持って帰りなさいって言ってくれて、だから、古いおむつをたくさん借りてきたんだ。久美さんも使った、久美さんのおしっこもたくさん吸った、久美さんのお下がりのおむつをね」
「……」
瞼をぎゅっと閉じた悠里さんの肩が震える。
「あ、勘違いしないでね。私が相談しなくても、お隣さん、悠里のおねしょのことは前から知っていたんだからね。家事のことに疎くて物干し場の様子を気をかけたこともない悠里は知らないかもだけど、うちの物干し場と隣の物干し場の間、生垣で遮っているけど、生垣の木がちょっと疎らなのよ。だもんで、わざと覗こうとしなくても、いやでもお互いに洗濯物が見えちゃうんだ。だから、毎日マットレスが立てかけてあることも見えちゃうし、普通ならパジャマなんて何日かおきくらいにしか洗濯なんてしない筈なのに、それが毎日干してあるのが見えたりしたら、何があったのか大体のことは察しがつくよね。それで、おばさんも里帰り中のお姉さんも朱美も、ずっと心配してくれていたんだよ」
しれっとした顔で説明する琴音。
けど、この琴音の説明には、ちょっとした嘘が混ざっている。うちと琴音ん家を遮る生垣が所々疎らになっていて、お互い物干し場の様子を見ようと思えば簡単に見ることができるのは確かだ。でも、だからこそ、お隣さんの様子を覗き見るだなんてお行儀のわるいことをしないよう、お互い気をつけてわざとそちらに目を向けないようにしている。なのにお母さんが琴音ん家の物干し場の様子を見ちゃったのは、マットレスや悠里さんのパジャマなんかを干す時に琴音と美音ちゃんがこれ見よがしにわざと騒いでみせて、それが気になって何があったんだろうってお母さんがふっとそちらに目を向けたからだった。そう、つまり、悠里さんが恥ずかしい粗相をしちゃったこと、琴音がわざとうちのお母さんに教えたってわけだ。琴音がわざわざそんなことをしたのには、自分の計画が順調に進んでいることを私に知らせるためという理由もあるし、それと、うちの家族が私たちの計画に協力してくれるようにするための準備という意味もあってのことだった。
「……」
悠里さん、無言のままぶるっと体を震わせる。
夏とはいっても、脱衣場はエアコンが効いているし、腰にタオルを巻いているだけの裸ん坊だ。それに、悠里が拭き取るまでは体にも髪にも拭き残しの水滴がたくさん付いていたんだから体が冷えるのも当り前。
でも、悠里さんが体を震わせた理由はそれだけじゃないみたい。だって、体が冷えたのだったら体全体を震わせる筈なのに、この時の悠里さん、腰から下腹部にかけてのあたりを震わせていたんだから。
「ほら、このままじゃ風邪をひいちゃうわよ。いい子だから、おむつにお尻を載せて、バスタオルの上にごろんしてちょうだい」
琴音、悠里さんの顔と水玉模様の布おむつを見比べながら、それこそ小っちゃい子をあやすみたいに優しい声で言う。
「……や、やだ。お、おむつだなんて、そんなの……」
やっとのこと、悠里さんの口から声が出る。 でも、それは、お母さんに我儘を叱られて泣き出しそうになっている小っちゃい子みたいな、情けなくて弱々しい声だった。
弱々しい声で言って力なく首を振って後ずさる。
「聞き分けのわるい子ね、悠里は。そんな、言って聞かせてもわからない子にはこうするしかないわね」
琴音、高校生とは思えない威厳のある声で言うと、後ずさる悠里さんの手首を掴んでぐいっと引き戻して
「この子の肩を押さえといて。どこにも逃げられないようにしておくのよ」
と美音ちゃんに指示。それからすっと腰をかがめて右手を振り上げたかと思うと、そのまま悠里さんのお尻に振りおろしちゃう。
ばっし〜ん!
脱衣場に響き渡る、とっても痛そうな音。「つ……!」
我慢できずに体をのけぞらせる悠里さん。
でも、それで済みはしなかった。
何度も何度も繰り返し右手の掌で思い切り悠里さんのお尻を叩く琴音。そのたびに脱衣場の空気が震える。
「や、やめて。お尻をぶつのはもうやめて……」
長男の威厳なんてどこへやら。
それまで駄々をこねていたのが、お母さんの折檻に耐えられなくて許しを乞う幼児さながら、悠里さん、涙目で訴えかける。
でも、そんなの琴音は無視。
それからも何度も力まかせに悠里さんのお尻を叩き続ける。そのたびに聞こえる、悲鳴にもならない呻き声。
そんなことが続いているうちに、悠里さんの口から
「……や、やだ。ほんとに、やだったらぁ……」
と、本当に情けない、でも聞きようによっては甘えてでもいるみたいな声が漏れて、悠里さんの下腹部が小刻みに何度も震え出す。
床に水滴が落ちる音が微かに聞こえたのは、そのすぐ後のことだった。
ぴちょんという音が微かに微かに聞こえて、それに続いてもう一度ぴちょんという音が聞こえて、それがいつしか連続した音に変わってゆく。
水滴は、悠里さんのおちんちんから溢れ出したおしっこだった。
床に落ちたおしっこの滴が無数の小さな飛沫になって、あたりを濡らす。
「ほら、ちゃんと言うことをきかないから、こんなことになっちゃう」
琴音、悠里さんに向かって呆れ声で言って、美音ちゃんがおむつカバーの上に十枚重ねで用意した股当てのおむつを掴み上げて、そのまま悠里さんのおちんちんに押し当てる。
少しの間、おちんちんから漏れ出すおしっこがおむつに吸い取られて、床に落ちるおしっこが途切れる。
だけど、しばらくすると、やっぱりまたおしっこが床をじくじく濡らし始めた。おむつで吸収しきれなかったおしっこがおむつから滲み出して悠里さんの内腿からくるぶしの内側を伝い流れて床を濡らしちゃう。
「わかる? 悠里は今、おもらしをしちゃってるんだよ。夜眠っている間のおねしょだけでも恥ずかしいのに、昼間もうたた寝の間におねしょしちゃって、今はお目々が覚めているのに、おもらしでおむつを濡らしちゃってるんだよ。そんなの、小っちゃい子と同じだよね。ううん、小っちゃい子でも、保育園の年長さんだったらそんなことしないよ。おもらしでおむつを濡らしちゃうのは、保育園の年少さんくらいまで。そう、里帰り出産で実家に帰ってきているお隣の一番上のお姉さんのお嬢ちゃん、早苗ちゃんくらいまでだよ。わかる? 悠里は、早苗ちゃんと同じ小っちゃい子に戻っちゃったんだよ。いつおねしょしちゃうか、いつおもらししちゃうかわからない小っちゃい子だからおむつが要るんだよ。悠里にお似合いの下着はパンツなんかじゃなくて、おむつなんだよ」
おむつから滲み出すおしっこの温もりを掌に感じながら、不思議な色の瞳を妖しく煌めかせて琴音がねっとりした口調で悠里さんに言い聞かせる。
「悠里はこれからずっとおむつなんだよ。でも、おむつをあてたらお尻がぷっくり膨らんで、ズボンなんて窮屈で穿けないよね。だから、スカートじゃなきゃいけないんだよ。スカートじゃなきゃいけないから、男の子じゃいけないんだよ。わかるよね。おむつの悠里は、スカートの女の子にならなきゃいけないんだよ。だから、おねむの時のパジャマも、おっきしている時の遊び着も、美音お姉ちゃんのお下がりを着せてもらう、可愛らしい妹になるんだよ」
おむつから滲み出して掌を濡らすおしっこが徐々に少なくなってくる。
「そろそろ、出ちゃったかな。じゃ、ちゃんとおむつを当てようね。もうこんなことにならないように、恥ずかしいおもらしで床を濡らしたりパジャマを濡らしたりしないように、おしっこが漏れ出さないように、たっぷりのおむつを当てようね。――替えのおむつを用意してちょうだい」
最後の方は美音ちゃんに指示して、脱衣籠と一緒に持って来ておいたペールの中に、悠里さんのおしっこでぐっしょり濡れたおむつをいとおしげにそっと滑り入れる琴音だった。
*
こんなにも恥ずかしい姿をさらしちゃった後のこと、もうすっかり琴音の言いなりになるしかないのは悠里さんにも痛いほどわかっている。
言われるまま水玉模様の布おむつにおそるおそるお尻を載せる。琴音に叩かれてまだひりひりと痛むお尻をふわっと包まれるみたいな優しく温かな肌触り。
思ってもみなかった柔らかな感触に、悠里さんの下腹部がじんと痺れて、頬にさっと朱が差した。
「気持ちいいでしょ?」
悠里さんの表情が変わるのを面白そうに眺めながら琴音が決めつける。
「……そ、そんなわけ……」
慌てて否定しようとするんだけど、胸の中を見透かされちゃったみたいに思えて悠里さん、口ごもってしまう。
「それに、可愛いだけじゃなくて、とっても安心できると思うよ、おむつを当ててもらったら」
「……」
重ねて言う琴音に、悠里さん、ますます頬を赤く染めて押し黙っちゃう。
「おむつはね、お母さんの愛情が形になったものなの。お母さんの優しい手の温もりと、お母さんに抱っこしてもらった時の限りない安心感が形になったもの。大きくなってからおむつだなんて最初は恥ずかしいと思うけど、すぐにおむつの虜になっちゃうわよ。賭けてもいいわ」
「……」
やっぱり何も言えなくて唇を震わせるだけの悠里さん。
でも、私だったら琴音の言葉に大きく頷いていたに違いない。一度きりの試しでしか経験していないけど、興味半分で自分でおむつを当ててみた時の体の疼きようは半端じゃなかった。女の人と男の人じゃ(体も心も)感じ方が違うから悠里さんがどうだかわからないけど、私だったら、一晩あてていたら絶対に虜になっちゃう。一見しただけじゃただの布きれで、どこにそんな魅力があるのか不思議だけど、おむつの肌触りは、琴音が言うように、子供を慈しむ母親の掌そのものだ。それに、「大丈夫だよ。おもらししちゃっていいんだよ」と甘ったるい声で囁きかけられてでもいるみたいな温かな安心感。
「あらあら。まだ、だんまりのままなの。でも、我を通していられるのも今の内だと思うわよ。さ、いつまでもこうしていちゃ、またいつおもらししちゃうかわからないから、ちゃんとしとかないとね。――美音、可愛いおもらしっ子の妹におむつをあててあげて」
くすくす笑いながら琴音がそう言って、悠里さんの上半身を床に押し倒した。とんでもない痴態をさらしちゃったせいで琴美の言いなりになるしかないって諦めたのか、悠里さん、抵抗をする気配なんてない。抵抗する代わりに、これから自分の身に起きることを見まいとして、ぎゅっと目を閉じることしかできずにいる。
「ええと、最初に、お肌に残っているおしっこの雫を綺麗に拭き取ってあげなきゃいけないんだったよね。じゃないと、おむつかぶれになっちゃうから。さ、綺麗綺麗するわよ。お姉ちゃんがちゃとしてあげるから、おねしょっ子でおもらしっ子の悠里は、おとなしくしていてね」
琴音に教えてもらったんだろう、おむつを取り替える手順を一つ一つ思い出しながら、美音ちゃんが手を動かし始める。美音ちゃんが先ず手にしたのは、赤ちゃん用のお尻拭き。
「ん……」
消毒用の薬剤成分を含んだお尻拭きがお股に触れた途端、ひんやりしたした感触に、悠里さんの口から呻き声が漏れる。
「うふふ、悠里ったら感じやすいんだ。こんなに可愛らしいおちんちんなのに、感じちゃうんだ」
ちょっぴり毒を含んだ声で言って美音ちゃんがくすっと笑う。
男の人のおちんちんを見てもまるで動じないのは、子供の頃によく一緒にお風呂に入っていて見慣れているというのもあるんだろうけど、それよりも、兄弟姉妹の固い絆から抜け出して意中の女の子(つまり、久美お姉ちゃんのことね)に告ろうとしていた兄に対する怒りのせいというのもあるのかな。それに、ま、ただでさえちょっぴり発育不全気味のおちんちんがお尻拭きの冷やっとした感触のせいで余計に縮こまっちゃって両脚の間に殆どかくれんぼう状態だから、ひょっとしたら、私でも気にもかけないかもしれないしね。
「で、次は、そうそう、これを忘れちゃいけないんだった。ちゃんとベビーパウダーをはたいとかないと、おむつかぶれになりやすいんだから」
お尻拭きの次に美音ちゃんが手に取ったのはベビーパウダーの丸い容器。さっと蓋を開けて、柔らかそうなパフでベビーパウダーの真っ白の粉を掬い取る。でも、掬い取ったパフじっとみつめて、なにやら思案顔。
「でも、琴音ねぇ、あまりたくさんでも駄目なんだよって言ってたっけ。たしか、おむつの中は通気性がわるくて蒸れやすいんだけど、ベビーパウダーが水分を吸収してくれるからお肌はさらさらのままでいられるんだったよね。でも、水分を吸収したベビーパウダーをそのままにしておくと、湿っけたベビーパウダーがお肌にわるさをして、かぶれやすくなっちゃうから、おしっこが出てなくてもこまめにおむつを取り替えてあげるか、じゃなきゃ、取り替えはしなくてもおむつを開けてお肌を綺麗に拭ってあげるとかした方がいいんだよって教えてくれたんだったよね。それに、ベビーパウダーが多すぎると、水分を吸収したたくさんのベビーパウダーでお肌がべとべとになって、逆におむつかぶれの原因になるんだったよね。だから、うん、きちんと気をつけてベビーパウダーをはたいてあげないとね」
琴音から言い聞かされた注意事項を思い出しながら小さな声で呟いて。でも、そこで何やら面白いことを思いついたのか、にまっと笑って、独り言めかしつつ、でも今度はよく通る声で、
「あ、だったら、私がベビーパウダーの分量を細工したり、なかなかおむつを取り替えてあげなかったりしたら、わざと悠里をおむつかぶれにさせちゃえるってことだよね。うふふ。おむつかぶれでお尻が痛いから優しくしてよ美音お姉ちゃんって泣きべそをかく悠里、可愛いだろうな。そしたら私、悠里を薬局へ連れて行ってあげなきゃね。そんで、薬局のお姉さんの目の前で悠里のおむつを開いて、こんな症状なんですけど、この子のお肌に合うおむつかぶれのお薬を選んでくださいってお願いしてあげるんだ。で、薬をどうやって悠里のお尻に塗ったらいいのかお姉さんに実際にやってもらって、それを手本にして、それから毎日、おむつを取り替えてあげるたびにお薬を塗ってあげなきゃね。おむつかぶれで赤くなっちゃった悠里のお尻も可愛いかもしれないし、うん、わざとおむつかぶれにさせちゃうのもいいかも。でも、痛くて泣いちゃうのはやっぱり可哀想だし、どうしようかな。――ま、悠里がいい子にしているかどうか見てから決めても遅くないや。琴音ねぇに相談しながらゆっくり考えようっと」
と、悠里さんの耳に届くよう、わざとらしく考え考えの素振りで言ってから、ベビーパウダーのパフをおちんちんの先っぽに押し当てちゃう。
「や……」
悲鳴とも喘ぎ声ともつかない、聞きようによってはひどく艶めかしい声を出しちゃう悠里さん。でも、美音ちゃんの手から逃げることはできない。
肉体の痛みを伴う力による支配というのは、人が思っているよりも有効だ。特に、圧倒的な体格差を日ごろから感じている相手からの力による支配なら尚更に。しかも、力まかせにお尻をぶたれ、痛みと屈辱のためにおもらしをしてしまい、おしっこでおむつを濡らしてしまったとなれば。
ついさっきの自分の痴態を思い出しちゃったんだろう、悠里さん、怯えとも諦めともつかない表情を浮かべて、美音ちゃんのなすがまま。それに、下手に逃げようとして、わざとおむつかぶれにされちゃったりしたら。
鼻を優しくくすぐるベビーパウダーの甘い香りと、いかにも楽しそうな美音ちゃんの笑顔。そして、それとは裏腹な悠里さんの切なくも力ない喘ぎ声が漏れる中、おちんちんをパフでいたぶって、悠里さんのお股にベビーパウダーの白化粧を施した美音ちゃん、
「うん、準備はこれでいいよね。じゃ、いよいよだね」
と、琴音とはまた異なる色の瞳を妖しく煌めかせて、悠里さんの左右の足首を左手で一つにまとめて掴んで、そのまま高々と差し上げちゃう。
「……!」
悠里さんの顔が恥辱に染まる。ぎゅっと目を閉じたままだから自分がどんな格好をさせられているのか見ることはできない。できないけど、自分が今、赤ちゃんがおむつを取り替えてもらう時のポーズをさせられていることはいやでもわかる。
「そのままじっとしているのよ。おもらしっ子の妹・悠里がいつ恥ずかしい失敗をしちゃってもいいように、お姉ちゃんがきちんとしてあげるからね」
左手で悠里さんの足首を差し上げたまま、お尻の下に広がっている股当てのおむつを、お尻の膨らみを包み込むようにしながらおへそのすぐ下まで、両脚の間をそっと通して縦に当てる。
ただし、十枚重ねになっている股当てのおむつをまとめてじゃなく、一枚ずつ、わざとゆっくり。そのたびに柔らかなおむつの端が腿の内側をさわっと撫でて、悠里さんのお股がひくひく震える。
ううん。悠里さんが受ける恥辱はそれだけじゃない。股当てのおむつを両脚の間に通す時、美音ちゃんは
「おむつを当ててあげる時、おちんちんは上向きにしちゃいけないんだったよね。おへそのあたりのお肌は薄くてバイ菌とかに弱いから、おしっこでおへそのまわりが濡れないように、おちんちんは下向き、つまり、お尻の方に向かせておかなきゃなんだよね」
と、わざと悠里さんに聞こえるように言って、ベビーパウダーのパフで可愛がってもらっても(あまりにも異様な状況に置かれているせいなんだろうけど)まだ両脚の間で隠れんぼをしている可哀想なおちんちんをお尻の方に向かせて、その上から股当てのおむつで押さえつけていたんだ。
それは、『戒め』なのだろう。女の子に告って家族の強い結び付きから抜け出そうとしていた悠里さんを家族のもとに繋ぎとめておくための戒め。そして、意中の相手との愛の営みの果てに生命の源となる白濁液を迸らせる役目を担うおちんちんを本来の向きとは真逆の後ろ向けに押さえつけ、その役割を奪ってしまうための戒め。
「で、それから、横当てのおむつだよね。股当てのおむつで押さえといてもおちんちんはじっとしてなくて右や左に動いちゃうから、そのせいでおしっこが横漏れしやすくなっちゃうんだよね。それを防ぐためにちょっと一手間かけるのが優しいお姉ちゃんの努めってとこね」」
股当てのおむつの後、美音ちゃん、それまで高々と差し上げていた足を床におろしてから、お尻の左右に広がっている横当てのおむつの左右の端を持ち上げて、おへその下で股当てのおむつの上に重ねた後、おむつカバーの左右の内羽根を持ち上げて横当てのおむつの上に重ねて、両方の内羽根をマジックテープでしっかり固定した。
今どき、本当の赤ちゃんを布おむつで育てる場合、横当てのおむつを使うことはない。昔は横当てのおむつも使うのが普通だったけど、横当てのおむつのせいで赤ちゃんの股間が圧迫されて、それが股関節脱臼の原因になることが知られるようになったせいで、今は股当てのおむつだけを使う『股おむつ』というのが当り前になっている。なのに(琴音の指示で)美音ちゃんが横当てのおむつを使ったのは、横漏れを防ぐためというよりも、おちんちんを束縛する戒めを更にきつくするためだ。そうして、それに加えて、よりいっそう強くお尻とお股を圧迫して、おむつをあてられている感触を悠里さんにいつも意識させておくため。
その後、美音ちゃんはおむつカバーの前当てを内羽根に重ねながら、左右に四つずつ付いているスナップボタンを下から順にぷつんぷつんと丁寧に留めて、最後に、前当ての内側と内羽根の表面を互いのマジックテープでしっかり留めちゃう。で、あとは、腰紐をきゅっと結わえておしまい。
「おとなしくしていていい子だったね、悠里は。これからもおむつを取り替えてあげるたびに、こんなふうにいい子にしているのよ。さ、もうすぐ終わるから、あとちょっとだけそのままにしてちょうだいね」
美音ちゃん、悠里さんを優しくあやして、おむつカバーの股ぐりからはみ出ている布おむつをおむつカバーの中に丁寧に押し込んであげる。こうしておけば、たっぷり厚めに当てたおむつからおしっこが滲み出しておむつカバーの股ぐりから横漏れしちゃうことはない。
「さ、できた。じゃ、体を起こすわよ。はい、おっきして」
おむつの当て具合を丹念に点検してから、美音ちゃん、背中と床の間に手を差し入れて悠里さんの上半身を抱き起こす。
そこへ琴音が
「初めてのわりには上手だったね、美音。これなら、安心して悠里のおむつのお世話をまかせられるよ」
と、にこやかに話しかける。
「えへへ、上手だったでしょ? だって、頭の中でいっぱい練習したんだもん。私、妹がほしくてほしくて、ずっと考えていたんだよ。妹がいたらどんなふうにお世話してあげようかなって。だから、おむつの当て方も、琴音ねぇに教えてもらってからスマホでいろんな動画を見て、頭の中でイメージトレーニングしていたんだよ。お兄ちゃんだった悠里にぃが妹の悠里になって、私、とっても嬉しいんだ。だって、ほしくてたまんなかった妹ができたんだもん。それも、おむつのお世話をしてあげなきゃいけない手のかかる小っちゃな妹ができたんだもん。お隣の一番上のお姉さんの子、早苗ちゃんだっけ、早苗ちゃんも頭の中でいろいろ想像してるんだろうな。もうすぐ妹ができて、どんなふうにお世話してあげようかって、わくわくしながら想像してるんだろうな。私の方が先に妹ができたから、妹ってこんなに可愛いんだよって早苗ちゃんに話してあげたいな」
はにかみながらも、ぱっと顔を輝かせる美音ちゃん。
「そうなんだ、そんなに妹がほしかったんだ。それで、ほしかった妹ができて、そんなに嬉しいんだ。じゃ、悠里にぃを妹にしちゃう最後の仕上げをしちゃおうか。いったん脱衣籠に戻した美音のお下がりのパジャマを悠里に着せてあげてちょうだい。それで、長男だった悠里にぃが、一番下の妹の悠里になっちゃうから」
美音ちゃんの言葉に優しく頷き返してあげながら琴音、脱衣籠からピンクのナイティを掴み上げて美音ちゃんに手渡した後、悠里さんの二の腕を掴んで両手を上げさせた。
「うふふ、そうだね。私が小学生の時に着ていた私のお下がりのパジャマを着せてあげたら、その時から悠里は本当に私の妹だね。小学生なのにおむつの外れないちょっぴり恥ずかしい、でも、だからこそ、とっても可愛い妹に」
美音ちゃん、悠里さんの両手を丁寧に袖に通させながら、ナイティをすつぽり頭からかぶせ、そのままさっとを裾を引きおろした。
それと同時に琴音が悠里さんの二の腕を掴んだまま体を引き上げるようにして床に立たせちゃう。
ピンクのチェック柄のおむつカバーを覆い包むみたいにしてナイティの裾がふんわりまいおりる。でも、いくら美音ちゃんの発育がいいといっても、小学校三年生か四年生の時のナイティだ。背が低くて華奢な体つきの悠里さんだけど、ちょっぴりサイズが小さいみたいで、元々ミニ丈だったのが、マイクロミニ丈みたいになっちゃう。そのせいでおむつカバーを完全に覆い隠すことができなくて、裾がふわふわ揺れるたびにおむつカバーが見え隠れする。どう言えばいいかな、公園なんかで、短いスカートの裾からおむつをちらちらさせながらママに手をつないでもらって散歩している、あんよのお稽古真っ最中の小っちゃな女の子を見かけることがあるよね、ちょうどそんな感じになっちゃうんだ、おむつカバーとナイティ姿の悠里さん。
「へーえ。いい線いくだろうなとは思っていたけど、まさか、これほどまでとはね。ついでだから、髪もいじっちゃおうかな。さっきはバスタオルで拭いてあげただけだから、ちゃんと梳かしてあげなきゃいけないことだし」
琴美、床に立たせた悠里さんの様子をしげしげと眺めてから大袈裟な溜息をついて、ヘアブラシを手にする。
それから後は悠里さんの髪を丁寧に梳かしてあげたり、部屋からヘアゴムを持って来るよう美音ちゃんに指示したりで、琴音、手を動かし続ける。でも、うっきうきなのが傍目にも明らかで、とってもご機嫌なご様子。
で、しばらくして、ようやく琴音が手を止める。
手を止めて、悠里さんの背中をそっと押して、壁に嵌め込みになっている大きな鏡の前に移動させる。
その間、悠里さん、ぎゅっと目を閉じたまま。自分が妹二人に何をされたのか、大体のことはわかる。わかるから、その結果を自分の目で見るのが怖くて、それで瞼を開けられない。
でもそのままだなんて琴音が許すわけがない。
「いつまでもそうしてないで、さ、目を開けなさい」
悠里さんと並んで鏡の前に立った琴音、悠里さんの体に覆いかぶさるようにして、悠里さんの顔を見おろして言い聞かせる。
だけど、悠里さんは体を固くするだけ。
琴音の目がきらっと光って
「お姉ちゃんの言いつけがきけないだなんて困った子だこと。困った子にはお仕置きが要るんだったわよね」
と言うなり、大きく右手を振り上げる。
気配を感じて悠里さんが身をすくめるのと、琴音が悠里さんのお尻に手を振りおろすのが同時だった。
でも、琴音、今度は手加減したみたいだ。大きな掌がお尻に当たる直前、ふっと力を抜いた。そのせいもあるし、たっぷり厚めに当てた布おむつとおむつカバーの上からというのもあって、叩かれた時も、少し気の抜けたくぐもった音しかしなかった。このぶんだと、痛みも殆ど感じていない筈。――痛みも殆ど感じていない筈なのに、琴音の手がナイティ越しにおむつカバーに触れた瞬間、悠里さん、体をびくんと震わせて、両目を大きく見開いちゃう。しかも、瞳をうっすら潤ませた涙目になって。
多分、何度も力任せにお尻をぶたれたあの時の痛みが蘇ってきたというのもあるんだろうけど、それよりも、想像もつかないくらいひどい恥ずかしさを覚えたからじゃないかな。だって、考えてもみてよ。高校生の男の子(しかも、学校じゃ生徒会の筆頭副会長を務めちゃうような男の子)が五つ下の妹が小学生の時に着ていたミニ丈のナイティを着せられて、その上おむつまであてられて、お仕置きとか言われて二つ下の妹におむつの上からお尻をぶたれちゃうんだよ? こんな生き恥、私だったら絶対に耐えられない。力まかせにお尻をぶたれる痛みが肉体へのお仕置なのに対して、今のは精神へのお仕置きだ。それも、絶対に耐えられない、想像を絶するほどの悲鳴を心にあげさせる、恥ずかしさの極みのお仕置き。
こんなとこを思いつくだなんて。
琴音、怖い子。
そんなふうにして無理矢理に目を開けさせられちゃった悠里さん。
大きな鏡に向かってきょとんとするばかりだ。なんていうか、鏡に映っているこの女の子は誰なんだろう?とでも思っているみたいに。
そんな悠里さんを琴音が
「なに自分に見取れてんのよ。あ、ひょっとして、とんでもないナルちゃんだったのかな、悠里って?」
と茶化す。
その時になって悠里さん、
「自分に見取れて……?」
と、ぽつりと呟いた。
それから、もういちど鏡をおそるおそる覗き込んで、映っているのが自分だと気がついて、ナイティの裾を慌てて引きおろそうとする。だけど、そんなことじゃおむつカバーを隠せないとわかると、涙目をますますうるうるさせて周囲を見回し、琴音と美音ちゃんの存在を今更ながら思い出したかのように、羞じらいがちにおどおどと目を伏せてしまう。
鏡の中にいるのは、なんて魅力的な女の子だろう。不安に大きな瞳を潤ませて、落ち着かぬげにぷっくりした唇を真っ赤な舌で湿らせて、薄い胸板を弱々しく震わせて、救いを求める術を知らずに瞳をきょときょと揺らすその女の子は、なんと蠱惑的なのだろう。お風呂上がりのすべすべした肌に薄く淡いピンクのナイティをまとい、さらさらの髪をカラーゴムで愛くるしいツインテールに結わえて、見た目の年齢にはふさわしくない幼児の下着にお尻を包んだその少女は、なんと可憐なのだろう。ことさら、年齢にふさわしくない下着であるおむつカバーのギャザーにむちっと締め付けられた腿は、なんと被虐的なのだろう。たっぷり当てたおむつでぷっくりと丸く膨らんだそのお尻は、なんと人の好奇を誘うのだろう。
「私たち三人の中で、元々、悠里が一番可愛い顔をしていたし、華奢な体つきをしていたからね。琴音ねぇと私は、なんていうか、美人で魅力だっぷりだけど、『女の子』の可愛らしさにはちょっと欠けているし」
実物の悠里さんと鏡の中の悠里さんを交互に見比べて、美音ちゃんが苦笑交じりに、いくらか嫉ましそうに言う。
「これで、悠里を女の子らしく躾け直す楽しみがますます大きくなっちゃったわね。ま、でも、お楽しみは明日からということにして、悠里はもうねんねしなきゃね。小っちゃい子が夜更かしするのは感心しないわよ」
少女と幼女が入り交じる悠里さんの姿を満足そうに眺めながら、いかにも保護者然とした口調で琴音が言った。
壁に掛かっている時計はまだ八時三十分。夜更かしというには早い時間だが、まだおむつの外れていない小っちゃい子にとっては夜更かしなのかもしれない。
「そうね。悠里の可愛い姿は明日からたっぷり楽しむとして、今夜はもうおねむにしてあげなきゃね。琴音ねぇ、悠里を寝かしつけるのに添い寝してあげるんでしょ? だったら、悠里がおもらしで濡らしちゃった床は私が綺麗にしておくから、琴音ねぇは早く悠里を部屋に連れて行ってあげてよ」
琴音に、見音ちゃんも口を合わせる。
「ごめんね、面倒くさいことをまかせちゃって」
「いいのよ。念願かなって、今日から私お姉ちゃんだもん。可愛い妹の恥ずかしい粗相の後始末をしてあげる優しいお姉ちゃんだもん」
「そうね、お姉ちゃんだもんね。――じゃ、あとのことは美音お姉ちゃんにまかせて、悠里は私と一緒にいらっしゃい」
琴音が悠里さんの手をくいっと引っ張った。
その勢いに前のめりに倒れちゃいそうになるのはかろうじて踏ん張ったけれど、ナイティの裾がふわっと舞い上がって、おむつカバーが半分ほど見えてしまう。だけど、たっぷり当てられたおむつのせいで思うように脚を動かせず、琴音に手を引っ張られてついて行くのに精一杯で、ナイティの裾を押さえることも覚束ない。
それは、公園なんかで時おり見かける、短いスカートの裾からおむつをちらちらさせながらママに手をつないでもらって散歩している、あんよのお稽古真っ最中の小っちゃな女の子そのままの姿だった。
*
階段を昇り、二階の廊下を少し歩いて琴音が悠里さんを連れて行ったのは、悠里さんの部屋ではなく、その隣の部屋だった。
「ずっと空き部屋だったけど、ここが今日から悠里の部屋よ。間違って元の部屋に行かないよう気をつけてね。もっとも、元の部屋には鍵を掛けておいたから間違って入っちゃうことはないでしょうけど」
そんなふうに言いながら琴音、静かにドアを引き開けて、悠里さんの背中に手をまわして部屋の中に押しやった。
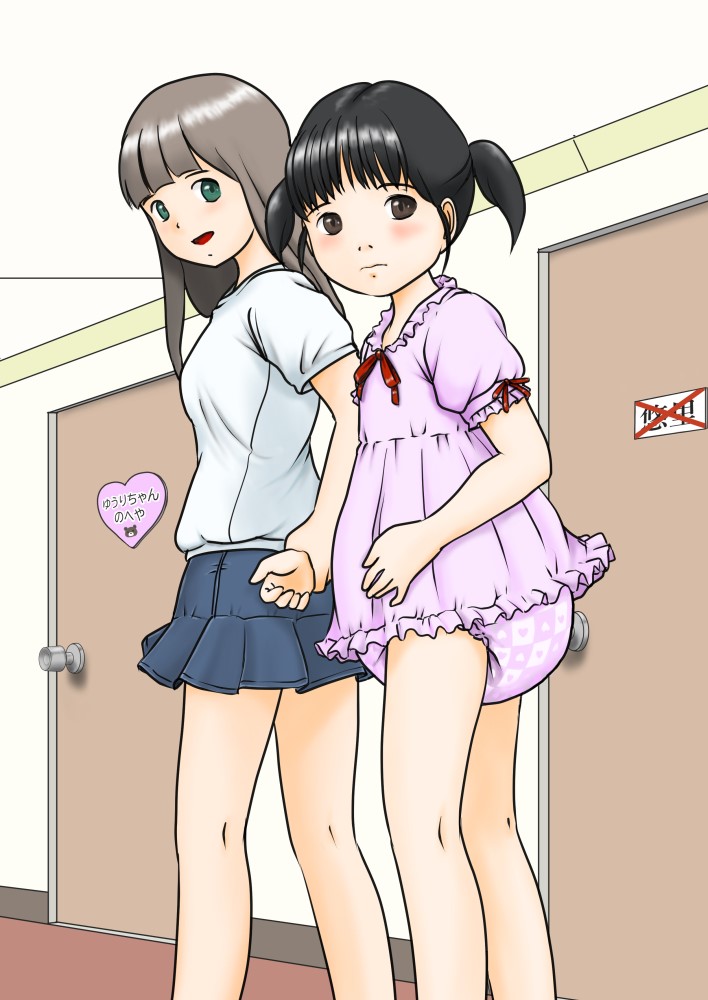
部屋に入った途端、ハーブの香りが鼻をくすぐる。
「毎日のおねしょのせいでおしっこ臭くなっちゃった部屋を可愛い悠里に使わせるのは可哀想だから、新しい部屋を用意してあげたのよ。でも、おねしょやおもらしがこれからも続くようなら、いくらおむつを当てていても、この部屋もおしっこの匂いがするようになるかもしれないでしょ。だから、アロマオイルを染みこませたポプリの小瓶を置いてあげたのよ。おねしょのことを気にしないでゆったりねんねできるように、気持ちを落ち着かせるラベンダーのアロマオイルよ」
意識しないまま子犬みたいにくんくんと鼻を鳴らす悠里さんに説明しながら、琴音は照明のスイッチを入れた。
間接照明の柔らかな光に調度品が浮かび上がる。どれも新品なんだろう汚れ一つなくて、「可愛い悠里のために用意してあげた」のがよくわかる、優しいパステルカラーの壁紙によく合う、フェミニンというよりもガーリーな雰囲気たっぷりの調度品ばかりだ。
中でも、ナイティと同じ淡いピンクの木製のベッドが目を引く。部位の一つ一つの角が丸く削ってあるのは小さな子供が怪我をしないようにという配慮のためだろうし、ベッドの両側が柵になっている(今は、手前側の柵が倒してあるけれど)のは、寝相の良くない小さな子供が転げ落ちないようにするためだろう。マットレスもベッドパッドもベッド本体と同じ淡いピンク色で揃えてあって、足元にきちんとたたんで用意してある薄手の毛布やタオルケットには、小さな女の子が大好きなアニメキャラ。
「小っちゃい子はもうおねむの時間よ。お姉ちゃんが寝かしつけてあげるから、さ、いらっしゃい」
唖然とした顔で立ちすくむ悠里さんの手を琴音が引っ張る。
その勢いで二歩三歩とベッドに歩み寄った悠里さんだけど、不意に我を取り戻したみたいにはっとした顔になって足を踏ん張っちゃう。
「いいのよ、遠慮なんてしなくても。今日からここが悠里のお部屋。あの箪笥もあの小物入れもあの収納棚もあのベッドも、みんな悠里の物。おねしょしちゃっても、美音お姉ちゃんにおむつを当ててもらったから新しいベッドを濡らす心配もないでしょ? だから、ほら」
弱々しくかぶりを振って足を踏ん張る悠里さんに、琴音が優しく言い聞かせる。
でも、悠里さんは一歩も動こうとしない。
「やれやれ、手間のかかる子だこと。いいわ、じゃ、お姉ちゃんがこうやってベッドまで連れて行ってあげる」
ひょいと肩をすくめてみせた琴音、悠里さんのお尻と背中に両手を搦めて、そのまま軽々と体を抱え上げてしまう。
「い、いや……!」
お姫様抱っこされた悠里さん、琴音の手から逃れようとして両足をばたばたさせるんだけど、そのたびにナイティの裾がふわふわ揺れて、おむつカバーが丸見えになっちゃう。
「悠里はそんなに聞き分けのわるい子だったんだ? だったら、聞き分けが良くなるようにしてあげないといけないね」
琴音、わざと呆れたように言って、こんなふうに付け加える。
「聞き分けのわるい子にはどうするんだったっけ。脱衣場でのこと、忘れちゃいないよね?」
途端に、お尻を力まかせに何度もぶたれた時の痛みと屈辱がありありと思い出されて、悠里さんの顔がひきつる。顔がひきつって、それまでばたばたしていた両足がぴたっとおとなしくなる。
「いい子ね、悠里は。たった一回だけのお仕置きでこんなに聞き分けがよくなるなんて、本当にいい子だわ。これからもそんなふうにするのよ。私も美音お姉ちゃんも、可愛い末っ子の悠里を叱りたくなんてないんだから」
お姫様抱っこした悠里さんの耳許に口を寄せて、琴音は優しく言った。
と、琴音の豊満な胸が頬に触れて、悠里さんの顔が真っ赤に染まる。
「あらあら、なにを恥ずかしがっているのかしら。女の子どうしなのに、しかも姉妹どうしなのに、変な悠里。でも、あ、そうか。お姉ちゃんのと比べて悠里の胸はまだ小っちゃいから、それが恥ずかしいのね? でも、大丈夫よ。悠里はまだおむつも外れていないちっちゃな子だもん。これから成長して、胸も大きくなるわよ。だから、そんなに恥ずかしがってないで、早くねんねしようね」
悠里さんが顔を真っ赤に染めた理由をわざと取り違えて、尚も唇を悠里さんの耳朶に押し当てるようにしておかしそうに言いながら、抱きかかえている華奢な体をベッドに横たえて、琴音が自分もその側にすっと横たわる。
「まだおむつも外れていない小っちゃな妹を一人でねんねさせるのは可哀想でしょう? だから、寂しくないように添い寝してあげる」
こともなげに言った琴音は左手を悠里さんの頭の下に差し入れて腕枕にすると、そのまま悠里さんの顔を自分の方に引き寄せた。
そうしておいて、右手だけでブラウスのボタンを外して胸元を大きくはだけ、ブラの肩紐もずらしてしまう。
張りのある豊かな乳房とぴんと勃ったピンクの乳首を目の前にして、悠里さんの顔がますます赤くなる。
「悠里にぃ、ずっと寂しかったんだよね。ずっとずっと寂しかったんだよね」
狼狽えるばかりの悠里さんの目をじっと覗き込んで琴音は言った。
「……!?」
「男の子はお母さんが大好きだもんね。女の子もお母さんのことは好きだけど、男の子はその何倍もお母さんが好きで、お母さんがちょっとどこかへ行っちゃうだけで悲しくなっちゃって、お母さんが少し長いお出かけでもしようものなら、恋しくて恋しくてたまんなくなっちゃうんだよね。だから、うちのお母さんみたいに滅多に家にいないとなると、寂しくて悲しくて恋しくて、どうしていいかわかくなくなっちゃうんだよね。でも、悠里にぃは頑張ったんだよね。自分も寂しくてたまんないのに、私と美音が不安がらないように頑張ってくれたんだよね。須藤家の長男として、一人きりの男の子として、二人の妹を守ろうとして、胸が張り裂けそうになる寂しさを我慢して、くじけそうになるのを我慢して、我慢して我慢して頑張ってくれた。だから。ありがとう、悠里にぃ。でも、頑張り過ぎた悠里にぃの心はぽっきり折れちゃった。だから、もういいんだよ。もう頑張らなくていいんだよ。だから、もう、私たちを守らなくていいんだよ。これまでありがとう、悠里にぃ。今度は、私と美音が悠里にぃを守ってあげる。悠里にぃが寂しくないように、私たちがお世話をしてあげる。だから、長男じゃなくていいんだよ。一人きりの男の子じゃなくていいんだよ。これまで頑張ってくれた分、今度は私たちに頼っていいんだよ。辛い長子じゃなくて、私たちに庇ってもらう末っ子になっちゃっていいんだよ。みんなを守る男の子じゃなくて、みんなに守ってもらう女の子になっちゃっていいんだよ。寂しい時や悲しい時に気持ちを表に出さない大人じゃなくて、感情をさらけ出しちゃう子供に返っていいんだよ」
琴音の言葉に、いつしか悠里さん、泣き出しそうな顔になってしまう。
「悠里にぃと違って、私と美音はお母さんに顔が似ている。中でも私が特に似ているってまわりの人たちからよくいわれるんだ。――私じゃ駄目? 私じゃ、お母さんの代わりはできない? ううん、私でいいよね?」
琴音は悠里さんの顔を更に自分の胸元に引き寄せた。
それを悠里さんが思いがけない力で拒む。
「……そう。私じゃお母さんの代わりはできないんだ」
寂しそうにぽつりと呟いて左手の力を弱める琴音。
しばらくの間、二人はまんじりともしなかった。
だけど。
不意に悠里さんの目から涙がこぼれて、腕枕をしている琴音のブラウスの腕を濡らしてしまう。
「悠里にぃ?」
ブラウスに広がる涙の跡と悠里さんの顔を琴音が見比べる。
悠里さんが琴音の乳首をおずおずと口にふくんだのは、そのすぐ後のことだった。
「いいのね? 本当に私でいいのね!?」
琴音の顔がぱっと輝いて、悠里さんの顔をそれまでよりもいっそう強く引き寄せた。
ちゅうちゅう。
ちゅぱちゅぱ。
もう悠里さんが拒むことはなかった。拒むどころか、自分から顔を琴音の乳房に埋めるようにして、無心に乳首を吸う。
「悠里。ああ、悠里」
琴音は、ツインテールに結わえた悠里さんの髪を優しく撫でつけながら、何度も名前を呼んだ。
だけど、悠里さんからの返事はない。返事をする代わりに、豊かな乳首にむしゃぶりつく。
「悠里、私の可愛い妹。ああ、悠里。いいわ、だっぷり吸ってちょうだい。子供の頃の寂しさを忘れるまで、いくらでも吸ってちょうだい」
琴音はもういちど悠里さんの髪を撫でつけてから、その右手を悠里さんの股間に這わせた。
「……!」
体をくねらせて琴音の手を振り払おうとする悠里さん。
だけど、琴音は執拗だった。
ナイティの裾をはだけさせて、おむつカバーの上から悠里さんの両脚の間を揉みしだく。
そこには、お尻の方に向けた状態でおむつに押さえつけられているおちんちんの先っぽがあった。おちんちんの中で最も敏感な部分だ。
「や、やめて……」
おむつカバーと布おむつ越しにおちんちんの先っぽを責められて、それでも乳首を咥えたまま、悠里さんが喘ぎ声をあげる。
「駄目よ、やめてあげない。だって、これはお仕置きだもの。悠里、お姉ちゃんのおっぱいを吸おうか吸わないでおこうか迷ったでしょ。迷った罰のお仕置きなのよ。お仕置きだから、やめてあげない」
一番感じやすいところを狙って、琴音の手がねっとり動く。おちんちん全体をまさぐるようにして揉みしだき、おちんちんの先っぽをおむつカバーの上から指の腹で撫でる。そのたびに柔らかい布おむつに敏感な部分を撫でさすられて、おむつの中でおちんちんがいやらしく蠢く。
「ううん、お仕置きだけじゃないわね。悠里ったら、おっぱいを吸うのがとっても上手なのね。お姉ちゃん、とっても気持ちよくなっちゃった。だから、これはご褒美も兼ねているのよ。お姉ちゃんを気持ちよくしてくれたことへのご褒美。ご褒美だから、やめないのよ」
琴音はおむつカバーの上から悠里さんのおちんちんの先っぽをきゅっと捻った。
「あ……!」
悠里さんの腰がびくんと震えた。
琴音の乳首を咥えていた口が半開きになる。
半開きになった口から
「……ま、ママ……」
と甘えた声を漏らして、もういちど琴音の乳首を咥えて、おむつの中で果ててしまう。
「悠里、お姉ちゃんののこと、ママって呼んでくれるんだ。いいわよ、お姉ちゃんがお母さんの代わりになってあげる。お母さんの代わりのママになってあげる。いくらでもママに甘えていいのよ、たっぷり可愛がってあげるから」
上気してピンクに染まった張りのある乳房を悠里さんの顔に押し当て、固い乳首を悠里さんの口にふくませて、ねとっとした声で琴音が囁きかけて、聞く者全ての気持ちをとろとろにとろかしてしまいそうな甘ったるい声で悠里さんの耳許に囁きかけて、優しく頬を撫でる。
だけど、おむつの中に精液を溢れ出させてしまった悠里さんは、いいようのない背徳感に苛まれ、琴音と目を合わせまいとして、ますます乳房に顔を埋めてしまう。
「恥ずかしがってるんだ、悠里。ママのおっぱいをちゅぱちゅぱしながら白いおしっこでおむつを汚しちゃったのが恥ずかしいんだ。でも、悠里はまだ小っちゃいんだから、おっぱいが欲しくなるのも、おしっこでおむつを汚しちゃうのも、ちっとも恥ずかしいことなんかじゃないんだよ。まだ小っちゃいんだから、おっぱいもおむつも当り前。恥ずかしがらなくても大丈夫。それよりも、お姉ちゃん、嬉しいんだ。ママ、とっても嬉しいんだ。だって、悠里、お姉ちゃん/ママのおっぱいを吸いながらおむつを汚しちゃったんだもん。これで悠里はお姉ちゃんの下の妹になってくれたんだよ。ママの娘になってくれたんだよ。いい子だね、悠里は。とってもいい子の妹で、とってもいい子の娘だね」
琴音は狂おしいほどの笑みを浮かべて、いかにもいとおしげに悠里さんの頬を指先でつついた。
それでも悠里さんからの返事はない。
それからの悠里さんは、絶頂の後の気怠い余韻と背徳感のせいで身じろぎひとつせず、ただ、琴音の乳首をぴちゃぴちゃと子猫みたいに舌の先で舐めるだけだった。
悠里さんが体を動かしたのは、それから十分ほど経ってからのことだった。琴音の乳房に顔を埋めたまま、けれど乳首から口は離して、右手をおそるおそる自分のお股に伸ばした。右手を伸ばして、おむつカバーのスナップボタンに指をかける。
それから悠里さんは右手で何やらもぞもぞやっていたんだけど、しばらく後、
「やだ。……やだよ、こんなのやだよぉ……」
と、よく耳を澄ましていないと聞き取れないほど小さな声で呟いて手の動きを止めてしまった。
「どうしたの、悠里?」
もの哀しそうな悠里さんの声に、気遣わしげな様子で尋ねる琴音。それこそ、小っちゃな妹の困った様子に心いためるお姉ちゃんや、幼い娘が泣き出しそうにしている様子に心乱す母親みたいに。
「……お、お尻のまわりがべとべとして気持ち悪いよ。脚の間もぬるぬるして気持ちわるくて……だから、お、おむつを外したいのに、……なのに、おむつカバーのボタンが外れなくて。……お、おむつを外してよ、お姉ちゃん。お願いだから、べとべとのおむつを外してよ、ママ」
琴音の顔を見ないようにまだ乳房に顔を埋めたまま、言葉に詰まりながら、けれど自分じゃどうすることもできないことがわかって、それで、今にも消え入りそうな声を絞り出して惨めな懇願をする悠里さん。
実は、悠里さんのお尻を包み込んでいるおむつカバーには、先端が或る特定の形をした棒状の器具を使わないと外れないような特殊なスナップボタンが使われている。器具を使わずに外すのは、絶対に無理。
え? どうして私がそんなことを知っているのかって?
だって、このおむつカバーを作ったの、私だもん。
考えてもみてよ。いくら小柄とはいっても、高校生の悠里さんのお尻を包み込めるような大きなおむつカバーなんて、どこにも売ってないでしょ。あ、ううん、病気の人とかお年寄りのために薬局なんかで売ってるのはあるよ。でも、それって、もっと味気ないデザインのでしょ? こんなに明るい色使いでこんなに可愛らしいデザインの大人用のおむつカバーなんかじゃないでしょ? だから、そう。私が作ったんだってば。
久美お姉ちゃんを赤ちゃん返りさせる計画を実行するために私が服飾文化研究部に入って縫製技術に磨きをかけて、それで、久美お姉ちゃんの体格にぴったりフィットのおむつカバーを作ったこと前に話したよね。で、その型紙を元にサイズを変更して、琴美の計画を手助けするために私が作ったんだよ、悠里さんのおむつカバー。うん、そう。作ったのは一枚だけじゃないよ。これからずっと悠里さんはおむつを当てて暮らすことになる。だから、洗濯の事とかを考えて、作ったのは十枚だったかな。で、もう少し詳しく言うと、十枚とも、久美お姉ちゃんのために作ったおむつカバーとお揃いのデザインに仕立ててあるんだ。でもって、久美お姉ちゃんが勝手におむつを外しちゃわないように特殊なスナップボタンを使っておむつカバーを作ったんだけど、そのあたりも悠里さんのとお揃いにしておいたんだ。
だから、どんなに頑張っても悠里さんが勝手におむつを外しちゃうような心配はないってわけ。
「そう。お尻のまわりがべとべとで気持ちわるいんだ。だから、おむつを外して欲しいんだ、悠里は。そうだよね。いやらい白いおしっこは普通のおしっこと違ってべとべとでぬるぬるで、おむつが吸収してくれなくて、いつまでもお肌に気持ち悪くまとわりつくんだよね。自分のおちんちんから溢れ出したいやらしいお汁でお尻を汚しちゃって、そのべとべとぬるぬるがいつまでもなくならないなんて、どれほど情けなくてどれほど惨めでどれほど泣き出したくなっちゃうことかしらね。――でも、駄目よ。おむつを外してあげることはできない」
それまでの慈愛に満ちた声とはまるで違った、なんだか背筋がぞくっとするような声で言ってから、琴音は首をゆっくり横に振った。
「おむつを外したら、せっかくの新しいベッドをおねしょで濡らしちゃうもの。ううん、ベッドだけじゃないよね。おねしょだけじゃなくておもらしまでしちゃう悠里だもの、新しいお部屋の床までびしょびしょにしちゃうに決まってる。だから、おむつは外してあげられないのよ」
琴音はきっぱり決めつけて、それから、わざと優しい声でこんなふうに付け加えた。
「外してあげることはできないけど、でも、おむつを取り替えてあげることはできるわよ。どうする?」
「……と、取り替えて……」
言われて一瞬は押し黙ってしまった悠里さん。でも、くぐもった声で短く答える。
「本当に困った子ね、悠里は。それだけじゃ何のことだかわからないでしょ? 相手の顔を見て、何を誰にどうして欲しいのか、ちゃんとお願いしなきゃ。おむつ離れできてなくても赤ちゃんじゃないんだから、そのくらいのことはわかるでしょ。それとも、まだお口のきけない赤ちゃんだったのかな、悠里は。それならそれで、赤ちゃんとして扱ってあげてもいいのよ?」
呆れたように言って、琴音、乳房から顔を離そうとしない悠里さんの顎先に指をかけて自分の方に顔を向けさせた。
「……と、取り替えて……僕のお、おむつ、取り替えて……」
強引に顔を上げさせられて、まるで何かに魅入られでもしたみたいに琴音の目から視線を外すことができずに、震える声で悠里さんは言った。
でも、それじゃ琴音は満足しない。
「駄目よ。『僕』じゃないでしょ? 悠里は女の子なんだから、自分のことは『私』って言わなきゃ。あ、ううん、小っちゃな女の子は自分のこと、名前で呼ぶんだっけ。そうね、その方が可愛いわね。それと、さっきの言い方じゃ、誰にお願いしているのかわからないよね。私の呼び方はお姉ちゃんでもママでもどっちでもいいから、さ、もう一度ちゃんとお願いしてごらん」
悠里さんの目を正面から覗き込んで琴音がぴしゃりと言った。
「……お、お願い。ゆ、悠里の……お、おむつを取り替えて……お願いだから、ママ……」
薄い胸板を弱々しく震わせながら悠里さん、屈辱のお願いを口にする。
「はい、よくできました。お仕置きをしなくても言って教えるだけでちゃんとできるなんて、悠里はいい子ね。おむつ離れはまだだけど、やっぱり、赤ちゃんなんかじゃなくてお姉ちゃんだわ。悠里が何をして欲しいのか、ママにもきちんと伝わったわよ」
琴音、ちょっぴり大袈裟に悠里さんを褒めそやす。
だけど、すぐに冷たい声でこんなふうに言い放った。
「でも、まだ駄目。悠里のお願いはわかったけど、まだおむつを取り替えてあげられないわね」
「ど、どうして? どうして、悠里のおむつ取り替えてくれないの? ね、どうしてなの、ママ? やだ、おむつ取り替えてくれなきゃやだ」
それこそ本当に小っちゃな女の子が母親におねだりをするように媚びた声を出してしまう悠里さん。
「だって、ばっちいんだもん。小っちゃな子のおしっこだったら汚いなんて思わないわよ。でも、今の悠里のおむつ、白いおしっこでべとべとに汚れちゃっているんだもの。そんな、いやらしいお汁で汚れたおむつなんて、ばっちくて、とても触れたものじゃないわよ」
冷たく決めつける琴音。
「そんな……だ、だって、でも……」
悠里さんの目が涙で潤んでしまう。
「だけど、そうね。確かに、いつまでもそのままじゃ可哀想ね。じゃ、今からママが言うことをよく聞いて、その通りにできたら取り替えてあげる。いい? ――小っちゃい子のおしっこだったら汚くないってママ言ったでしょ? だったら、ばっちくていやらしい白いべとべとのおしっこを普通のおしっこで綺麗にしちゃえばいいのよ。わかる? おしっこをして、いやらしいお汁をおしっこと一緒におむつを吸い取ってもらえばいいの。それなら、普通におしっこで濡れちゃったおむつだもの、ママ、ばっちいと思わないから取り替えてあげられるわよ」
ついさっきまでの冷たい声から一転、謎々でも楽しむかのような口調の琴音。
「で、でも……」
わざとおむつの中におしっこをするだなん。それに……。
「脱衣場でおもらしをしちゃってからまだあまり経ってなくて、おしっこが出ないのよね。だったら仕方ない、このままねんねするしかないわね。おねむの間におねしょしちゃって、それで白いべたべたを綺麗にするといいわ。そしたら、明日の朝、おむつを取り替えてあげる」
琴音、小さく小首をかしげて、なんでもないことのように言う。
でも悠里さんにしてみれば、大人の証である精液を幼児の下着であるおむつの中に溢れ出させてしまった屈辱の残滓にまみれたまま一晩を過ごすなんてこと、できる筈がない。
「いいわ、待ってなさい。いい物を持ってきてあげるから」
なんとも表現しようのない表情を浮かべる悠里さんの顔を見て、琴音はすっとベッドからおり立った。
「え……!?」
突然の琴音の行動に、悠里さん、ますます表現しようのない顔になっとしまう。敢えて例えるとしたら、それまで自分のそばにいた母親が急にどこかへ行ってしまおうとする時の小さな子供の顔みたいとでも言えばいいんだろうか、胸の中の寂しさがありありと表情に表われたような、不安いっぱいの顔。
「そんなに心配しなくても大丈夫よ、すぐに戻ってくるから」
悠里さんの表情を見て、いかにも満足そうな顔で琴音は言った。
待つほどもなく部屋に戻ってきた琴音は、オレンジジュースを入れたコップを左手に持っていた。
そうして、右手を悠里さんの背中の下に差し入れて上半身を起こさせ、持ってきたコップを手渡しながら
「水分を摂ればおしっこが出やすくなるわよ。だから、はい」
と、甘ったるい声で悠里さんの耳許に囁きかけた。
悠里さん、なんだかとろんとした目になって、小さくこくんと頷く。
頷いて、琴音から受け取ったジュースをこくこくと飲み干してしまう。
悠里さんの腰がぶるっと震えたのは、それから間もなくのことだった。
ベッドの傍らで悠里さんの様子を窺っていた琴音がそのことに気づいてベッドに上がり、悠里さんのすぐ側で膝立ちになった。そんなふうにすると、ちょうど琴音の胸と、上半身を起こしている悠里さんの顔が同じくらいの高さになる。
「出ちゃいそうなのね?」
ベッドの上で膝立ちになった琴音、悠里さんの頬を両手で包み込んで顔を上げさせて、不安そうにきょときょと動く瞳を覗き込んで言った。
それから、悠里さんの頬を包んでいた両手を離すと、部屋を出る時にはいったん元に戻しておいたブラウスの胸元を再び大きくはだけ、ブラの肩紐をずらして、左手を悠里さんの後頭部にまわしてぐいっと引き寄せ、ピンクの乳首をもういちど悠里さんの口にふくませる。
「いいわよ、ママのおっぱいをちゅぱちゅぱしながら出しちゃいなさい。今度は、白いべとべとのいやらしいおしっこじゃなくて、透き通ったさらさらのおしっこを」
「出ちゃう。ママ、悠里、おしっこ出ちゃうよ。おむつにおしっこ出ちゃうよ」
水分を摂ればおしっこをしたくなるとはいっても、それはあまりに唐突すぎる尿意だった。けれど、それが不自然な尿意だということに気づく余裕も、その時の悠里さんにはなかった。
それに加えて悠里さんには、どういうわけか、琴音の甘い囁き声が耳を通さずに心の奥深いところに直接囁きかけているように感じてならなかったのだけれど、それがどういうことなのかを気にする余裕もありはしなかった。
固い乳首を咥え、甘い囁き声に誘われるまま、うっとりした目をして悠里さんは下腹部の力を抜いた。
それに合せて、おむつカバーの股ぐりに琴音が右手をそっと差し入れる。
「いいのよ、出しちゃって。悠里はお姉ちゃんの小っちゃな妹で、ママの小っちゃな娘。おしっこでおむつを濡らしちゃっても恥ずかしくなんてないのよ。悠里が濡らしちゃったおむつはお姉ちゃんが取り替えてあげる。白いべとべとじゃなくなったおむつはママが優しく取り替えてあげる。悠里が何度おむつを濡らしても、そのたびに取り替えてあげる。だから、たくさん出しちゃおうね」
指先に伝わる生温かい感触を楽しみながら、なおも琴音は甘ったるい声で悠里さんの心に囁きかけるのだった。
*
――というような(悠里さんの新しい部屋に仕掛けておいた監視カメラで録画した)映像をスマホで見終った美音ちゃんが
「へーえ、悠里をすっかり手懐けちゃったんだ、琴音ねぇ。計画が始まって一週間しか経ってないのに、すごいね」
と感心しきりに言った後、ベッドの側に置いてある(汚れたおむつを入れておく)大ぶりのペールに目をやって
「でも、そのおかげで悠里が濡らすおむつが増えちゃったんだね。やれやれ、これからは毎日の洗濯が大変なことになりそう」
と、今度は苦笑交じりに言って、おどけた仕草で肩をすくめてみせた。
そんな美音ちゃんに琴音は
「ううん、洗濯は私がやっておくから心配しないで」
と応じるのだが、美音ちゃんは
「いいよ、今日は洗濯も料理も私がやるよ。だって、琴音ねぇ、まともに眠ってないんでしょ? いいから、そのまま横になっていてよ。それに、琴音ねぇがいなくなったら悠里が泣いちゃう」
と、体を起こそうとする琴音を制して、お構いなくとでもいうふうに軽く手を振ってみせる。
そんなふうに美音ちゃんが琴音を気遣うのも無理はない。だって、ジュースを飲んた後、悠里さんはずっと琴音の乳首をちゅぱちゅぱし続けていたんだから。ジュースを飲んですぐ後のわざとのおもらしの後始末でおむつを取り替えてあげる時は琴音の説得に応じて渋々おっぱいから離れてくれたんだけど、おむつを取り替えてもらってすぐにまた乳房にむしゃぶりついて、そのまま琴音が添い寝してお腹をぽんぽんと優しく叩いて寝かしつける時も、目を閉じて寝息を立て始めてからも、悠里さんは琴音のおっぱいをちゅぱちゅぱし続けていた。ぐっすり眠っているからもういいだろうと思って琴音がそっと体を退いた時も、意識はない筈なのに、気配を察して、乳首から口を離すまいとして顔を乳房に擦り寄せた上に両手で乳房を包み込むようにしてしがみついてくるほどだった。そんなわけで琴音は殆ど一睡もしていない状態だったんだから。
悠里さんの体を強引に引き離すことも難しくはなかった。だけど、眠っている間も自分の乳房を求める悠里さんを、乳首を口にふくんでいない間は今にも泣き出しそうにして不安そうな表情を浮かべる悠里さんを、琴音は拒めなかった。このままじゃ朝までちっとも眠れそうにないわねと胸の中で苦笑しつつも、琴音は自ら進んで悠里さんにおっぱいを吸わせてあげることにした。だって、悠里はお姉ちゃんの小っちゃな妹だもの。だって悠里はママの可愛い娘だもの。悠里さんの唇が動いて乳首を強く吸うたび、兄弟姉妹の結び付きから抜け出ようとしていた悠里さんへの怒りが薄まってゆくように感じられた。怒りの代わりに、悠里さんのことがいとおしくてたまらなく感じられてゆく。お姉ちゃんはここにいるよ。お姉ちゃんはどこにも行ったりしないよ。いつまでもおっぱいをちゅぱちゅぱさせてあげるよ。だから、悠里もどこへも行かないでね。ママはここにいるわよ。ママは悠里だけのママ。気の済むまでおっぱいをちゅうちゅうしていいのよ。だから、悠里は他の人のところへなんか行かないでね。
ジュースに混入した薬剤のせいで、悠里さんは夜中に三度おねしょをしてしまった。そのたびに琴音は悠里さんの体を引き離そうとせず、スマホで美音ちゃんを部屋に呼んで、悠里さんのおむつを取り替えてくれるよう頼んだ。これまでに何があったのかを手短に話す琴音の説明を聞いた美音ちゃんは琴音の依頼をいやがったりしないで、むしろ、うきうきでいそいそと悠里さんのおねしょのおむつを取り替えてあげていた。
そんなふうに夜を過ごして、朝になって琴音と悠里さんの様子を見にやってきた美音ちゃん、琴音の指示に従ってスマホを操作して録画映像を見て、琴音の簡単な説明だけじゃわかりにくかった事情もちゃんと知ることができたというわけだ。で、ということは、つまり、美音ちゃんだって夜中に三回も目を覚まして悠里さんのおむつを取り替えてあげたということになる。だったら、美音ちゃんだってお疲れの筈。なのに、まるで疲れた様子をみせることなく、それどころか、悠里さんにおっぱいを吸わせるために殆ど眠れなかった琴音の体を気遣うんだから、本当に健気でいい子だ。いいな、こんな姉妹関係。私の気持ちなんて知ろうともしなかった(赤ちゃん返りする前の)久美お姉ちゃんとは大違いだ。ほんと羨ましい。
「それにしても、こんなに琴音ねぇになついちゃうなんて。おねしょが始まっていつもおどおどして私たちと目を合せようとしなかった悠里にぃなのに、嘘みたい」
無意識のうちに琴音の乳首をちゅぱちゅぱし続ける悠里さんのやすらかな寝顔を見おろして、さも感慨深げに美音ちゃんは呟いた。
それから、瞳をきらりとさせて琴音に
「これって、やっぱり、琴音ねぇが手に入れたあの薬のせいなんでしょ? そろそろ教えてよ、あれが本当はどんな薬なのか。まさか、危ない薬なんかじゃないよね?」
と尋ねる。
「そうね。せっかくだから、どんな薬を悠里にのませたのか、きちんと説明しておこうかな。私が手に入れたのは、危ない薬なんかじゃないわよ。そんなじゃなくて、ちゃんと承認された薬なの。――世の中には、ちょっとしたことを大変な負担に感じて、そのストレスで心の病気になっちゃう人がいるのよ。そんな人たちの心を穏やかにするために開発された、精神に対して作用するする薬、つまり向精神薬の一種なんだけどね。ちょっとしたことを大変な負担に感じる人というのは、警戒心が強くて些細なことにこだわる傾向があるんだけど、時として、警戒心が昂じて猜疑心に転化しちゃうことがあって、そうなると、まわりの人たちが談笑しているだけなのに、それを自分のことを嘲笑しているんだって感じるようになったり、静かな場所でまわりの人たちが雰囲気を乱さないよう気遣って声をひそめて会話しているのを、自分の悪口をひそひそ囁きあっているんだって思い込むようになったりして、日常生活にも支障をきたすほどになってしまうことがあるの。そんな人たちの猜疑心を解きほぐして、警戒心を抑制するために開発されて、ちゃんとした治験を経た上でたくさんの国で承認された薬なのよ」
ベッドの縁に腰かけてこちらの様子を窺っている美音ちゃんに向かって、悠里さんに腕枕をしたままのせいで左腕がじんじん痺れているのを気にするふうもなく話し始める琴音。
「ただ、承認されて広く使われるようになった後でわかったことなんだけど、この薬にはちょっとした問題があったのよ。治験の時は被治験者に万一のことがないよう一回一回の服用量をとても厳密に管理していたから問題にはならなかったんだけど、いざ承認薬として医療現場に出回るようになると、服用量の管理が治験期間に比べると少し曖昧になっちゃうんだけど、この薬、のむ量が適正な服用量から少しでも逸脱すると効き目が極端に変わるってことがあとでわかって、結局は承認が取り消されて回収されちゃったの。ただ、効能が強力で即効性にも優れているから、一部の医療機関がこっそり在庫を隠し持っていたりしてね、それを融通してもらったのよ」
そこまで言って美音ちゃんの反応を確かめるように少し間を置いてから、琴音が先を続ける。
「もう少し詳しく説明すると、服用量が適正量よりも少ない場合はさほど問題にならないんだけど、少しでも多いと、薬をのんだ人の警戒心を極端に抑制してしまうという問題が発生することがわかったのよ。人は日常生活を送る上で、適度な警戒心を持たなきゃいけない。このことは美音にもわかるよね。簡単な例で言うと、警戒心がまるでなくなって、外出する時に戸締まりをしないなんてことになったら、自分から進んで泥棒を家に招き入れるようなものだし、ある程度の警戒心がなきゃ、外出先ですぐにいろんな事故に遭っちゃうでしょうね。そんな、日常生活を送る上で必要な最低限の警戒心までなくしちゃうのよ、服用量が少しでも多いと。それでも、薬をのむのを二日とか三日とかでやめればすぐにでも元に戻るんだけど、服用量が多いまま一週間ほどのみ続けると、警戒心が極度に抑制される結果として、他人に対する依存心が極度に肥大化しちゃうことになるの。警戒心が抑制されて日常生活を送る中で何度も何度も危険な目に遭って、自分自身による判断というものに自信が持てなくなって、何をするにしても周囲の誰かに頼るようになっちゃうってわけね。自分じゃ何も判断できなくて、誰かに頼りきりで、言われることに対してまるで警戒しない――極めて暗示にかかりやすい、周囲の誰かの言いなりになってしまう、自我がとても脆弱な、そんな人になっちゃうのよ、最終的には」
そう言って琴音、意味ありげな視線を悠里さんの顔に向ける。
「あ、そういうことか。よぉくわかったわ、琴音ねぇが悠里をあっさり手懐けちゃった経緯が。確かに、一応は危ない薬じゃないみたいね。一時的にでも世界中のたくさんの国で承認されたんだから。でも悠里ねぇは、食事に混ぜて、服用量をわざと間違って悠里にぃに薬をのませ続けた。で、そんなふうにして、一週間が経った。要するに、危ない薬じゃないけど、使い方が危なかった。ううん、わざと危ない使い方をした。そういうことよね?」
こちらも悠里さんの顔に視線を向けて、美音ちゃんが意味ありげに笑ってみせる。
「ぴんぽ〜ん、大正解。正解のご褒美に、もう少し教えてあげる。本来は精神に作用する薬なんだけど、服用量が極端に多いと自律神経にも影響が出るようになってね、膀胱の機能に乱れが生じて、尿意をちゃんと感じられなくなっちゃうのよ。薬を飲ませた最初の日からおねしょが始まったのは、つまり、それほどたくさんのませたからってこと。でも、そんなにたくさん何日ものませ続けたら精神も自律神経もぼろぼろになっちゃうから、二日目からは適正量よりもちょっぴり多めにしかのませてないわよ。わざわざたくさんのませなくても、効能の蓄積効果があって、自律神経への影響は当分続くからね。ただ、昨夜寝かしつける時には、ジュースに混ぜてたくさんのませちゃった。あのままだとなかなかおしっこが出なくて可哀想だったから。そのせいで、当分の間は日に何度もおもらしやおねしょをしちゃうことになるでしょうね。だから洗濯物も増えて美音にもいろいろ迷惑をかけることになっちゃうと思う。そのあたりのことはごめんね」
最初の方は冗談めかした口調だったけど、最後の方は美音ちゃんに対して申し訳なさそうな口調になる琴音。
けれど、そんな心配なんて無用とばかりに琴音ちゃんは
「そんなこと気にしないでよ。欲しくてたまらなかった妹のお世話ができることになったんだから、洗濯物が増えたって、却って嬉しいくらいなんだよ、私」
と、ころころ笑って明るい声で応じる。
「そう言ってもらえると心強いわ。じゃ、薬の効き目について最後にもう一つだけ話しておこうかな。あのね、私、薬の効き目だけで悠里を手懐けちゃったわけじゃないんだよ。例えば催眠術とかもそうなんだけど、誰かに催眠術をかけたとして、その人を操って犯罪をさせようとしても、そんなことは不可能なのよ。催眠術にかかった人が日ごろから心の中で絶対にしちゃいけないって思っていることや、あまりしたくないなと感じていることに対しては、どんなに意識を操られていても、無意識のうちに精神的なブレーキがかかるように人の心はできているの。私が手に入れた薬を使った場合もそれと同じで、願望の強弱はあるにせよ、薬を飲んだ人が日ごろから望んでいることにしか暗示効果は意味がないのよ。だから、悠里にぃが日ごろから今までの生活に満足していたのなら、少しくらい多めに薬をのませても、今みたいなことにはなっていなかった筈。なのに、悠里にぃは薬をのんだ最初の日からおねしょするようになっちゃったし、一週間が経った昨日には、私たちの言いなりで、末っ子の妹になっちゃった。それも、おむつ離れできない手のかかる小っちゃな妹にね。それって、つまり、悠里にぃが日ごろからそんなふうになりたいって心の中で思っていたということなのよ。私たちの妹になりたいっていう具体的な願望を抱いていたわけじゃないにしても、『誰かを庇護しなきゃいけない辛い立場』から『誰かに庇護される立場』へ逃げ出したいというような漠然とした欲求とかを日ごろから抱いていたんだと思う。――だから、長男だった悠里にぃを末っ子の妹・悠里に変貌させちゃったこと、後悔する必要なんてないのよ。私たちは、悠里にぃが心の中で漠然と思い描いていた望みを具体的な形として叶えてあげるお手伝いをしただけなんだから。私たちがしなきゃいけないのは、今の悠里にぃの心の中を慮ることなんかじゃない。私たちがしなきゃいけないのは、小っちゃな妹になった悠里が幸せになれるように育て直して躾け直してあげることなのよ。そのためには、悠里を甘やかすだけじゃ駄目。必要なら叱ってあげる覚悟も持たなきゃいけない。私が言っていること、美音ならわかってくれるよね?」
自分にとも美音ちゃんにとも、どっちにとも取れるように琴音は言って、悠里さんの髪を優しく撫でつけた。
そこへ美音ちゃんが悪戯めいた口調で
「甘やかすだけじゃ駄目よとか言っているくせに、悠里を一番甘やかしているのは琴音ねぇなんじゃない? ゆうべ寝かしつける時から今までずっとおっぱいをあげているままだし、映像の中じゃちょっぴり怖そうなことも言っていたけど、本当は甘々なのが見え見えだったし。言ってる本人が、叱ってあげる覚悟とやらはどうしちっゃたのかしらね?」
と冷やかす。
美音ちゃんに冷やかされて琴音は照れくさそうにしながら
「だって、仕方ないでしょ。悠里ったら、こんなに可愛いんだよ。こんなに可愛い悠里を叱るだなんて、そんなことできるわけないじゃない」
と、くすっと笑って可愛らしく舌の先をちろっと唇から出してみせる(てへぺろ)。
「やれやれ。大変な親馬鹿で、とんでもない姉馬鹿だこと。この調子じゃ、悠里には私が厳しくしてあげないといけないわね。すぐ上のお姉ちゃんの私が」
琴音の返答に美音ちゃんは大袈裟に呆れてみせてから、無心に琴音の乳首を吸う悠里さんの顔にとびきり優しい眼差しを向けて
「急におねしょをするようになっちゃって満足に眠れなかったのが、琴音ねぇのおっぱいを吸って気持ちが落ち着いてゆっくり眠れるようになったのね。琴音ねぇと私がこんなに騒がしくしても目を覚まさないなんて、よほど疲れていたんだね。いいわ、ゆっくりねんねしなさい。おねむの最中に汚しちゃったおむつはお姉ちゃんが優しく取り替えてあげるから、いい夢を見ながら好きなだけねんねなさい」
と静かな声で言ってから、琴音に向かって
「せっかく気持ちよさそうにねんねしている悠里を起こしちゃ可哀想だから、琴音ねぇも一緒にゆっくり寝てなさいね。さっきも言ったけど、今日は料理も洗濯も私がやっちゃうからさ。お昼ご飯ができたら起こしにくるから、可愛い悠里と一緒にいい夢を見てちょうだい」
と労いの声をかけたんだけど、そのすぐ後、何やら思いついたことがある様子で
「洗濯したおむつは庭の物干し場じゃなくて、二階のバルコニーに干した方がいいかな? だって、あそこの方が日当たりがいいからさ。可愛い悠里のお尻を包むおむつだもん、お日様の光をたっぷり浴びてほこほこに気持ち良く乾かしてあげたいよね」
と、自分のお下がりのナイティの裾から半分ほど見えているおむつカバーにちらと目をやって尋ねた。
それに対して琴音が
「そうね、おむつは二階のバルコニーの方がいいわね。よく乾くし、それに、あそこならお隣の朱美の部屋からよく見えて、私たちの計画が順調に進んでいることを知らせる合図にもなるし」
と少し考えて応じる。
それを聞いて軽く頷いた美音ちゃん、たくさんのおむつで重くなったペールを提げて部屋を出て行こうとしたんだけど、ふと足を止めると、くるりと振り返って
「それにしても琴音ねぇ、とっても感じやすいんだね。スマホの小さな画面でもはっきりわかるくらい、うっとりした顔してたもん、悠里におっぱいをあげている時」
と、からかいの言葉を投げかけた。
それに対して返ってきたのは、
「だって、悠里ったら、おっぱいを吸うのがとっても上手なんだもん。ちゅぱちゅぱ吸いながら、時々舌で乳首の先を舐めちゃったりしてさ。私、感じちゃって、今もお股がぬるぬるなんだよ。ママでお姉ちゃんの私なのに、悠里とお揃いのおむつのお世話になんなきゃいけないよね、これじゃ」
という、少し照れくさそうな声だった。
それで美音ちゃんが
「そうなんだ。そんなに気持ちいいんだ、悠里におっぱいを吸ってもらうのって。じゃ、そんな気持ちのいいこと私も経験してみたいから、今夜は私が悠里に添い寝してあげようかな」
と小さな声で呟くと、その声が耳に届いたんだろう、琴音から
「いいわよ、今夜は美音が添い寝してあげて。毎晩こんなじゃ私も体がもたないから、二人交替で添い寝してあげようよ。ただ、悠里におっぱいを吸われると本当に気持ちよくなってお股がぬるぬるに濡れちゃうから、下着を汚すのがいやなら、悠里のおむつを借りた方がいいかもよ、本当に」
という言葉が返ってくる。
「やだ。おむつだなんて、そんな恥ずかしいことできるわけないじゃない。おもらしっ子の悠里じゃないんだから」
冗談とはわかっていても、つい顔を赤らめて慌てて首を振っちゃう美音ちゃん。
そうして、二人がくすくす笑い合う。
二人の笑い声にも、悠里さんが目を覚ます気配は一向にない。
厚手のカーテン越しに夏の朝のお日様の光が柔らかく差し込むその部屋には、穏やかで幸福な時間がゆっくり流れていた。
*
琴音と美音ちゃんが一晩ごと交替で悠里さんを寝かしつけるのが日課になって一週間が経った日の昼前。
須藤家の玄関が何やら騒がしい。
実はその日、私と琴音それぞれの計画の進み具合をメールや電話だけじゃなく実際に会ってお互い確かめておきたいよねという話になって、私と琴音でいろいろ考えた結果、うちのお母さんが手料理を振る舞いたいから来てちょうだいって言ってるよという名目で琴音たちを我が家へ誘うことにした。
そんな経緯で、琴音と美音ちゃんが悠里さんを家から連れ出そうとしているわけだ。ただ、言葉巧みに悠里さんを部屋から連れ出したまではいいんだけど、なんとなくおかしな気配を察したんだろう、悠里さんが玄関から外へ出るのを嫌がって騒いでいるというのが、今の状況。
「や! 悠里、お出かけしない。お留守番してる!」
手首を掴んで強引に玄関の外へ連れ出そうとする美音ちゃんに対して、両足を踏ん張って抵抗する悠里さん。
ただ、今の悠里さんには、須藤家の長男としての矜持とか、生徒会筆頭副会長としての威厳なんて微塵も見当たらない。そこにいるのは、お姉ちゃんの言うことに逆らって駄々をこねる幼女でしかなかった。お姉ちゃんの言うことを嫌がる理由をきちんと説明するわけでなく、たどたどしい幼児言葉で金切声をあげ、コットンのトレーナーにデニムのミニスカート、明るい色遣いの星の柄が可愛いソックスという装いで盛んにいやいやをしながら玄関の外へ連れ出されまいとして足を踏ん張る幼女。体格や服装で判断するなら『少女』と呼ぶのがふさわしいのかもしれないんだけど、デニムのスカートの裾から見え隠れしているのが普通のショーツじゃなくてぷっくり丸く膨らんだ熊さん柄のおむつカバーだから、どうしても『幼女』に思えてしまう。
この一週間、琴音や美音ちゃんに寝かしつけられるたび、おむつカバーの上からおちんちんをいじられて白濁したいやらしいお汁でお尻のまわりをべとべとにしては、その気持ち悪さから逃れるために、わざとおもらしすることを強要されていた。そのせいで、いつの間にか、おむつにおしっこをするという行為が第二の自我に刷り込まれて、夜のおねしょのおむつだけじゃなく、昼間もおもらしのおむつが要るようになってしまったのだった。
「まだおむつも外れていない小っちゃな子が一人でお留守番なんてできるわけないでしょ。いつまでも駄々をこねてないで、美音お姉ちゃんにお手々を繋いでもらいなさい。お隣のおばちゃま、とってもお料理が上手だから、みんなでご馳走になりましょうよ」
横合いから琴音が宥める。
だけど悠里さん、
「やだ! 悠里、お出かけしない。お隣ん家、行くの、や! 久美ちゃんと会うの、恥ずかしい。だから、やだ。やだったら、やなの……」
と、それまでよりも尚いっそう抵抗するんだけど、途中から声が少しずつ小さくなって、しまいには聞き取れないほどになっちゃう。
悠里さんが我が家を訪れるのをこんなにも拒んでいるのは、今の自分の恥ずかしい姿を誰かに見られるのに耐えられないからだ。須藤家の長男であり生徒会筆頭副会長の悠里さんが今や琴音と美音ちゃんの妹、それも、おむつも外れていない小っちゃな妹に(琴音との関係で言えば、幼い娘に)なり下がっちゃった、その恥ずかしい姿を他人の目にさらすなんて、できる筈がない。しかも、我が家を訪れたりしたら、よく見知った私やお母さんや佳美お姉ちゃんに、その恥ずかしくてたまんない姿を間近でまじまじと見られちゃうんだ。玄関から連れ出されまいとして悠里さんが両足を踏ん張るのは当り前のこと。悠里さんの気持ち、私にもよくわかる。
ただ、でも、これはちょっとおかしいんじゃないかなと思うところもある。だって、いくら小柄で美音ちゃんよりも非力だといっても、本当は悠里さん、高校三年生の男の子なんだよ。だったら、たとえ力ずくで美音ちゃんの手を振り払うことはできないとしても、もっと年長の男の子らしく、「いつまでもそんなことをしてるんじゃない。さっさと手を離しなさい」とがつんと言ってやればよさそうなものじゃない? なのに悠里さん、すっかり小っちゃな女の子になっちゃった見た目のまんま、たどたどしい幼児言葉で駄々をこねるだけ。なんだか、とてもじゃないけど、外出を(そして、我が家を訪れるのを)本気で拒んでいるんじゃないかもって訝しがられても仕方ないよね?
だけど実は、このことには、それなりの理由があったりするんだ。で、それなりの理由というのには、琴音がこっそり悠里さんにのませているあの薬が関係している。琴音が(わざと)服用燎を多めにのませているせいで、悠里さんは日常生活を送る上で必要な最低限の警戒心までなくしちゃってる。更にそこに薬の暗示効果まで加わって、今の要理さんは琴音や美音ちゃんの言うがままになっちゃっているわけだ。でもって琴音と美音ちゃんが悠里さんのことを自分たちの小っちゃな妹として扱っているものだから、悠里さんの、なんていえばいいのかな、無意識領域とでも表現すればいいんだろうか、要するに心の奥深いところに、薬を使った琴音の暗示の繰り返しとひそかに悠里さんが抱え持っていた願望を胚芽として、本来の自我とはまた別の『須藤家の三姉妹の甘えんぼうの末っ子』としての、第二の自我とでもいうようなものが芽生えて、『須藤家の長男』としての本来の自我とせめぎ合うようになっちゃったんだね。で、本当は強固でなくちゃいけない本来の自我が、薬のせいで時が経つにつれてどんどんへなちょこになっていって、今じゃもう、第二の自我の方がだいぶ優勢。もう少し詳しく言うと、基本的な行動様式とか、情緒とか、感情とか、自分じゃ意識しなくても自然と体や心の動きとして表われる部分の大半が第二の自我と繋がってしまって、本来の自我と結び付いているのは、理性とか判断力とかの、意識してようやく表われる部分しか残っていない状態という有り様。
いや、理性とか判断力とかが残っているんだったらいいんじゃない?とか思われるかもしれないけど、実は、それは大間違い。理性とか判断力とか、あまり役に立たないんだな、これが。ま、何人かで一つのことを成し遂げるとか、日常生活をそつなく送るとかにはとても重要で役に立つんだけど、でも、一人の人間の中で他の部分と比較するということになると、これが駄目。こいつら、実は雑魚キャラだったりする。簡単に言っちゃうと、『傍観者』でしかないわけよ、理性とか判断力とかいうのは。普通なら、何か行動を起こそうとする時、その行動が自分に害を及ぼさないか、周囲に害を及ばさないか、自分に得になるのかならないのかというのを理性とかが判断して、それから実際の行動に移るということになるんだけど、今の悠里さんみたいに基本的な行動様式とか感情とか情緒とかが第二の自我に繋がっている状態だと、本来の自我と繋がっている理性がなんらかの判断をくだしても、その判断を第二の自我に拒絶されちゃったら、結局のところ何も行動は起こせない。つまり、理性とかの判断の結果は、実際の言動には全く反映されないってわけ。そう、結局のところ、元は自分の容れ物だった肉体が自分の意図するところとはまるで別の行動を取っているのをただ眺めていることしかできないというわけだ。しかも、本来の自我と相反する行動を体が取るたびに苛立ちとか悲しみとか恥ずかしさとか屈辱といった負の情動反応だけはありありと感じながら。
でもって、須藤家の三姉妹の甘えんぼうの末っ子としての第二の自我と結びついている基本行動様式や情緒や感情に従って、琴音や美音ちゃんの言いなりの悠里さんの体や心は動くから、知らず知らずのうちに悠里さんは、小っちゃな女の子そのままに振る舞ってしまうということになる。でも、同時に、そのことに対して理性や判断力に基づく負の情動反応として羞恥を感じるから、小っちゃな女の子に完全になりきることもできなくて、時おり、今みたいに琴音や美音ちゃんの言うことに逆らって駄々をこねちゃうことがあるというわけなんだ。
本来の自我のせいで今は玄関の外へ連れ出されまいとして両足を踏ん張っているものの、それが長続きすることは絶対にない。だって、体の動きは第二の自我の支配領域だし、いくら恥ずかしがっても、ちょっと前までは漠然とした欲求にすぎなかったのが繰り返される暗示によって具体的な願望になっちゃった『小っちゃな女の子として振る舞おうとする心の動き』をいつまでも抑え込むことはできないんだから。
考えようによっちゃ、理性も判断力もなくしちゃった方が、よほど楽かもしれない。身も心も小っちゃな女の子になりきって、琴音ママや美音お姉ちゃんに可愛がってもらって、あれこれとお世話してもらっている方が、へんに羞恥を覚えるよりも、ずっと楽かもしれない。
でも、実際に悠里さんが理性も判断力もなくして恥ずかしさを感じなくなったとしたら、ちょっぴり困っちゃう人たちがいるんだよね。で、それが誰かというと、琴音と美音ちゃんだったりする。えっ?と思ったでしょ。意外でしょ。でも、事実なんだよ。理性と判断力を失って悠里さんが羞じらいの表情をしめさなくなったら、二人は確実に困ってしまう。正確に表現すると、物足りなくなってしまう。女の子の格好でお出かけすることが恥ずかしくてお姉ちゃんたちに逆らう悠里さんを相手に、二人は『駄々をこねてばかりの妹/娘を叱って躾ける』育児の楽しみを味わっているんだよ。もしも悠里さんがとっても物わかりがよくて二人の言うことに素直に従うばかりじゃ、お人形遊びをしているのと同じだもの。意思のない人形なんかじゃない、自分の判断で動く人間を相手にするからこそ、刺激があって面白くて夢中になれるんだよ。厳密に言うと、育児の楽しみだけじゃなくて、人が本来的に胸の奥底に抱え持っている支配欲を満足させたり、実の兄を年端もゆかぬ小っちゃな妹扱いすることで背徳的な悦びを覚えたり、肉体的にも精神的にも相手をいたぶることで加虐的な悦びを感じたりと、普段の生活じゃあまり得られない異形の感情を味わっている二人なのに、悠里さんがすんなり小っちゃな女の子になりきっちゃったら、そんな禁断の蜜の味を楽しめなくなってしまうんだから。
あ、説明が長くなっちゃったね。
ま、というわけでそれまで足を踏ん張っていた悠里さんなんだけど、いつまでもこのままじゃ埒が明かないと判断した琴音が
「ふぅん。悠里、おっぱいが欲しくないんだ。ママも美音お姉ちゃんも、いつまでも駄々をこねる聞き分けのわるい子にはおっぱいなんてあげたくないんだけど、それでいいんだ?」
と、少し意地悪な声で言った途端、
「や、やだ。悠里、おっぱい欲しい。ママと美音お姉ちゃんのおっぱい欲しいの!」
と感情をあらわにして喚いたかと思うと、そのすぐ後には
「……悠里、ママと美音お姉ちゃんのおっぱいがいいの。おっぱい、ないないなんて、やなんだから……」
と力なく声を震わせ、
「ふ…ふぇ、ふぇ〜ん、ぅぇ〜ん……」
と泣きべそをかいて、最後にはとうとう手放しで泣きじゃり始めちゃう。
薬のせいで第二の自我が形成される、まさにその最中に琴音と美音ちゃんがが悠里さんにおっぱいを吸わせて寝かしつけるようになったせいで、第二の自我の中で感情を司る部分が乳房や乳首やおっぱいといったものに関連する事柄に異様に敏感になっちゃって、感情を抑えられなくなってしまうんだ。ここ一週間ずっと悠里さんにおっぱいを吸わせて寝かしつけていた琴音と美音ちゃんがそのことに気づかないわけがない。だから二人とも、悠里さんが駄々をこねて手をつけられない状態になった時は、お尻をぶつといった肉体的なお仕置きではなく、こうやって心理的なお仕置きによって悠里さんをおとなしくさせるのが常態化していた。
しかも二人が役割を分け合って、例えば今みたいに琴音がおっぱいを拒絶して悠里さんの感情を掻き乱してから、その少し後に美音ちゃんが
「ほら、いつまでも駄々をこねるから、とうとうママに叱られちゃった。でも、お姉ちゃんは、悠里が本当はとってもいい子だってこと、ちゃんと知っているよ。いい子だけど、ずっとお家にいたのに急にお出かけするよって言われてびっくりしちゃったんだよね。赤ちゃんじゃないのにおむつが外れてなくて、スカートの裾からおむつカバーが見えちゃうかもしれないなんて、とっても恥ずかしいよね。だから、本当はいい子なのに、駄々をこねちゃったんだよね、ママはあんな厳しいこと言っているけど、お姉ちゃんは悠里の味方だよ。ママのおっぱいをもらえないんだったら、今夜はお姉ちゃんが添い寝してあげる。お姉ちゃんが悠里におっぱいをあげる。だから、そんなに泣かなくていいんだよ」
と、とびきり優しく言って聞かせて体をそっと抱き寄せるといったことをして、二人に対する悠里さんの依存心をますます昂じさせる手段まで駆使して。
そんな二人に悠里さんが逆らい続けられる筈がない。
「……美音お姉ちゃん、今夜、悠里と一緒にねんねしてくれるの? ……ママは駄目って言ったけど、美音お姉ちゃんのおっぱい、悠里、ちゅうちゅうしていいの?」
と涙声ですがるように尋ねて、美音ちゃんの胸元に顔を埋めて甘えちゃう悠里さん。
「いいよ。お姉ちゃんのおっぱい、好きなだけちゅうしちゅうしていいんだよ」
すがりつく悠里さんの背中を優しく撫でさすりながら美音ちゃんは言って、少しだけ間を置いて、こんなふうに悠里さんの耳許に囁きかける。
「でも、ママが駄目って言ってるのにお姉ちゃんが勝手におっぱいをあげたりしたら、お姉ちゃんがママに叱られちゃうよね。だから悠里、ママにごめんなさいしておこうよ。悠里、何もわるいことなんてしてないよ。ちょっびりびっくりしちゃって恥ずかしがっていただけなんだから。でも、ママにごめんなさいしておこうね。お姉ちゃんがママに叱られないように」
そんな、幼い子供の自尊心を上手にくすぐりながら結果として保護者に向かって謝罪させるというみえすいたやり方に、本当は高校三年生なのに幼女としての第二の自我に言動を操られるようになってしまった悠里さんは易々とのせられて
「うん。悠里、ごめなさいする。美音お姉ちゃんがママに叱られるの、悠里、や。だから、ママにごめなさいする」
と、美音の胸元に顔を埋めたまま上目遣いに言ってから、視線をおそるおそる琴音の方にに向けて
「……こめんなさい、ママ。悠里、駄々をこねて、ごめんなさい。……悠里、ママと美音お姉ちゃんと一緒にお出かけする。悠里、美音お姉ちゃんにお手々つないでもらって、お隣ん家、行く。だから、ごめんなさい」
と、媚びを売るような口調で声を震わせてごめんなさいを言っちゃう。
本当は高校生の男の子が、五つ年下の妹が小学生だった頃のお下がりの服を着せられるだけでなくスカートの裾からおむつカバーを見え隠れさせる恥ずかしい姿でお出かけさせられる羞恥と屈辱。それに加えて、偽りの母親や偽りの姉のおっぱいを口にふくむことができなくなるといった理由で、母親に叱られて泣きじゃくりながらごめんなさいをする幼女そのままに許しを乞う恥辱。だけど、そんな恥辱に対して、今や、本来の自我ができることは僅かだ。幼女の装いで家の外へ連れ出される羞恥と屈辱に抗うために両足を踏ん張って抵抗してみても、その姿は傍目には、聞き分けのよくない幼女が駄々をこねているようにしか映らない。美音ちゃんに甘えて胸元に顔を埋め、おそるおそる琴音にごめんなさいをする悠里さんの目の下と頬が恥辱で微かに赤く染まるのだけれど、第二の自我に操られる悠里さんの無意識の言動に対して本来の自我が存在感をしめすことができるのは、そんな僅かなことでしかなかった。
「いいわ。今は美音お姉ちゃんに免じて許してあげる。でも、これからもずっと美音お姉ちゃんが味方してくれるかどうかなんてわからないんだから、日ごろからいい子でいなきゃ駄目よ。本当はママだって可愛い悠里におっぱいをあげたくてたまらないのよ。だから、ママと美音お姉ちゃんの言いつけに素直に従う、聞き分けのいい子でいなさいね」
美音ちゃんにすがりついたままごめんなさいをする悠里さんに、琴音は穏やかな声で言った。
そうして、こくんと頷く悠里さんの頭を優しく撫でながら
「きちんとごめんなさいできたから本当はこれ以上は聞かなくてもいいんだけど、これからのこともあるから、やっぱり聞いておくわね。悠里はどうしてお出かけをあんなに嫌がっていたの? 小っちゃい子はお出かけが大好きな筈なのに」
と、その理由を充分すぎるほど知っているくせに、わざと不思議そうな顔をして、誘いをかけるように尋ねる。
「……だって、小っちゃい女の子の格好でお外へ行くの、恥ずかしいんだもん。悠里、ほんとは小っちゃい女の子なんかじゃないのに」
琴音の問いかけに、悠里さんは伏し目がちに、琴音の視線から逃れるために美音ちゃんの胸にますます深く顔を埋めておどおどした声で答えた。
それが、今の本来の自我にできる精一杯の反応。
「あらあら、おかしなことを言うのね、悠里ってば。いい? 赤ちゃんじゃないのにおむつだなんて、せいぜい保育園の年少さんくらいまでなのよ。それで、保育園の年少さんっていったら、お隣の早苗がそうだよね。だから、悠里は早苗ちゃんと同い年なのよ。でも、悠里は保育園の年長さんにしちゃ体が大きくて、年長さん向けにお店で売っているお洋服が着れないから、美音お姉ちゃんが小学生の時のお下がりを着せてあげているのよ。つまり、悠里は、本当よりもずっとお姉さんらしいお洋服を着ているってことになるの。なのに、小っちゃい女の子みたいで恥ずかしいだなんて、おかしな悠里」
悠里さんの返答に、琴音がくすっと笑う。
そこへ美音ちゃんが、悠里さんの背中をとんとんと優しく叩きながら
「あ、そんな言い方しちゃ駄目じゃない、琴音ねぇったら。小っちゃい子はお姉さんに憧れて、自分も早くお姉さんになりたいって思って、ついついお姉さんぶっちゃうんだよ。悠里のそんな気持ちも考えてあげないなんて、お母さん失格だよ、琴音ねぇったら。――ね、悠里もそう思うでしょ?」
と、琴音と目配せを交わしつつ、最初の方は琴音をたしなめるように言って、後の方は悠里さんに同意を求めた。
同意を求められて悠里さんは何も答えられずにいたんだけど、しばらくすると上目遣いに琴音と美音ちゃんの顔をちらちら見比べながら、躊躇いがちに
「……あ、あのね、悠里、難しいことはわかんない。わかんないけど、ママ、お母さん失格なんかじゃないもん。悠里のママ、とっても優しいママだもん。悠里、ママ、大好きだもん。――悠里がいけないんだもん。悠里、保育園の年少さんなんだよ。お隣の早苗ちゃんと同い年の、保育園の年少さんなんだよ。なのに、美音お姉ちゃんが小学校の時のお洋服を着せてもらって、お姉さんみたいにしてもらったのに、小っちゃい女の子みたいで恥ずかしいって、悠里、駄々こねちゃって。悠里がいけないんだよ。だから、ママはいけなくなんてないの!」
と、ちょっぴりムキになって琴音を庇う。
それに対して琴音と美音ちゃんはもういちど目配せを交わし合ってから、美音ちゃんが
「あらあら。さっき、お姉ちゃんは悠里の味方をしてあげたんだよ。なのに悠里ったら、お姉ちゃんじゃなくてママの味方をしちゃうんだ。本当に悠里はママ大好きっ子なんだね。ま、でも、保育園の年少さんっていったら、大抵はそうだよね。悠里がママ大好きっ子でママの味方をするのも仕方ないよね。だって、保育園の年少さんだもん。いいわ。だったら、大好きなママに抱っこしてもらいなさい」
と言って、悠里さんを琴音の方に押しやった。
「ありがとう、悠里。ママの味方をしてくれてありがとう。それに、自分がいけないんだよって言えて、とってもお利口さんだよ、悠里は。そんな悠里のこと、ママも大好きなんだから」
美音ちゃんがこちらへ押しやった悠里さんの体を抱き寄せて、琴音は、悠里さんの顔を自分の胸元に埋めさせた。
「ママ、大好き。悠里、ママも美音お姉ちゃんも大好き」
悠里さんは琴音の胸に顔をなすりつけて言って、少し照れくさそうに
「それとね。悠里、同い年の早苗ちゃんとお友達になりたい。お友達になって、一緒に遊ぶの。ね、早苗ちゃんもおむつなのかな。悠里と同じで、まだパンツじゃなくておむつかな」
と言って、ぱっと顔を輝かせた。
輝く顔の頬が少しだけ赤く染まっている。高校生の男の子としての自我は、その羞じらいの色に微かに名残を留めているだけだ。
*
さて、そんなふうにして騒ぎが収まって玄関から外へ出た悠里さんだけど、実際に家の外へ連れ出されると、何か新しい行動を取るたびに(ある意味、お節介なことに)本来の自我が羞恥を覚えてしまって、やっぱり足が進まないといった状態に戻っちゃって、なかなか門扉まで辿りつけそうになかったりする。
と、なかなか歩みが進まない悠里さんの様子に、とうとう美音ちゃんが立ち止まって、繋いでいた手を離すと、悠里さんの後ろにすっとまわりこんで、後ろから悠里さんの手首を掴んで、そのまま両手を上げさせてしまう。
「え……?」
美音ちゃんが何をしようとしているのかわからなくて不安にかられた悠里さん、おどおどした様子で後ろを振り返ろうとするんだけど、それを美音ちゃんが
「駄目よ、ちゃんと前を向いてなきゃ」
と、優しい声のくせに、なぜとはなしに有無を言わせない口調で制して、それから、琴音に向かって

「ほら、琴音ねぇ、早く撮ってよ、長男だった悠里にぃが末っ子の三女になった記念の写真。私が小学生の時に着ていた服もこんなによく似合っているんだから、可愛らしく撮ってあげてよね」
と声を弾ませる。
それを聞いた琴音が、にっと笑って軽く頷き、着ている夏用の制服のポケットからスマホを取り出して二人に向けた。
「や、やだ。こんな格好、写真に撮っちゃやだ」
悠里さんは慌ててその場から逃げようとするんだけど、後ろから美音ちゃんに両手を掴まれていて、どうすることもできない。
「ほら、そんなに暴れないの。せっかく可愛いところを撮ってもらうんだからおとなしくしてなさい」
美音ちゃんがそんなふうに悠里さんを宥めている間にも、シャッター音が何度も耳に届く。
「やだったら、や。悠里、お写真、きらい」
なおも美音ちゃんの手から逃れようとして悠里さんが体をくねらせるんだけど、そのたびにスカートの裾がふわふわ揺れて、熊さん柄のおむつカバーが半分ほど見えちゃう。
「あ、いかにも小っちゃい子らしくて、そういうポーズもいいわね。じゃ、どうせだから、こんなふうにして、と」
それまでは悠里さんの顔の高さにスマホを構えていた琴音だけど、スカートの裾からおむつカバーが見えたり隠れたりしている様子に、すっと腰をかがめて、これまでよりも低い位置から少し仰ぎ見るような角度でスマホを構え直す。
こうすると、見え隠れしていた可愛いおむつカバーが正面からばっちりだ。
「やだ、そんなの、や!」
悠里さんが金切声をあげて体を捻る。
と同時に美音ちゃんが、それまで掴んでいた悠里さんの手を離した。
悠里さん、自由になった両手でスカートの裾を急いで押さえる。
それは、パンツが見えても気にしないくらいの年ごろの幼女がお姉ちゃんぶって羞じらいのポーズをとる時みたいな、あどけなくて、ちょっぴりぎこちなくて、そうして、背徳感たっぷりの姿だった。
もちろん琴音は、その可愛らしい姿もスマホに収めることを忘れない。
「ママが写真を撮ってあげている間も随分と恥ずかしがっていたわね。お家の中じゃママと美音お姉ちゃんと一緒にお隣のお家へ行くんだって言っていたのに、お出かけするの、また恥ずかしくなっちゃったのかな?」
何枚も写真を撮り終えてから二人の方に歩み寄って、琴音が悠里さんに話しかける。
言われて、悠里さんは小さくおずおずと頷いた。
すると琴音が
「そりゃ、恥ずかしいよね。本当は高校三年生の男の子で学校じゃ生徒会の役員まで務めている悠里にぃが美音のお下がりを着て、スカートの下にはおむつを当てているんだもん、恥ずかしくないわけないよね」
と、悠里さんの心を抉るように冷ややかにずけっと言う。
それに対して顔を真っ赤にするだけで何も言い返せない悠里さん。ぎゅっと目を閉じて顔を伏せてしまう。
だけど、琴音はすぐに口調をがらっと変えて、寸前の意地悪な声が嘘みたいな優しい声で
「でも、これを見てごらん」
と言って、撮ったばかりの写真が映ったスマホの画面を悠里さんの目の前に差し出した。そうして、
「ほら、これと、これも。あ、これもよく撮れてるよね」
と声を弾ませて、画面に映る写真を次々に切り替えてゆく。
自分の恥ずかしい姿が映るスマホなんて見まいとするんだけど、琴音の言葉に抗いきれずに、ついつい画面に目をやってしまう悠里さん。
「ね? どれも、とっても可愛らしく撮れているでしょ?」
最初は渋々スマホに視線を向けていたのが、次第に悠里さんが食い入るように画面を凝視するようになってゆく様子に、琴音はいっそう優しい声で語りかけた。
思わず悠里さんがこくんと頷く。
そこへ琴音は
「でもね、可愛らしく撮れているのは、スマホの性能がいいからでもないし、ママの撮り方が上手だからでもないんだよ。美音お姉ちゃんのお下がりのお洋服が可愛いからっていうのはちょっとはあるかもしれないけど、でも、それも、ほんのちょっとだけ。画面に映っている悠里が可愛いのは、ここにいる本物の悠里が可愛いから。ただ、それだけの理由なんだよ」
と、これ以上はないくらい優しい声で言い聞かせる。
「……可愛い? 悠里、可愛い?」
顔を伏せたまま、躊躇いがちに、けれどちょっぴり明るい声で聞き返す悠里さん。
「可愛いよ、悠里は。ママのご自慢の娘だもの、世界一可愛いに決まってる。こんなに可愛い女の子、どこにもいないよ」
琴音は『可愛い』を何度も繰り返し言ってから、悠里さんのほっぺを両手でそっと包み込んで顔を上げさせ、不安そうにきょときょと揺れる瞳を正面から見据えて
「こんなに可愛い子が男の子なわけないでしょ。どこからどう見ても、悠里は可愛い女の子。私の可愛い愛娘。まだおむつが外れないのはちょっぴり困るけど、そんなのも可愛い保育園の年少さん。お隣の早苗ちゃんとお友達になりたがっている、明るくて元気いっぱいの女の子。お笑顔がとってもよく似合う小っちゃな女の子なんだから」
と心に滲み入るような声で『可愛い』を更に何度も繰り返して、最後に
「だから、ママと美音お姉ちゃんと一緒にお隣のお家へ行こうね。早苗ちゃん、悠里が来るのをまだかまだかって待っているよ。だから、もういちど美音お姉ちゃんにお手々を繋いでもらって、さ、行きましょう」
と言って、たっぷり当てたおむつのせいで丸く膨らんだおむつカバーの上から悠里さんのお尻をぽんと叩いた。
「うん。悠里、美音お姉ちゃんにお手々繋いでもらって、お隣ん家、行く。お隣ん家で早苗ちゃんと一緒に遊ぶ。お隣ん家のおばちゃまとおねえちゃま、悠里のこと可愛いって言ってくれるかな。ママみたいに、可愛いって言ってくれるかな」
うっとりした表情で瞳をとろんと潤ませて悠里さんは呟いて、美音ちゃんに手を繋いでもらう。
第二の自我がますます強固になり、本来の自我が次第に希薄になってゆく。それを止めることは、もう誰にもできそうにない。ううん、そもそも、それを止めようと思う人なんて一人もいないんだ。
*
来客を告げるチャイムが鳴った。
誰が来たのか、インターフォンのカメラで確認するまでもない。
いそいそと玄関のドアを押し開けると、きちんと高校の夏用の制服を着た琴音と、こちらも中学校の制服に身を包んだ美音ちゃんが立っていた。そして、美音ちゃんの制服の袖口をきゅっと掴んで二人の後ろに隠れておどおどしている悠里さん。あ、ううん。もう『悠里さん』なんかじゃないや。須藤家の末っ子の『悠里ちゃん』だ。
「よく来てくれたわね。それにしても、うちへ来るのにわざわざ制服だなんて、ちょっと堅苦しすぎるんじゃない?」
私は、琴音と美音ちゃんの顔を見比べて、少しばかり呆れたように言った。
「だって、おば様にはいつも会っているけど、佳美お姉さんとは久しぶりだもん。それに、佳美お姉さんは私たちと同じ高校の卒業生、つまり、学校の先輩ってことになるでしょ。だから、失礼のないようにと思ってね」
私の呆れ声に、それらしい理由を付けて琴音が答える。
でも本当は、そんな理由でわざわざ制服を着てきたんじゃない。制服を着ている本当の理由は、高校生男子から幼女への悠里ちゃんの変貌ぶりを私の家族に強く印象づけるためだ。琴音と美音ちゃんがきちんと高校と中学校を着ているのに対して、制服なんてまだ早い小っちゃな女の子に悠里ちゃんがなっちゃったことを私のお母さんや佳美お姉ちゃんに一目でわかってもらうためのちょっとした演出。
で、そんな演出の効果はすぐに表われた。
私よりも少し遅れて玄関にやって来たお母さんと佳美お姉ちゃん、内気で引っ込み思案の小っちゃな女の子さながらに制服姿の二人の後ろに隠れている悠里ちゃんを目にするなり
「あらあら、この子が悠里ちゃんですって? 終業式の日の朝には顔を会わせたから、それからまだ二週間ちょっとしか経ってないのよね。なのに、そんな短い間に随分と可愛らしくなっちゃって。おばちゃま、びっくりしちゃった」
「私は里帰り出産でこっちへ帰ってきてからまだ一度も顔を見てなかったから、会うのはだいぶ久しぶりになるわね。それにしても、こんなに変わっちゃうなんてね。うふふ、とっても可愛いわよ、悠里くん、あ、ううん、悠里ちゃん」
と、口々に悠里ちゃんの可愛らしさを褒めそやすんだけど、二人がそうするには、琴音と美音ちゃんが制服姿できっちりしているのに比べて、悠里ちゃんが美音ちゃんのお下がりの可愛い遊び着姿なのも大いに影響しているに違いない。だって、高校生の男の子としては小柄な悠里ちゃんにしても、中学一年生の女の子としては大柄な美音ちゃんと比べて、極端に背が低いわけじゃない。確かに美音ちゃんの方が背が高いけど、二人の差は十センチもない筈だ。なのに、美音ちゃんが制服で、悠里ちゃんがいかにも少女っぽい遊び着のせいで、実際よりも悠里ちゃんの体が小さく見えて、それが悠里ちゃんをより幼く可愛らしく見せているというわけだ。
でも、ただ、それにしても、古くから親しくしている隣家の長男で高校三年生の男の子が、コットンのトレーナーにデニムのミニスカートという格好で、本当なら妹である琴音と美音ちゃんに頼りきりで二人の背中におどおど隠れちゃうような小っちゃな女の子そのままに振る舞うようになっちゃったことを訝しむどころか、可愛い可愛いと目を細めるだなんてことを私のお母さんと佳美お姉ちゃんがしてしまうのを不思議に思う人は多いんじゃないかな。
というわけで、そのあたりのところも説明しておこう。
とは言っても、難しいことなんて、これっぽっちもないんだけどね。
だって、考えてもみてよ。久美お姉ちゃんが赤ちゃん返りしちゃっても(いや、実は私が強引に赤ちゃん返りさせちゃったんだけどね、正確に言うと)、それをすんなり受け容れちゃうような二人なんだよ? 「育児の楽しみがずっと味わえるからいいわね」とか「早苗ちゃんたちが早坂のお家に戻っちゃっても寂しくないからいいわね」とか「本当の赤ちゃんだった時に面倒をみてあげていた頃に戻って私も若返ったような気分になれるし、いいんじゃない」とか「早苗の遊び相手ができてよかったわ」とか言って、自分の娘/妹が赤ちゃん返りしてしまったことをすんなり受け容れちゃうような二人なんだよ? そんな人たちには、大学受験の重圧だとか、生徒会役員の責任の重さに伴う精神的なストレスだとか、今どきのジェンダー論とか、LGBT云々だとか理由を付けて、久美お姉ちゃんの赤ちゃん返りみたいに、悠里さんが子供に戻っちゃったんだってと説明しておけば、それでなんとなく納得してくれるんだよね。うん、そうだよ、本当だってば。現に、ほら、こうして、二人とも悠里ちゃんのこと可愛い可愛いって言って、今にも頭を撫で撫でしそうにしているんだから。
というわけで、我が家の玄関での騒ぎも一段落ついた頃。
「あれ? 早苗ちゃんが見当たらないけど、お昼寝かな?」
玄関から奥へ続く廊下を見渡して、琴音が小首をかしげて訊いてきた。
それに対して私は
「あ、早苗ちゃんだったら、久美と一緒にリビングにいるよ。遊んでもらっているんだ」
と、久美お姉ちゃんのことを『久美』と呼び捨てにしたり、わざと主語をぼかして説明した。
私のそんな説明に琴音と美音ちゃんは意味ありげにそっと頷いてみせたけど、悠里ちゃんは、顔見知りである私のお母さんと佳美お姉ちゃんからすっかり小っちゃな女の子扱いされちゃって、顔を真っ赤に染めるばかりで、私の説明にはまるで反応をしめさないでいる。ま、計画の進行に合せて久美お姉ちゃんがどんなことになっているのか琴音と美音ちゃんには事細かに伝えてあるけど、悠里ちゃんには何も教えてないから、それも無理はないんだけど。
「ああ、そうなんだ。久美ちゃんと一緒にリビングにいるんだ」
私の説明を聞いた琴音は久美お姉ちゃんのことを『久美ちゃんと』呼んで、にっと笑ってみせた。
で、私が
「呼んでこようか? 悠里ちゃんも大人たちに囲まれてちゃ窮屈だと思うし、同い年くらいの女の子どうしの方がのびのびできるから」
と気を利かせるふうを装って言うと、琴音が軽くウィンクしてみせて
「わるいんだけど、そうしてやってくれる? 悠里、早苗ちゃんとお友達になりたくて仕方ないのよ。お部屋にあげてもらってからでもいいんだけど、小っちゃい子は、こうと思うと気がはやっちゃって少しの間でも待つことを嫌がるから」
と返してきた。
で、早苗ちゃんを連れて私が戻ってきた時にはみんな靴を脱いで上り框から廊下に移っていたんだけど、悠里ちゃんは相変わらず顔を真っ赤にして美音ちゃんの制服の袖口を掴んで二人の後ろに隠れるようにしているままだった。
それにしても、子供というのは、私たちが思っている以上に目敏いものなんだね。大人たち(早苗ちゃんから見れば、制服姿の美音ちゃんも充分に大人だ)に混じって自分と同じような遊び着姿の女の子がいることにすぐ気づいて、久美ちゃんママ(あ、これ、私のことね。とりあえず、赤ちゃん返りした久美お姉ちゃんのママは私だよって説明したら、それ以後、私のことを『朱美おばちゃん』じゃなく『久美ちゃんママ』って呼ぶようになったんだ、早苗ちゃん)が話してくれた悠里ちゃんとかいうのがこの子だなって思いついて、元々あまり人見知りしない性格なものだから悠里ちゃんのすぐそばまでとてとて歩いて行ったかと思うと
「私、早苗。保育園の年少さん」
と短い自己紹介をしてから、自分よりも随分と背が高い悠里ちゃんのことをちょっと不思議そうな顔でひとしきり眺めまわして、でもすぐに人なつこい笑顔になって
「悠里ちゃんでしょ? お隣ん家の子が遊びに来るよって久美ちゃんママに教えてもらったの。琴音お姉さんと美音お姉さんと、それと、悠里ちゃんだよって、お名前も教えてもらったの。悠里ちゃん、背が高いけど、小学生?」
と、まわりの大人たちに臆するふうもなく悠里ちゃんに話しかける。
「え? 悠里、悠里は……」
高校三年生だよとつい答えそうになって、けれど悠里ちゃんは慌てて口をつぐんじゃう。
美音ちゃんのお下がりを着せられてスカートの下にはおむつを当てられた姿で本当の学年を答えられるわけがない。でも、だけど、どう答えればいいんだろう。そんなふうに本来の自我が判断に迷っているうちに、琴音と美音ちゃんが繰り返し言い聞かせた偽りの年齢を刷り込まれた第二の自我の意のままに
「悠里も年少さんだよ。早苗ちゃんと一緒で、保育園の年少さん」
という言葉を(理性の制止なんてまるで無視して)発してしまう。
「そうなんだ、悠里ちゃん、早苗と一緒なんだ」
悠里ちゃんの返答に声を弾ませる早苗ちゃん。
だけど、すぐにもういちど悠里ちゃんの体、特に下半身をまじまじと眺めながら
「でも、一緒じゃないところもあるよね。だって、ほら」
と、自分のスカートをぱっと捲くってみせた。
きょとんとする悠里ちゃんの目に、アニメキャラをフロントプリントしたショーツが映る。
「わかった?」
しばらくの間、体を後ろに反らせ気味にして自分が穿いているショーツをちょっぴり自慢げに悠里ちゃんにみせつけてから、早苗ちゃんはスカートを元に戻したんだけど、悠里ちゃんがきょとんとしたままなのに気がつくと、今度は悠里ちゃんのスカートをさっと捲り上げちゃう。
「え……?」
突然の出来事にすぐには何があったのかわからなかった悠里ちゃんだけど、みんなの視線が自分の下腹部に集まっていることに気がついた途端、
「い、いやぁ!」
と甲高い悲鳴をあげて、慌ててスカートの裾を両手で押さえた。
でも、もう遅い。それまでは琴音と美音ちゃんの後ろに隠れてスカートの裾を盛んに引っ張って恥ずかしい下着をかろうじて隠していたんだけど、早苗ちゃんにスカートを捲り上げられて、熊さん柄のおむつカバーをとうとうみんなに見られちゃった。
それまでは、どうにかこうにか、私のお母さんと佳美お姉ちゃんにはおむつのことを気づかれずにすんでいた悠里ちゃんだけど、実は、早苗ちゃんは悠里ちゃんの姿を一目見た時からスカートの下にどんな下着を身に着けているのか見抜いていたんだ。ま、考えてみれば、それも当り前のことなんだけどね。だって、大人の目の高さだと悠里ちゃんの下腹部を見おろすような感じになるからスカートの裾を引っ張っていればどうにかなるけど、悠里ちゃんよりもだいぶ背が低い早苗ちゃんだと視線も下がって、意識しなくてもスカートの中を覗き込むような感じになっちゃうんだよね。ま、悠里ちゃんがそんなことまで気がまわらなかったとしても仕方ないと思う。仕方ないんだけど、でも、もうどうすることもできない(もっとも、悠里ちゃんのおむつのことは前もって私からお母さんと佳美お姉ちゃんには伝えてあるから、今更っちゃ今更なんだけど)。
「これでわかったよね。悠里ちゃんと早苗、年少さんなのは一緒だけど、一緒じゃないことがあるよね。早苗、もう、お姉さんパンツなんだよ。この前、ママと久美ちゃんママと一緒にお買い物に行った時に買ってもらったお姉さんパンツなんだよ」
早苗ちゃん、自分のスカートの裾を少し持ち上げて、ショーツをちょっとだけ悠里ちゃんに(勿体ぶるように)みせつけるみたいにして、もういちど体を後ろに反らせてみせる。
「へーえ。早苗ちゃん、おむつを卒業してパンツになったんだ。これでいよいよお姉ちゃんだね。おめでとう、早苗ちゃん」
琴音が、自慢げに胸を張る早苗ちゃんに向かってぱちぱちと手を叩いてみせてから、おむつカバーをその場の全員に見られちゃったせいでスカートの裾を両手で押さえた姿のまま、ちゃんと息ができているのかどうかわからないほど浅い呼吸を何度も繰り返すだけの悠里ちゃんの顔をちらっと見た後、私の方に振り向いて
「早苗ちゃん、いつからパンツなの? 朱美ん家の二階のバルコニー、毎日おむつがたくさん干してあるよね。だから、早苗ちゃんがパンツになったなんてちっとも気がつかなかったよ」
と、ちょっぴり不思議そうに訊いてきた。
「えーと、たしか、一週間ほど前だったかな。――ちょうど、琴音ん家が二階のバルコニーに悠里ちゃんのおむつを干すようになった日くらいだったと思う」
私も悠里ちゃんの顔をちらと見て、それで悪戯心をくすぐられて、余計に悠里ちゃんを恥ずかしがらせるようなことを付け加えて琴音に説明した。それから、
「ただ、うちには、おむつを汚しちゃう子がもう一人いるからね。その子の方がおむつをたくさん汚しちゃうから、早苗ちゃんがパンツになっても洗濯するおむつの枚数が目立って減るわけじゃなくて、それで琴音は気がつかなかったんじゃないかな」
という説明も付け加えておく。
すると、
「あ、そうか。早苗ちゃんだけじゃなくて久美ちゃんもいるんだっけ、おむつを汚しちゃう子。たしかに、久美ちゃんは早苗ちゃんよりも体が大きくて汚しちゃうおむつの枚数も多いから、早苗ちゃんがおむつを卒業したこと、私がわからなかったのも仕方ないかもね」
と、琴音がご丁寧に私の説明をなぞって繰り返す。
このわざとらしいやり取り、悠里ちゃんに聞かせるためにやっているんだ、本当は。悠里ちゃんに聞こえるように声も少し大きくして。なのに、小っちゃな女の子の格好をしているだけじゃなく、おむつを当てていることまで私の家族に知られて狼狽えてしまっている悠里ちゃん、何の反応もしめさない。私や琴音にしてみれば、ちょっと拍子抜け。でも、ま、いいや。すぐに、想像もしていなかったような現実と直面することになるんだから。その時に悠里ちゃんがどんな顔をするか、今から楽しみにしておくとしよう。
で、そんなわざとらしいやり取りが終わって、まだ唇を震わせるだけで身じろぎ一つしない悠里ちゃんに琴音が
「早苗ちゃん、おむつは卒業しちゃって、もうパンツなんだって。なのに、悠里はまだおむつ。だったら、同じ年少さんでも、早苗ちゃんの方がお姉ちゃんだよね。だから、『お友達になって仲良く遊ぶ』んじゃなくて、『お友達になってもらって、仲良く遊んでもらう』んじゃなきゃいけないよね。なのに、パンツの早苗お姉ちゃんの方からおむつの悠里の方へ来てくれたんだよ。本当はおむつの悠里の方からパンツの早苗お姉ちゃんへ先にご挨拶しなきゃいけないのにね。だけど、もう、順番が違っちゃったことはいいよ。でも、きちんと悠里から早苗お姉ちゃんにご挨拶して仲良くしてくれるようお願いしておかなきゃね。――どう言えばいいか、わかるかな?」
と、優しい口調ながら悠里ちゃんの羞恥心を更にくすぐって話しかける。
だけど、悠里ちゃんはのろのろと首を振るだけだ。
「じゃ、ママが教えてあげる。だから、きちんと早苗お姉ちゃんにお願いするのよ。いいわね?」
琴音に言われて、悠里ちゃんが今度は力なく頷く。本当は頷きたくなんてないのに、薬の暗示効果のせいで頷いてしまう。
小さくこくんと頷いた悠里ちゃんの耳許に琴音が
「ちょっと長くなるから、全部を覚えるのは悠里には難しいと思う。だから、ママが小さな声で教えてあげる。悠里はその通り早苗お姉ちゃんに言えばいいのよ。できるわね?」
と囁きかけた後、これからどう言えばいいのか、私たちには聞こえないような小声で続けた。
それを悠里ちゃんが
「……悠里はまだ、お、おむつです。だから、早苗……お姉ちゃんと同じ年少さんでも、悠里の方が……い、妹です。妹だから、早苗お姉ちゃんにいろいろ教えてもらって、仲良くしてもらって、……遊んでもらいたいです。お姉ちゃんの言いつけをちゃんと聞いて……いい子にするから、悠里と仲良くしてください。……お、お願い、早苗お姉ちゃん」
と、顔を真っ赤にして、恥ずかしさに震える声で途切れ途切れに口移しで繰り返す。
羞恥のせいで言葉が途切れ途切れになるのが、幼女がたどたどしい口調で年長の少女に何やら話しかけているように聞こえて妙に愛くるしい。
「お利口さんなんだね、悠里ちゃん。まだおむつなのに、ちゃんとご挨拶できて、本当にお利口さん。こんなにお利口さんだったらおむつもすぐばいばいできるから頑張ろうね。早苗もおむつだったけど、妹のお世話をしてあげたらパンツになったんだよ。自分よりも下の子の面倒をみてあげるようになったら急にしっかりしてきたわねってママ、びっくりしてたんだよ。悠里ちゃん、早苗よりも妹だけど、お部屋に悠里ちゃんよりも小っちゃい子がいるから、お世話してあげようよ。難しくてよくわかんないけど、その子、月齢十二ケ月なんだって。月齢十二ケ月の赤ちゃんで、名前、久美ちゃんっていうんだよ。久美ちゃんのお世話してあげたら、悠里ちゃんもパンツのお姉さんになれるよ、きっと」
恥辱に満ちた悠里ちゃんの『ご挨拶』を聞いた早苗ちゃん、にこにこ顔で言って、悠里ちゃんの手を引いてリビングルームに向かって駆け出そうとする。
突然のことにびっくりしつつも、早苗ちゃんと歩速を合わせて足を動かしながら、我が家にやって来てから何度も『久美ちゃん』という名前を耳にしたことがあるのを今更ながら思い出す悠里ちゃん。早苗ちゃんは久美ちゃんのことを、月齢十二ケ月の赤ちゃんで、妹だと言った。佳美さんのお腹は大きいままだから、早苗ちゃんの下の子はまだ生まれていない筈。だったら、久美ちゃんというのは?
羞恥よりも、なぜとはなしに言いしれぬ不安に苛まれながら、後ずさりしたくてたまらなくなる気持ちを抱えつつ、早苗ちゃんに手を引かれるまま、久美ちゃんという赤ちゃんがいるリビングルームに向かって、ふわふわ揺れるスカートの裾から見え隠れするおむつカバーのことを気にかけるゆとりもなく歩みを続ける悠里ちゃんだった。
*
「久美ちゃん、お昼寝だったんだよ。それで、おっきしてぐずってたから、早苗がガラガラであやしてあげたら、またねんねしちゃって。それでどうしようかなって思ってたら久美ちゃんママが、お隣ん家のみんなが遊びに来たよって早苗を呼びに来てくれたんだ。久美ちゃん、まだねんねかな。それとも、もうおっきしてるかな」
そんなふうに説明しながら悠里ちゃんの手を引っ張って、早苗ちゃんがリビングルームに入って行く。
二人に続いて私たちがリビングルームに入ると、部屋の真ん中あたりに敷いたおねしょシーツの上で、スカートの付いた可愛らしいロンパースを着て胸元をガーゼ生地のよだれかけで覆った赤ん坊が、お腹にタオルケットをかけて寝転がって、手の甲で瞼をぐりぐりしていた。
「あ、久美ちゃん、おっきしたんだ」
赤ん坊が手の甲で瞼をぐりぐりしているのを見て、弾んだ声でそう言った早苗ちゃん、悠里ちゃんと手を繋いだまま赤ん坊のそばへ駆け寄る。
「ねぇね、ねぇね」
早苗ちゃんが近づいてくるのに気がついて、赤ん坊がきゃっきゃと嬉しそうな声をあげ、たどたどしい口調で早苗ちゃんを呼んだ。
「この子が久美ちゃんだよ。可愛いでしょ。仲良くしてあげてね」
床に座るよう悠里ちゃんに手招きで指示して自分も赤ん坊のすぐそばに座った早苗ちゃん、赤ん坊を手短に紹介して、すぐ、今度は赤ん坊に向かって
「お隣の悠里お姉ちゃんだよ。早苗お姉ちゃんと同じ年少さんで、久美ちゃんと同じおむつなんだよ。三人でちょっとずつ同じだから、みんなで仲良くしようね」
と悠里ちゃんのことを紹介した。
部屋に入ってすぐ、床に寝そべっているのが普通の赤ん坊なんかじゃないことは悠里ちゃんにも一目でわかった。赤ん坊にしては随分と(というか、異様なほど)体が大きいし、それに、よだれかけで覆われた胸が、目立つほどではないにしても膨らんでいるのが見て取れた。ちょうど、そう、背が低くてバストの発育が思わしくないことにコンプレックスを抱きながらも自分の役目を健気にこなす、充分すぎるほどに見知った女の子。目の前にいる赤ん坊は、その女の子と同じような体つきをしていた。
早苗ちゃんが繰り返し口にする『久美ちゃん』という名前。赤ん坊にしては発育のよすぎる体つき。
それまでわざと目をそらしていたけれど、一度だけ大きく息を吸い込んで、悠里ちゃんは赤ん坊の顔にちらっと目を向けた。
同時に、赤ん坊も悠里ちゃんの顔を見上げる。
ちらっと見るだけのつもりだったのに、視線と視線が絡み合って、目をそらせなくなってしまう。瞬きをすることも忘れて、二人とも大きく目を見開いたまま。
だけど、早苗ちゃんと悠里ちゃんに続いて私がそばに歩み寄ると、久美ちゃんと呼ばれた赤ん坊は不意にはっとしたような顔になってお腹の上のタオルケットを撥ねのけ、寝返りをうってうつ伏せになると、両方の手足をばたばた動かして一目散に這い這いで私の目の前にやって来た。
そして、両手を差し伸べる私の胸の中にとびこんでくる。
「あらあら。久美ったら、こんなに人見知りだったっけ? それとも、たくさんの人が急に部屋に入ってきてびっくりしちゃったのかな?」
体の大きな赤ん坊――夏休みが始まる前まては私の二番目の姉だった久美お姉ちゃん、今は赤ちゃん返りしちゃって私の娘になった久美が大慌てで私の胸の中にとびこんできた理由ははっきりしている。だけど、私はわざととぼけて、不思議そうに小首をかしげてみせた。
久美が力なくいやいやをする。体は大きいけど、そんな仕草は赤ん坊そのままで、とっても愛くるしい。
「でも、変ね。みんな、初めて会う人じゃないでしょう? だって、みんなお隣のお家の人で、特に悠里ちゃんとは大の仲良しじゃなかったっけ?」
小首をかしげたままそんなふうに言う私の声は、久美には少し意地悪に聞こえたかもしれない。
そのせいかどうか、久美はもういちどいやいやをして、私の胸に顔を埋めた。
ちらと横目で窺うと、ついさっきまで床に座っていた筈の悠里ちゃんも、琴音に何か耳打ちされた途端、膝立ちになって、琴音の胸に顔を埋めていた。琴音が悠里ちゃんにどんなことを言ったのか、私には簡単に想像がつく。琴音は「これから、大好きな久美ちゃんとたくさん遊べるよ。よかったね」と悠里ちゃんに耳打ちしたにちがいない。
夏休みに入ってからこちら、つまり、私と琴音の計画が始まってからこちら、悠里ちゃんと久美は会ったことがない。というか、会える状況なんかじゃなかった。だから、お互い、各々の様子なんて知りようがない。そんな二人が久しぶりに顔を会わせた――互いに、思いもよらぬ姿で。
久美はひどく狼狽え、今の自分の恥ずかしい姿を相手に見られないように、そして同時に、相手の恥ずかしい姿を見ないようにと、私の胸に顔を埋めて固く目をつぶっている。それは、悠里ちゃんも同じ。
「急にどうしちゃったの、二人とも?」
事情を知らない早苗ちゃんのきょとんとした声が、ほどよく冷房の効いたリビングルームの空気をそよがせた。
*
お昼ご飯の準備ができても、久美は私にしがみついて離れなかった。もちろん、悠里ちゃんも琴音に抱きついたまま。
「やれやれ、せっかく、関西に住んでいる知り合いが『揖保乃糸』のひね物を贈ってくれたから腕によりをかけたんだけどねぇ」
各々の『ママ』の胸に顔を埋めたままの悠里ちゃんと久美の背中と、座卓の上に並べた素麺の工夫料理(短く切った素麺をご飯に見立てて巻き寿司にした素麺寿司だったり、素麺をフライパンで軽く焦げ目が付けくまで焼いてアンかけにした堅焼き素麺だったり、素麺のぺぺロンチーニだったり)を見比べて、お母さんが小さく溜息をついた。
久美の体がびくんと震えたのは、それとほぼ同時だった。
「どうしたの?」
私は久美の背中を優しくとんとん叩いて訊いてみた。
だけど、返事はない。
でも、それがどういうことなのか、私にはすっかりわかっている。
待つほどもなく
「ふ……ふぇ……ぇーん、ふぇーん、う、ぅえーん」
という涙声が久美の口から漏れ出して、しばらくすると、手放しで泣きじゃくり始めた。
「あ、久美ちゃん――」
「そうね。お昼寝の間は大丈夫だったけど、おっきしてからしくじっちっゃたみたいね。それにしても早苗ちゃん、泣き声を聞いただけでよくわかったね」
久美の様子に何があったのかすぐに察した早苗ちゃんが心配顔で私に何か伝えようとしてくれる。それを優しく褒めてあげると、早苗ちゃんは得意そうな顔になって
「だって、早苗、お姉ちゃんだもん。いつも久美ちゃんのお世話をしてあげているから、泣き声を聞いたら、久美ちゃんがどうして泣いてるのか、すぐにわかるんだよ。お腹が空いておっぱいがほしい時と、一緒に遊んでほしい時と、おむつが濡れてお尻が気持ちわるい時と、どれも泣き方が違うんだよ。それでね、今のは、おむつが濡れちゃった時の泣き方なんだよ」
と説明してくれた。
「すごいね、早苗ちゃん、お母さんみたいだね。これなら、もうすぐママに赤ちゃんが生まれても、ちゃんとお世話してあげられるよ」
私は、久美のロンパースの股ぐりに右手の指を差し入れ、更におむつカバーの股ぐりに指を差し入れて、指先に伝わる温かい液体の感触を楽しみながら早苗ちゃんの幼い自尊心をくすぐった。半ば本心から感心してのこともあるけれど、ことあるごとに大袈裟に褒めそやすことで早苗ちゃんはますます喜んで久美の面倒をみてくれるようになる。本当は自分よりもずっと年下の姪っ子から逆に赤ん坊扱いされ続けて、久美の心は赤ちゃん返りからますます脱却できなくなるにちがいない。そんな目論見もあってのことだった。
「でも、泣いてばかりじゃ久美ちゃん可哀想だね」
私に褒められた早苗ちゃん、面映ゆそうな顔になって、久美がお昼寝をしていた場所に転がっているガラガラを拾い上げると、私にしがみついたままおむつを濡らす久美の耳許で、そのプラスチック製の玩具を振り鳴らした。
からころ。
からころ。
軽やかな音色が部屋の空気を優しく震わせる。
ガラガラの音を耳にして、久美の泣き声が少しずつ小さくなって涙が途切れ途切れになってゆく。
もう少し抱っこしてあげて、落ち着いたらおむつを取り替えてあげよう。
そう思った矢先の出来事だった。
今度は悠里ちゃんがぐずりだして、ついさっきまでの久美と同じように、琴音にしがみついたまま大声で泣きじゃくり始めた。
「あらあら、いくら久美ちゃんと大の仲良しだからって、そんなところまで一緒じゃなくてもいいのに」
久美を抱っこしたまま体の向きをちょっと変えて悠里ちゃんたちの様子を窺うと、膝立ちになっている悠里ちゃんのおむつカバーの股ぐりに琴音が右手の指を差し入れて、呆れたように、でも、見るからに満足そうな顔でそんなふうに悠里ちゃんに話しかけていた。
そこへ横合いから美音ちゃんが
「もう、琴音ねぇはほんっとに悠里に甘いんだから。いい? 悠里はもう保育園の年少さんなんだよ。保育園のお姉さんのくせに、赤ちゃんの久美ちゃんと同じようにおむつを汚しちゃうなんて、もっと厳しく叱らないと駄目じゃない、琴音ねぇったら。そんなふうに甘やかすから、いつまで経ってもおむつが外れないのよ、悠里は」
と、(本当のところは、悠里ちゃんがおむつなのは自分も荷担している計画のせいなのに)わざときつい口調で言って、
「ほら、久美ちゃんはもうすぐ泣きやむわよ。赤ちゃんが泣きやむのに、年少さんがいつまでも泣いててどうするの。お姉ちゃんのお気に入りのハンカチを貸してあげるから、もう泣きやみなさい」
と、制服のポケットから取り出したハンカチを悠里ちゃんのほっぺに押し当てた。
それでも、悠里ちゃんが泣きやむ気配は一向にない。
おむつを濡らしちゃった久美が泣きじゃくったのも、早苗ちゃんにガラガラであやしてもらって泣きやんだのも、同じようにおむつを汚しちゃった悠里ちゃんが泣きじゃくっているのも、そうするように私たちが『躾け』たからだ。
久美は赤ちゃん返りした後、おむつが濡れても、それを伝える術を知らなかった。ぐっしょり濡れたおむつがお股の皮膚にべっとり気持ち悪くまとわりついても、おしっこをたっぷり吸収したおむつが冷えて背中がぞくりとしても、なんとなくむずがる様子をみせるだけで、どんなふうに不快感をしめせばいいのかわからずにいた。悠里ちゃんが薬のせいで第二の自我を胸の中に宿したように、私を親鳥に見立てた再刷込み/リインプリティングによって赤ちゃん返りした久美の中にも、優等生の高校生としての本来の自我とはまるで違う、自分では何もできない無力な赤ん坊としての第二の自我が芽生えた。本来の自我は、赤ん坊がおむつを濡らした時には不快感に耐えられず泣きじゃくるということを知識として有している。だけど、自分が赤ちゃん返りしてしまったという屈辱に抗い、恥ずかしい粗相の不快感のせいで赤ん坊そのままに泣きじゃくることを拒んだ。一方、芽生えたばかりの第二の自我は、まだ明確な形をなさず、それ自体としての意思や情動や知識を有するには至っていなかった。要するに、赤ちゃん返りしてすぐの第二の自我は『新生児』の段階であり、その内側はまだ『空っぽ』だったわけだ。ところで、ここで話は少し横道にそれるんだけど、赤ちゃん返りさせた久美をどのくらいの月齢の赤ん坊として扱うか、実は私は、久美を赤ちゃん返りさせることを夢想していた頃から決めていた。新生児だと手がかかって仕方がないだろうし、二歳くらいだとイヤイヤ期の真っ盛りあたりで面倒だから、イヤイヤ期を迎える直前の、育児の楽しみを一番味わえるだろうという思いで、私は久美を月齢十二ケ月(年齢でいうと一歳)の赤ん坊として扱うことに決めていたんだ。さて、話を戻して。赤ちゃん返りしてすぐの久美に宿った第二の自我は、その内側がまだ空っぽだったからこそ、外界からの情報を取り込んで独自に咀嚼し自分の一部として『空っぽ』を埋める勢いがすごかった。標準的な月齢十二ケ月の赤ん坊の振る舞いを説明する育児教材用のビデオを見せてあげたり、育児書の内容をかいつまんで読んであげたりしたら、第二の自我はすぐにそれを自分のものにして、ほんの短い間で、第二の自我に言動を委ねる久美は、私が頭の中で思い描いていた通りの月齢十二ケ月の赤ん坊として振る舞うようになった(ただ、正直に言っちゃうと、標準的な月齢十二ケ月の赤ん坊に比べれば、話せる言葉は少し多いんだけど、逆に、つかまり立ちなんてまだまだというふうに、私好みの赤ちゃんになるよう、発育具合を少し工夫しておいたんだけどね)。で、久美に(正確には、久美の第二の自我に)見せた育児教材用のビデオには、おむつが濡れた不快感で泣きじゃくる赤ん坊を撮影したシーンを何種類も混ぜておいた。これで、私の目論見通り、おむつを濡らすたびに恥ずかしい粗相を泣き声で自分から教えるお利口さんな赤ちゃんのできあがりというわけだ。その後、早苗お姉ちゃんにあやしてもらったら泣きやむといった心理的なプロセスも付加して、私にとっては、適度に手をかけて育児の楽しみを存分に味わえる都合のいい赤ちゃんに久美を躾けることができたというわけ。
計画の進み具合を連絡し合う際、そんな経緯を話したら琴音も乗り気になっちゃって、悠里ちゃんには「悠里、ちっちなの。ちっちのおむつ、取り替えて、ママ」と言葉でおもらしを教えるよう躾けるつもりだったのを、「だって、言葉で知らせるのはもっと『成長』してからでもいいしね。小っちゃいうちは泣いてしらせてくれる方が可愛いっしょ」と言って、久美と同じように、おむつを汚しちゃったことを泣き声でしらせるように『躾け方』を変えた。ため、久美と悠里ちゃん、二人の泣き声がリビングルームに響きわたることになったというのが今の状況だ。
「すぐに泣きやんでお利口さんの久美ちゃんと、いつまでも泣きやまない悠里。これじゃ、どっちがお姉さんかわからないわね。あ、そうだ。久美ちゃんのロンパースを借りて悠里にも着せてあげようか? 泣き虫の悠里には赤ちゃんの格好の方がお似合いだよ」
ほっぺを濡らす涙をハンカチで拭いてあげながら、そう意って美音ちゃんが悠里ちゃんをからかう。
「や! 悠里、赤ちゃんじゃない。保育園のお姉さんなんだから、赤ちゃんのお洋服、や!」
美音ちゃんにからかわれて涙ながらにほっぺを膨らませる悠里ちゃん。その仕草は、もうすっかり年少さん、それも、同じ年少さんでもパンツの早苗ちゃんよりもずっと幼い、おむつの年少さんだ。
すると美音ちゃんが、ついさっきのきつい口調が嘘みたいな柔らかい声で
「だったら、もうそろそろ泣きやまなきゃね。ほら、お姉ちゃんがこうしてあげるから、いつまでもぐずってないの」
と言って、琴音に替わって悠里ちゃんの体を正面から抱き寄せ、中学一年生としては豊かな胸に悠里ちゃんの顔を埋めさせた。
少女から大人の女性への変貌をとげる只中にある美音ちゃんの体から、その時期の女の子に特有の甘酸っぱい匂いが立ちのぼって、悠里ちゃんを包み込む。
途端に悠里ちゃんの目がとろんとして、それまで溢れ出ていた涙が止まり、表情が穏やかになってゆく。久美が早苗ちゃんにあやしてもらうと機嫌を良くするのと同じように、琴音は、美音ちゃんにあやしてもらうと泣きやむように悠里ちゃんを『躾け』ていたのだった(思えば、美音ちゃんが悠里ちゃんに厳しく接するのは、美音ちゃんなりの優しさの発露なのかもしれない。美音ちゃんが小っちゃな子供だった頃、須藤家の長男である悠里さんは、母子家庭だからとか、そのお母さんも殆ど家にいないからとか何かと冷たい目を須藤家に向ける世間から陰口をたたかれないようにと、妹たち、特に幼い美音ちゃんを厳しく躾けた。だけど美音ちゃんは、そんな『悠里にぃ』を憎んでなんていない。だからこそ、今度は、その恩返しとして、悠里ちゃんを厳しく躾け、悠里ちゃんがいい子でいいつけに従ったら、(琴音に負けず劣らず)でれでれの甘いお姉ちゃんになっちゃうんじゃないだろうか)。
「やれやれ、やっと泣きやんでおとなしくなった。これでゆっくりおむつを取り替えてあげられるわね」
琴音は、ようやく泣きやんで改めて美音ちゃんから受け取った悠里ちゃんを軽々と抱き上げてすっと立ち上がると、久美が寝そべっていた場所まで歩いて、敷いたままになっているおねしょシーツの上に悠里ちゃんを横たわらせた。
だけど、悠里ちゃんの体をおろしたのは、おねしょシーツの真ん中じゃなく、端っこの方。
琴音が何をしようとしているのかすぐにわかった私は、抱っこしている久美の体を、悠里ちゃんが寝転がっているおねしょシーツの片方の端におろした。
「仲良しさんの悠里と久美ちゃん。二人並んでおむつを取り替えてあげるわね。ほら、こんなふうにお手々を繋いで。大好きな相手とお手々を繋いでおむつを取り替えてもらうんだから、もう泣いたりしないよね」
同じおねしょシーツの上に並べて横たわらせた悠里ちゃんと久美の手を強引に繋がせて、琴音は不思議な色の瞳をきらきらさせて言う。
二人は慌てて手を離そうとするんだけど、その手を美音ちゃんが押さえて離させない。
悠里ちゃんと久美は、互いに目を会わせまいとして、ぎゅっと瞼を閉じて顔を天井に向けた状態で体を固くしちゃう。
そんな二人の様子を面白そうに眺めながら、二人の耳にもはっきり届くようちょっぴり大きな声で琴音が
「ところで、相談があるんだけど」
と、勿体ぶった口調で私に話しかけてきた。
琴音が何を言おうとしているのか私にはわかっている。わかっているけど、悠里ちゃんと久美に聞かせるために、わざと
「ん? なによ、相談って」
と訊き返す。
私が訊き返すと、琴音は少し間を置いて
「せっかくだから、私が久美ちゃんのおむつを取り替えてあげて、朱美に悠里のおむつを取り替えてもらうのもいいかなとか思うんだけど、どう? ママ友どうし、これから、どっちかが忙しい時は手が空いている方が子供たちの面倒をまとめてみてあげることもあるかもしれないでしょ。そんな時に備えた予行演習みたいな感じでさ」
と、二人の様子をちらちら窺いながら応じる。
琴音の言葉が終わらないうちに二人が今にも泣き出しそうな顔になって、唇を震わせる。
「あ、いいわね。確かに、ママ友どうし助け会わなくちゃね。家もお隣どうしだし」
私はわざとらしい笑みを浮かべて大袈裟に頷いてみせた。
悠里ちゃんと久美はこわばった表情で弱々しくいやいやをするんだけど、それ以上のことは二人にはできない。
と、早苗ちゃんが久美の顔のすぐそばに膝をついて座り、さっきよりも大きな音でガラガラを振り鳴らした。同時に、二人の手を押さえたまま美音ちゃんが上半身を前のめりにして、悠里ちゃんの口元に固い乳房を近づける。
たちまち、悠里ちゃんと久美の表情が緩んだ。
だけど、二人の顔に浮かんでいるのは、幼児のあどけない笑みではなく、ぎこちない泣き笑いの表情だった。
ま、それも仕方ないか
あ、そうだ。ここで一つ、大事なことを話しておくね。琴音は私たちの間柄を「ママ友どうし」と表現した。確かに、それは間違っていない。でも、それには、「今のところは」という条件がつく。私も琴音も、そんな間柄を続けるつもりなんてない。計画がこのまま順調に進んだ後、私たちの間柄はもっと濃密になる予定だ。実は、そのことは琴音のお母さんと音ちゃんにも、私のお母さんと佳美お姉ちゃんにも前もってそれとなく話して賛成してもらっている。この部屋の中でそのことを知らないのは、早苗ちゃんと悠里ちゃん、それに久美だけ。年端もゆかぬ子供たちは、大人の事情なんて気にかけずに、夢中で遊んで、いい夢を見ながらねんねして、無邪気に笑って、そうして、たっぷりのおもらしで柔らかなおむつをぐっしょり濡らしていればいいんだから(あ、早苗ちゃんはもうパンツだっけ)。大人の事情で子供たちの無垢な気持ちをわずらわせるなんて可哀想なことをしちゃいけないんだから。
ま、それがどういうことなのかは、もう少しお話が進んでから明かすとして、今は悠里ちゃんと久美のおむつに話題を戻しておこう。
自分のことをよく知っている人たちの視線を集めた状態で(それも、本当は高校三年生にもなる自分が)おむつを取り替えられるなんて、言葉では表現しようのない屈辱の極みだ。二人ともすぐにでもこの場から逃げ出したいにちがいない。だけど、繋いだ手を美音ちゃんに押さえられて体を自由に動かせず、早苗ちゃんにガラガラであやされて逃げ出す気力も削がれ、私と琴音のなすがままになるしかない悠里ちゃんと久美。
悠里ちゃんの足元に膝をついて座った私はデニムのスカートをお腹の上まで捲り上げながら
「よろしくね、悠里ちゃん。でも、まさか私が悠里ちゃんのおむつを取り替えてあげることになるなんてね」
と、ことさら優しい笑顔で話しかけてあげた。
それは、半ば本心から出た言葉。お隣に住む二つ年上で、学校じゃ先輩。そんな男の子のおむつを取り替えてあげることになるなんて。
でも、悠里ちゃんから返事はない。
ま、仕方ない。でも、小っちゃい子には、どんな些細なことでも話しかけてあげることが大切だ。いくら人見知りする子でも、こちらから笑顔で話しかけてあげれば、いずれは心を開いてくれるだろう。
「あ、悠里ちゃんと久美ちゃん、お揃いのおむつカバーだ。なんだか、双子みたい」
と、早苗ちゃんが嬌声をあげた。
月齢十二ケ月の赤ちゃんと保育園の年少さん。そんなふうに扱われている二人だけど、本当は同い年(の高校生)だ。それに、男女の違いはあるものの、二人とも丸っこい童顔で小柄なところも同じで、お揃いのおむつカバーでお尻を包んでいると、幼い双子に見立てることもできなくはない。
二人お揃いのおむつカバー、本当は服飾文化研究部で縫製技術の腕を上げた私が作ってあげんだよということはおくびにも出さずに私は腰紐に手をかけた。そうして、早苗ちゃんが無邪気な言動を繰り返すたびに悠里ちゃんと久美の羞恥心が煽りたてられる様子に胸の中でくすくす笑いながら腰紐をほどいた後、新しいおむつを準備しておいた衣装籠から小さな棒状の器具を取り出して、その器具を使っておむつカバーのスナップボタンを外し、おむつカバーの前当てを悠里ちゃんの両脚の間に広げる。
ぐっしょり濡れた水玉模様の布おむつがあらわになる。それも、おちんちんを後ろ向きにしておむつをあてられているから、おむつの後ろの方がよく濡れていて、前の方は、濡れているというよりも湿っているだけと言ったほうがいい箇所もあった。
「おむつカバーもお揃いだし、おむつの濡れ方も久美と同じだね、悠里ちゃん。でも、悠里ちゃんも久美も女の子なんだから、同じ濡れ方でもちっとも不思議じゃないんだっけ。いっぱいちっち出ちゃったね。お尻、気持ちわるいよね。すぐに取り替えてあげるからいい子にしているのよ」
と、さりげなく悠里ちゃんを恥ずかしがらせてから、私は悠里ちゃんの左右の足首を右手で一つにまとめて掴んで、そのまま高々と差し上げた。
隣では琴音が久美を同じようにしている。
私と琴音は呼吸を合わせて、ぐっしょり濡れたおむつを手前にたぐり寄せて、(久美のお世話に慣れた早苗ちゃんが持ってきてくれた)ペールに滑り込ませた。
悠里ちゃんと久美、二人の下腹部が同時にみんなの目の前にさらされた。
「ちゃんとお手入れしてあげているのね。久美ちゃんのお股、つるつるですべすべだわ」
隣から、含み笑いが混じった琴音の声が聞こえる。
「悠里ちゃんこそ、綺麗なお股だこと。うふふ。小っちゃい子は本当にお肌がつるつるで羨ましいわね」
私は琴音とまるで同じ口調で、琴音にというよりも、悠里ちゃんと久美に聞かせることを意識して相槌を打った。
二人は本当の幼児じゃない。だけど、下腹部の肌がつるつるですべすべなのは事実だ。それは、琴音が向精神薬と同じルートで入手した塗り薬のおかげだ。その塗り薬は世界中に愛用者が少なからずいることから、優れた効能を有していることは証明済みで、なんでも、皮膚の保水力を高めることで、老化してかさかさになった皮膚をもちもちぴちぴちしっとりな若い頃のお肌に蘇らせてくれるという効き目を発揮するらしい。しかも、皮膚の若返りと同時に無駄毛の処理もしてくれる除毛成分も含有しているから、年配の特に女性の愛用者が多いらしい。おむつを取り替えてあげるたびにその薬を下腹部全体に万遍なく(わざと多めに)塗ってあげているから、二人とも、お股のお肌はつるつるで、無駄毛一本なくすべすべしているというわけだ。私も琴音も、お風呂上がりに新しいおむつを当ててあげる時には決まって、各々の愛娘に向かって、ママがきちんとお手入れをしてあげているから綺麗なお肌になってよかったねとにこやかな声で話しかけながら手鏡をかざして『お手入れ』の結果を見せてあげるのが日課になっている(大人の証である恥毛が一本残らずなくなってしまった自分の股間を初めて見た時の久美の顔は今でもありありと思い出せるほどだ)。
「あれ? 悠里ちゃんのお股、なにか変だよ」
あらわになった悠里ちゃんの股間に力なく垂れ下がるおちんちんを目敏くみつけて早苗ちゃんが不思議そうな顔で言った。
「ああ。これはね、おちんちんよ。早苗ちゃんのパパのお股にも付いているから、お風呂に入れてもらった時に見たことがあるんじゃないかな?」
悠里ちゃんの股間にじっと見入る早苗ちゃんに、琴音が教えてあげる。
だけど早苗ちゃんは
「早苗、パパのおちんちん見たことあるよ。でも、こんなのじゃなかったよ。パパのおちんちん、もっと大きくてもっと固くて、なんていうのかな、もっと強そうだった。でも、悠里ちゃんのこれ、小っちゃくて柔らかそうで、弱そうだよ。それに、女の子にはおちんちんなんてないんでしょ? だから、これ、おちんちんなんかじゃないよ」
と考え考え応じて、ふっと何かを思いついたような表情を浮かべると
「あ、わかった。悠里ちゃん、お股をいじったんじゃないかな。お股はとってもデリケートなところだからいじっちゃ駄目よって、ママ、いつも早苗に言うんだよ。悠里ちゃん、お股をいじったから腫れちゃったんじゃないかな。だったら、悠里ちゃん可哀想だよ。お医者さんに連れて行ってあげてよ」
と、子供ながらにいかにも心配そうな顔で琴音に言った。
「早苗ちゃんは優しい子なんだね。会ったばかりの悠里のことを心配してくれる優しい子。うん、わかった。近いうちにお医者様にみてもらうね。だから、安心して」
胸の中でくすくす笑いながら、琴音は真剣な顔をつくって答える。それから、悠里ちゃんの顔を見て、真剣な表情のまま
「ということだから、お医者様に治してもらおうね、腫れたお股。でも、お薬で治せなかったら、腫れたところを切り取っちゃった方がいいのかな。お医者様と相談してみなくちゃね」
と話しかけた。
途端に、悠里ちゃんが怯えた顔になっていやいやをする。琴音の目つきは、冗談で言っているとは思えないほど真剣だった。
「じゃ、お股の腫れのことは琴音にまかせて、急いでぱたぱたをして新しいおむつを当ててあげようね。このままじゃ、お尻が冷えて風邪をひいちゃう」
私は怯えた様子の悠里ちゃんに優しく言って、柔らかいパフでベビーパウダーをそっと掬い取ると、パフを悠里ちゃんの股間に押し当てた。
「はい、ぱたぱたー。いい匂いがするでしょ?。 みんな、この匂いが大好きなんだよ。なんだか、この匂いを嗅ぐと穏やかな気持ちになれるよね。――それで、ぱたぱたが終わったら新しいおむつだよ」
はたき残したところがないよう丹念にパフを動かして悠里ちゃんの下腹部をベビーパウダーでうっすらとお化粧してあげてから、おちんちんをお尻の方に向けさせて、股当てのおむつを当ててあげる。股当てのおむつは八枚。久美もそうだけど、本当の赤ちゃんと比べるとずっと体が大きいからもっと枚数を増やさなきゃいけないかなと思っていたんだけど、近ごろじゃおしっこをしたくなったらまるで我慢できずにしくじっちゃうから、おもらしの回数が増えて、そのかわり、おもらし一回ずつのおしっこの量が少なくなって、八枚で充分だ。で、八枚のおむつを重ねてまとめて当てるんじゃなくて、おむつの感触を体に憶えさせるために、一枚ずつ、それも、おむつの端で内股をすっと撫でるようにして当ててあげる。おむつに内股を撫でられるたびに頬を染める悠里ちゃんの様子ったら、可愛らしくて仕方ない。
その後、横当てのおむつを当てておむつカバーの内羽根で押さえ、内羽根に前当てを重ねて、前当ての左右の端に縦に四つ並んでいるスナップボタンを全部留めてあげたんだけど、その頃には琴音の方は久美のおむつの交換をすっかり終えていて、ブラウスの胸元をはだけてブラの肩紐をずらした状態で、久美の体を抱き上げようとしていた。久美と違って悠里ちゃんはおちんちんを後ろに向けさせたり、おちんちんの先っちょの位置をちゃんとしながらおむつで押さえつけたりしなきゃいけないから、慣れないうちは手間取っちゃうんだ。それでも、私の方も琴音にさほど遅れることなくおむつカバーの腰紐をきゅっと結わえて、おむつカバーからはみ出ているおむつを股ぐりの中に丁寧に押し込んで、悠里ちゃんのおむつの交換を終えることができた。
でもって、その後、ブラウスの胸元をはだけるところまでは琴音と同じなんだけど、ブラの肩紐をずらすことはしなかった。というのも、私、三日前から普通のブラじゃなく、ネットでいろいろ調べているうちにみつけて通販で買った授乳用のブラを着けているんだ。うすいピンクベージュの地味な色合いのブラでちっともお洒落じゃないけど、久美がおっぱいをせがんだらすぐに乳首を口にふくませることができて久美がむずがらないから大満足。なんだか最近は自分のことよりも久美がご機嫌になるようにってことばかり考えているみたいで、ちょっぴり不思議な気分。
そんなふうに久美に対するのと同じような気持ちで悠里ちゃんの体を横抱きにして、口に乳首をそっと押し当てた。いつもの琴音の乳首とは微妙に感触が違うのか、悠里ちゃんはちょっと怪訝な顔をしたけど、おっぱいが唇に触れると口にふくむのがすっかり習い性になっちゃっているんだろう、最初はおずおずと私の乳首を咥えて、でもすぐに、ちゅぱちゅぱと大きな音をたてて吸うようになった。
下腹部がきゅっとなって、胸の中がじんじん暖かくなる。
私の乳首を無心に吸ってくれる悠里ちゃんのことが久美と同じくらい、たまらなく愛おしく感じられる。
私と琴音は今、子供を育てる中で最も幸福な瞬間にいるにちがいない。
*
しばらくの間そんなふうに幸せに浸っていた私と琴音だけど、壁に掛かっている時計がとっくにお昼をまわっていることに気がつくと、互いにそっと目配せを交わし合って、悠里ちゃんと久美を各々の胸に抱いたまま、こちらの様子を見守っている家族の方に向かって座り直した。
そうして私が、少し改まった口調で
「私たちの都合でお昼ご飯が遅くなっちゃってごめんなさい。でも、せっかくだから、お昼ご飯はもう少し待ってもらって、私たちの話すことを聞いてほしいの」
と切り出す。
家族が揃って頷くのを確認してから私は
「ちょっと前にもそれとなく話したのと同じ内容なんだけど、みんなが集まっている場でもういちどきちんと話して、みんなの気持ちを聞いておきたいの。だから、少し時間をください。――実は、私と琴音は、十八歳になって成人したら一緒に住もうねって決めているの。成人したら、女の子どうしだけど、結婚しようって」
と続けて、いったん口を閉じた。
そのあとを今度は琴音が
「私の母にも前もって話したんですけど、みなさんもご存じの通り母はああいう性格だから、よそ様にご迷惑をかけないんだったら二人の思うようになさいっていう返事でした。唐突なことで申し訳ないんですけど、できれば朱美のご家族にもきちんと許していただいた上で一緒になりたいと考えて、こうして二人でお願いすることにしました」
と殊勝な顔つきで言って、二人揃って頭を下げる。
しばらくの沈黙があった後、最初に口を開いたのはお母さんだった。
「琴音さんのお母様は反対してらっしゃらないのね。ま、私があなたたちと同じ年ごろだった頃とは世の中も随分変わって、そういうことも当たり前になりかけているしね。いくつかの自治体じゃ、同性パートナーどうしで一緒に暮らすカップルを支援する条例も制定されているみたいだし。でも、私たちが住んでいる○○市じゃ、そういう条例はまだ制定されていないわよ。女の子どうし一緒に暮らすのはいいけど、ちょっとした日常生活を送るだけでもいろいろ苦労するんじゃないかしら?」
少し心配そうにそう言うお母さんだったけれど、琴音が
「はい、おば様のおっしゃる通りです。ただ、そのことについては、ある程度の目途が立っています。母の仕事を引き継ぐために、私は既に母のお得意様やバイヤーと交流を持っているんですけど、お得意様の中には有力な政治家や有能な弁護士、行政機関で役職に就いている方が何人かいらっしゃって、その方々のお力添えをいただけることになっているんです。市としては条例を制定いていないけれど、或る種の特例措置を講じることは可能だとおっしゃっていただいています。ですから、おば様がご心配しておられる点についてはなんとかなるかなと私たちは考えています」
と言葉を選びながら説明すると
「そう。なら、私が反対する理由はないわね。ただ、女の子どうしだと子供ができないから、もっと孫がほしい私としちゃ複雑なところだけど、ま、それは私の我儘というものでしょうね」
と、安堵の表情で小さく頷いた。けれど、その顔に『もっと孫が』と口にする時に寂しそうな蔭が落ちるのを私は見逃さなかった。
だから私は、わざと明るい声で
「やだな、お母さんったら。孫なら、早苗ちゃんがいるし、もうすぐ早苗ちゃんの妹が生まれるじゃない」
と言ってから、横抱きにしている悠里ちゃんの顔を見おろして
「それに、ほら、ここにも新しい孫が二人もいるでしょ。この子たちは私と琴音の娘、つまり、お母さんの孫なのよ」
と、にこりと笑って付け加えた。
そんな私の言葉にお母さんは
「え? だって……そりゃ、久美が赤ちゃん返りしちゃって、なんだか、娘というよりも孫みたいな感じだなと思うことはあるわよ。でも、いくら『孫みたい』だといっても、久美は娘。孫なんかじゃないわよ。それに、悠里ちゃんまで私の孫だなんて、なんの冗談かしら」
と戸惑いながら応じるのだけれど、それに対して琴音が
「あの、おば様、そのことに関してなんですけど、それについてもお得意様の方々のお力添えでなんとかなりそうなんです。お得意様の方々のご尽力で私と朱美には、正式な婚姻関係にある旨を記した新しい戸籍を作成していただけるらしく、しかも、私たちの新しい戸籍が整った時点で、私たちの戸籍に悠里と久美ちゃんを私たち二人の娘として記載していただけるという約束も頂戴しています。こうすることで、悠里も久美ちゃんも私と朱美の実子、つまり、おば様からみれば本当の孫ということになります。いかがでしょう、これでご納得いただけないでしょうか」
と新たな説明をすると、少し考えてから
「あらあら。この年齢で四人も孫に恵まれるだなんて、私はなんという果報者でしょう。悠里ちゃんとは血は繋がっていないけれど、世の中には、子供の再婚相手の連れ子を本当の孫みたいに可愛がっている方も珍しくないからね。ええ、わかりました。そういうことなら、いよいよ私には二人の『結婚』に反対する理由はありません」
と相好を崩して頷いた。
お母さんとのそんなやり取りの後に口を開いたのは佳美お姉ちゃんだった。
「私は賛成も反対も述べません。あなたたち二人がそう決めたのなら、そういうことなんでしょう。でも、これからの接し方を考える上で一つ訊いておきたいことがあるの。ちょっとプライバシーに踏み込むような質問になっちゃって申し訳ないんだけど――二人の内、どちちらが夫でどちらが妻の役割を担う予定なの? 言い方を変えて訊き直すと、悠里ちゃんと久美の、どちらがパパでどちらがママになる予定のかしら?ということだけど」
確かに、身内どうしの間柄をきっちりしておく上で、それはとっても大切な事柄だ。
私は佳美お姉ちゃんの顔を正面から見ながら
「私たち、旦那さん役とか奥さん役とか、性別によって区分される役割分担は考えてないの。せっかく女の子どうしの婚姻関係なんだから、両方ともが奥さんでママでいいよねって、二人で話し合って決めたんだ。佳美お姉ちゃんの質問に対する答えとしちゃ中途半端かもしれないけど、ごれでわかってもらえると嬉しいんだけどな」
と説明した。
私の説明に佳美お姉ちゃんは
「そう。じゃ、琴音ちゃんは私の義理の妹ってことでいいのね、弟じゃなく。いいわ、今の朱美の説明で納得してあげる」
と微笑んでくれたんだけど、すぐに悪戯っぽい顔になって
「琴音ちゃんが説明してくれた新しい戸籍ができたら、悠里ちゃんも久美も、私の妹である朱美の娘だから、私からみれば姪っ子ってことになるわけね。で、早苗からみれば二人とも従妹になるわけか。あ、それに、美音ちゃんからみても二人は姪っ子、つまり美音ちゃんは若くして叔母さんになっちゃうんだ。うふふ。これからは叔母(伯母)ちゃんどうし、よろしくね」
と美音ちゃんに向かってにこにこ笑ってみせた。
それに対して美音ちゃんは
「私、ずっと妹がほしくて、悠里が妹になった時は随分嬉しかったんですよ。なのに、今度は姪っ子になっちゃうだなんて。ま、妹でも姪っ子でも、どっちでもいいってことにしておきます。どっちにしても、私がお世話してあげなきゃいけないんだし、甘々な琴音ねぇの代わりに私が厳しく躾けてあげなきゃいけないんだし。ということで、こちらこそ改めてよろしくお願いします」
と苦笑交じりに、でも満更でもなさそうに言って人なつこい笑顔になった。
と、そこへお母さんが遠慮がちに割って入って
「どころで、新居はどうするつもりなの? 私としてはみんなと一緒に賑やかに暮らしたいけど、新婚さんとしちゃ親の目を気にせずにラブラブしたいだろうしね」
と訊いてきた。
お母さんの質問に私が
「そのことだったら、琴音ん家の方が部屋が多いから、そっちの家に住もうかなって二人で話しているんだ。空き部屋を女の子らしく模様替えして悠里ちゃんが使っているんだけど、その部屋を悠里ちゃんと久美の子供部屋を兼ねた育児室として使う予定だしね。ただ、お母さんが言う通り二人きりになりたい時もあると思うから、その時は子供たちをこっちの家に預けるつもり」
と答えると、
「あらあら、随分と身勝手なママだこと。ま、いいわ。お父さんが家にいなくて寂しい思いをしてきた分、これからは孫の相手をして賑やかに暮らすのもいいわね」
と、悠里ちゃんと久美が私と琴音のおっぱいを吸う様子に目を細めながら、美音ちゃんに
「子供たちをうちで預かる時は美音叔母ちゃんも一緒にいらっしゃいね。新婚さんのそばにいると邪険にされちゃうわよ」
と言ってわざとらしいウィンクをしてみせた。
それに美音ちゃんが
「そうします。どうせ私は新婚さんのお邪魔をする意地悪な小姑ってことになるわけだから、その時はこちらでお世話になります。それで、家に戻ったら意地悪な小姑の本領を発揮して朱美お義姉さんをいびって楽しむことにします。今から覚悟しておいてね、朱美お義姉さん」
と返して、部屋中のみんながひとしきり明るい声で笑い合う。
そして、その後、みんなの笑い声が鎮まるのを待って、佳美お姉ちゃんが私と琴音の顔を見比べながら
「新居のこともある程度は考えてあるんだったら、私から一つ提案があるんだけど」
と話しかけてきた。
「どうせなら、あなたたち、すぐにでも一緒に暮らし始めた方がいいんじゃないかしら。新しい戸籍とかは、二人が成人してから作成してもらうんでしょう? でも、成人っていったら、今から二年ほども先のことになっちゃう。今から二年間どっちつかずの生活を続けるなんて、子供たちに良くないんじゃないかな。だから、成人とか新しい戸籍とかは後のことにして、今からでも親子四人の生活を始めて、子供たちを慣れさせるべきだと私は思うの。どっちつかずの生活を二年間続けて、それで改めて新しい家族関係を築こうとしても子供たちは戸惑うばかりだと思うのよ。そりゃ、あなたたちにはあなたたちなりの将来設計とかもあるでしょうけど、でも、考えてもみてよ。あなたたちは、ちゃんと結婚する前に子供を授かった、でき婚カップルみたいなものなのよ。だったら、世間のでき婚カップルと同じように、自分たち二人のことよりも、子供たちの幸せを先ず考えるべきなんじゃないかな。お節介かもしれないけど、人生の先輩からの忠告として二人で話し合ってほしいんだけどな」
真剣な眼差しでそう言ってくれた佳美お姉ちゃんの言葉に、はっとした表情で私と琴音は顔を見合わせた。
言われてみれば、確かにそうだ。
ううん、言われなくても、そこまで考えるべきだったんだ。
話し合う必要なんて、これっぽっちもなかった。私と琴音は無言で頷き合い、代表して私が
「佳美お姉ちゃんの忠告に従って、私たちは今夜から一緒に暮らすことにする。でも、一つだけ我儘を聞いてほしいんだ。今夜から一緒に暮らすということは、つまり、今夜が二人で過ごす初めての夜、要するに、初夜ということになるんだけど、記念すべき初夜は二人だけで過ごしたいわけで、ええと、だから、早速で申し訳ないんだけど、今夜は子供たちをこっちで預かってもらいたいなぁなんて。本当に身勝手だけど、お願い」
と、『初夜』という言葉を口にする時はほっぺを赤く染めながら、みんなに言った。
私たちのそんな『我儘』をみんなは快く聞き入れてくれたんだけど、その時に美音ちゃんが
「あ、小姑が家から追い出される場面が早速きちゃった。これって、佳美さんの提案のせいですよね。だったら、佳美さんに責任を取ってもらわなきゃ。今夜の夕飯、私はこちらの家でいただくことになるから、これまで食べたことのないようなすっごいご馳走をお願いしますね」
とこれ見よがしにほっぺを膨らませてみせて、もういちど笑い声が湧き起こった。
「小っちゃい子がいるだけで、こんなに和むもんなんだね。こんなふうだと、孫には成長してほしいような成長してほしくないような、複雑な気持ちになっちゃうわね」
みんなが笑い合う中、感慨深げなお母さんの呟き声が印象的だ。
(でも、そのことだったら安心していいよ、お母さん。悠里ちゃん――あ、この子も久美と同じ、私の娘になるんだ。だったら、『ちゃん』付けで名前を呼ぶのはおかしいよね。私の子供と琴音の子供、分け隔てがあっちゃいけないよね。だから、悠里ちゃんじゃなく、悠里。それでいいんだよね――悠里と久美はいつまでも成長しないで、ずっとずっと赤ちゃんと年少さんのままでいるからね。琴音の仕事のお得意様の中には、すごく優秀なお医者様もいて、そのお医者様は、人の外見を若いままに保つ研究をしているんだって。見た目が若いだけで不老不死ってわけじゃないけど、それでも凄い研究だよね。それで、研究は順調に進んでいて、もうすぐ治験が始まるらしいよ。でね、琴音の伝手で、悠里と久美を被治験者のリストに入れてもらっているんだ。だから、うまくいけば、ずっと可愛いままの悠里と久美を手元においておけることになるんだよ)
私は胸の中でお母さんに教えてあげた。もしも治験がうまくいかなかったら失望させちゃうことになるから今はまだ言葉にして教えてあげることはできないけれど、きっとうまくいくよ。嬉しい報告が届く日が来るのをもう少しだけ待っていてね。
*
お昼ご飯の後は子供たちのお昼寝タイム。 リビングルームの床にバスタオルを三枚広げて、その上におねしょシーツを一枚ずつ、お互いに手を繋ぐことができるよう間隔をあまり広げずに敷く。
ほら、ねんねだよと言ってもなかなかおっぱいから離れようとしない悠里と久美だけど、早苗ちゃんがお姉さんらしく率先してママ(このママというのは、佳美お姉ちゃんのことね)のそばに歩み寄ってパジャマに着替えさせてもらうと、それを真似て久美も琴音の手を離れ、私の方にやって来ようとした。だけど、私が悠里を抱っこしたままなのを見ると、もうすっかり上手になった這い這いで
「ばぁば、ばぁば」
と、私のお母さんの所へ近づいて行く。本当は私に着替えさせてほしかったんだろうけど、私が悠里におっぱいをあげているのを見て遠慮したんだろう。その点、(元が優等生だけあって)気遣いのできる、ご自慢の娘だ。 ただ、早苗ちゃんと久美がお昼寝の準備をしてもらっている間も、悠里は私のおっぱいにしがみついたまま離れようとしなかった。
「ほら、妹の久美もばぁばに着替えさせてもらっているわよ。なのに、お姉ちゃんの悠里がいつまでもおっぱいだなんて変でしょ」
そう言って私が悠里のほっぺを指でつんつんしてみると、悠里からは
「悠里、お昼寝しない。悠里、パジャマ持ってきてないもん」
という、ちょっぴり拗ねた声が返ってきた。
それを聞いた琴音が、あっという顔をして
「おば様や佳美さんへのご挨拶のことで頭がいっぱいで、パジャマのことをすっかり忘れていたわ。ごめんね。すぐに家へ戻って取ってくるわね」
と慌てた様子で言う。
ふぅん、しっかり者の琴音でもミスなんてすることがあるんだ。でも、たしかに、両家の顔合わせみたいなことをして、お母さんと佳美お姉ちゃんへの挨拶なんかじゃ随分と緊張したにちがいないから、今回のことは仕方ないか。
「いいよ、わざわざ取りに戻らなくても。前もってこっちで用意しておいた物があるから、それを使えばいいよ。替えのおむつが入っている衣装籠の隣に、それよりも大きな衣装籠があるでしょう? うん、そう、そう。その中に薄いブルーの生地の――ああ、それよ。それを広げてみて」
今にも駆け出しそうにする琴音を押しとどめた私は、二つ並べて用意しておいた衣装籠の片方からブルーの生地の衣類を取り出すよう言って、両手で衣類の肩を持ってみんなによく見えるよう大きく広げてもらった。
「あ、保育園の制服だ」
遊び着からパジャマに着替えさせてもらった早苗ちゃんが、琴音が手にした衣類を見て嬌声をあげる。
そう。早苗ちゃんの言う通り、それは、早苗ちゃんが通っている保育園の制服を模して私が仕立てたセーラースーツだった。
ただ、正確に言うと、制服というわけじゃないんだ、これ。早苗ちゃんの保育園の制服は、男の子が丈の短いセーラースーツの上着に白の半ズボンの組み合わせで、女の子はセーラースーツの裾を伸ばしてスカートにして白のストライプをあしらったワンピースになっている。私が仕立てたのは、女の子の制服のスカートになっている部分を、股間にスナップボタンが横に四つ並んだかぼちゃパンツみたいな形に変更した、そんな衣類だ。
「へーえ、保育園の制服をモチーフにしたロンパースね。よくできてるじゃない。朱美ったら、こういうことに関してだけはセンスがいいのよね」
半ば感心したような半ばからかうような佳美お姉ちゃんの声。
ぴんぽーん。佳美お姉ちゃん、大当たり。
小っちゃい子は眠っている間もよく体を動かす。簡単に言うと、寝相がわるい。特に夏場はそうだ。だから、お知らず知らずのうちに腹を出して寝冷えしちゃう。お昼寝の間にそんなことにならないように、早苗ちゃんは上下がボタンで繋がってお腹が出ないようになっているパジャマをママに着せてもらったし、久美は、肌に傷がつかないようボタンの代わりに布紐で合わせ部分を留めるようになっている短肌着の上に、内股をボタンで留めるようになっていてお腹が出ないコンビオールをばぁば(私のお母さん)に着せてもらっている。そんな二人に比べて、悠里は美音ちゃんのお下がりのワンピースタイプのナイティを着てねんねしていると琴音が言っていた。そんなじゃ、可愛い我が子が風邪をひいてしまう。だから、私が作ってあげたんだ、特製のロンパース。ちなみに、早苗ちゃんが着ている上下つなぎのパジャマも、久美の短肌着とコンビオールも、どっちも私のお手製。上下つなぎのパジャマは市販品も多いんだけど、まだ年少さんのくせに選り好みが激しい早苗ちゃんのお気に召すようなデザインのがなかなか売ってなくて、私が作ってあげることにした。久美の短肌着とコンビオールは、そもそも、本当の赤ちゃんと比べるとずっと体が大きい久美が着られるようなものなんてどこにも売ってない。だから、私が作るしかなかった。そうやって早苗ちゃんのと久美のと、普段着も含めてかなりの数の衣類を仕立ててあげた私にとって、悠里に着せるロンパースの一着や二着作るくらい、てんで苦にならない。それどころか、むしろ、普段の遊び着も外出用のちょっとお洒落な洋服も、新しい戸籍ができて保育園に通うようになったら必要になる制服もスモックも体操着も水着も、喜んで私が作ってあげる(ま、悠里の体に合うサイズのを保育園指定の業者が手配するのは難しいだろうなという理由もあるんだけど)つもりだ。うふふ。可愛い姉妹のペアルックのデザインをもう何着分も頭の中に思い浮かべているくらい張り切っちゃってるんだからね。
でも、当の悠里は
「悠里、そのパジャマ、や。赤ちゃんのパジャマみたいで恥ずかしい」
と、あまり乗り気じゃない。
だけど、まわりのみんなが
「保育園の制服みたいで、お姉さんらしくていいじゃない。とっても可愛いし」
「せっかく朱美ママが作ってくれたんだから着てあげなさいよ。すごく可愛いパジャマだよ」
「可愛い悠里ちゃんにお似合いの可愛いパジャマだね。ほら、早く着てみせてよ」
と口々に『可愛い可愛い』を連発するうちに(薬の暗示効果と相まって)
「可愛い? パジャマ、可愛い? 悠里、可愛い?」
と少しずつその気になってきたらしく、ちょっぴり迷った後、おずおずと乳首から口を離して
「……悠里、そのパジャマ着てみたい。悠里にパジャマ着せて、朱美ママ」
と、はにかんだ様子で頬を薄紅色に染めて甘えた声で私にねだった。
*
特製のロンパースを着た悠里は想像していたよりもずっと可愛かった。早苗ちゃんのこと、天使みたいだとずっと思っていたけど、それに負けないくらい愛くるしい。特に、たっぷり当てたおむつのせいでロンパースのお尻がふっくら丸く膨らんでいるところなんてたまらない。

その思いはお母さんも同様らしく、
「あらあら、すっかり見違えちゃったわ。さっきまでの遊び着も活発そうでよかったけど、こっちはお姉さんらしさとあどけなさがうまい具合に混じり合って、本当に可愛らしいこと。こんなに可愛い孫ができるなんて夢みたいだわ。あ、そうだ。今日は悠里が私の孫になってくれた特別な日。特別な日を記念して、ばぁばが膝枕で寝かしつけてあげる。さ、ばぁばのところへいらっしゃい。悠里はちゃんとあんよできるよね」
と相好を崩して、悠里に向かって両手を大きく広げてみせた。
一瞬きょとんとする悠里。
だけど、躊躇ったのは本当にほんの一瞬だけ。
すぐに、面映ゆそうな、そのくせ、微塵の陰りもない嬉しそうな笑みを浮かべて
「ばぁば、悠里のばぁば」
と声を弾ませて美保ばぁば(私のお母さんのこと。以後、表記がこんがらないように、呼称を『美保ばぁば』に固定します)の胸にとびこんだ。
美保ばぁばは悠里の体を胸に掻き抱いて
「ばぁばのところへよく来てくれたね。よく、ばぁばの孫になってくれたね。悠里はばぁばの宝物。本当に、よく来てくれたわね」
と、それまで聞いたことのないような慈しみに満ちた声と共に、背中を両手で何度も何度も撫でさすった。
その様子を早苗ちゃんも久美もじっと見ている。でも、自分のばぁばを悠里に取られちゃうというような拗ねた表情は二人ともしていない。今日が本当にとても特別な日だということを幼心に感じ取っているんだろう。
その後、美保ばぁばは自分の太腿に悠里の頭を載せさせて膝枕をし、悠里のお腹をぽんぽんと優しく叩きながら、どこか遠いところを見るような目をして、誰にともなく
「今日は特別な日だから、少し昔話でもしようと思うの。古い話だから退屈かもしれないけど、よかったら聞いてちょうだい」
と言って、ぽつりぽつりと、自分の若い頃のことを話し始めた。
「この中にはそんなことを知っている人はいないけど、琴音さんたちのお母さん――真由美さんと私は古くからの知り合いなのよ。いいえ、知り合いというような水くさい間柄じゃないわね。家が隣どうしの幼馴染みで、幼稚園から大学までずっと一緒だった。そして……」
そこまで話してほんの少しだけ逡巡の表情を浮かべて、でも、すぐに続きを話し始める。
「……親元を離れて少し遠い都会の大学に入って、二人で共同生活を始めたの。マンションの一室を二人で借りて、今ならルームシェアとか言うんでしょうね。そうして、共同生活が始まったその日、二人――私と真由美さんは愛し合った。それはそれは激しく愛し合った。今と違って、誰にも打ち明けられない時代だったの。それに、二人とも、地元じゃ旧家の娘でね、世間体もあって、世間には絶対に知られちゃいけなかった」
美保ばぁばが悠里のお腹を叩く手つきはひたすらに優しい。
「二人とも、女性の同性愛者、レズビアンでね、いいえ、厳密に言うと、レズビアンの性向が強いバイセクシャルでね、私の初恋の相手は真由美さんだったし、真由美さんの初恋の相手は私だった。胸の中のざわめきが収まることはまるでなく、成長するにつれて不埒な欲望はますます強くなっていった。そうして、共同生活が始まったその日、二人は欲望のまま互いの体をむさぼり合った」
部屋中がしんと静まり返る。
「だけど、大学を卒業すると同時に愛欲の日々は終わりを告げた。故郷に戻った私たちは親の言うまま見合いをさせられることになった。でも、真由美さんは、そんな古い因習に抗う勇気を持っていた。私に、家を出て二人で暮らそうと言ってくれた。だけど、私にはそんな勇気はなかった」
そこまで話して、美保ばぁばは言葉を探すためなのか、少し間を置いた。
「勇気はなかったし、それにもう一つ、どうしても真由美さんの申し出に従えない理由があった。真由美さんから見ればひどくちっぽけな理由で、ひどく身勝手な理由。そんな理由で自分の愛を拒むなんてと怒りを覚えても仕方の無いような理由。でも、私にとっては、どうしても譲れない理由だった。それは、簡単に言ってしまえば、私が無類の子供好きだったという、本当に取るに足らない身勝手な理由。若い内に欲望のまま愛欲にまみれるのは、それはそれでいいかもしれない。だけど、生涯を真由美さんと――同性を伴侶として暮らすことを考えた時、せっかくの申し出を受け容れることはできなかった。だって、女性どうしだと子供をつくれないもの。子供というのは、単に両親の遺伝子を引き継いだだけの存在なんかじゃない。両親の愛が、生命を宿した結晶としてこの世に姿を現した、何ものにも代え難い、それはそれはいとおしい存在。私は心からそう信じていた。だから、年老いて二人だけで生活している自分たちを想像して、それを受け容れることができなかった」
美保ばぁばは、うつらうつらし始めた悠里の顔を見ながら何度も瞬きを繰り返した。
「結局、真由美さんは一人で家を出て、大学時代に知り合った留学生の伝手を通じて個人で貿易商を営むことになった。私は親の言うままお見合いをして、その人と結ばれた。それが康正さん、つまり佳美たちのお父さん。私はバイセクシャルで、積極的にとはゆかないけれど、男性を受け入れることができるし、康正さんは私の過去を薄々察していながら私を愛してくれて、三人の子供にも恵まれた。これ以上の生活を望んだりしたら罰が当たるでしょうね。その一方、真由美さんは、私との同居生活の思い出を忘れるためか、仕事に没頭すると同時に、女性よりもむしろ男性と浮き名を流し、一時の逢瀬を重ねる生活を送るようになった。その結果として三人の子供を授かった」
美保ばぁばは、なんとも表現しようのない表情で、琴音、美音ちゃん、悠里の顔に遠慮がちな目を順に向けた。
「でも、真由美さんは男性とかりそめの愛で交わっても悦びを得ることはなかった。それどころか、却って、男というものの存在に対する否定的な情念が昂じるだけだった。ただし、男という存在に対して憎しみや怒りや妬みや鬱陶しさを覚えたわけでは決してなかった。真由美さんが男という存在に対して胸の中に抱いたのは、憐憫の情だった。男という存在それ自体に、そして、男たちが築いてきたこの社会に。男というものは、そして男たちが築き上げた社会は、なんと下劣でなんと醜悪でなんと小賢しくてなんと陰鬱なのだろう。そんな社会を築き維持することしかできない男という在り方を限りなく憐れんだ」
美保ばぁばの目は悠里の顔に向けられたまま。
「けれど、そんな真由美さんに最初に生まれたのは、皮肉なことに男の子。血を分けた我が子であっても、いいえ、我が子だからこそ、その男の子を憐れんだ。それから二人続けて生まれた女の子に対して、長男への哀れみの情を隠そうとしなかった。今となっては、幼い頃の記憶は曖昧になっているものの、母親から受け継いだ男への、兄への憐憫は、成長する女の子たちの胸の中で着実に育っていた。だけど、繰り返して言うけれど、それは憎しみや怒りや妬みや鬱陶しさといった感情などでは決してなかった。女の子たちが胸の中に抱いたのは、深い憐れみの情。そして、それが転じた、憐れみの対象でしかない兄をなんとしてでも『救済』したいと願う激しく強い情動。憐れみと願いは徐々に女の子たちの胸の内で大きくなり、無意識領域の大半を占めるまでになった」
美保ばぁばの視線が悠里の顔から琴音と美音ちゃんの顔に移った。
「憐れみと願いを胸の内に宿しつつ、女の子たちは『きっかけ』を待った。そして、もうすぐ夏休みという或る日、とうとう『きっかけ』が訪れた。――これまで話したことは、全て私の想像。でも、思い違いなんかじゃ絶対にない。真由美さんのことで私が知らないことなんて一つもないんだから」
そこまで話して、美保ばぁばは口調をがらりと変えて
「そういうことよね、琴美さんと美音さん? でも、誤解しないでね。私はあなたたちを責めるためにこんな話をしているんじゃないの。何が良くて何が悪いのか。誰が正しくて誰が間違っているのか。私はそんなことを話したいわけじゃないのよ。ただこれまでの経緯を一度きちんと受け止め直しておかないと、これからの新しい生活の意味がまるで違ったものになってしまう。ただ、そう思ってのことなのよ」
二人に向かってそう話しかける美保ばぁばの顔には穏やかな笑みが浮かんでいる。
「私と康正さんが念願のマイホームを購入して一年後、真由美さんがお隣の家を買った。それは、意図してのことじゃなく、偶然の結果だと私は信じているの。ちょうどその頃、ここいらの地域の再開発が大々的に行われて、いくつかの建設会社が損得抜きのキャンペーン価格で競うようにして新築住宅を販売していたしね。あれだけ大々的に宣伝されれば、この地域に興味を向ける人が大勢いて、その中に真由美さんがいてもおかしくないもの。それに、真由美さんは、いつまでも私に執心するような人じゃない。そのことは私が一番よく知っている。あの時から年月を経て、わだかまりが一切残っていないとは言えないものの、それなりに人生経験を積んできた私たちには、お互い、いわゆる普通のご近所づきあいをおくることができる程度のゆとりはできていた。ま、普通よりも幾らかは親密な近所づきあいかもしれないけど。そんなふうにして再び始まった真由美さんと私の交流。それから今までに過ぎ去った年月」
美保ばぁばの感慨深げな声。
「話を少しだけ戻すけど、『きっかけ』は、朱美が何やら面白そうな計画を立てていそうだと琴音さんが気づいたことだった。その頃に服飾文化研究部の部室で朱美が夢中で制作していた特別な衣装とかを目にして、なんとなく思い当たるところがあったんじゃないかしらね。それから、雑談交じりに計画の内容を断片的に朱美から聞き出して、最終的にその全貌を推し量った琴音さんは、朱美の計画を利用することにしたのよね? 悠里さんが久美に告ろうとしていると琴音さんは朱美に告げた。それに乗じて琴音さんは朱美の計画の協力者になりおおせた。悠里さんが久美に告ろうとしていたという事実は、おそらく、なかったんじゃないかしら? 絶対にとは言わないけど、そうなんだと思う。ま、そんなこと今さら詮索してもしようがないわね。それが事実だったとしても事実じゃなかったにしても、いずれは琴音さんと朱美は協力して計画を進めることになるんだから」
美保ばぁばは私と琴音の顔をすっと目を細めて何度も見比べた。
「計画――真由美さんの長男である悠里さんを『救済』するための計画。悠里さんに対して限りない憐憫の念を抱いた琴音さんと美音さんは、悠里さんから男としての属性を全て除去して、自分たちと同じ女としての属性を与えようと考えた。男であることをやめさせて、新たに女としての人生を歩ませること。それこそが、底知れぬ憐憫の対象である悠里さんを『救済』する方法に他ならない。ただ、そうするためには悠里さんをいったん幼児に戻して、女の子として育て直し、躾け直す必要がある。朱美が久美を赤ちゃん返りさせる計画を立てていることを知って、その対象に悠里さんを含むよう計画を練り直し、琴音さんが朱美の計画に協力しているかのように装いつつ、実は琴音さんの方が朱美を協力者に仕立てていたのよね。悠里さんを幼児に戻す計画の協力者に」
くすっと美保ばぁばが笑った。
「繰り返しになるけど、私は琴音さんと美音さんを責めるためにこんな話をしているんじゃないのよ。むしろ、その逆。私は応援しているの、あなたたちを。真由美さんの娘である琴音さんと、私の娘である朱美。それは、時を経て再び出会った真由美さんと私。もうひとりの真由美さんと、もうひとりの私。私はね、今度こそうまくやってほしいの。過去の二人が結局はかなえることができなかった夢を、再び出会った二人には是非ともかなえてほしいの。でも、ま、心配はしていないわ。今度こそうまくやってくれるって信じている。あの時は、子供がほしくてたまらなかった私のせいで願いを果たせなかった。だけど、今はもう子供がいるんだもの。悠里と久美という可愛らしい子供を既に授かっているんだものの。だから、大丈夫、きっとうまくやってくれる。そう信じて応援している」
そんなふうに言って口を閉じた美保ばぁばの表情は穏やかだった。人はこんなにも穏やかな顔になれるのかと驚いてしまうほど穏やかな表情。
ばぁばに膝枕をしてもらって気持ちよさそうにねんねしている悠里は、何かいい夢でも見ているんだろう、とても幸せそうな顔で寝息をたてている。
早苗ちゃんに手を繋いでもらったままおねむの久美は、あどけない顔ですやすやとやすらかな寝息。
*
夏の日の昼下がり。
気怠くも心地よい時間が流れる中、不意に
「ぅ、ぅう、ぅえーん。ふ、ふぇーん」
という泣き声が静寂を破った。
「あらあら、どうやら、おねむの間にしくじっちゃったみたいね」
美保ばぁばが、いかにも愛おしそうな目で、膝枕をしてあげている悠里の顔を見おろして呟いた。
「ばぁばの膝枕が気持ち良くて、おしもが緩んじゃったのかな」
それまでの堅苦しい雰囲気を払いのけようとして、私は努めて明るい声で応じた。
それと前後して
「ふぇふぇ、ぇーん。う、う、ぅぇーん」
と、別の泣き声。
泣き声の主は久美だった。
「うふふ。本当に仲良しね、悠里と久美は。いいわ、二人とも私がおむつを取り替えてあげる」
美保ばぁばが相好を崩して、嬉しそうな声で言う。
「いいよ。私と琴音で取り替えるからお母さんはゆっくりしていてよ」
そう私は言ったんだけど、美保ばぁばが
「布おむつを当ててあげるには、なるべく横漏れしないように、ちょっとしたコツがあってね。さっき二人がおむつを取り替える様子を見ていて思ったのよ、実際に悠里か久美のおむつを取り替えてあげながらいろいろ教えておいた方がよさそうだなって」
と言うものだから、お願いすることにした。
「取り替えた後で、布おむつの縫い方も教えてあげるわね。これから先、いくらあっても足りなくなりそうだから、愛情をたっぷり込めて手縫いで仕立ててあげなさい」
悠里のおむつを取り替える準備をいそいそと始めながら、美保ばぁばは、どこにでもいそうな、孫が可愛くて仕方のないお人好しのおばあちゃんの顔になって声を弾ませた。
その柔和な顔を目にして、ふと私は疑念を抱いた。計画を頭の中に思い浮かべて、計画を練って、計画を実行したのは、本当に自分たちの意思によるものだったのだろうか。ひょっとしたら、琴音のお母さんと私のお母さんが共謀して私たちにあの薬をのませ、計画を遂行するよう仕向けたのではないだろうか。
――でも、ま、それが事実なのかどうかなんて、実のところ、どうでもいいことだ。琴音と私は互いに生涯の伴侶を得ることができたし、可愛い子供たちも授かった。満ち足りた幸福の中で、些細な『真実』とやらを見つけ出したとして、今更それが何ほどの意味を持つというのか。
隣の家の二階のバルコニーでいろんな柄の布おむつが夏のお日様の光を浴びて風に揺れる様子が、リビングルームの大きなガラス戸越しに見える。隣から見える我が家のバルコニーでも、洗濯したばかりのおむつがたくさん風にそよいでいる。
隣り合って仲良く建っている二軒の家のバルコニーにおむつが見当たらなくなる日が来ることは永遠にないだろう。
|