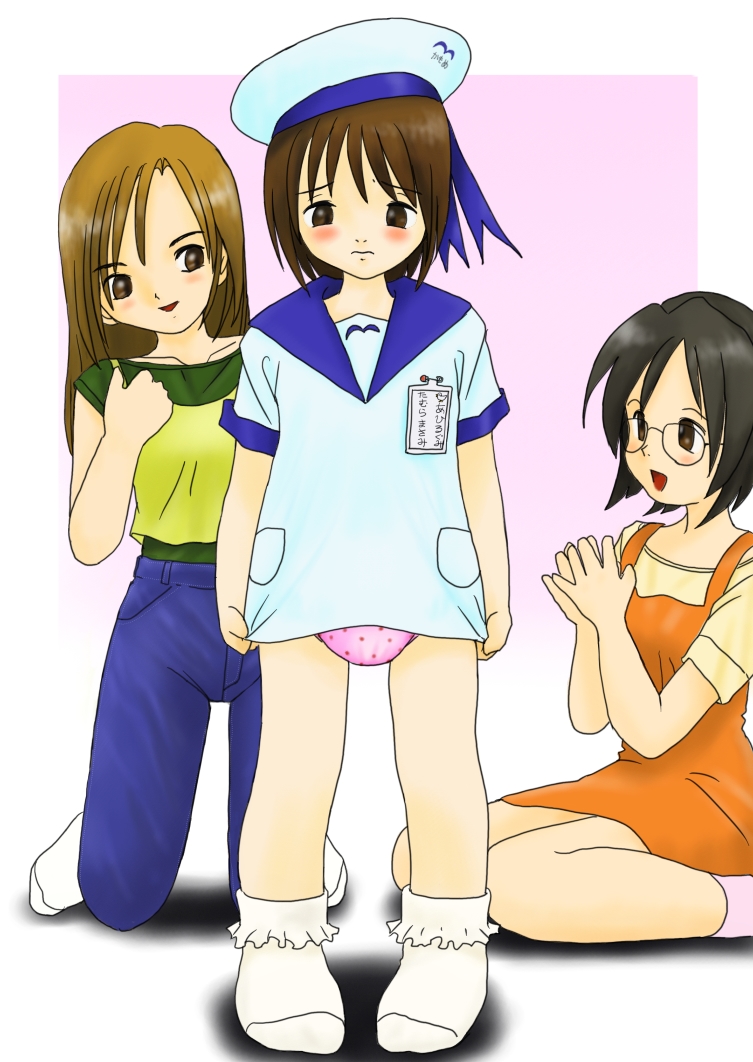幼児への誘い・4
雅美の体を支えるために膝立ちの姿勢になっていて真っ先にスカートの短さに気づいた香奈は、少しばかり言いにくそうに紀子に声をかけた。紀子お薦めの仕立て屋のしたことにケチをつけるみたいで、なんとなく口にするのが躊躇われる。 「……この制服、スカートが短いんじゃないかしら。採寸が間違っていたとか、型紙を起こす時に何か数字を間違ったとか、そういうことはないかしら」 「いいえ、そのようなことはございません。その長さに仕立てるよう申しつけたのは私でございます」 香奈の言葉を紀子はやんわり否定した。 「カモメ幼稚園の本当の制服はスカートが膝丈になっていることは私も存じています。けれど、その長さですと、今の雅美お嬢ちゃまにはスカートが邪魔になってしまいます。まだあんよがお上手でない雅美お嬢ちゃまには、なるべく短いスカートでないと、スカートがまとわりついて、余計にあんよが上手にできません。ただでさえ、おむつのせいで歩きにくうございますから。それに、おむつを取り替える時も、長いスカートですと邪魔になりますでしょう? その点、このくらい短くしておきますと、おむつを取り替える台がない所でも、立っちのまま取り替えることもできますし」 「あ、そういうことだったんですか。すみません、事情も知らないで余計なこと言っちゃって」 香奈は申し訳なさそうに肩をすくめた。 「いえ、よろしいんですよ、気になさらなくても。幼稚園の制服というのは、おむつの外れたお子様向けにデザインしてあるのが普通でございますから、香奈お嬢様がこの特別注文の制服のスカートが短いとおっしゃるのはもっともなことでございます」 却って紀子の方が恐縮したように恭しく頭を下げた。 「そうだよね。年少さんでも、幼稚園に入る子なら、おむつが取れてるのが普通だよね。でも、私と同じクラスに一人だけまだおむつの取れてない子がいたよ。そういえば、その子の制服、お母さんが寸法を仕立て直したとかで、随分スカートが短くなってた。紀子さんが言ったみたいに、おむつだとスカートが短い方がいいのかな」 雅美の頭にかぶせたセーラーキャップの角度を微妙に調節しながら、真澄が小首をかしげて言った。 「そうでございましょうね。でも、これで安心ですわ。真澄お嬢様がおっしゃったように、幼稚園でも年少さんなら数は少なくてもまだおむつ離れしていないお子様もいらっしゃるのですね。それでしたら、雅美お嬢ちゃまをお外に連れて行ってあげても、おむつのことを変に思われることもございませんでしょう。いえ、正直なところ、今も迷っていたのでございますよ。幼稚園に通うようなおねえちゃんがおむつですと、周りの人から変に思われないか。かといって、おむつを外しておねえちゃんが穿くようなパンツですと、雅美お嬢ちゃま、いつおもらししてしまうかしれませんし、どうしたものかと。いえ、でも、これで安心でございます。お嬢ちゃまにはおむつで水族館に行っていただけますわ。それでよろしゅうでございますね、奥様」 最初からおむつで外出させるつもりだったのに、わざとらしい安堵の溜め息をついてみせて、紀子は美智子に同意を求めた。 「もちろんですとも。万が一おもらしでもして周りの方々に迷惑をかけたらいけませんからね。――さ、用意はいい? 雅美ちゃんのお着替えが終わったのなら出発しますよ」 「は〜い」 美智子のあとに続いて、ランチバスケットを手に持った香奈と、雅美の手を引いた真澄が元気よく廊下に足を踏み出した。 そこへ 「お待ちください。忘れ物です、奥様」 と大慌ての紀子の声が飛んでくる。 なにごとかと振り向いた四人に向かって紀子が差し出したのは、ウサギの顔を模した蓋の付いたリュックサックだった。蓋がウサギの顔を模したデザインになっているだけでなく、小さな手と足まで飾りに縫い付けた、それこそ幼稚園児くらいの子が大喜びしそうな可愛いリュックだ。 「替えのおむつとおむつカバーでございます。お弁当やジュースはどこでも買えますけれど、雅美お嬢ちゃまのおむつカバーはどこにでも売っているというものではございません。おむつはベビー用品売場で出来合いのものを手に入れることができるかもしれませんけれど、おむつカバーは、大きな赤ちゃんの体に合わせて仕立てさせた特別注文でございますから」 そう言うと、紀子は、替えのおむつとおむつカバーで大きく膨らんだアニマルリュックを雅美の背中に背負わせた。 まるで本当に小さな子供みたいに自分のおむつを入れたリュックを背負わされる羞恥にまみれながら、けれど、もう雅美には、抵抗する気力など残っていなかった。美智子と紀子だけでなく、埼玉からやって来た二人の妹からも徹底的に赤ん坊扱いされて、それを拒む気力はすっかり失せてしまっていた。ただ、羞恥と屈辱とが姿を変えた被虐的な悦びにじんじんと疼く下腹部から滴る恥ずかしいおつゆで新しいおむつをぬるぬるに濡らすことしかできない雅美だった。 *
神戸市立須磨海浜水族園。 慌てて駆け寄る香奈と真澄。 けれど、真澄が手を引いて立たせるまでの間に、倒れた拍子にお尻の上まで捲れ上がったスカートの下から覗いたおむつカバーを、ホールを行き交う大勢の来館者に見られてしまった。その中には、 「あ、ママ、見て見て。あの子、幼稚園かな。幼稚園なのに、おむつしてるよ。赤ちゃんみたいだね」 と言って無遠慮に雅美のお尻を指さす、この春に小学校に入ったばかりくらいの少女もいた。さすがに母親の方は 「ダメよ、そんなこと言っちゃ。おむつが取れる時はみんなばらばらなんだから、幼稚園の子でもおむつをしてても仕方ないの。そんなこと言われて、あの子が恥ずかしがったら可哀想でしょ?」 と言って少女をたしなめるのだが、それでも、幼稚園児にしては大柄な雅美のお尻がおむつカバーに包まれている姿にちらちらと好奇の目を向けているのが明らかだった。 「大丈夫、雅美ちゃん? 痛くなかった? これからは勝手に走っちゃダメよ。雅美ちゃんはまだあんよが上手じゃないんだから」 怪我が無いかどうか、真澄が引き起こした雅美の膝のあたりに目をやって確認しながら、制服に付いた埃をぱっぱっと払って香奈が言った。 雅美は無言で頷いたものの、さっきの少女が香奈の言葉を耳にしたらしく、 「ママ、あの子、あんよも上手じゃないだって。幼稚園みたいなお洋服だけど、本当は赤ちゃんかもしれないよ」 と言っているのが聞こえて、思わず頬を真っ赤に染めてしまう。そうして、(あの子、私のこと、本当は赤ちゃんかもしれないって言ってる。私、本当は大学生なのに。なのに、赤ちゃんかもしれないって。私、やっぱり、そんなふうに見えるのかな。幼稚園の制服もまだ早い、赤ちゃんみたいに見えるのかな)頬を赤くしながらそう思うと、真夏の暑さで蒸れ始めているおむつカバーの中が、汗とはまた違う濡れ方でぬるぬるしてくる雅美だった。 「怪我も無いみたいだし、じゃ、お魚の所へ行きましょう。雅美ちゃんの大好きなお魚さんでちゅよ」 香奈はそう言うと、顔を赤くして黙りこんでしまった雅美の背中をそっと押した。 真澄に手を引かれて水槽の方に歩きかけた雅美だが、すぐに首をぶるんと振って立ち止まってしまう。 「どうしたの、雅美ちゃん。せっかく、雅美ちゃんの大好きなお魚がいっぱい泳いでるのに」 雅美が足を止めたことを訝って、真澄が気遣わしげな口調で訊いた。 「お魚、もういい。お魚、あとで見るから、別の所へ行く」 大水槽はあとで見ればいいから、とりあえず、ここから離れたい。このまま、おむつカバーを見られた来館者たちと一緒に水槽の前にいるのは恥ずかしい――雅美は本当はそう言いたかった。けれど、そんな大人びた口調で話して、それが誰かの耳に届いたりしたら、更に好奇の目で見られてしまう。そのことは雅美にもわかっていた。わかっていたから、わざと幼児めいた喋り方をせざるを得なかった。 「そう。じゃ、どこがいいか探してみようか」 雅美が本当に言いたいことをすぐに理解した香奈は、入館する時に貰った園内マップを広げてじっと見つめた。そうして、ここがいいかなと呟いて、雅美の方に向き直る。 「この建物の屋上にタッチプールっていうのがあるわ。人が泳ぐプールじゃなくて、ヒトデとかナマコとかを飼ってて、自由に触れるんだって。ここなら雅美ちゃんに喜んでもらえるかな」 香奈の提案に雅美は無言で頷いた。一刻も早くこの大ホールから離れることができるなら、行き先はどこでもいい。 「それじゃ、行きましょう。あ、でも、注意書きがあるわね。ええと、タッチプールで飼っている生き物は、水に浸けたまま触ってください。水の外に長い間出していると干からびて死んでしまいます、だって。雅美ちゃん、お約束できるかな? ヒトデとかをお水から出しちゃいけないのよ。いいわね?」 海洋生物に対する知識なら雅美の方がずっとあるというのに、香奈はそれこそ小っちゃな子供に言い聞かせるみたいに言った。 けれど、それに対して、黙って頷くしかない雅美。 「香奈おねえちゃん、エレベーター、あっちだよ」 香奈と雅美が会話を交わしている間に目敏くエレベーターホールをみつけていた真澄が、雅美が顔を上げると同時に歩き出した。 真澄に手を引かれた雅美がおぼつかない足取りでよちよちと歩いて行く様子を後ろから見守る香奈の顔には、少し意地悪な笑みが浮かんでいた。 ホールで大水槽の魚を見た後は、螺旋状に伸びるスロープを歩いて上の階へ行くのが順路になっている。スロープ沿いの壁にも幾つも水槽が填め込みになっているし、上の階にも大小様々の展示室があるから、大半の来館者は直接エレベーターで屋上へ行くようなことはしない。 だから、エレベーターの中には、雅美たち三人の他には誰もいない。 雅美は、ほっと溜め息を漏らした。ようやく他人の目を気にしなくてもよくなったと思うと、少し緊張が解ける。 けれど、緊張は解けても、ひどい羞恥はそのままだ。いかにも保護者然とした顔で雅美の両側に立っているのが実の妹だと思うと、あらためて屈辱と羞恥で胸がいっぱいになってくる。しかも、真澄がおむつカバーの上から雅美のお尻をぽんと叩いてこんなことを言うから尚更だった。 「おむつ、大丈夫? ちっち、出てない?」 雅美のスカートを僅かに捲り上げるようにしておむつカバーの上からお尻を叩きながらそう言う真澄の仕草は、幼い妹を気遣う優しい姉そのままだった。とはいえ、真澄は雅美のことを気遣ってばかりいるのではない。わざわざそんなふうにしておむつの具合を確かめるのは、雅美の羞恥を掻き立てるためだった。美智子と紀子の前だけでなく、どこでも誰の目があるところでも赤ん坊そのままに振る舞うようになるまで雅美の赤ちゃん返りを進めるために、わざと羞恥心を刺激して、雅美に自分は赤ん坊なのだと思い知らせてやってほしいと予め美智子に言いふくめられていたから、その通りにしているのだった。 美智子が水族館へ行こうと言い出したのも、自分の企みを実行に移すためだった。雅美が昼寝をしている間に家へやってきた二人に向かって、美智子は、自分の計画を残らず話した。雅美が胸の中に赤ちゃんの頃に戻りたいという思いを抱いているという事実を強調しながら、美智子が雅美を高志のお嫁さんにしたいと思っていること、高志が実は奇妙な性癖を持っていて赤ちゃんみたいな女の子が好きなこと、美智子が本当は女の子も育ててみたいと思っていたこと、真似事でもいいから紀子が育児を経験してみたいと願っていたこと、そんなことを包み隠さず美智子は香奈と真澄に話して協力を求めたのだった。 初めて美智子の話を耳にした時はひどく驚き戸惑ったけれど、美智子の胸の内を聞いているうちに、いつしか二人とも美智子の手助けをしてもいいかなと思うようになっていた。すらっと背が高くて頭が良くてスポーツも万能の高志は香奈と真澄の憧れの的だったから、もしも雅美が高志と結ばれれば高志が義理の兄になるということもあるし、それに、なにより、高校生や中学生の女の子というのは、日頃から何か面白い刺激に満ちた出来事が起きないかと期待に胸をいっぱいにしているものだ。そんな二人に、(妹にとってはいつも口うるさい姉である)雅美を赤ちゃん返りさせたいから協力してほしいという申し出が伯母からあったのだ。言われてみれば、こんなに面白いことは他に思いつかない、滅多に経験できない刺激的な出来事だった。 次第に二人は美智子の話に引き込まれ、わくわくしながら美智子の話に耳を傾けるようになっていった。そうして、雅美の心に、二人の妹に対する依存心を芽生えさせるために雅美を人混みの中に連れ出したいと言った美智子の言葉に従って、こうして三人で須磨海浜水族園へ美智子の車でやって来たのだった。 けれど、雅美自身がそんな事情を知っているわけがない。四人で秘密裏にじわじわと進めている企みなのだから。 「……」 ちっち出てないのと真澄に訊かれて、雅美は無言で首を振るばかりだった。おむつは濡れていないものの、そのことを口にするのも恥ずかしい。七歳も年下の妹に向かって「ちっち、出てない。おむつ、大丈夫だもん」と言葉にして言えるわけがない。 「大丈夫よ、真澄。雅美ちゃんが言わなくても、これが教えてくれるから。雅美ちゃんが恥ずかしがってちっちを教えてくれなくても、おむつが濡れたらこの機械が知らせてくれるから」 押し黙ったままの雅美の代わりに言ったのは、美智子から預かった小さな受信機を雅美の目の前でこれみよがしに振ってみせる香奈だった。 「うふふ、そうだったわね。雅美ちゃんがちっちしちゃったら、おむつの中の発信器から電波が出るんだったわね。よかったわね、雅美ちゃん。伯母様が便利な機械を用意しておいてくれて」 真澄がそう言ってもういちどおむつカバーの上から雅美のお尻をぽんと叩くのと、エレベーターが停まって扉が開くのとが殆ど同時だった。 本館の屋上は、普通のビルでいえば八階くらいの高さに相当するだろうか。北側には、六甲山系に連なる高取山がそびえ、南側に目を転じれば、すぐ眼下に広がる海水浴場から瀬戸内海の島々と明石海峡大橋が一望にできる。スロープと階段を上って一階のホールから幾つもの展示室を経由して屋上にやって来た来館者の殆どは、双眼鏡も備えて展望台を兼ねている南側に集まるため、屋上の真ん中付近にあるタッチプールの周りは意外と人影が少ない。 「ほら、雅美ちゃん、ヒトデもイソギンチャクもナマコもいるよ。触ってごらん」 海岸の磯溜まりを模して人工的に作った岩肌と天然の海水で出来たタッチプールを取り囲む金属製の手摺りに雅美をつかまらせて、真澄が、手摺りのすぐ向こうの水の中で優雅に触手を揺らしているイソギンチャクを指さした。 もともとが海洋生物に興味があって大学も生物学科に進んだ雅美だ。真澄に言われるまでもなく、早くも、目の前の岩肌に貼り付いているヒトデの表面を、ヒトデの負担にならないよう慎重に指先で撫でまわしている。その姿は、珍しい海の生き物に興味を抱いておそるおそる指で触れる幼児そのままだった。普通の人とは比べ物にならないほど海洋生物に対する知識を持った大学生が雅美の本来の姿だと気づく者など一人もいない。 「すぐ戻ってくるから、雅美ちゃんはそのまま遊んでてね。おねえちゃんたちは売店で飲み物を買ってくるから。戻ってきたら、そこのベンチでお昼ご飯にしまちょうね」 まるで小さな子供そのままにヒトデの表面を撫でまわす雅美に向かって香奈はそう言うと、真澄を連れて売店の方に歩き出した。 すぐに戻ってくるからと香奈は言った。 けれど、二十分経っても三十分待っても、香奈も真澄も戻ってこなかった。 最初のうちはヒトデやナマコに触れることに夢中になっていた雅美も、次第に不安になってくる。 両手を水の中から手摺りに戻した雅美は二人の姿を求めて周囲の様子をきょろきょろ見回してみたけれど、どこにも妹たちはいなかった。 売店に行くと言っていた香奈の言葉を思い出してそちらの方に目を凝らしても、見憶えのある姿は見当たらない。二人とも背が高いから、そこにいればすぐ目につく筈なのに。 いいようのない不安がじわじわと雅美の胸を満たし始めた。本当の幼稚園児と比べても頼りない足取りでよちよち歩きしかできない、おしっこをしたいと思った時にはもうおむつを濡らしてしまう、そんな雅美だから、見知った顔が全くない人混みの中に一人で放っておかれると、自分の無力さが身にしみて実感される。 しばらく迷ってから、ようやく雅美は決心した。このまま一人ここにいるよりは、妹を探しまわって体を動かしている方が幾らかでも気が休まるように思える。 雅美がおそるおそる手摺りから手を離して頼りない足取りでタッチプールのそばから離れようとした時、階段を駆け上がってきたのだろう、息を弾ませた小学生らしき少年が二人、タッチプールを目指して通路口から一目散に走ってきた。 二人の少年は肩で息をしながら、無造作にタッチプールの海水に手を突っ込むと、岩影にひそむヒトデに手を伸ばして、そのまま、水の中からつかみ上げた。それだけではなく、比較的固い表面の方ではなく、ヒトデを掌の上で裏返すと、いろんな器官が集まっている柔らかい腹側を指先で押したり引っ掻いたりし始めている。 その様子を目にした雅美は、一瞬、自分の無力さと不安を忘れた。その代わり、海洋生物を愛する研究者としての怒りが胸を占める。もともと、小柄なくせに正義感だけは人一倍強く、どちらかといえば引っ込み思案な性格をしているくせに、いったんこうと決めたら自分の信念を曲げない頑固なところもある雅美だ。 「あんたたち、何をしてるの。さっさとそのヒトデを水の中に返してあげなさい!」 自分が今どんな格好をしているのかも忘れて、雅美は二人の少年に向かって大声で言った。妹たちの手でおむつを取り替えられるのを嫌がって弱々しく首を振っていたのと同じ人物とは思えない、凛とした声だった。 突然の声にぎくっとした少年たちは慌ててヒトデを元の場所に戻すと、声が聞こえた方におどおどした様子で振り向いた。けれど、てっきり周囲の大人に叱られたとばかり思っていたのに、声の主が自分たちと同じくらいの体つきの少女だということに気がついて、ひどく戸惑ったような、とてもバツの悪そうな、なんとも表現できない顔つきになった。そうして、やがて、本当はしちゃいけないことをしているんだと自分でもわかっていて、そんなところに、それをこんな少女に注意されたのかという思いが重なって、八つ当たりじみた行き場のない怒りが胸の中に沸き上がり、見る間に顔が赤くなってくる。 「なんだよ、チビ助。お前みたいなチビ助が俺達に何のモンクがあるんだよ」 実際の年齢からすれば小柄な雅美でも、小学校低学年の児童くらいの身長はある。実際、怒りで顔を真っ赤にしている少年と比べれば、僅かながら雅美の方が背が高いだろう。少年にもそのことはわかっているが、虚勢を張るために雅美のことをチビ助呼ばわりしているのだ。 けれど、雅美が着ているセーラースーツの胸元に縫い付けてある名札に刺繍した文字を少年の一人が読み上げた途端、虚勢は虚勢でなくなった。 「カモメようちえん アヒル(ねんしょう)ぐみ たむらまさみ――おい、哲也。こいつ、生意気なこと言ってるけど、幼稚園の年少だぞ」 「なぁんだ、やっぱりチビ助じゃん。幼稚園の年少組のチビ助のくせに、よくも俺達に生意気なこと言ってくれたな。あやまれよ、チビ助」 相手が(実は大学生なのだが)幼稚園児、それも年少組の園児だとわかると、哲也と呼ばれた少年は、先にも増して嵩にかかって大声で喚きたてた。 「な、なによ。悪いのはそっちでしょ。そっちこそあやまりなさいよ。水の中の動物を水の外に出さないでくださいって注意書きにも書いてあるじゃない。あんたたち、そんなことも読めないの?」 相手が小学生低学年とはいえ、身長は殆ど違わない。それに、男の子が二人だ。相手が本気になれば敵わないだろう。さすがに、言い返す雅美の声は微かに震えていた。 「なんだよ、まだそんな生意気なこと言ってんのかよ。あやまるのはお前の方なんだよ」 哲也はづかづかと雅美に近づいてくると、いきなり、どんと胸を突きとばした。 ただでさえ両脚の筋肉が弱くなっていて一人で立っているのがやっとの雅美だ。力まかせに胸を突きとぱされたりしたから堪らない。両手を手摺りに伸ばす間もなく、そのまま、コンクリートの床にお尻を打ちつけて倒れてしまう。背中に背負ったアニマルリュックのおかげで幸い頭を打つこともなく、すぐに上半身だけは起こすことができたものの、まるで力の入らない両脚では、自力で立ち上がることができない。 しかも、床に尻餅をついて倒れる時に丈の短いセーラースーツのスカートが捲れ上がって、水玉模様のおむつカバーが丸見えになってしまっていた。 「おい、哲也。あれって……」 「ああ、あれ、普通のパンツじゃないな。親戚のねえちゃんが家に遊びに来た時、赤ちゃんを連れてきたんだけど、その子がしてたのと同じだ。あれって、おむつカバーだぜ。間違いないや」 哲也は、いかにも意地悪そうな笑みを浮かべて、雅美が倒れているすぐその前にしゃがみこみ、あらためて確認するように雅美のスカートの中を覗き込んだ。 「へん、幼稚園にもなって、まだおむつが外れないチビ助だったんだな、お前。おねしょだけじゃすまなくて、昼間もおもらししちゃうんだな。カモメ幼稚園ってどこにある幼稚園か知らないけど、幼稚園の先生も大変だな。赤ちゃんみたいにおむつを汚しちゃう生徒がいるんだもんな。言ってみろよ、一日に何回おむつを取り替えてもらうんだよ。お前が汚したおむつ、ビニール袋に入れて持って帰るのかよ。お前の母ちゃんも大変だよな。幼稚園に行く子のおむつの洗濯しなきゃいけないなんてな。俺なんて、二つの時にはおねしょもしなくなってたんだぜ。――陽介、お前は?」 スカートの乱れを直そうとして慌てて伸ばした雅美の手を乱暴に振り払って、哲也は尚も雅美のおむつカバーを正面から覗き込んで言った。 「お、俺か? 恥ずかしいけど、俺、幼稚園の年長までおねしょしてたんだ。けど、おねしょだけだぞ。おもらしは幼稚園に入る頃にはしなくなってたんだからな」 少しばかりむきになりながらも、陽介と呼ばれた少年は正直に答えた。 「だよな。幼稚園になっておもらしなんて、恥ずかしいよな。幼稚園になって、おもらしだからおむつなんて、俺だったら、恥ずかしくて幼稚園なんか行けないや。幼稚園だけじゃないぞ、動物園だって買い物だって水族館だって、おむつじゃ恥ずかしくて行けないや。おい、チビ助。お前、本当に勇気があるんだな。おむつでお出かけするなんて、本当に勇気があるよ。そんなに勇気があるから、俺達に生意気なことも言えるんだな。感心しちゃうよ」 わざとみたいに大げさに哲也は肩をすくめてみせた。 そんな哲也に、けれど、雅美はもう何も言い返せなくなっていた。スカートの下のおむつカバーを見られた今、言い返す言葉など一つも有りはしなかった。
|
|
|
|
|
|
| 戻る | 目次に戻る | 本棚に戻る | ホームに戻る |