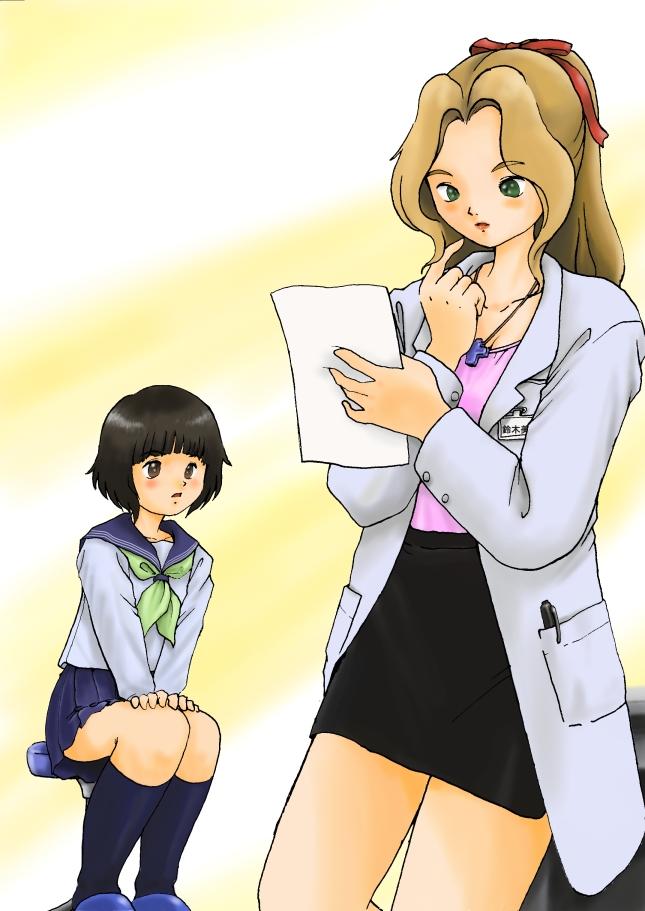|
ママは私だけの校医さん
《1 診察室の二人》
四月も半ばを過ぎた、うららかな春の昼下がり。
「佐藤さん、佐藤真衣さん。お待たせしました、お入りください」
診察室の扉が開いて、淡いピンクの白衣に身を包んだ若い女性看護師が姿を現し、待合室のソファに身を固くして腰かけている少女に向かって優しく呼びかけた。
「あ、はい……」
真衣と呼ばれた少女はどこか躊躇いがちに応え、おずおずと立ち上がった。
今日は土曜日。他の開業医と同様、ここ、鈴木医院も午後は休診だ。それに、午前の受付終了間際にやって来た真衣より先に受付を済ませていた患者たちは既に診察が済んで帰路についているから、真衣が診察室に姿を消すと、待合室はがらんとしてしまう。
「その後、具合はどうかな?」
真衣が椅子にお尻をおろすのを待って、純白の白衣を身にまとった女医が話しかけた。白衣の胸元には、鈴木美幸と記された名札がクリップで留められている。
「あ、あの……どうと言われても、その……」
真衣は、おどおどした様子でそう応えるのが精一杯だった。もともと内気なところにもってきて、鈴木医院を訪れた理由が理由だから、とてもではないが弾んだ声で返事などできるない。
「そう。じゃ、変わりなしってことね」
美幸は穏やかな笑みを浮かべつつも、真衣の胸の内をすっかり見透かしてしまうかのような一瞥をくれて短く言い、細かな数字が並んだデータシートを机の上に広げて言葉を続けた。
「先週の土曜日に採尿したでしょ? その時のおしっこを詳しく調べた結果が出ているんだけど……」
美幸の言葉に、けれど真衣は口をつぐんで、ぎこちなく頷くだけだ。
そんな真衣の様子に、美幸は穏やかな笑顔のまま言った。
「心配しなくていいわよ、糖も蛋白も出てないし、雑菌の種類や個数の値も正常範囲内だから。それに、先週の診察でも特に異状は見受けられなかったから、体は大丈夫よ」
「……そ、そうなんですか?」
真衣は蚊の鳴くような声で言った。
「ええ、特に異状は見当たらないわね、私の診察の範囲内では。ただ、念のために、さっき採尿したおしっこの検査結果が出てから、それも合わせて判断することにしましょうか」
美幸は軽く頷いて言ってから、僅かに首をかしげて付け加えた。
「ああ、それと、前に渡しておいた問診票の内容も見ておかないとね。ちゃんと書いてきてくれた?」
「え、あ、は、はい……」
美幸に言われて、真衣は、頬を微かに赤く染め、おどおどした様子で茶色の封筒を差し出した。
「いいわ。じゃ、見せてもらうわね」
美幸は、受け取った封筒の封を無造作に開け、引っ張り出した四つ折りの紙をさっと広げて、そこに記入されている幾つもの数値を一つ一つ丹念に目で追った。
一瞬、診察室がしんと静まりかえる。
「あの、あの……どうなんですか?」
静寂に耐えかねたかのように、真衣がいかにも不安そうな面持ちで問いかける。
だが、すぐには返事がない。
美幸が問診票を机の上に置き、真衣の顔に視線を戻したのは、それからしばらくしてからのことだった。
「あ、あの……」
改めて真衣が躊躇いがちに声をかける。
が、丁度その時、真衣を診察室に招き入れた看護師が、新しいデータシートを持って検査室から戻ってきた。
「ごめんなさい、もうちょっとだけ待っていてね」
美幸は、いったん真衣の顔に戻した視線を、今度は看護師から受け取った新しいデータシートに向け直した。
「……」
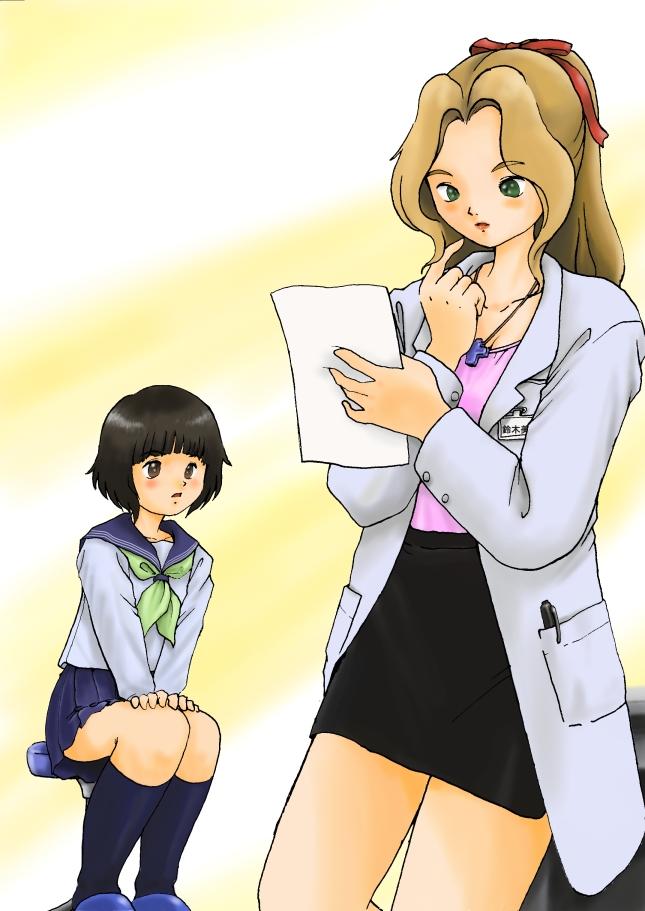
問いかけを遮られた真衣だが、不満そうな表情を浮かべる様子はなく、むしろ、ますます不安げな面持ちになって唇をきゅっと噛み、時おり美幸の顔をちらちらと覗い見るばかりだ。
「うん、今日のおしっこにも変な数値は出ていないわね。このぶんなら、膀胱の炎症とか、そういう心配はないわね。よかった、見立て通りで」
新しいデータシートに目を通しつつ、先週のデータシートとカルテにもちらちらと目をやって、美幸は、不安そうな表情を浮かべる真衣に向かって落ち着いた声でそう声をかけた。
その説明に一瞬は安堵の面持ちになった真衣だが、じきに、元通りの不安そうな表情を浮かべたかと思うと、よく注意していないと聞き取れないような力ない声で言うのだった。
「でも、でも……だったら、どうして? どうして治らないんですか、私の、お、おね……」
聞きようによってはどこか責めるみたいな調子でそう言った真衣だが、それ以上は続かなかった。言葉を最後まで言い終えることなく口ごもってしまう。
「肉体的な異状が認められないのだったら、精神的な原因があるってことになるわね」
殆ど間を置かずに美幸は応じ、更に、真衣が途中で飲み込んでしまった言葉をずばりと口にした。
「おそらく心理的な要因が強いんだと思うわ、佐藤さんの夜尿――おねしょの原因は」
美幸の唇を衝いて出た『おねしょ』という言葉に、真衣の頬がかっと熱くなる。
そう、真衣が鈴木医院を訪れるようになったのは、高校入試の三週間ほど前から始まって、無事に第一志望の高校に入学できた今も続いている恥ずかしい病気を治療してもらうためだった――。
*
幼い頃に母親を交通事故で亡くした真衣は、父親である優の男手一つで育てられた。少し内気ではあるものの、小さな頃から、まるでひねくれたところがなく、常に絶やすことのないおとなしそうな笑みのために周りの誰からも愛され、母親がいない寂しさというものを殆ど感じさせない、素直な少女だ。
そんな真衣が中学三年生になり、学校に提出する進路希望調査書に第一志望として記入したのは、啓明女学院高校の名前だった。
少し気の弱いところのある真衣にしてみれば、男女共学の公立学校が幾らか負担になっていたのは否めない。それでも義務教育はどうにか我慢していたのだが、高校に進む時には女子校がいいなという漠然とした思いを抱くようにもなっていた。そんな時、進路を決めるために父親の優とあれこれ相談していて、今は亡き母親が高校生の時に通っていたのが啓明女学院高校だと聞かされたのだった。優が言うには、真衣の母親は大学も啓明女学院を出て、卒業した後は或る製薬会社に営業事務として採用され、その製薬会社の先輩で営業職に就いていた優と知り合い、それがきっかけで結婚に至ったということだった。そんなことがあって、女子校に進みたいという漠然とした思いと、若かった頃の母親が過ごした青春時代を追体験してみたいという願望とが渾然となり、真衣は微塵も躊躇うことなく、第一志望として啓明女学院高校の名を挙げたのだった。
もっとも、自分でそうと決めても、実際に啓明に入学するのは容易なことではなかった。学区の中でも啓明は偏差値が高い方で、第一回の模試では合格判定はBしか取れなかった。それでも、いったんこうと決めた後の真衣は、日頃の内気な性格が嘘のように一途に勉強に打ち込んだ。そうして、模試の回数を重ねるたびにB判定とA判定とを行ったり来たりするようになり、昨年の年末と今年の一月に行われた模試では続けてA判定を取れるまでになっていた。
が、ここから真衣は更に大変な目に遭うことになる。根を詰めて勉強に打ち込みすぎたせいか、いよいよあと三週間で入試という日になって、急に熱を出して寝込んでしまったのだ。学校から帰ってきて夕飯の支度をしている途中で感じ始めた体のだるさはまるで衰えることなく、出始めた熱はあっという間に三九度を超えてしまうといった具合で、父親の帰宅を待つことも辛くなって、せっかく用意した夕飯を口にすることもなく、とうとう、倒れ込むようにして布団に潜り込んでしまったほどだ。翌日も翌々日も熱が下がる気配はなく、うんうん唸りながら布団の中で体中を汗まみれにするしかない日が続いた。
父親の優としても愛娘の具合は気になって仕方ないのだが、インフルエンザが流行しているこの時期、製薬会社で営業次長の職にある身としては、自ら担当する病院や開業医との間の折衝をこなしながら部下のフォローや部署間のマネジメントも疎かにするわけにゆかず、とてもではないが休暇の取得を申し出られるような状況ではなかった。これまで男手一つで育てられてきた真衣にしてみれば父親の置かれたそんな立場も充分に理解しており、弱音を吐くようなこともなく、食事を摂るのが困難な中、自分でミルクを温めて飲んだりしながら、辛い日々をやり過ごすしかなかった。
容態が好転したのは、そんな状況を我慢して四日ほどを辛うじて乗り切った頃だった。朝になって目を開ける時、それまでの何日かとは違う、体のだるさは残っているものの少しばかり呼吸が楽になったような感じがして、随分ほっとした気分になったものだった。そうなれば、持ち前の若さもあって回復は早く、その日の夕方には熱も三七度五分ほどに下がり、それまでは牛乳やプリンだけで済ませていた食事も、どうにか自分で用意できるまでになっていたし、自分で用意した軽い夕飯を摂った後、帰宅の遅い父親を待とうかどうか迷ったものの、再び体調をくずさないようにと早めに床についたのがよかったのだろう、その翌朝には、久しぶりに爽やかな目覚めを迎えることができた。
しかし、実は、その朝こそが、それまで予想だにしなかった懊悩の日々の始まりだったのだ。

ベッドの中でう〜んと伸びをして、気怠さも感じずに瞼を開けた真衣だったが、ふと下腹部に違和感を覚えた。
ここ数日は高熱のせいでひっきりなしに汗をかいていたから、下腹部に覚えるじとっとした感触もそのせいかと最初は思ったが、すぐに、そんなじゃないことがわかった。今はもうすっかり熱も下がって、上半身はさらっとしているし、下半身でも、腿の下から足首、足の裏にかけては汗をかいている様子がない。じとっと湿っぽいのは、おヘソのちょっと下から股間、お尻の膨らみから太腿にかけての下腹部に限られていた。
ひょっとしたらという思いと、まさかそんなという思いとが頭の中で交錯する。
真衣は右手でおそるおそる掛布団の端を持ち上げた。
途端に、体臭と薬の成分とが入り混じった、なんともいいようのない匂いが鼻を打つ。
真衣は下唇をぎゅっと噛みしめ、のろのろと右手を動かした。
やがて掛布団がすっかりはだけ、長袖のパジャマを着た真衣の体があらわになる。
「あ……」
左手を敷布団について上半身を起こした真衣の口から、短く弱々しい声が漏れた。
真衣の瞳に映ったのは、ぐっしょり濡れたパジャマのボトムと、お尻が載っているあたりがうっすらと黄色に染まったシーツだった。
鼻につくその匂いと、一目でそれとわかる濡れ方。真衣の下腹部がぐっしょり湿っているのが汗のせいなどでないことは火を見るより明かだった。
入試も近いから症状が少しでも軽くなればすぐに登校しようと思っていた真衣だが、結局、その日も学校を休まざるを得なかった。おねしょの事実を気づかれないようにするには、父親が会社へ行くため家を出るまで自分の部屋から出るわけにゆかず、父親が出社した後に、掛布団や敷布団、それに自分のパジャマや下着を処置しなければいけなかったからだ。布団から剥ぎ取ったシーツや下着を放り込んだ洗濯機をまわし、薄いシミになった布団を木陰に隠すようにしてベランダに干しす真衣にとって、目を覚ました時に一瞬だけ感じた朝の清々しさなど、とっくにずっと昔のことになってしまっていた。今はただ、この恥ずかしい粗相の痕跡を消し去ってしまうのに精一杯だった。
情けない洗濯を終え、その後は惚けたようにベッドの端に腰かけるだけの時間が過ぎて、その日の夕方には熱もすっかりひいたが、胸の内は鬱々とするばかりだった。そうして、結局、父親のために簡単な夕飯を用意した後は何もする気分になれず、『まだ体調がすぐれないから先に寝ます』という父親宛のメモを食卓に置いて布団にもぐりこむしかできない真衣だった。仕事に忙しい優が真衣のメモの内容に微塵の疑いも抱かなかったことがせめてもの救いといったところだろうか。
(あれは何かの間違いだったのよ。昨日のことは悪い夢に決まってる。もうあんな馬鹿なことがあるわけない)不安にかられながら自分にそう言い聞かせて無理矢理の眠りについた真衣を翌朝になって待ち受けていたのは、しかし、前の日の朝と同様の下腹部から伝わってくるじっとり湿っぽい感触だった。
突如として始まったおねしょは、その翌日になっても治らなかった。そのせいで、熱のせいを合わせると、もう一週間近くも学校を休んでしまったことになる。
入試を目前に控えてこれ以上休むなんてとんでもない。それに、一週間以上も学校を休んだりしたら、いくらなんでも父親に怪しまれるに違いない。かといって、(あまり考えたくはないが)これからもこの恥ずかしい失敗が続くようだと、寝具をどう処置していいものか。学校に遅刻しないようにするには、父親の出社と殆ど同じ時刻に真衣も家を出なければならない。しかし、そうすると、シーツを洗ったり布団を干したりしている時間は取れない。だいいち、洗ったシーツやシミの付いた布団をベランダに干したまま出かけたりしたら、誰の目に触れるかしれたものではない。
その日は土曜日で真衣はもともと学校が休みだったが、幸いなことに、父親は忙しい時期のため休日出勤になっていた。
なんとかするチャンスは今日しかない。下腹部を包むいやな感触を我慢しながら父親が出かける時刻になるまでベッドにもぐりこんだまま、真衣は覚悟を決めるしかなかった。
なんの前触れもなく始まったおねしょだから、やはり突然に治るんじゃないか。そんな期待も少しはあったが、逆に、これで三日間も続いたおねしょがあっけなく治るわけがないという諦めに近い思いの方が強かった。今の真衣にできるのは、おねしょをしてしまっても布団やパジャマを汚さずにすむ方法を実行に移すこと、それだけだった。
ともあれ、あれこれ苦心しつつもどうにかこうにか入試を乗り切り、第一志望の啓明に入学できた真衣だったが、環境が変わったらひょっとしてという淡い期待も裏切られ、高校に入っても、おねしょが治る気配は一向になかった。
春になるとインフルエンザの流行も収まり、会社の決算期も済んで、優の仕事も、それまでに比べれば幾らかは落ち着いてくる。そのため残業も減って、真衣と一緒にいる時間が増える。これまでの真衣なら、ただ一人の肉親である優と一緒にいられることを喜んだろうが、おねしょが始まってからは、恥ずかしい秘密を父親に知られまいかと気が気ではないというのが偽らざるところだ。
そんな時に出会ったのが、鈴木医院の副院長である鈴木美幸だった。
高校に入学してすぐに校内で行われた健康診断で内科の診察にあたっていたのが美幸だった。美幸の父親である鈴木医院の院長がなかなかのやり手で、公立・私立を問わず、ここいら一帯の多くの学校から校医としての指定を受けていたからだ。
健康診断で聴診器を胸に当てられ言葉を交わしたのはごく短い時間でしかなかったが、落ち着いた中に厳しさと優しさとを併せ持った美幸の雰囲気に、なぜとはなしに真衣は心を惹かれてならなかった。それがあったからこそ、自分の恥ずかしい病気をこの美しい女医に相談してみようという気になったのだ。中学校の時にも保健室の教諭なり校医なりに相談した方がいいかなと思ったこともあるのだが、保健室の教諭に相談したりすると、相談の内容がどこからともなく洩れ出して学校中の噂になるんじゃないかという不安が先に立ってしまい、また、校医に相談しようにも、中学校指定の校医が中年男性だったこともあって、結局は誰にも助けを求めることができずに中学校を卒業してしまっていたというのが実情だ。
初めての出会いからこちら、絶えず胸の中に美幸の顔を思い浮かべる日が続き、とうとう、健康診断があった週の土曜日、躊躇いながらも、真衣は鈴木医院を訪れていた。そして、美幸に問われるまま、羞じらいの表情を浮かべつつもこれまでの経緯を話し、おしっこを採尿カップに取り、内診台の上で羞恥の姿勢を取ったのだった。
*
――そんなふうにして先週の土曜日に初めて鈴木医院を訪れ、いろいろと検査をしてもらった結果でも、二度目になる今日の検査でも、身体にこれといった異状は認められないと美幸は断言したわけだ。だから、おねしょの原因は精神的なものしか考えられないと。
「で、でも、あの、心理的って言われても……」
美幸の見立てに、真衣は戸惑いの表情を浮かべるばかりだ。高熱が原因で身体に異状をきたしたのだとばかり思い込んで、その治療さえ済めば恥ずかしい失敗も終わるに違いないと決めてかかっていただけに、『心理的な要因』と言われてもどう反応していいかわからない。
「……じゃ、じゃ、熱は関係なかったんですか? 私、熱のせいで体のどこかがおかしくなって、それで、毎晩、お、おね……しょを……」
「熱が全く無関係ということじゃないと思うわよ。ただ、それが全ての原因だってわけじゃなくて、なんていったらいいかな――そう、きっかけになったんじゃないかなってことなのよ」
「きっかけ……ですか?」
真衣は要領を得ない顔で聞き返した。
それに対して美幸が、片方の眉をちょっと吊り上げるようにして問いかける。
「辛いことを聞くようで申し訳ないんだけど、佐藤さん、小さい頃にお母様をなくされているんだったわよね?」
「え? ええ、はい」
「だったら、夜尿のことをお母様には相談できない。それは仕方ないとして、で、お父様には相談した?」
「い、いえ……忙しい父に心配かけたくありませんから……」
考え考え言葉を選ぶようにして応じる真衣に対して、美幸が僅かに首をかしげ、重ねて訊いた。
「心配かけたくないから? ――本当にそれだけ?」
「……」
思わず真衣が返答に詰まる。
「恥ずかしかったからじゃないの?」
たたみかけるようにして美幸が問い質した。
「……そ、そうかもしれませんけど……」
真衣は困ったような顔で目を伏せた。
それに対して美幸は、それまでよりもずっと穏やかな表情を浮かべて優しく言う。
「肉親とはいっても、男の人に夜尿のことを知られるのは恥ずかしいわよね? いいのよ、それはそれで当たり前のことなんだから。ただ、佐藤さんの夜尿を治すために、私は、医師として、本当に些細なことでも一つ一つ正確に知っておかなきゃいけないの。だから、佐藤さんも、恥ずかしがらずにどんなことでもできるだけ正直に話してちょうだい。いいわね?」
「……あ、はい。ごめんなさい、先生」
叱りつけるわけでもなく、妙に甘やかすわけでもない、優しいくせにどこか威圧感のある美幸の口調に、真衣は思わずこくんと頷いてしまう。
「わかってくれればいいのよ、そんなに神妙な顔をしなくても。でも、念のためにもういちどだけ言っておくわね。お父様には恥ずかしくて打ち明けられないようなことでも、私には包み隠さず話してちょうだい。同じ女性どうし、少しは話しやすいでしょ?」
教え諭すようにそう言う美幸を目の前にして、突然、真衣の脳裏に、在りし日の母親の姿が蘇った。
それは、真衣が幼稚園の年長クラスだった時のこと。どちらかというと手がかからず、おむつ離れも早かった真衣だったが、夏の盛り、暑くて、寝る前にジュースをたくさん飲み過ぎた日があった。しかも、その日は夏休みの最中で、昼間に遊園地へ連れて行ってもらい、幽霊屋敷にも入っていた。そんなこんなで、ぐっすり眠っている間に尿意を催した上、怖い夢を見て、ついおねしょをしてしまった。しかし、おねしょに気づいた母親は叱りもせず、「お父さんには内緒にしとこうね。真衣はこれまでずっといい子で、おもらしやおねしょでお母さんを困らせたことなんて一度もなかったんだから、今度のおねしょは何かの間違いに決まってる。だから、お父さんには話さないでおこう。でも、これから、何か困ったことがあったら、どんなことでも隠さないでお母さんには話してちょうだい。女どうし、ちゃんと相談に乗ってあげるから」と優しく言い聞かせて真衣の体をぎゅっと抱きしめてくれたのだった。
真衣の脳裏に蘇ったのは、その時の母親のこれ以上はないくらい優しい笑顔と、両手のぬくもりだった。しかし、そんなことがあった一ヶ月ほど後、買い物に出かけた母親は、交通事故に遭って還らぬ人となってしまったのだ。
「うん……あ、は、はい……」
真衣は頭をぶるんと振って、もういちど小さく頷いた。
「そう、それでいいのよ」
美幸はすっと目を細めて真衣の顔を覗き込んだ後、再びカルテに目を走らせながら続けて言った。
「ところで、佐藤さんはトイレが近い方かな? 問診票には、この一週間、毎日トイレへ行った時間も書いてもらったんだけど、それを見ると、普通よりも回数が多いみたいね。そのあたりのことも少し詳しく聞いておきたいんだけど、自分でどう思う?」
「それは、あの……近い方だと思います」
真衣は少し口ごもりぎみに応えてから、意を決したようにこう言い直した。
「いえ、思うんじゃなく、近いです。問診票にも書いた通り、学校じゃ授業と授業の間の休憩時間になるたびにトイレへ行ってるし、小学校や中学校の遠足とか修学旅行じゃ、バスに乗っていても、いつになったらサービスエリアに停まってくれるか、そればかり気になって景色なんてちっとも見てなかったくらいですから。今も、通学で電車に乗るたび、駅ごとにおりてトイレへ行った方がいいんじゃないかって不安になるほどですし」
「そうなの。でも、トイレが近くても、今度の夜尿が始まるまでは夜尿は大丈夫だったんだから、それが直接の原因とは考えにくいわね。それに、トイレが近いのも、膀胱の機能に異状がある場合よりも精神的な原因の場合の方が多いし――トイレが近い理由、自分なりに何か心当たりはないかな?」
真衣の返答に、美幸はカルテをペンの先でぴんと弾いて言った。
「……心当たりなら、ないこともないですけど……」
いったんは意を決した真衣だが、再び明かな逡巡の表情を浮かべ、弱々しい声になってしまう。
「約束したでしょ、どんなことでも話してくれるって」
「あ、は、はい……」
美幸に励まされ、視線を床に落として真衣が口にしたのは、辛い思い出にまつわる事柄だった。
交通事故に遭って還らぬ人となってしまった母親の通夜。真衣は、横たわる母親の亡骸に寄り添って泣き続けた。お腹が空くのも喉が渇くのも、時間の経過とともに次第に高まってくる尿意のことも忘れて、ひたすら泣き続けた。そうして、とうとう、大勢の弔問客の目の前でしくじってしまったのだった。けれど、一ヶ月前のおねしょの時とは違って、下着を濡らしてしまった真衣を暖かく抱きしめてくれる母親はもういない。そのことがまた悲しくて、真衣は流れ続ける涙を止めることができなかった。
無論、そんな真衣をなじる者などいない。親類も弔問客も、真衣のことを不憫がって遠巻きに見守るだけだ。その中で、ただ一人、真衣の肩に手を載せる人物がいた。それは、自分も最愛の伴侶をなくして泣き出したいだろうに、それを堪えて優しい声をかけた父親・優だった。
優は真衣に対して叱るでもなく憐れむでもなく、ただ、これ以上はないだろうと思えるくらい優しい声で「真衣は幼稚園の年長さんなんだから、もうおもらしは卒業しなくちゃいけないね。いつまでも失敗していると、お母さんが安心して天国へ行けないだろう? お母さんを安心させてあげるためにも、しっかりした子になろうね」と囁きかけた後、真衣を隣室に連れて行って、慣れない手つきで新しい下着と洋服に着替えさせたのだった。
お母さんを安心させてあげなくちゃ。安心して天国に行かせてあげなくちゃ。真衣は心の奥底に父親の言葉をしっかり刻みつけていた。ただ、幼い真衣の心に、その言葉はあまりに深く強く刻みつけられてしまった。優の手で新しい洋服に着替えさせられた後は、涙ながらに眠りにつく前も、翌日の葬儀でも、そして再び幼稚園に通い始めてからも、僅かな尿意を覚えただけですぐにトイレへ駆け込むのが習い性になってしまったのだ。それは、まさに、強迫観念さながらだった。そして、その習い性は、高校生になった今も続いている。
「そう、そんなことがあったの。ごめんなさいね、辛いことを思い出させちゃって」
途切れ途切れに話す真衣の説明を聞き終わった美幸は微かに表情を曇らせて言った。
「……いえ、どんなことでも話すって約束しましたから」
話している最中とは裏腹に、説明を終えた今、真衣はいっそ晴れ晴れしたような顔つきで小さくかぶりを振った。
「ありがとう、そう言ってくれると助かるわ。――で、頻尿の原因がそういうことで、小さい頃からこれまでずっと少しでもおしっこをしたくなるたびに我慢しないでトイレへ行っていたとすると、ひょっとしたら膀胱があまり成育していない可能性も考えられるわけか。初めてうちに来てくれた先週の土曜日は、そういうところまで気にしないで簡単に触診しただけだったけど、いずれ、膀胱の容量を測定するとか、もう少し詳しく調べなきゃいけないみたいね」
美幸は真衣の顔と下腹部とに交互に視線を走らせた後、カルテにボールペンで何やら横文字と記号を記入しながら言った。
「あの……そういう検査って、難しいことをするんでしょうか?」
美幸の言葉に表情をこわばらせて真衣が訊いた。
「あ、痛いわけじゃないし、そんなに時間がかかるってわけじゃないから、心配することはないわよ。とりあえず、心理療法と並行してそちらも進めてみましょう」
カルテへの記入を終えて、美幸は再び穏やかな笑顔に戻った。
「わかりました。……それで、心理療法って、私は具体的にどうすればいいんでしょうか?」
真衣は気持ちを切り替えるように軽く息を吸って、おずおずと美幸の顔を見た。
「あまり難しく考えることはないのよ。たとえば、そうね、学校で休み時間になるたびに行っているトイレを我慢して、二時限に一度しか行かないようにしてみるとか、おしっこをしたくなっても、まだ大丈夫だって自分に言い聞かせてみるとか。あとは――」
美幸は『心理療法』のための具体的な指示を幾つか申し伝え、真衣がそれを自分の手帳にメモを取ったのを確認して、穏やかな笑顔のまま言った。
「じゃ、今日はこれくらいにしましょう。私が言ったこと、無理しない範囲でいいから、なるべく気にかけて生活してみてちょうだい。中でも、学校でのトイレ我慢は重要だから、特にそのことは忘れないでね」
「わかりました。頑張ります、私」
真衣はもういちど手帳に視線を走らせ、自分を励ますようにわざと大きく頷いて診察椅子から立ち上がった。
「いいわ。じゃ、また来週」
「ありがとうございました。来週ここへ来るまでには一回でも二回でも失敗の回数が減っていればいいんですけど」
「そうなるよう、私も祈っているわ」
くるりと踵を返して診察室から出て行く真衣の後ろ姿をじっと美幸は見送った。
「これでいいのね?」
真衣の足音が遠ざかってゆく様子を診察室の扉越しに確認して、美幸はわざとのようにゆっくり振り返り、それまで物陰にひそんで事の成り行きを見守っていた人物に声をかけた。
「うん、これでいいんだと僕は思うよ。真衣のためには、こうするのが一番だと思う」
物陰から姿を現し、真衣が出て行った扉を見据えてそう応えた人物は、真衣の父親・優だった。
「ん、わかった。優さんがそう言うなら私は一向に構わないわ。――あ、そうそう。学校との折衝も済んでいるから、そっちもいつでも大丈夫よ」
美幸も優の横に並び、診察室の扉にちらと目をやって言った。
「ありがとう。無理なお願いばかりして申し訳なく思っているよ。でも、これが真衣にとって――いいや、僕たち三人にとって一番いいことなんだ。天国のあいつも賛成してくれるに違いないさ」
優は扉を見据えたまま美幸の腰に手をまわした。
|