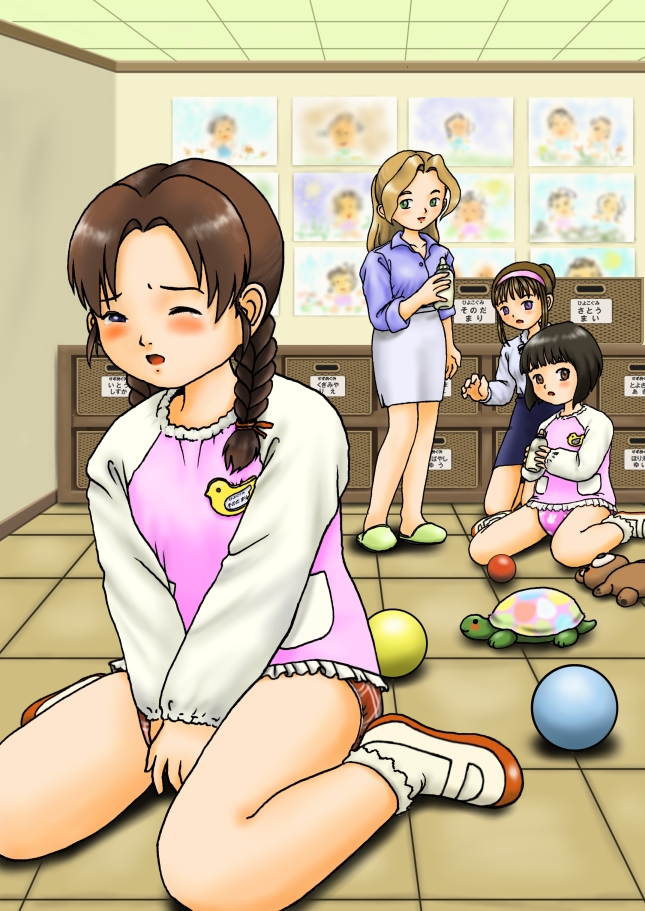|
《28 再び流れ始める時間》
それからしばらく後、おねしょシーツの上に横たわる茉莉の姿があった。とうとう我慢できなくなって溢れ出したおしっこを吸収したショーツと布おむつはもちろん、おしっこの飛沫に濡れたソックスやスカートだけでなく、スーツの上衣にブラウス、インナーシャツとブラまで矧ぎ取られて丸裸にされた、あられもない姿だ。
そして、その傍らには、お尻を床にぺたんとつけて座り、茉莉の様子をみつめている真衣の姿。おむつを取り替えられた後、セーラースーツを脱がされ、園内着に着替えさせられた真衣は、体操服の上に、制服に付いているのと同じひよこ形の名札を胸元に安全ピンで留めたスモックといういでたちだった。ただ、おむつでぷっくり膨らんだお尻には体操服の下衣であるハーフパンツが窮屈で穿けなかったせいで、腰骨よりも少し下くらいの丈しかないスモックの裾からおむつカバーが半分ほど見えてしまっている(もっとも、ハーフパンツについては、おむつのお尻に窮屈なのは前もってわかっていたくせに、実際に穿かせてみて駄目なことを身をもって思いしらせ、真衣に更なる羞恥を与える目的で美幸が美沙に指示してわざわざ用意させていたのだった)。しかも、おしゃぶりを口にふくまされ右手にはガラガラを持たされたままという、実際の年少さんよりも幼児めいて見える姿だ。
「さ、今度はちゃんとおむつをあてようね。さっきはおしっこが飛び散らないようにするためにパンツの中におむつを重ねただけだったけど、今度はおむつカバーも使ってちゃんとあててあげるから、いくらおもらししちゃっても大丈夫よ」
棚の下からバッグを持ってきた美沙が、おねしょシーツのすぐそばに膝をついて言い、バッグから取り出した十枚ほどの布おむつを茉莉の目の前に差し出した。
と、おむつの端に施された『ひよこぐみ そのだまり』という刺繍が目に留まって、それまで呆けたような顔をしていた茉莉の頬に朱が差す。
「随分たくさんのおむつだなって思っていたでしょ? 二日分なら、籠にしまったので充分。いくら念のためだとはいっても、バッグに残った分は余計なんじゃないかな。そう思っていたでしょ? そうね、真衣ちゃんが一人で使うには充分過ぎて余っちゃうわよね。でも、バッグに残っていたのは真衣ちゃんのおむつじゃないのよ。わかるでしょ? ほら、ちゃんと茉莉ちゃんの名前を刺繍しておいてあげたんだもん、わからないわけないわよね。これもクラスのみなんが縫ってくれたおむつなのよ。ひょっとしたら、茉莉ちゃん自身が縫ったおむつもこの中に混じっているかもしれないわね」
美沙はそう言いながらおむつの端の刺繍を指先でなぞってみせてから、次にバッグから真新しいおむつカバーを取り出した。
「こっちは、ママがわざわざ茉莉ちゃんのために追加注文してつくってもらったおむつカバーよ。真衣ちゃんのおむつカバーを茉莉ちゃんに使わせてもいいけど、茉莉ちゃんが真衣ちゃんと同じくらい一日に何度もおむつを汚しちゃうと、枚数が足りなくなっちゃうもんね」
あらかじめ茉莉の名前を刺繍しておいた布おむつと、前もって追加注文しておいたおむつカバー。そんな物が準備されているところを見れば、茉莉が真衣と同じようにおむつを受け容れるに違いないと美幸と美沙が思っていたのは明かだ。
茉莉はますます頬を赤らめ、羞恥に顔を歪めた。
それを見た美幸が、すっと目を細めて真衣に話しかける。
「ほら、茉莉ちゃんがむずがっているわよ。真衣ちゃんはお姉ちゃんなんだから、おしゃぶりを茉莉ちゃんにあげなさい。可愛い妹がむずがらないようにね」
「え? ……茉莉お姉ちゃんが真衣の妹?」 思ってもみなかった美幸の言葉に、真衣は怪訝な表情で訊き返した。
「そうよ。もう茉莉ちゃんは幼稚舎の園田先生でもないし、茉莉お姉ちゃんでもないの。それどころか、真衣ちゃんよりも後で年少さんになったんだから、真衣ちゃんの妹なのよ。だから、これまでは『園田先生』とか『茉莉お姉ちゃん』とか呼んでいたけど、これからは『茉莉ちゃん』って呼んで可愛がってあげなきゃ駄目よ。だって、真衣ちゃんの方がお姉さんになるんだもの。だから、おしゃぶりをあげてちょうだい。それが、茉莉ちゃんが真衣ちゃんの妹になったシルシなのよ」
美幸はこともなげにそう言って真衣の口からおしゃぶりをつまみ取り、真衣の掌を広げさせて、その上におしゃぶりをそっと置いた。
屈辱に満ちた表情で茉莉は顔をそむけたが、美沙の両手で頬を包み込まれ、強引に真衣の方に顔を向け直させられてしまう。
「あ、あの、茉莉……ちゃん、これ……」
しばらく躊躇った後、真衣がおずおずとおしゃぶりを差し出した。
だが、茉莉は唇に力を入れて頑なにおしゃぶりを拒む。
そこへ、笑いを含んだ美幸の声が飛んできた。
「いつまでも我を張ってないで正直になりなさいって言ったでしょ? だいいち、これを見れば茉莉ちゃんの本心なんてお見通しなんだから、今さら恥ずかしがっても無駄よ」
美幸は笑い声で『これ』と言いながら、茉莉の股間を指先でつっとなぞった。
そこには、本来なら豊かに生え揃っている筈の恥毛が一本も見当たらなかった。しかし、美幸の指先に伝わる感触から、生まれついての無毛でないことは明かだ。
「自分で剃ったのね? 真衣ちゃんのことが羨ましくて自分で剃ったんでしょう? 真衣ちゃんみたいになりたくて」
美幸は、生えかけの飾り毛がちくちく触れる下腹部から指を離し、その指先を茉莉の目の前に突きつけて言った。
茉莉からの返事はない。
「でも、このぶんだと、剃ったのは一回だけかな。一回だけ剃って、もう生えかけてきているのに、あとは何もしていないみたいね」
美幸は、いたわるように言った。
それに対してようやく茉莉が口を開く。
「……怖かったから。……真衣ちゃんみたいになりたくて自分で剃ってつるつるにしたのはいいけど、赤ちゃんみたいになっちゃった自分のあそこを見て、私ったらなんて馬鹿なことをしてるんだろうって後悔して……剃った毛が生えてきてちくちくするけど、今度また剃ったりしたら、取り返しのつかないことになっちゃいそうな気がして……自分が自分じゃなくなっちゃいそうな気がして……だから……」
「そう、自分が自分じゃなくなっちゃいそうだって思ったの。でも、それは違うわよ。茉莉ちゃんが自分の本当の気持ちに気がついて、本当の自分に戻るためには、もっと綺麗にして、真衣ちゃんみたいにつるつるのすべすべにしなきゃいけないのよ。――自分でするのが怖いんだったら、ママがちゃんとしてあげる。魔法の薬を使って、すべすべにしてあげる」
諦めの表情を浮かべ言葉を探し探し応じる茉莉に向かって美幸はなんとも表現しようのない笑顔で言い、ベビーパウダーの容器の横に置いてある小さな丸い容器を持ち上げた。
「あ、それ……」
美幸が『魔法の薬』と言いながら手に取ったのがおむつかぶれの薬の容器だということに気がついて、真衣が怪訝そうな声をあげた。
「そうよ、真衣ちゃんが美沙お姉ちゃんに昨夜まで塗ってもらっていたお薬の内の一つよ。このお薬はね、普通のおむつかぶれのお薬よりもずっとよく効くお薬なの。おむつかぶれを治すだけじゃなく、おむつかぶれになりにくいようにする効き目もあるのよ」
美幸は素っ気なく言った後、僅かな間を置き、微かに語気を強めて付け加えた。
「それに、女の子の大事なところをつるつるすべすべにしてくれる効き目もね」
真衣の股間を見た茉莉が感情の昂ぶりを抑えきれずに自ら飾り毛を剃り落としたとしたら、それは、真衣が美幸の手で黒い茂みを処分されてから何日も後のことの筈だ。なのに、茉莉の股間には再び恥毛が生えかけているというのに、それよりもずっと前に処置を受けた真衣の股間にはその気配さえないどころか、今や僅かな痕跡も残っていないという事実。そして、意味ありげに美幸が付け加えた言葉。
「……!」
真衣は、はっと息を飲んだ。
だが、本当のことを知るのが怖くて、美幸を追求する言葉を口にすることはできない。
美沙も自分が真衣の下腹部に塗り込んでいた薬の正体に今更ながら薄々気づいたようで、美幸が手にした容器を凝視したまま身じろぎ一つしない。
一瞬、教室の中がしんと静まりかえる。
その静寂を破ったのは、美幸が容器の蓋を捻る、きゅっという音だった。
「ほら、可愛い妹におしゃぶりを咥えさせてあげるのよ、真衣ちゃん。茉莉ちゃんはさっきからずっと、お姉ちゃんにおしゃぶりを咥えさせてほしくてうずうずしているんだから」
美幸はおむつかぶれの薬(という口実の、実は強力な脱毛クリーム)を指先に掬い取り、真衣の顔を横目で見て言ってから、薬を掬い取った指先を秘部の周辺に軽く押し当て、茉莉の顔を覗き込むようにして念を押した。
「そうよね、茉莉ちゃん? 真衣お姉ちゃんの可愛い妹になった茉莉ちゃんは、真衣お姉ちゃんがちゅうちゅうしていたおしゃぶりを自分もちゅうちゅうしたくて我慢できないのよね? だったら、ちゃんとおねだりしなきゃ駄目よ」
自ら恥毛を剃り落とした恥ずかしい秘部をあらわにした姿でおねしょシーツの上に横たわる茉莉が、美幸の言葉を拒むことなどできる筈がない。
「ま、真衣……真衣お……真衣お姉ちゃん、茉莉もおしゃぶりをちゅうちゅうしたいの。……真衣お姉ちゃんのお、おしゃぶり、茉莉にちょうだい」
茉莉は真衣と目を合わさないようぎゅっと瞼を閉じ、震える声で途切れ途切れに言った。
「……」
思ってもみかった事の成り行きに、真衣はどうしていいのかわからない。
だが、真衣にしても、美幸の言葉を拒むことができないのは茉莉と同じだ。茉莉の下腹部に脱毛クリームを丹念に塗り込み続ける美幸から
「どうしたの、真衣お姉ちゃん? 早くおしゃぶりをあげないと、可愛い妹の茉莉ちゃんがべそをかいちゃうわよ」
と言われると、下唇をぎゅっと噛みしめて右手を動かし、茉莉の唇におしゃぶりを押し当ててしまう。
「よかったわね、茉莉ちゃん。優しい真衣お姉ちゃんにおしゃぶりを咥えさせてもらって。二人は仲良しだから、これからも一つのおしゃぶりを二人で順番にちゅうちゅうするのよ」
限りない羞恥のせいでひりひりに乾いた唇に真衣の唾に濡れたおしゃぶりが触れるぬめっとした感触に身震いしながら、茉莉は、なぜだか下腹部がじんじん痺れてくるのを抑えられないでいた。
「じゃ、いつ失敗しちゃってもいいように、おむつをあてようね。あ、そうそう。鞄の中に残っているおむつは、茉莉ちゃん用の籠の中にしまっておいてもらえるよう杉下先生にお願いしておくわね」
茉莉がおしゃぶりをおずおずと口にふくむ様子を満足げに眺めながら、美幸は、真衣の棚の下段に二つ並べて置いてある籠に『ひよこぐみ そのだまり』という名札を取り付けながら、バッグに残っているおむつとおむつカバーを籠に収納しておくよう美沙に指示した。もちろん、バッグの中の布おむつに名札と同じ文字の刺繍が施してあることはいうまでもない。
たくさんのおむつを入れた籠が上下二段に並んでいれば、さすがに目立つ。しかも、幼稚舎から高等部まで一貫教育をモットーにしている啓明だから、幼稚舎の教諭が高等部の生徒の名前を知っていても不思議ではなく、たとえ『ひよこぐみ』というクラス名が付け加えてあったとしても、『さとうまい』と『そのだまり』という、どこかで目にしたような憶えのある名前が並んでいれば、お試し保育で休日に預かっている年少クラスの子供というのが本当は誰なのか、おぼろげながら見当をつける教諭もいるかもしれない。しかし、そうなったらそうなった時のこと。その教諭も企みの協力者に仕立ててしまえば問題はない。もうすっかり慣れた手つきで美沙が茉莉のおむつを収納籠にしまう様子をちらと見て、美幸は、新しいおむつカバーに布おむつをいそいそと敷き重ねた。
*
その後、茉莉は、自分の名前を刺繍したおむつをあてられてから、先に園内着に着替えさせられた真衣と同様、体操服の上衣の上にスモックを重ね着し、スモックの裾からおむつカバーを半分ほど覗かせた、実際の幼稚舎の園児と比べても尚いっそう幼児めいて見える装いを強要された。美幸が持って来ていたバッグに体操服やスモックが二着ずつ入っていたのは前述した通りだが、茉莉はそれを、真衣が汚してしまった時の着替えだと思っていた。しかし実は、その内の一着ずつこそが、予め茉莉のために用意されていた園内着だったのだ。
おむつをあてられ、腰骨のあたりまでしかないスモックを着せられて、真衣と共に絵本を読んで聞かせてもらったり、真衣とお揃いのよだれかけで胸元を覆われて美幸から口移しでお弁当を食べさせてもらう茉莉には、日頃の生真面目なクラス委員長や茉莉お姉ちゃんとしての面影など微塵も残っていなかった。いつしか茉莉は、真衣と同様、自分では何もできない甘えん坊の年少さんになり果てていた。
いや、年少さんどころか、美幸の手によって眼鏡を外されてしまったせいで教室の中を歩くのも覚束ず、ちょっとしたことですぐに尻餅をついてしまうものだから、それこそ、ようやくよちよち歩きができるようになったばかりの赤ん坊といった方が近いかもしれない。近眼のため度の強い眼鏡をかけている茉莉だが、いつもの教室ならどこに何があるかわかっているから、視界がぼやけていても、微かに見える輪郭を頼りに障害物を避けて歩き回ることもできる。しかし、十数年ぶりに訪れて記憶も定かではない上に昔と比べれば備品の配置もまるで変わってしまっている幼稚舎の教室を眼鏡無しでちゃんと歩けるわけがない。一歩進むにも、足元に何かがあるのではないかとおどおどしっぱなしで、頼りなげに両手を前に広げ、おむつでぷっくり膨れたお尻を後ろに突き出した、見るからに危なっかしい歩き方になってしまうのも当たり前だ。
そんな茉莉が、再びじわじわ強まってきた尿意にとうとう我慢できなくなったのは、午後二時ごろの少し早いオヤツの時間、温かいミルクが入った哺乳壜の乳首を強引に咥えさせられてすぐのことだった。
「ち、ちょっと待って、お願いだから、哺乳壜を離して」
美沙が支え持つ哺乳壜からミルクを飲んでいる真衣と向き合う格好で椅子に座り、腰をかがめた美幸の手で哺乳壜の乳首を唇に押し当てられた茉莉は、羞恥に顔を歪めながら懇願した。
「どうしたの? 喉が渇いてないのかな?」
わざと不思議そうな表情で美幸は茉莉に訊き返した。
「……お、おしっこなの……」
哺乳壜の乳首を口にふくまされたまま、茉莉は微かに首を振った。
「なんだ、おしっこなの。だったら、そのまましちゃえばいいのよ。たぶん、お姉ちゃんの真衣ちゃんだってミルクを飲みながらしちゃってると思うわよ。だから、妹の茉莉ちゃんが遠慮することなんてないの。そのためのおむつなんだもの、哺乳壜をちゅうちゅうしながらしちゃいなさい。今日から年少さんになったばかりの茉莉ちゃんは赤ちゃんと同じなんだから、ミルクをちゅうちゅうしながらおむつを汚しちゃっても、お行儀がわるいだなんて誰も思わないから」
家で真衣に使わせている哺乳壜と同様、茉莉に咥えさせた哺乳壜の乳首にも細工がしてあって、茉莉が吸わなくてもミルクが勝手に流れ出るようになっているから、哺乳壜の乳首を口にふくんだまま喋ると、唇の端からミルクが溢れ出してしまう。美幸は、こぼれ出たミルクの雫をガーゼのハンカチで拭き取りながら、あやすように言った。
そこへ美沙が、こちらもあやすような口調で話しかけてきた。
「そうよ、茉莉ちゃん。真衣お姉ちゃんなんて、もうおむつをびしょびしょにしちゃってるんだから、妹の茉莉ちゃんがしくじっても、ちっとも恥ずかしくなんてないわよ」
そう言う美沙は、左手で哺乳壜支え持ったまま、右手の指を真衣のおむつカバーの中に差し入れて、おむつの様子を確認していた。
「ほら、思った通りだ。だから、さ、茉莉ちゃんも」
美幸は哺乳壜を茉莉の口にあてがったまま、空いている方の手でおむつカバーの股間をぽんと叩いた。
と、茉莉がぶるんと首を振って哺乳壜の乳首から口を離し、椅子からぱっと立ち上がった。
「急にどうしたの、茉莉ちゃん。何をそんなにむずがっているの?」
美幸は、かがめていた腰をすっと伸ばし、後ずさりする茉莉の顔を正面から見て言った。茉莉の唇からミルクの雫がこぼれ出し、顎先から伝い落ちて、スモックの胸元にうっすらとシミをつくる。
「お、おむつにおしっこだなんて、いや。わ、私は真衣ちゃんじゃないんだから、ちゃんとトイレへ行くの」
茉莉はセーラースーツの胸元が濡れるのもかまわず震える声でそう言い、唇を「へ」の時に曲げた。
胸の奥底にひそんでいた想いを美幸に見透かされ、豊かな乳房に顔を埋めた瞬間、その想いを抑えきれなくなってショーツとおむつを汚してしまった茉莉。その時は感情の昂ぶりを鎮められず、思いの丈を爆発させてしまったものの、いざ本当におむつをあてられ、真衣と同じように幼稚舎の園児そのままの格好を強要された今になってみると、このまま尿意に耐えかねておむつを汚したが最後、もう二度と引き返せない道に足を踏み入れてしまいそうな気がして、尿意のせいだけでなくぶるっと体が震える。排尿障害という病気を言い訳にできる真衣とは違って、健康そのものの茉莉にとって、おむつが自分のおしっこでじわじわ生温かくなってゆく感触を正当化できる口実など、一つもないのだ。
正門と教室の他はどこも鍵がかかっていて幼稚舎のトイレは使えない状態だから、おしっこをしたくなったら、中等部か高等部の校舎へ行くしかない。だが、丈の短いスモックにおむつカバーという姿で幼稚舎の建物から出られるわけもない。自分でもそんなことはわかっているのだが、今の茉莉には、踵を返し、教室の入り口に向かって駆け出すことしかできなかった。
しかし、眼鏡を奪い取られたせいで周囲の様子がよく見えないくせに勢いよく駆け出したものだから、足元に転がっていた布製のボールを踏みつけて体のバランスを崩し、三歩も進まないうちに、板張りの床に尻餅をついてしまう。
直後、茉莉の顔に絶望的な表情が浮かんだ。
その表情が何を意味するのか、それとまるで同じ表情が何度も真衣の顔に浮かぶのを目にしてきた美幸と美沙にはすっかりお見通しだった。
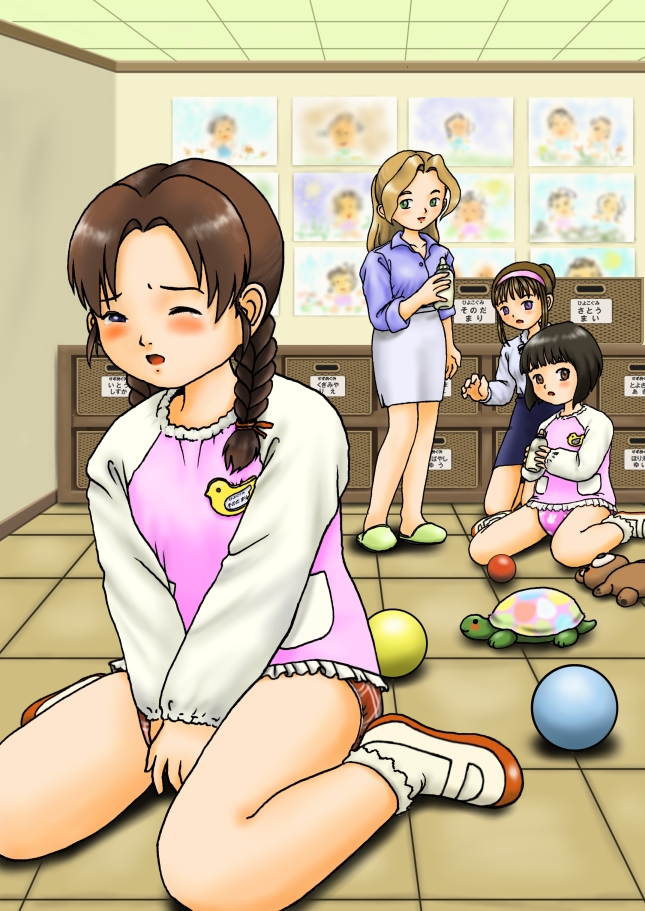
「あらあら、茉莉ちゃんてば、思っていたよりもずっとお転婆さんだったのね。でも、小っちゃい子はそれくらい元気な方がいいわね。それに、今はとってもお転婆で手のかかる茉莉ちゃんも、すぐにおとなしくなるに決まっているもの。そうよね、最初のお転婆ぶりが嘘みたいに思えるほど素直ないい子になった真衣お姉ちゃんの妹なんだから。――さ、急に走って喉が渇いたでしょう? 飲みかけだったミルクを最後まで飲んじゃいましょうね。おむつはミルクを飲み終わった後で取り替えてあげるから、ミルクを飲みながらおしっこをたっぷり出しちゃいなさい」
床に尻餅をついて入り口の方に虚ろな目を向ける茉莉の口に、膝立ちになった美幸が改めて哺乳壜の乳首をふくませた。
「入園のお祝いに真衣ちゃんにミルク飲み人形をプレゼントしようかなって思っていたんだけど、この調子じゃ、わざわざ買う必要はなさそうね。だって、人形を買わなくても、ミルクを飲みながらおむつを汚しちゃう茉莉ちゃんっていう妹ができたんだもの。それに、茉莉ちゃんがミルク飲み人形で遊びたくなったとしたら、その時は真衣ちゃんに哺乳壜でミルクをあげれば、真衣ちゃんもすぐにおしっこでおむつを濡らしちゃうし。うふふ。二人が仲良く一緒にいれば、お互いに、自分専用の生きたミルク飲み人形を持っているのと同じってことになるなるわね」
真衣に哺乳壜のミルクを飲ませながら二人の様子を眺めていた美沙が、笑いを含んだ声で言った。
茉莉は、限りない羞恥で身を焼かれる思いだった。けれど、その羞恥が被虐的な悦びを与えてくれるのも、また、事実だった。
これから、茉莉のおむつを取り替えるたびに、おそらく美幸と美沙は、茉莉の秘部が奇妙な濡れ方をしていることに気づくことだろう。さらりとしたおしっこだけでは説明のつかない、もっと粘りけのあるぬるぬるした濡れ方をしていることに。だが、それに気づいても、二人はそっと目を合わせて互いに無言で頷き合うだけに違いない。
*
それから更に時間が経って午後の五時になると、真衣と茉莉は園内着からセーラースーツに着替えさせられ、運転席に美幸が、助手席に美沙が乗る車の後部座席に座らされた。もちろん、特製のチャイルドシートに二人並んでだ。茉莉は真衣たちとは一緒に暮らしていないのだが、幼稚舎を出る前に美幸が茉莉の家に電話をかけ、保健委員会のことで打ち合わせをしたいから今夜は茉莉をこちらで預かると告げて母親の許しを得た上で車に同乗させたのだった。
入門の時だけでなく門を出る際にも職員証や学生証の確認が行われるのだが、何の問題もなくすんなりパスしたのは美幸だけだった。幼稚舎の教諭に扮した美沙が職員証ではなく学生証を提示すると、係員は不審げな表情を浮かべ、学生証の写真と美沙の顔とを何度も見比べたのだが、その間、幼稚舎の制服を着せられてチャイルドシートに座らされた真衣と茉莉は高等部の学生証をおずおずと提示して、後部座席を確認する別の係員に訝られていた。結局は体育大会に行われる仮装行列の準備と練習だという美幸の偽りの説明でなんとかことなきを得たものの、平仮名で名前を記した名札を付けたセーラースーツを着せられ、身動きが取れないようにチャイルドシートに座らされた状態でスカートの裾からおむつカバーを覗かせた自分たちの姿を係員にじろじろ眺めまわされる間、二人は羞恥に身を焼かれる思いだった。
しかし、車がようやく正門を通り抜けて道路に出ても、二人の羞恥がおさまることはなく、家に辿り着くまでの間、隣の車線を並走する車の窓からの視線がたまらないほど痛かった。幸い信号待ちや渋滞に引っかかることは殆どなく、車が停車している間にじろじろ覗き込まれることはなかったものの、まわりの車に乗っている人たちが怪訝な表情を浮かべているのは、こちらからも容易に窺いしれた。襟の広いセーラースーツの胸元に付けた黄色の名札は意外に目立つし、隣を走るのがワゴンや四輪駆動車など背の高い車だと、高い位置から見おろされる格好になって、窓越しとはいえ、上半身だけではなく、おむつカバーまで目についてしまう。追い越しざまに見られるだけならともかく、同じような速度で並走していると、何気なくこちらの様子を目に留め、小さな女の子が下着を丸見えにしてチャイルドシーツに座っているんだなと思って最初は気にも留めなかった相手が、やがて不思議そうな視線を何度も向けるようになり、いつしか、乗り合わせた者どうし明かな好奇の表情で何やら会話を交わし始めるのが二人には耐えられなかった。
しかも、美幸がわざと遠回りをし、余分な時間をかけて車を走らせるものだから、オヤツの時間にたっぷりミルクを飲まされた真衣と茉莉は、じわじわと尿意が高まってくるのを抑えられないでいた。
二人が揃って内腿を擦り合わせるのをルームミラー越しに確認した美幸は、助手席の美沙に向かって無言で頷いてみせた。
合図を受けた美沙が、体を捻るようにして後ろに振り向き、長い腕をいっぱいに伸ばして、真衣の口におしゃぶりをふくませる。
オヤツのミルクを飲みながらしくじった後、二時間ほどして再びおむつを汚してしまい、それから更に二時間弱が経過した今、排尿のきっかけになるおしゃぶりを咥えさせられて、それ以上の我慢などできるわけがなかった。真衣は、隣を走る車の窓からの視線を痛いほど感じながら、チャイルドシートの上で膀胱の緊張を解いた。いや、意識して緊張を解いたのではなく、勝手に解けてしまったという方が正確だろう。いずれにせよ、おむつカバーの中にじわじわ広がってゆくぬくもりに、真衣は身震いを止められないでいた。
その後、真衣の腰がひときわ大きくぶるっと震えるのを見届けた美沙は、真衣の口からおしゃぶりをつかみ取り、続けて茉莉の唇に押し当てた。
真衣とは異なりさほどおしっこが近いわけではない茉莉だが、床に尻餅をついた拍子におむつを汚してしまってからもう四時間近く経つわけだから、こちらもとっくに我慢の限界を迎えていた。それでも内腿をもじもじ擦り合わせながらなんとか耐えていたところに、おしゃぶりを口にふくまされたものだから堪らない。真衣がおしゃぶりを咥えておむつを汚す場面をこれまでに何度も繰り返し目撃してきたのに加え、ついに今日は、美幸の乳首を吸いながら、或いは哺乳壜のミルクを飲みながら、自分がおむつを汚してしまったのだ。想像を絶する羞恥に満ちたその体験によって心の奥底が激しく揺さぶられ、意識しないまま、真衣を真似るかのようにおしゃぶりを咥えた瞬間、下腹部の力を抜いてしまったとしても不思議ではない。もちろん、他の車からの視線が気にならないわけがない。眼鏡を外されたままだから、隣の車に乗っている者がこちらを凝視していたとしても茉莉にはその表情を読み取ることなどかなわないが、それでも、まわりの様子がよく見えないぶん却って感覚が鋭く研ぎ澄まされ、隣の車線を並走する車からの視線が痛いほど感じられるのだ。しかし、いったん溢れ出したおしっこの流れを止めることなどできるわけがない。。
おしゃぶりを咥えて下腹部を震わせる茉莉の様子を見ていると、ついさっきまでの自分自身の姿をみせつけられているような気がしてきて、たまらず、真衣は視線を窓の外に向けてしまう。
と、見憶えのある建物が目に映った。
どこにもありそうな鉄筋コンクリート造りのその建物は、この三月に真衣が卒業したばかりの中学校に違いなかった。
そうして、しばらく車が走って次に見えてきたのは、こちらもやはり真衣が卒業した小学校だった。それからしばらくして、今度は、十年余り前に卒園した幼稚園の建物が近づいてくる。
美幸は、あてもなく車を走らせているのではなかった。真衣と茉莉におむつを汚させるために、本当なら三十分ほどで家へ帰りつく道を、わざと遠回りして余計な時間をかけているのだが、美幸の目的はそれだけではなかった。むしろ、本当の目的は、真衣に、自分が卒業した学校や幼稚園の建物を改めてみせつけることにあった。それも、卒業した順番とは逆に、中学校、小学校、幼稚園という順序で。
幼稚園にあがる前には昼のおむつも夜のおむつも外れていた真衣。なのに、高校生になった筈の今、幼稚園の前を車で通る真衣のお尻はぐっしょり濡れたおむつに包まれている。じわじわ冷えてきたおむつのせいで小刻みな身震いを止められないまま、卒業した順番とは逆に所縁のある学校を巡るささやかなドライブは、自分の置かれた立場をこれでもかというくらい真衣に思い知らせるために美幸が仕組んだ少し意地悪な小旅行だった。
*
ぐるりと遠回りした末にようやく帰りついた佐藤家。
車からおりた真衣と茉莉はリビングルームへ連れて行かれ、床に敷いたバスタオルの上に二人並んで寝かされて、真衣は美沙の手で茉莉は美幸の手でスカートの裾をお腹の上まで捲り上げられた。
「初めての幼稚舎で緊張したでしょ? でも、もういいのよ。お家に帰ってきたんだから、いつもの赤ちゃんに戻ってママやお姉ちゃんに甘えていればいいの。真衣ちゃんがしてほしいことは、これまでと同じようにママとお姉ちゃんがみんなしてあげるから」
丸見えになったおむつカバーの前当てに指をかけて、美沙は、とびきり優しい声で真衣に言った。
その隣では、美幸が茉莉のおむつカバーに手を伸ばしながら、これ以上はないくらい優しい声をかけている。
「お家にはちゃんと連絡しておいてあげたから心配しなくていいのよ。明日の夕方にはお家に送ってあげるから、それまでの間は真衣ちゃんの妹になってママとお姉ちゃんにたっぷり甘えてちょうだい。これから茉莉ちゃんは週末のたびに幼稚舎の年少さんになって、土曜日の夜はこのお家で赤ちゃんになるのよ。羨ましくて仕方なかった真衣ちゃんと同じ赤ちゃんに――ううん、真衣お姉ちゃんの可愛い妹に」
甘ったるい声でそんなふうに話しかけ、揃って目の前の真衣と茉莉のおむつを取り替える美幸と美沙の姿は、まるで、いつまでもおむつ離れできない甘えん坊の双子の幼稚園児を甲斐甲斐しく世話する優しい母親としっかり者の姉さながらだ。
やがて、おむつカバーの前当てと横羽根が広げられて、ぐっしょり濡れたおむつがあらわになる。どちらも、名前と幼稚舎のクラスとを刺繍した、高等部のクラスメート手縫いのおむつだ。美幸と美沙は同時に真衣と茉莉の左右の足首を一つにまとめ持って高々と差し上げると、おしっこを吸って重くなったおむつを手前にたぐり寄せてポリバケツに入れてから、差し上げていた足をバスタオルの上に戻した。
そうして、その後は、
「さ、おむつかぶれが治った真衣ちゃんは、またおむつかぶれにならないようにぱたぱたしておこうね。ほら、いい匂いでしょ」
「今日からおむつのお世話になる茉莉ちゃんは、おむつかぶれになりにくいように、お肌をつるつるのすべすべにするお薬を塗っておこうね。おむつがよく似合う、赤ちゃんのお肌になれるお薬を」
と、それまで揃って同じように動いていた美幸と美沙の手が今度ばかりは別々に動き、美沙はベビーパウダーの蓋を開けてパフを真衣の下腹部に押し当て、美幸は脱毛クリームを指先に掬い取って茉莉の下腹部に入念に塗り込みんでゆく。その間、真衣と茉莉はぎゅっと瞼を閉じたままだ。おむつカバーに包まれた自分の下腹部や、おむつカバーとおむつを広げられてあらわになった自分の無毛の股間を目にするのは耐え難いし、隣でおむつを取り替えられている級友の姿を目の当たりにするのも、それがそのまま自分の姿なのだと思い知らされることになるから、とてもではないが我慢できるものではなかった。
少しの間だけ別々の動きをした美幸の手と美沙の手が、ベビーパウダーと脱毛クリームの塗布が終わると再びぴったり息を合わせて動き出し、すっかり手慣れた様子で真衣と茉莉のお尻の下に新しいおむつを敷き込み、おむつカバーの横羽根と前当てをマジックテープで留め、おむつカバーからはみ出た布おむつをおむつカバーの中に押し込めば、それでおしまいだ。
二人同時に新しいおむつをあて終えた美幸と美沙は、真衣と茉莉をバスタオルの上に立たせると、続いてセーラースーツを脱がせ、室内着に着替えさせた。
「真衣ちゃんは今日から幼稚舎に通うようになったし、可愛い妹もできたから、これまでよりもちょっぴりお姉さんらしいドレスにしようね」
そう言って美沙が真衣に着せたのは、昨日までのベビーワンピースではなく、アリスタイプのエプロンドレスだった。ただ、『ちょっぴりお姉さんらしく』とはいっても、背中のエプロンの結び目や肘のあたりを飾り立てるフリルがベビーワンピースに比べれば本当にちょっとだけおしゃまな感じがするものの、全体のふんわりしたラインや、ワンピースと同じベビーワンピースの生地で縫製してあるところなど、いかにも、小さな女の子向けの仕立てになっているのは変わらない。しかも、普通のアリスドレスならスカートとパニエとの組み合わになっている筈なのに、美沙が真衣に着せたエプロンドレスのスカートの内側は、ロンパースや昨日までのベビーワンピースと同様、おむつを取り替えやすいよう股間にボタンが並んだゆったりしたボトムスが縫い付けになっていた。
一方、美幸は
「茉莉ちゃんは今日からおむつのお世話になるようになったばかりの赤ちゃんだから、これを着せてあげるわね。そのうち美沙お姉ちゃんに新しいお洋服をつくってもらうけど、それまでは真衣お姉ちゃんのお下がりで我慢してちょうだい」
と話しかけながら、昨日まで真衣が着せられていたベビーワンピースの内の一着を茉莉に着せていた。
揃ってセーラースーツを着ている時はまるで双子のような雰囲気さえあった二人だが、片やエプロンドレス、片やベビーワンピースといういでたちになると、茉莉と同じようにおむつでお尻をぷっくり膨らませ、茉莉よりも幾らか背の低い真衣でも、『ちょっびりお姉さん』に見えなくもない。しかも、茉莉の方は「赤ちゃんなんだから、これもちゃんとしておこうね」と、ワンピースの胸元を大きなよだれかけで覆われたから尚更だ。
「うふふ。二人ともとっても似合っているわよ。じゃ、着替えも終わったし、夕飯にしましょう。今日は帰りが遅くなっちゃったから、途中で買ってきたコンビニのお弁当だけど仕方ないわね。あ、でも、真衣ちゃんと茉莉ちゃんは、買い置きのベビーフードよ。コンビニのお弁当みたいな香辛料をたくさん使った食べ物を小っちゃい子に食べさせるわけにはいかないもの」
帰りが遅くなったのは自分がわざと遠回りしたせいなのに、そんなことはおくびにも出さずに美幸はしれっとした顔で言い、茉莉の手を引いてリビングルームをあとにした。
美沙に手を引かれた真衣が、歩を進めるたびにふわっと舞い上がるアリスドレスの裾を片手で押さえながら二人に続く。
替えのおむつを収めたバスケットや、ひよこの形をした名札を胸元に付けたセーラースーツと、洗剤を溶かした水を張って汚れた布おむつを浸けたポリバケツ。人影が消えてしんと静まり返ったリビングルームに残された数々の物を見て、ついさっきまでそこでおむつを取り替えられていたのが実は高校生だと言い当てられる者など皆無だろう。真実を知っているのは、薄いカーテンの隙間から室内の様子をじっと見守っている銀色の月だけに違いない。
*
それから更に数時間後。
もう随分と高いところまで昇った月の光が差し込む自分の部屋で、美幸は、机の上に置いた二つの写真立てをじっとみつめていた。
向かって左側にある写真立てには、真衣の部屋の机に置いてある写真立てに入っているのと同じものを焼き増しした写真が収まっていた。そして、右側の写真立てには、幼稚舎の臨時入園式の様子をデジカメで撮影し、遠回りした帰り道の途中に立ち寄った写真店でプリントした写真の中の一枚。
左側の写真に写っているのは、幼い頃の真衣と、若い母親。公立幼稚園の入園式に臨み、華やかに飾りたてられた正門の前で二人仲良く並ぶ、笑顔が眩い母娘連れの姿だ。一方、右側の写真には、啓明女学院幼稚舎の表門の前に並んでいる真衣、美幸、茉莉の姿があった。
(結局、あなたとは離れ離れになったままでしたね。自分のものにしたいと思ったものは何でも手に入れてきた私がたった一つだけこの手にできなかったのが、あなたです)
美幸は、写真に写っている若かりし頃の真衣の母親に向かって心の中で囁きかけた。
(でも、そんなあなたも、大切なお嬢さんを独り残すのは気がかりだったんですね。だから、あなたは、真衣ちゃんを私に託すことにした。――いいえ、今はいないあなたの本心がわかる筈なんてありません。でも私は、愛おしくてたまらないお嬢さんをあなたが私に託してくれたと信じることにしたんです。私に託すために、私と真衣ちゃんを引き合わせてくれたんだと信じることにしたんです。優さんとの出会いは、私と真衣ちゃんが出会うためのきっかけにすぎなかった。そうなんでしょう?)
写真から返答があるわけがない。しかし、かまわず美幸は胸の中で囁きかけ続けた。
(あなたがいなくなってすぐ、真衣ちゃんの頻尿症状が出現した。そして、あなたと私が卒業した啓明に入学した時期と前後して真衣ちゃんの夜尿が始まった。それもみんな、私と真衣ちゃんとの出会いの機会をつくるために天国のあなたが神様にお願いしてくれたからだと信じることにしたんです)
無言で囁きかける美幸の瞳が、月の光を受けて銀色に煌めいた。
(あなたの大切な宝物のことは私にまかせてください。傷一つ付けないよう大切に守ります。どんなことがあっても傷が付かないよう、この世で最も柔らかな布にそっと包んで、一生に渡って守り抜きます。そう、これ以上はないくらい優しく柔らかなおむつにずっと包み込んで)
美幸はふっと溜息をついて、机の隅に据えた小さなスピーカーの方に振り向いた。特製のベビーベッドの枕元にセットしたマイクが拾った音を伝えてくれるスピーカーだ。
今、スピーカーから微かに聞こえてくるのは、やすらかな寝息だけだった。寝息は二人分。一人は真衣、もう一人は茉莉だ。
夕飯と入浴を済ませた後、育児室そのままにしつらえられた真衣の部屋に連れて行かれた二人は、一緒に、特製の大きなベビーベッドに寝かされた。もうすっかりそれが習い性になってしまっている真衣は、サークルメリーがかろやかなメロディを奏でる中、美幸が口ずさむ子守唄を聴きながら、ぽんぽんとお腹を叩かれてすぐに寝かしつけられてしまったし、一方の茉莉も、夕飯のベビーフードに美幸が混入した睡眠導入剤のせいで階段を昇る途中からうとうとし始めており、こちらも、まるで意識を失うようにすっと眠りに墜ちてしまうのに、まるで時間はかからなかった。
(でも、もうすぐ、この寝息が泣き声に変わるんですよ。おむつが濡れちゃったことを教える泣き声にね。最初にべそをかくのは真衣ちゃんでしょうね。でも、真衣ちゃんの泣き声がしてすぐ、茉莉ちゃんもべそをかくと思いますよ。だって、二人は本当に仲のいい姉妹になっちゃったんだから)
スピーカーから聞こえる寝息に耳を傾けながら、美幸は、悪戯めいた笑みを浮かべて、再び真衣の母親の写真に向かって胸の中で囁きかけた。
(だから、安心してください。あなたがいなくなって、思いきり甘えられる相手を失った真衣ちゃんは、無理に無理を重ねて、小さいうちから何でも自分でこなすことをおぼえてしまいしまた。実際の年齢とはまるで似つかわしくないほどしっかりしなきゃと事あるごとに自分に言い聞かせて育ちました。その時から、真衣ちゃんの時間は止まってしまったんです。自然にゆっくり過ぎてゆく時間から、一足跳びで大人になる時間に飛び移ってしまったんです。そして茉莉ちゃんは、両親の期待に応えようとして、真衣ちゃんとは別の意味で、やはりこちらも、急いで大人になる時間に乗り換えてしまったんです)
美幸は、幼稚舎の表門の前でおむつカバーが見えないようにセーラースーツの裾をさかんに引っ張っている写真の中の真衣と茉莉に視線を転じた。
(そんな二人と、美沙さんと、そして私が出会った。それは偶然なんかじゃなく、必然だったんです。いいえ、あなたがそうさせてくれたんだと信じています。私たちが出会って、真衣ちゃんも茉莉ちゃんも、本当の自分の時間に戻る決心を強くしたんです。大急ぎの時間からおりて、ゆっくり流れる時間へ、もういちど乗り換えようとしているんです。私と美沙さんは、それを手伝ってあげたいんです。飛び越えてしまった時間を巻き戻して、もういちど最初からやり直させてあげたいんです。そう、あなたがいなくなってしまった時に戻って。幼稚園の入園式の日を迎えて笑顔いっぱいだったあの頃に真衣ちゃんを戻してあげたいんです)
美幸は、写真の中の真衣と茉莉の羞恥に満ちた表情を目にしてくすっと笑い、母親の写真に視線を向け直した。
(今はこんなに恥ずかしそうにしている二人だけど、すぐに笑顔を取り戻しますよ。心の中の一番深い所に身を隠していた幼い時の本当の自分がひょっこり姿を現して、嬉しそうに笑うに決まっています。土曜日の夜だけこのお家に預かることにした茉莉ちゃんも、すぐに、ずっとここにいたいって言い出すに決まっているんです。高等部の授業を受けている途中でも、真衣ちゃんみたいにセーラー服の下におむつをあててほしくて、私がいる保健室へやって来るに違いありません。いつもずっと真衣ちゃんや美沙さんと一緒にいたいって言い出すのは目に見えているんです)
美幸はそっと瞼を閉じた。
(優さん、海外出張から帰ってきたらびっくりするでしょうね。だって、真衣ちゃんがすっかり赤ちゃん返りしちゃった上に、知らないうちに真衣ちゃんにお姉ちゃんと妹ができているんですもの。でも、かまいませんよね? だって、優さん、子供が大好きで、子供がたくさんできてもいいように部屋数を増やすよう工務店の人にお願いしていたんでしょう? だったら、娘が三人になっていても喜んでくれますよね? いいえ、喜んでくれるに違いありません。だって、私がそう決めたんですから)
再び瞼を開けた美幸の瞳は、月の光とはまるで異なる妖しい輝きをたたえていた。
そこへ、とんとんとドアをノックする音が美幸の耳を打つ。

「ちょっといいかな、ママ。茉莉ちゃんに着せてあげるベビー服のデザインを考えているんだけど、生地の組み合わせで迷っているのよ。気に入った柄が多すぎて、私だけじゃ決められないみたい」
美幸の返事も待たずにドアを開け、顔をみせたのは美沙だった。
「帰り道の途中に立ち寄った手芸店で買った生地でしょう? あそこにあるのはどれも可愛いから、あれこれ迷っちゃうのも仕方ないわよね。いいわ、私も一緒に組み合わせを考えてあげる」
美幸は鷹揚に頷いて椅子から立ち上がり、自分の部屋から廊下に出ると、妖しい光を宿した目を再び母親の写真に向けてから、ゆっくりドアを閉めた。
主のいなくなった部屋に残された写真立ての中で、窓から差し込む冷たい月の光を浴びて、真衣の母親は相変わらぬ優しい笑みを浮かべていた。
[完]
|