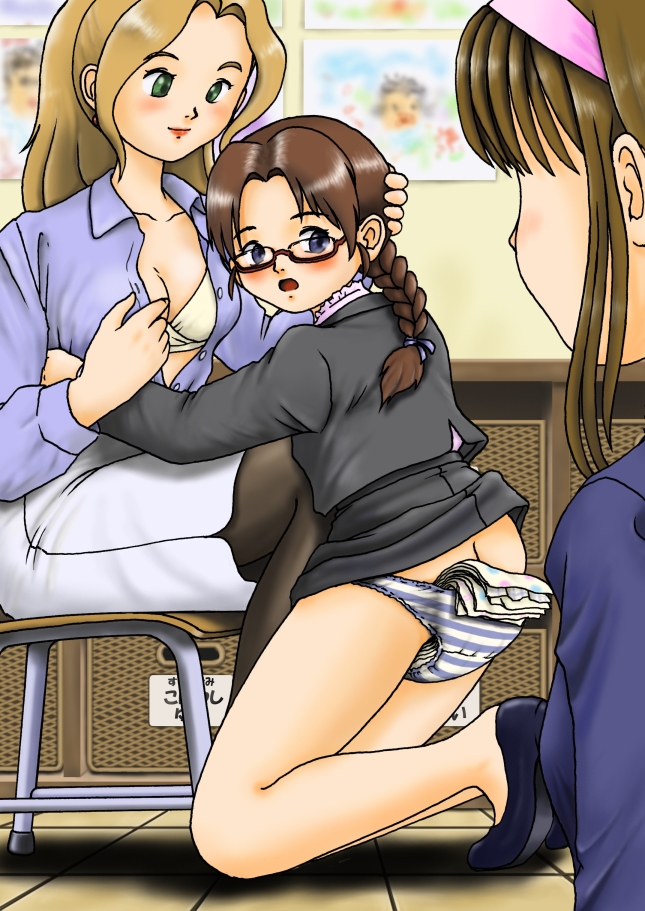|
《27 抑えきれない想い》
「それじゃ、真衣ちゃんも聞きわけよくしてくれるようだから、改めてオリエンテーションを続けましょう。――まず、お母様。お子さんを幼稚舎に預けるにあたって、何か不安に思っておられることがおありでしたら遠慮無くおっしゃってください」
真衣が唇を噛みしめて顔を伏せると同時に、芝居がかった口調で美沙が言った。
「はい、やはり一番の心配事は、挨拶の中でこの子が自分でも申しましたように、まだおむつ離れできないことでしょうか。なんというか、よそさまのお子さんに比べて全体的に発育が遅れているようなところがありまして、それが気がかりで」
美沙の問いかけに、こちらも芝居気たっぷりに美幸が応じる。
「たしかに、そういうところが見受けられますね。特に、十六歳になってもまだおむつが外れないところなど、お母様としては不安に感じられるかもしれません。けれど、そのための年少クラスですからご安心ください。とっくにおむつ離れした年中さんには厳しくすることもありますが、たとえ十六歳のお子様が相手でも年少さんにはできる限り優しく接します。おむつのお世話も私どもがちゃんといたしますので心配なさらないでください。」
安心どころか、真衣にとっては何の慰めにもならない、むしろ屈辱きわまりない返答を美沙がする。
「それでしたらよろしいのですけれど。でも、おむつのことだけじゃなく、この子ったら、まだまだ甘えん坊さんで。幼稚舎に入るのに、こんなことでいいのかどうか。――これを読んでいただけますか」
美幸は、真衣が肩に掛けたままにしている通園鞄の蓋を開けると、表紙に『れんらくちょう ひよこぐみ・さとうまい』と書いてあるノートを取り出し、美沙の目の前に差し出した。
「お預かりいします。――ああ、なるほど。まだお母様のおっぱいをせがんだり、子守唄を歌ってあげないと寝つかないわけですか。――それに、離乳食がメインで、普通のご飯はお姉様に口移しで食べさせてもらっていると。遊ぶ時はガラガラで、おしゃぶりも手放せないということのようですね。承知しました。たしかに、幼稚舎に入るような年ごろのお子様としては随分と甘えん坊さんのようですね。しかも、本当は十六歳という年のお子様にしては。いえ、前もってこういうことを知らせておいていただければ、それに合わせた保育カリキュラムを組ませていただきますから、お母様はご安心ください。それと、お預かりしている間におむつをどれくらい汚したかとか、自分でご飯を食べられたかとか、そういったことはこちらが連絡帳に書いて通園鞄に入れておきますので、ご家庭でご覧になって、お子様の発育具合をご確認いただければと思います」
中学二年生の時に職場体験で行った近くの幼稚園での様子を思い出しながら美沙は如才なく応え、連絡帳を閉じて机の隅に置いた。
その後を、今度は茉莉が引き継ぐ。
「それでは、次に、忘れ物がないかどうか確認させていただきます。通園鞄を預かってもよろしいでしょうか」
いささか棒読みぎみに茉莉は言って通園鞄を受け取り、中に入っている物を一つずつ机の上に並べていった。
「まず、園田先生が預かった連絡帳。それから、小さなお子さんは汗をかきやすいのでガーゼのハンカチが二枚に、ティッシュ。はい、お弁当も忘れていませんね。それに、お絵描き帳とクレヨンもちゃんと入っています。結構です。あら、これは……」
最後に茉莉が苦笑交じりに通園鞄から取り出したのは、高等部の制服を着ている時も胸ポケットに入れて真衣が肌身離ず持たされているおしゃぶりだった。
「これは本来なら幼稚舎に入るようなお子さんには必要のない物かと思われますが、特別に認めることにしましょう。――あと、着替え類はお母様がお持ちのバッグの中でしょうか」
おしゃぶりをクレヨンの箱の隣に並べ、通園鞄の中を確認し終わった茉莉は、次に、美幸が手に提げて持ってきている大きなバッグに視線を向けた。
「はい、園内着などはこちらに入れて持ってきています。ご確認ください」
「それでは拝見いたします」
通園鞄に続いて大振りのバッグを受け取った茉莉は手早くファスナーを開け、中を覗き込んだが、しばらくすると小さく頷いて、顔を伏せたままの真衣に向かって声をかけた。
「どうやら忘れ物はないみたいだから、真衣ちゃん、先生と一緒に来てちょうだい」
その声に、不安に満ちた表情で真衣がおそるおそる顔を上げる。
「そんなに心配しなくても大丈夫よ。幼稚舎の子供たちは、通園する時は制服だけど、園にいる時は体操服とスモックに着替える決まりになっているの。それで、脱いだ制服は自分で各々の籠に入れて、体操服なんかを入れてきた袋や通園鞄と一緒に棚に置くことになっているのよ。だから真衣ちゃんも、自分で着替えて、制服なんかを籠に入れて棚に置くお稽古をしようね。真衣ちゃんは年少さんだから、まだきちんとできないかもしれないけど、先生が手伝ってあげるから心配しなくていいのよ」
茉莉はそう言ってバッグの把手をつかみ、すっと立ち上がった。
それと同時に、美幸が真衣の腰を持って強引に椅子から立たせ、背中をとんと押す。
茉莉が真衣を連れて行ったのは、教室の後ろの方の壁際に造り付けになっている二段の棚の前だった。棚とはいっても園児の身長に合わせてかなり低い位置にあり、二段の棚は更に幾つもの区画に仕切られていて、それぞれの区画に、名札の付いた収納籠が収めてあった。
その棚の端に、籠が二つ並べて収めてある、他の倍ほどもある大きさの区画が設けられていた。見ると、二つの籠にはどちらも『ひよこぐみ・さとうまい』と記された名札が付いている。
「真衣ちゃんは他の園児に比べて体が大きいから制服も嵩張るでしょう? それに、他の子供たちには必要ない着替えも入れておかなきゃいけないから、籠の数を増やして、大きな棚を用意しておいたのよ。じゃ、お母様が持って来てくださった鞄に入っている物を籠に入れてからお着替えを始めようね」
自分用の区画が他の園児の区画よりもずっと大きいことに怪訝な表情を浮かべる真衣に向かって茉莉は『他の子供たちには必要のない着替えも入れておかなきゃいけない』という部分を強調して言い、収納籠を二つとも棚からおろして板張りの床に置くと、美幸から預かったバッグを真衣の目の前に押しやった。
「さ、最初は何が出てくるかな。真衣ちゃんが自分で鞄から出して籠に入れるのよ。上手にできるかどうか、先生、ここで見ていてあげるわね」
茉莉にそう言われ、真衣は、少し離れた所に座っている美幸と美沙の顔をちらと見た。二人とも、こちらをじっとみつめている。ここで茉莉の言いつけに逆らったりしたら手痛い仕打ちが待ち受けているのは明かだった。
真衣はバッグの中におずおずと両手を差し入れ、最初に触れた衣類をつかみ上げた。
真衣がバッグから取り出したのは、園内で体操服の上に着るスモックだった。もちろん、制服と同様、真衣の体に合うようなサイズのスモックなどあるわけがないから、これも美沙の手作りだ。
「一番目はスモックだったわね。じゃ、次は何かな」
茉莉は、真衣がスモックをきちんと折りたたんで籠に入れるのを見届けてから、先を促した。
「あら、今度もスモックね。どうして真衣ちゃんのお母様は同じスモックを二着も用意してくださったのかしら」
茉莉の言う通り、真衣が二番目に取り出したのも、一着目とまるで同じスモックだった。それを見た茉莉は要領を得ない顔になったが、続けて真衣がバッグからつかみ上げた生地をを目にした途端、納得顔になった。
「あ、そうか。真衣ちゃんは年少さんだもん、まだ上手にお弁当を食べられなくてスモックを汚しちゃうかもしれないのね。だからお母様は念のためによだれかけを持たせてくださったけど、それだけじゃ心配で、替えのスモックも用意してくださったみたいね。よかったわね、優しいお母様で」
そう、真衣がスモックの後でバッグから取り出したのは、細かなフリルの飾りレースで縁取りした大きなよだれかけだった。バッグに何が入っているか知らされていないまま手探りで順番に衣類をつかみ上げてゆく真衣がよだれかけを引っ張り出して頬を赤く染める様子をおかしそうに眺めながら、茉莉はくすっと笑って言った。
よだれかけをさっさと丸めるようにして籠に放り込んだ真衣がその次に取り出したのは、肩口から袖先にかけてピンクのラインが入った半袖の体操着の上衣が、替えの分も入っているのかスモックと同じように二着と、それに続いて、ハーフパンツタイプの体操服の下衣が、これもやはり二着だった。そこでいったんは真衣も幾らか落ち着いた表情になったのだが、体操服の後でつかみ上げた布地を目にした途端、再び顔を真っ赤に染め、取り出しかけた布地を慌ててバッグの中に押し込んでしまう。
「あら、駄目じゃない。せっかく取り出した物をまたしまっちゃうなんて。次は何が入っていたのか、先生に見せてちょうだい」
真衣がつかみ上げかけたのが何なのか、すぐに見当をつけた茉莉がバッグに右手を突っ込み、再びしまいこまれた布地を引っ張り出した。
案の定、それは、真衣の名前を刺繍した布おむつだった。それも、今度は名前だけでなく『ひよこぐみ』という文字が追加してあった。級友たちが縫いあげたおむつに美沙が刺繍を施したものに違いない。
「他の子供たちは体操服やスモックを小さな可愛い布袋に入れて持ってきているのに、真衣ちゃんのお母様が大きな鞄を持ってきていたのは、こういうことだったのね。そうね、替えのおむつをたくさん持ってこなきゃいけないんだもの、小さな布袋じゃ入りきらないわよね。だから、他の子供たちと違って、真衣ちゃんだけ籠が二つも要るのよね」
茉莉は大げさに頷き、まだ何も入っていない方の籠を手前に引き寄せた。
「それじゃ、体操服やスモックみたいな普通の着替えはそっちの籠に入れておいて、真衣ちゃんにしか必要のないおむつはこっちの籠に入れておこうね。でも、たくさんのおむつだから入りきらないかしら」
茉莉は『真衣ちゃんにしか必要のない』という部分と『たくさんのおむつ』という部分を改めて強調して言い、真衣が自分ではなかなか手を動かそうとしないのを無視して、次々におむつをバッグから引っ張り出し、きちんと三つ折りにして収納籠に積み重ねていった。
だが、さすがに『たくさんのおむつ』だ。バッグに入っていたおむつを半分ほど移すと、もう収納籠がいっぱいになってしまう。
「仕方ないわね、残りは鞄に入れたまま棚の近くに置いておきましょう。でも、これだけたくさんあれば今日と明日の分には充分だし、かなり余るかもしれないわね。だったら、余った分はこのまま籠に入れて来週の通園日まで棚に置いたままにしておくといいわ。いちいち持って帰ったり、また持って来たりするのは大変だもの」
おむつでいっぱいになった籠を棚に置き、まだ半分ほどおむつが残っているバッグを棚の下に置きながら、茉莉はこともなげに言った。
それを聞いた真衣の顔がこわばる。
「ま、待ってよ、茉莉お姉ちゃん。おむつをこのまま置いておくだなんて……」
真衣は引きつった表情で訴えかけた。
だが、真衣の言葉が終わらないうちに、諭すように茉莉が言う。
「お姉ちゃんじゃないわよ。ここにいる間はひよこ組の副担任・園田先生なんだから忘れちゃ駄目よ。――ま、それはいいとして、おむつは置いたままでかまわないのよ。他の子供たちだって、汚さなかった着替えは三日に一度くらいしか持って帰らないことがあるんだもの。汗を吸う体操服は毎日持って帰って次の日にまた持って来るのが普通だけど、スモックとかは、クレヨンやお弁当で汚さなかったら一週間に二回くらいしか持って帰らなくてもいいのよ。だから、使わなかった替えのおむつも置いておけばいいの」
「でも、だって……」
茉莉はなんでもないように言うが、真衣にしてみれば、言われるがままになるわけにはゆかない。
「うふふ。月曜日になって私たちが高等部に戻った時、ここには幼稚舎の年中さんがいるわよね。その子たちにおむつを見られるかもしれないって、それが心配なのかな」
「……」
茉莉が指摘する通りだった。しかし、そうだと頷くのも躊躇われる、
「大丈夫よ、気にしなくても。幼稚舎の園長先生には本当の事情を高等部の校長先生から話してもらっているけど、幼稚舎の他の先生方や園児たちには園長先生が、幼稚舎がお休みの日に何ケ月間か、入園を希望している子をお試し保育で預かることになったって説明してくれているの。来年入園する子をお試し保育で預かるんだから、その子、今はまだ年少クラスの年だってことになるでしょ? 年少さんだったら、おむつのお世話になっていても不思議じゃないもの、おむつの入った籠が置いてあっても誰も変に思わないわよ。『ひよこぐみ・さとうまい』って刺繍してあるんだもの、まさか、このおむつのお世話になっているのが高等部の佐藤真衣さんっていう大きなお姉さんだなんて思う子や先生は一人もいない筈よ」
茉莉はそう説明して真衣をなだめる。
「でも、おむつカバーが……」
真衣はぶるんと首を振って言い募った。
美幸がバッグに入れて持ってきたのは布おむつだけではない。替えのおむつカバーも持って来ているのは当然だ。むろん、茉莉は特製の大きなおむつカバーも収納籠に入れておいた。
「ああ、そうだったわね。おむつは赤ちゃん用のサイズに縫ったのをそのまま使っているけど、おむつカバーは十六歳の真衣ちゃんのお尻の大きさに合わせて特別につくってもらったのを使っているから、それを見られたら変に思われちゃうかもね」
茉莉はにっと笑って言った。
「だ、だったら……」
「それでも心配することなんてないわよ。ほら、こうしておけば、もう大丈夫。――啓明に入る子は躾も行き届いているから、みだりに他の子の棚を覗き込んだりしないもの。幼稚舎からずっと啓明の私が言うんだから間違いないわ」
茉莉は、真衣の心配を余所に、籠の中の布おむつでおむつカバーを覆い隠し、これでよしとでもいうように両手をぱんと打ち鳴らした。
「でも、そんなじゃ見えちゃう。それだけじゃ、いつおむつカバーがみつかっちゃうかしれないよぉ」
おむつカバーをバッグに戻そうとして真衣が棚の上の収納籠に手を伸ばしかけた。
と、それまでことの成り行きを見守っていた美沙がさっと立ち上がり、真衣の背後から厳しい声をかける。
「駄目よ! せっかく園田先生がちゃんとしてくれたんだから、勝手にいじっちゃ駄目!」
突然の美沙からの叱責に、びくっと体を震わせて真衣が振り返った。
美沙は、机の上からおしゃぶりをつかみ上げ、こちらに向き直った真衣の唇に押し当てる。
いつしかすっかりそれが習い性になってしまっている真衣は、反射的におしゃぶりを口にふくんだ。
「入園式の日から先生に反抗しちゃ駄目でしょ。しばらく、そうやって静かにしてなさい」
真衣が咥えたおしゃぶりを美沙は指の先でぴんと弾き、穏やかな口調に戻って言った。
「……」
真衣の顔に絶望の表情が浮かぶ。
建物の中ほどにあってあまり日の当たらない底冷えのする教室にずっといたため、臨時入園式が始まる直前から感じていた尿意がいつもより早く強まってきていた。そんなところへ日頃から排尿のきっかけとして咥えさせられているおしゃぶりを口にふくまされたのだから堪らない。
おしゃぶりの先が唇に触れた瞬間、最初の数滴がじくっと漏れ溢れ出たかと思うと、おしゃぶりを咥えた時には、もうとてもではないが我慢できずにじわっと溢れ出し、布おむつをじっとり湿らせていた。
「あ、ああ……」
今の真衣には、湿っぽい感触がおむつカバーの内側いっぱいに広がってゆくのを感じながら、収納籠に手を伸ばすのも忘れ、替えのおむつを収納した棚の前に立ちすくみ、虚ろな目で美沙の顔を見上げるのが精一杯だった。
*
しばらくして、真衣の腰と太腿がぶるっと震えた。
「もういいの? もう出ちゃったのかな?」
真衣の様子をじっと見守っていた美沙が、確認するように言った。
だが、真衣からの返答はない。
すると美沙はすっと手を伸ばして真衣が咥えているおしゃぶりをつかみ取り、あやすような口調で重ねて言った。
「出ちゃったら先生に教えてくれなきゃ駄目よ。幼稚舎だからって遠慮することはないの。お家でお母様に教えている通りすればいいのよ。さ、おむつが濡れたこと、いつもはどうやって教えているのかな」
おしゃぶりを奪い取られた真衣は、どこか遠くを見ているような目を美沙の顔に向けたまま、僅かに口を動かした。
やがて、よく見ていないとわからないほど小刻みに震える唇から、弱々しい泣き声が漏れる。
「……おぎゃあ……」
「そう。真衣ちゃんは赤ちゃんみたいに泣き声でおむつが濡れちゃったことを知らせるの。でも、恥ずかしがることなんてないのよ。真衣ちゃんはまだ年少さん、赤ちゃんと同じようなものなんだから」
粗相のたびに泣いて教えるよう繰り返し躾けてきた成果を真衣が幼稚舎の教室でも発揮したことに満足げな笑みを浮かべた美沙は、真衣の背中に両腕をまわしてそっと体を抱き寄せ、耳元に囁きかけた。
「高等部の教室でも泣き声で知らせる真衣ちゃんだもの、幼稚舎で同じことをしても恥ずかしいわけがないわよね」
その言葉に、真衣が頬をかっと赤らめ、誰とも目を合わすまいとして美沙の胸元に顔を埋める。
「あらあら、連絡帳にも書いてあった通り、本当に甘えん坊さんだこと。真衣ちゃんはお家でもこんなに甘えん坊さんなのかな」
家庭での真衣の生活ぶりや、真衣が顔を隠した本当の理由を充分に承知していながら、美沙は、いかにも呆れたというふうな口調で言った。
言われて、真衣は美沙の胸元にますます深く顔を埋める。
そんな二人の様子を美幸は穏やかな笑顔で見守っていたが、ふと、茉莉の方に視線を転じて、きらりと瞳を輝かせた。
何日ぶりかに登校した日の五時間目、真衣は茉莉が見守る中、美幸の手でおむつを取り替えられた。息をこらしてその様子を見つめていた時の、熱に浮かされたような茉莉の顔つき。それから数え切れないくらいの回数にわたって、真衣は茉莉の目の前でおむつを取り替えられた。そのたび、茉莉ははやり、我を忘れたかのようにうっとりした表情を浮かべ、とろんとした目で真衣の下腹部を繰り返し嘗めるようにみつめていた。
今も、そうだ。
(やっぱり、私の勘は当たっていたようね)胸の中で美幸は短く呟いて舌なめずりをした。
「……先生、園田先生? ――ちょっと、茉莉、どうしちゃったのよ、茉莉ったら!?」
初めの方は幼稚舎・ひよこ組の担任教諭を演じて茉莉に呼びかけていた美沙だが、なかなか返事をしようとしない相手に痺れをきらしたのか、最後の方は声高に茉莉の名を呼んだ。
「あ……」
その時になってようやく我に返ったかのように茉莉は瞬きを繰り返し、まだどことなくとろんとしたままの目で美沙の顔を見た。
「……ご、ごめんなさい。私ったらぼんやりしちゃって。でも、もう大丈夫だから、用事があるなら言ってちょうだい、美沙――あ、ううん、杉下先生」
「しっかりしてちょうだいよ。私たちは幼稚舎の先生。預かった子供のお世話をないがしろにしちゃいけないのよ。それも、自分じゃ何もできない年少さんを預かっているんだから尚更よ。このまま真衣ちゃんを放っておいたらお尻が気持ち悪くて可哀想でしょ?」
美沙は軽く溜息をつき、取りなすように続けた。
「ま、おむつを汚しちゃったのが恥ずかしくて私のおっぱいに顔をないないしちゃう真衣ちゃんの可愛らしさにうっとりする気持ちはわかるけどさ。じゃ、おねしょシーツを広げてちょうだい。少しでも早くちゃんとしあげないと、せっかく治ったおむつかぶれがぶり返しちゃうから」
「あ、う、うん。ごめんね、真衣ちゃん。すぐに用意するから、ちょっとの間だけ待っていてね」
日頃の生真面目さはどこへ行ってしまったのか、少し慌てた様子で茉莉は言い、教室の隅に置いてある大きな紙袋からおねしょシーツを取り出して、収納籠が置いてある棚のすぐ前の床に敷いた。そうして、もういちど紙袋に手を差し入れ、様々な形の容器を幾つか抱えて戻ってくると、おねしょシーツのそばに並べる。
おねしょシーツも幾つかの容器も、今朝のうちに美沙と茉莉が保健室から幼稚舎の教室へ運んできた物だ。いつもなら真衣と一緒に美幸の車で通学する美沙だが、今日は朝から臨時入園式用に門を飾りたてたり教室を片付けたりするために電車とバスを乗り継いで早めに学院にやって来て、茉莉と一緒に(ちなみに、疑似家族とはいっても、茉莉は美幸たちと同居しているわけではなく、自分の家から通っているのだが、今朝は美沙としめし合わせて同じ時間に学院へ来ていた)、真衣だけのための入園式の用意をし、真衣の世話をするのに必要な小物類を高等部の保健室からこちらへ運び込んで、美幸と真衣が来る前にすっかり準備を済ませていたというわけだ。
「さ、いいわよ。いつまでもお顔をないないしてないで、おむつを取り替えようね」
準備が整ったのを見て取った美沙は、まだ顔を自分の乳房に押し付けている真衣の体を優しく後ろに押しやった。
だが、真衣が美沙の体から離れる様子はない。
「ほら、駄目でしょ、杉下先生に甘えてばかりじゃ。いつまでも甘えん坊でって、お母様が心配なさるわよ」
なかなか美沙から離れようとしない真衣の腰に手をかけて茉莉が言い、強引に後ろへ引っ張った。
その様子は、いかにも、大好きな先生にすがり付いて離れない聞き分けの悪い園児と、それをたしなめる幼稚舎の教諭さながらだ。
しかし、そうしている間にも、自分よりも体の大きな二人の手で真衣は易々と美沙の体から引き離され、もうすっかりお馴染みになったおねしょシーツの上に寝かされてしまう。
「さ、おむつを取り替えようね。はい、お口が寂しくないように、お母様が鞄に入れておいてくださったこれをちゅうちゅうするといいわ。それと、これを振って遊んでいてね。その間にすぐに取り替えてあげるから」
美沙は、おねしょシーツの上に横たわった真衣の口に、いったんつかみ取ったおしゃぶりを再び咥えさせ、保健室から持ってきておいたガラガラを握らせた。ロンパースやベビーワンピースに比べれば幼稚舎の制服を着せられた真衣はちょっぴりお姉ちゃんの筈だが、まだおむつの外れない年少さんという設定だから、赤ちゃん扱いもあながち的外れではない(もっとも、十六歳という実際の年齢を考えなければの話だが)。
美沙は、美幸の方にちらと振り返って意味ありげに頷いてみせてから、真衣が着ているセーラースーツの裾をお腹の上まで捲り上げ、丸見えになったおむつカバーの前当てに指をかけた。
マジックテープを剥がすベリリという音が教室の空気を震わせ、真衣の羞恥をくすぐる。
美沙は、真衣の両脚をO形に曲げさせ、外した前当てを両脚の間を通しておねしょシーツの上に広げた。それから、互いに重ねて留めてある横羽根を外して真衣の腰の左右に広げる。
あらわになったおむつの端には、収納籠にしまったおむつとは違って、『さとうまい』という名前だけが刺繍してあった。それに、よく目を凝らして見てみれば、幾らか布地がくたびれぎみなのが見て取れる。そう、今、真衣のお尻を包み込んでいるのは、美沙の妹からお下がりにもらった方の布おむつだった。「うちの家は、お父さんの考えで、義務教育の間は公立っていう方針になっているのよ。でも、妹ったら、啓明の幼稚舎の制服が気に入っちゃって、啓明に行くんだ啓明に行くんだって駄々をこねていたの。ま、今は両親に説得されて公立の幼稚園に通ってるんだけどね。でも、そんな妹の願いが通じたのかしら。こうして、妹のおむつだけでも啓明に通えることになったんだもの。妹のおむつを貰ってくれた真衣ちゃんに感謝しなきゃいけないわね」
おしっこを吸い取ったばかりでまだ冷えきっていないおむつに目をやって美沙はどこか感慨深げに言い、続けて、真衣の顔を覗き込んでからかうような口調で付け加えた。
「でも、皮肉なものね。妹は幼稚園に上がるずっと前におむつ離れしていたから、真衣ちゃんに使ってもらわなかったら、このおむつも啓明の幼稚舎へ来ることなんてなかった筈なのよ」
そう言われて、真衣は、唇の代わりにおしゃぶりを噛みしめ、顔をそむけることしかできなかった。
と、そらした視線の先に何十枚もの絵が壁に貼ってあることに気がつく。幼稚舎に通園させられることになった羞恥と屈辱とでまわりの様子を窺う余裕もなくしていたのが、おねしょシーツの上に横たわらされて壁の上の方に目を向けるしかない今になってようやく目に留まった絵だ。
どの絵にも、幼い子供の姿がクレヨンで描かれていた。顔だけの絵もあれば、バストショットもあるし、全身像もあったが、少したどたどしい描線と、描かれた子供たちが着ている衣類から判断するに、どうやら、この教室の本当の主である年中クラス・すずめ組の園児たちが級友どうし互いの姿を描きあったもののようだ。そう思ってよくよく目を凝らしてみれば、何枚かの絵はかなり詳しい描き込みがしてあって、描かれた園児が身に着けているセーラースーツの胸元に留められた名札には、『年中クラス・すずめ組』というクラス名と園児の名前がちゃんと漢字で書かれたものも混じっていた。
「どれも上手でしょう? 年中クラスのお姉さんたちはみんなお絵描きもうまいし、漢字だって書けるのよ。真衣ちゃんはまだ年少さんだから平仮名しか読めないけど、頑張ってお稽古すれば漢字だって読んだり書けたりするようになるからね。――あ、でも、ご挨拶の中の『おむつ』や『十六さい』が読めなかったから、平仮名と数字のお勉強をもっとちゃんと済ませてからじゃないと無理かな」
美沙は手を休めることなくおむつの交換を続けながら、壁に貼っている絵に視線を向けて言った。そうして、もういちど真衣の顔を覗き込んで、わざと優しく言って聞かせる。
「でも、よかったわね。絵だけど、おむつを取り替えてもらうところをお姉さんたちに見ていてもらえて。今はまだおむつの外れない年少さんだけど、早くパンツのお姉ちゃんになれるといいねって、みんなで応援してくれているみたいじゃない? 幼稚舎じゃ、こうしてお姉さんたちに励ましてもらって、高等部じゃ、クラスのみんなにおむつを縫ってもらって。本当に真衣ちゃんは幸せだこと」
「やめて……そんなこと言っちゃやだ」
おしゃぶりを咥えているせいのくぐもった声で真衣は懇願するように言った。
そこへ、茉莉のかすれた声が割って入る。
「本当に、なんて幸せなのかしら、真衣ちゃんは。本当に――本当に、なんて羨ましいのかしら、真衣ちゃんてば。本当に、なんて、なんて……」
「……!?」
いつもとはまるで違う、なんだか喘いでいるかのような声に、真衣は思わず大きく目を見開いて茉莉の顔を見上げた。
茉莉は、瞬き一つせずに、じっと真衣を見据えていた。
真衣は戸惑いの表情を浮かべ、ごくりと唾を飲み込んだ。
と、美幸がゆっくり椅子から立ち上がり、足音を忍ばせて美沙のそばに歩み寄る。
「そろそろかしら」
美沙の傍らに立った美幸はすっと腰をかがめて美沙に耳打ちした。
それに対して美沙も声をひそめ、なんともいいようのない笑みを浮かべて美幸に囁き返す。
「もう、いい頃だと思うわよ。朝早くから二人でいろいろ準備をしてきたけど、その間、茉莉は一度もトイレへ行ってないもの。幼稚舎には私たちしかいないから、鍵を開けてもらっているのは表門と正面入り口、それに、この教室だけで、トイレへ行こうと思っても教室から廊下に出てすぐの所にある防犯シャッターが閉まっているから行けないようになっているの。だから、おしっこをしたくなったら、休みの日でもクラブ活動で校舎の鍵が開いている中等部か高等部のトイレを使わなきゃいけないんだけど、ここからだとかなり遠くて、よほど切羽詰まらなきゃなかなか行く気にならないし、茉莉がトイレへ行きそうなそぶりをみせたら、私が用事を頼んでわざと行けないようにしておいたのよ。私は保健室から荷物を持って来る時に行っておいたから大丈夫だけど、茉莉にはその時もトイレへ行かせないようにしておいたから、もうそろそろの筈よ」
真衣のお尻の下に新しいおむつを敷き込みながらそう囁く美沙の言葉に、美幸はすっと目を細めて小さく頷き、美沙のもとを離れて、茉莉がいる方に向かって静かに足を踏み出した。
茉莉の方に歩を進める美幸の背中をちらと見てから、美沙は、おねしょシーツのそばに置いてある丸い容器の蓋を開けた。と、どこか懐かしいような甘い香りがふわっと広がる。
美沙が蓋を開けたのは、塗り薬ではなく、ベビーパウダーの容器だった。
「いい匂いでしょう? もっと早くこの匂いを真衣ちゃんに嗅がせてあげたかったんだけど、おむつかぶれで赤くなったお尻にベビーパウダーを使うと却ってひどくなっちゃうから、これまでママに止められていたの。でも、昨夜、おねしょで汚しちゃったおむつを取り替える時、ママがお尻の具合を丹念に診て、もうおむつかぶれはすっかり良くなったみたいだからって、今日からベビーパウダーを使わせてくれることになったのよ。またおむつかぶれにならないよう、ちゃんとぱたぱたしておこうね。でも、それにしても、おむつかぶれが治った真衣ちゃんのお肌は本当にすべすべでつるつるね。とても十六歳とは思えないわ。本当の赤ちゃんみたいで、ちょっぴり羨ましくなっちゃうわね」
甘い香りに引き寄せられたかのように顔をこちらに向けた真衣にそう話しかけて、美沙はベビーパウダーのパフを手に取った。
ベビーパウダーには皮膚をさらさらに保つ効果があり、おむつカバーに包まれて湿っぽくなりがちな赤ん坊の下腹部がおむつかぶれにならないよう予防する目的で使うのが一般的だ。しかし、おむつを治療する効果があるわけではなく、逆に、おむつかぶれになってしまった皮膚に塗布すると、皮膚を刺激して症状を悪化させる場合も少なくない。そのため、おむつかぶれになってしまった場合はベビーパウダーの使用をいったん中止しなければならない。真衣の場合は、美幸の企みで、わざとおむつかぶれにさせられていたせいで、これまでベビーパウダーを使う機会はなかった。なのに美幸が美沙に向かってベビーパウダーを使うよう指示したということは、美幸の企みが目的を果たしたということ他ならない。そう、自分が本当は何のための薬を塗っているのか正確なことを知らぬまま美沙が真衣の股間に繰り返し塗布し続けた脱毛クリームのせいで、真衣の股間は、美沙が弾んだ声で言った通り、これ以上はないくらい『すべすべでつるつる』になってしまったのだ。いみじくもこれも美沙が口にした通り、『本当の赤ちゃんみたい』に。美幸の手で飾り毛を剃り落とされた時に残っていた毛根は綺麗に姿を消し、今や、微かな痕跡も残っていなかった。
僅かな産毛の影もない真衣の秘部に沿って美沙が手にした柔らかなパフが動きまわり、童女そのままに化した下腹部にうっすらと白化粧を施してゆく。
一方、美幸は、ベビーパウダーの優しく甘い香りが漂う中、美沙と真衣から目を離せないでいる茉莉のすぐそばに歩み寄り、耳朶に唇を触れ合わせんばかりにして囁きかけた。
「羨ましいんでしょう、真衣ちゃんが? 羨ましくて仕方ないのよね、真衣ちゃんのことが?」
美幸が近づいてきていることにも気づかず、真衣のおむつを取り替える美沙の手元をじっと凝視していた茉莉は、はっとした表情で振り向いた。
「いいのよ、口に出して言わなくても。園田先生、――いいえ、茉莉、――ううん、茉莉ちゃん。あなたがどんな気持ちを胸に抱いているかなんて、ママにはすっかりお見通しなんだから」
こちらに振り向いたきり何も言えずにいる茉莉の耳元で尚も囁きかけてから、美幸はおもむろに自分の首筋に手を伸ばし、真珠のネックレスをゆっくり外した。
その時になってもまだ茉莉は唇を小さく震わせて立ちすくんだままだ。
外したネックレスを棚の端に置いた美幸は、茉莉の目の前でスーツの上衣を脱ぎ去り、体を反らしぎみにしてブラウスのボタンを外し、胸元をはだけた。
「え……!?」
ようやく茉莉の口から声が漏れ出た。しかし、それは、まるで言葉にならない短くあえかな呻き声だった。
「真衣ちゃんはママや美沙お姉ちゃんのおっぱいを吸いながらおむつを汚すのが癖になっちゃってるの。今はおっぱいじゃなくおしゃぶりのことも多いけど、もともとはおっぱいだったのよ。そのことは茉莉ちゃんもよぉく知っているわよね? 知っていて、それが羨ましくて仕方なかったのよね?」
美幸は、胸元がはだけてあらわになった授乳用ブラのカップをまるで躊躇することなくずりおろし、豊かな乳房を前方に突き出して、ねっとりと絡みつくような声で語りかけた。
「だから、さ、いらっしゃい。ママのおっぱいが欲しいんでしょう? 真衣ちゃんみたいにママのおっぱいにむしゃぶりつきたいんでしょう? 真衣ちゃんはおしゃぶりを咥えて美沙お姉ちゃんにおむつを取り替えてもらっているから、今は、ママのおっぱいは茉莉ちゃんだけのものなのよ。だから、遠慮なんてしなくていいの。さ、いらっしゃい」
美幸は茉莉の背中に腕をまわして手前に引き寄せた。
一瞬は身を退こうとした茉莉だが、すぐに、まるで崩れ落ちるようにして美幸の体にもたれかかり、豊かな乳房に顔を埋めてしまう。
「そう、それでいいのよ。今の茉莉ちゃんは大人のお洋服を着て幼稚舎の先生になっているけど、それは『ごっこ遊び』なのよ。茉莉ちゃんは『幼稚舎の先生ごっこ』をしているだけなの。だって本当の茉莉ちゃんは、ママのおっぱいを吸いながらおしっこをしちゃうような小っちゃな子なんだから」
美幸はあやすように言いながら、美沙に向かって目で合図を送った。
真衣に新しいおむつをあて、おむつカバーの前当てを留め終えた美沙は、美幸からの合図を受けてすっと立ち上がり、棚の下に置いてあるバッグから布おむつを何枚か取り出すと、茉莉の背後に忍び寄った。
自分の乳首を茉莉の唇に押し当てながら、美幸がもういちど合図を送る。
美沙はその場で膝立ちになり、やおら茉莉のスカートを捲り上げると、あらわになったショーツに手を伸ばして、そのまま膝のあたりまで引きおろした。
思わず茉莉は振り返りかけたが、美幸の手で阻まれてしまう。
「気にしなくていいのよ。美沙お姉ちゃんは茉莉ちゃんがママのおっぱいを吸いながらおしっこをしちゃっても大丈夫なようにしてくれているだけなんだから」
茉莉の後頭部を掌で包み込むようにして、美幸はわざと優しく言い聞かせた。
「で、でも……」
強引に美幸の乳首を口にふくまされたせいでくぐもった声になりながらも、茉莉は喘ぎ声とも悲鳴ともつかぬ声を漏らした。
その間に美沙は、膝まで引きおろした茉莉のショーツの内側に、バッグから取り出した布おむつを重ね入れて再び引き上げた。真衣に穿かせていたトレーニングパンツとは違って普通のショーツだからあまりたくさんのおむつを重ね入れることはできないものの、久々に登校した日に階段の踊り場で真衣に対してそうしたのと同じ措置だ。
「ち、ちょっと、美沙、何をしてるのよ!?」
思ってもみなかった仕打ちに、茉莉はくぐもった声で喚いた。
それを美幸が少しきつい調子でたしなめる。
「なんて言葉遣いをするの、茉莉ちゃんたら。『美沙』じゃなくて『美沙お姉ちゃん』でしょ? それに、美沙お姉ちゃんは、茉莉ちゃんがおしっこをしちゃっても床を汚さないようにしてくれているんじゃないの。それを『何してるのよ』なんて言っちゃ駄目じゃない」
「な、なに馬鹿なこと言ってるのよ。どうして私が美沙のことを『美沙お姉ちゃん』なんて呼ばなきゃいけないのよ。だいいち、私がおしっこをしちゃうだなんて……」
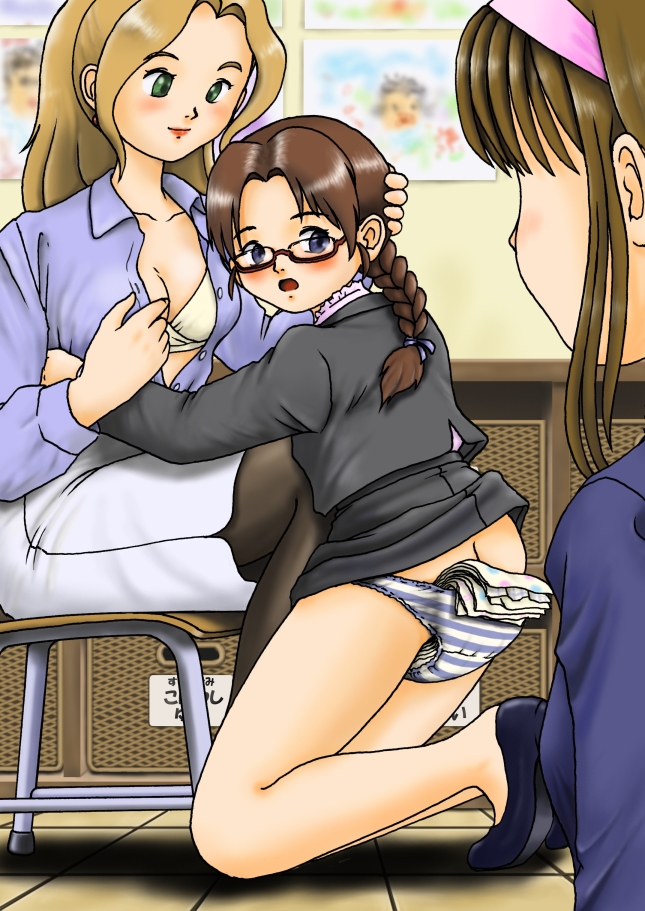
茉莉は幾らか激昂した様子で喚いた。だが、美幸の手で後頭部を押さえられ乳首を口にふくんだままな上、そろりと手を伸ばした美沙にショーツと布おむつの上から恥ずかしい部分をいじくられたせいで、言葉が最後まで続かない。
「だって、茉莉ちゃんは真衣ちゃんのことが羨ましてたまらないんでしょう? おしっこをしたくなったらいつでもしちゃって、ママや美沙お姉ちゃんにおむつを取り替えてもらっている真衣ちゃんのことが羨ましくて仕方ないんでしょう?」
美幸は茉莉の耳元で甘く囁きかけた。
「よ、よしてよ、冗談は。あ……」
再び抗弁しかけた茉莉だが、美沙の巧みな指運びで秘部を責めたてられ、やはり途中で言葉を飲み込んでしまう。
「いつまでも強情を張ってないで、正直になった方がいいわよ。このままじゃ辛くなるばかりなんじゃないかしら? ――自分でもわかっている筈よ。真衣ちゃんの秘密を知った時、茉莉ちゃんは『ずっと妹が欲しかった』と言って私たちの仲間になったんだったわよね。あの時は私もそれで納得して茉莉ちゃんを迎え入れたわ。でも、その後の茉莉ちゃんの様子を見ていると、ちょっと違うんじゃないかなと思い始めるようになったの」
「……」
「茉莉ちゃん、本当は妹が欲しいんじゃなくて、自分が妹になりたいんじゃないの? 『妹がいれば両親の関心が二人に分かれて自分はもっと伸び伸び育つことができたと思う』って茉莉ちゃんは言ったけど、本当は『頼りになるお姉ちゃんがいてくれれば、私は両親の目なんか気にせずに好きなようにできた筈』って思っているんじゃないの? ううん、好きなようにできたっていっても、茉莉ちゃんが我儘でそんなことを考えていたとは私は思わない。もっと素直に、まわりのお友達と好きなだけ遊べたらいいなっていう気持ちになって、それがちょっと高じちゃっただけだと思う。それに、お友達と遊ぶにしても、みんなの前に立つんじゃなくて誰からも庇ってもらえる、そんな存在になりたいとも思っていたでしょう?」
「……」
「でも、いいのよ。小さい頃からずっと素直ないい子で、みんなの期待を一身に集めて、学校へ入ってからはずっとクラス委員長を通している茉莉ちゃん。いつも重い荷物を背負って、辛かったでしょう? いつ目に見えない重圧に押しつぶされてもおかしくないほど辛かったんでしょう? そんな茉莉ちゃんがもっと本当の自分でいたいと願っても、ちっとも変じゃないわ。小さい頃に戻って、仲良しのお友達ときゃっきゃっ言って走り回りたくなったとしても、それは当たり前のことだわ。みんなの前に立つばかりじゃなく、みんなの後ろからよちよちついていって、みんなから庇ってもらいたくなっても、全然おかしくなんてない。――本当は、そうなんでしょう? 自分の気持ちをどうやって言葉にしていいのか自分でもわからなく、ついつい『妹が欲しかった』って言っちゃったんだよね?」
「……」
「真衣ちゃんのお姉さんになりたかったんじゃなくて、真衣ちゃんと同じになりたかったのよね?」
最後に美幸は穏やかな声ながら有無を言わさぬ調子で決めつけた。
「そんな……真衣ちゃんと同じになりたかっただなんて……ずっとクラス委員長の私が、高校生のくせにおむつ離れできない真衣ちゃんと同じになりたいだなんて……」
茉莉はもう喚き立てることもなく、美幸の乳首を咥えたまま、呟くようにぽつりと言った。
「そんなに我を張らずに自分の気持ちに正直になっちゃった方が楽なのに。いいわ、じゃ、茉莉ちゃんに選ばせてあげる。――美沙、もういいわよ。あとは茉莉ちゃん自身の問題だから、どうするのか、本人に選んでもらいましょう」
美幸は穏やかな声で言い、それまで茉莉の頭を押さえつけていた手を離すと、目の前で膝立ちになっている美沙に向かって指示してから、改めて茉莉の耳元に囁きかけた。
「おしっこが溜まっているところに、このまま美沙お姉ちゃんに恥ずかしい部分をいじられていたら、間違いなくしくじっていたでしょうね。でも、ママが美沙お姉ちゃんに言いつけて、茉莉ちゃんの大事なところをいじるのはやめさせてあげたわよ。それに、無理矢理おっぱいを吸わせるのもやめてあげた。だから、あとは茉莉ちゃん本人の問題よ。茉莉ちゃんはどうしたい? ママのおっぱいから口を離してトイレへ行くこともできるわよ。そしたら、また幼稚舎の先生に戻ることもできるし、真衣ちゃんの二番目のお姉ちゃんでいることもできる。だけど、このままママのおっぱいを吸いながら、おむつとパンツをおしっこでびしょびしょにしちゃってもいいのよ。その時は、真衣ちゃんと同じ、ママの娘で美沙お姉ちゃんの可愛い妹にしてあげる。――さ、どっちがいい?」
朝早くからトイレへ行きそびれた上、美沙の指で秘部をいじられたせいで、おしっこは今にも溢れそうになっている。迷っていられる時間はもう殆ど無い。
茉莉は一度だけすっと大きく息を吸い込んで、美幸の体にしがみついた。
|