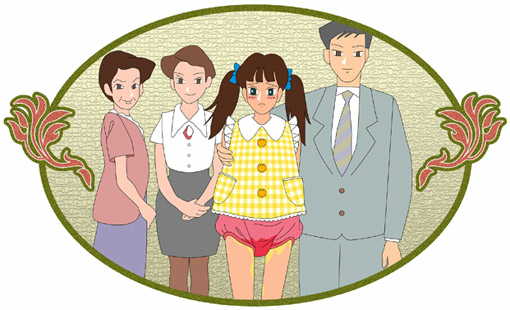
|
ある町に、明治の代から続く高名なお医者様の家系がございます。 お名前を佐竹と申します。もともとはお屋敷を診療所として近在の方の診察や診療をなさっておいででしたものを、昭和の世になると、広大な敷地に立派な建物を建てられて、今に続く『佐竹総合病院』の経営を始められたのでございます。 現在、佐竹総合病院の理事長は、佐竹美津子様がお務めになっておられます。美津子様は、佐竹総合病院の若き院長先生であられる佐竹雄大様のもとへ、隣の市にある、こちらもやはり大きな私立総合病院の理事長のお家から嫁いでこられた方でございます。雄大様と美津子様は、それは傍目にも仲睦まじくいらして、お互いにいたわり合いながら病院の運営にあたっておられました。そのかいもあったのでございましょう、優秀なお医者様も集まってくださいました。その上、お二人の間に男のお子様も授かりまして、康夫様と名づけられましたそのお子様は、重いご病気にかかられることもなく、すくすくとお育ちになったのでございます。佐竹総合病院の未来は、誰の目にも安泰でございました。 それなのに、どこに魔事が待っているかは本当にわかったものではございません。あれは、康夫様が中学校にあがられた年でございましたでしょうか。ある会議に出席されるために雄大様は飛行機にお乗りになりました。そうしたところ、ご不幸なことに、その飛行機が事故を起こしてしまったのでございます。ええ、ええ、当時は新聞やテレビでも大きく報道された、あの事故でございます。 美津子様のお嘆きは、それはもう、大変なものでございました。周りから見ておりましても、こちらの胸が引き裂かれるかと思えてしまうくらいの、お慰めのしようもないような嘆きようでございました。 ところが、芯のお強い方だったのですね、美津子様は。あるいは、まだ中学生になったばかりの康夫様を守っていかなければいけないという母親としての思いのためなのでございましょうか、お弔いの次の日には、涙の跡もお見せにならずに理事会を招集し、事務局長とお会いになり、職員たちと話し合い、院長先生亡き後の病院経営の先頭に立たれたのでございます。その後、美津子様が涙をおこぼしになられる姿を見た者は一人もいなかったと聞いております。 月日が流れて、康夫様は雄大様と同じ東京の医大に進まれました。そうして去年の春、お医者様の免許もいただいて、研修医として佐竹総合病院に戻っておいでになられたのです。美津子様のお喜びようといいましたら、それはもう、たいそうなものでございました。今は主のいない院長の椅子に康夫様が座られるのも、すぐのことだともおっしゃられて。そうそう、新しい院長先生になられる康夫様におふさわしい女性も既に決めておられるようなことも耳にしたことがございます。 ですのに、世の中というものは、そうそうお思い通りにいくようにはできていないようでございますね。 康夫様が病院に戻ってこられる少し前に、佐竹総合病院は新しい看護婦を迎えておりました。たしか、山口享子、岡谷舞江、それに藤井紀子の三人だったと記憶しています。その内の岡谷舞江というのが、他の二人と比べて華奢と申しますか、どこか線の細いような感じを受ける看護婦でございました。職員たちが心配したのも無理のない話でございましたわ。なにせ、重症の患者さんをきちんと看護できるものかどうか、正直に申しますと、かなり不安がございましたもの。ところが、いざ業務に就いてみると、岡谷看護婦の働きはなかなかどうして立派なものでございました。いつも笑顔で、どんなことでもてきぱきこなして。看護婦というお仕事が楽しくてしかたない――そんな印象さえ受けましたわね、ええ。いつのまにか、岡谷さんは患者さんたちの間でもマスコットにような存在になりまして、お医者様たちも彼女には一目置くようになったのでございます。それは、康夫様も例外ではございませんでした。 お小さい時からお父様の跡を継ぐことを運命づけられて、お父様が亡くなられた後は殊更、美津子様から追いたてられるようにしてお勉強ばかりの生活でございましたわ、康夫様は。大学に進まれてからも、厳しいスケジュールの講義や実習に精一杯でございましたでしょうね。そうしてやっとのことで研修医として病院に戻ってきた時、目にとまったのが岡谷さんでございます。……こういうことを申しあげると美津子様に失礼とは存じますが、雄大様に先立たれてからの美津子様は、涙をお流しになることもなくなったと同時に、笑顔もお忘れになってしまわれたような方でございました。病院の行く末や幼い康夫様のことを考えると、ついついそうしてしまうのかもしれません。 けれど、そういう事情があったとしても、康夫様にとって、笑ってくださらないお母上というのは、どうにもうとましいと申しますか、誤解を承知で申しあげますと、恐ろしくもある存在だったのではないかと思ってしまいます。ですから、病院に戻ってきて目にした岡谷看護婦という人にひどく心を惹かれたのも、ごく自然な成り行きだったのでございましょう。ご自分のお母上とはまるで異質の(そんな女性がいるということさえ想像もなさったことのないような)女性だったのですから。 初めて出会ってから一ケ月ほどが経って、康夫様は岡谷さんにご自分のお気持ちを伝えられました。岡谷さんの方は少なからず驚きながらも(それはそうでございましょうね、なにせ、将来の院長先生からの告白でございますもの)、結局は、康夫様のお気持ちを受け入れたました。その日から、康夫様と岡谷さんの交際が始まったのでございます。 そうして、それから一年後、お二人は美津子様に、結婚を認めてほしいとおっしゃったのです。 もちろん、美津子様は反対されました。美津子様にしてみれば、康夫様に裏切られたような思いがなさったことでしょうね。これまで手塩にかけてお育てになった康夫様が、美津子様には一言の相談もなさらずに岡谷さんと交際を始めてしまわれて、あまつさえ、お二人だけで結婚の約束まで交わしていらしたのですから。それでは、美津子様がひそかに決めておかれた方とご一緒になった康夫様に佐竹総合病院をますます盛りあげていただくという長年の夢が、それこそ文字通りの夢と消えてしまいます。 美津子様は、お二人のお言葉に、頑として反対なさいました。 そうするうちに、お二人は、岡谷さんのお腹に康夫様のお子様が宿っていると美津子様に打ち明けられたのでございます。そうなると、事情は一変いたしました。同じ女性として、しかも幼かった康夫様を女手一つで育て上げてこられた経験のある身として、美津子様は岡谷さんに堕胎を勧めることはできなかったのでございます。岡谷さんのお腹にご自分の血を引く命が宿っているとお知りになった時、美津子様は決心を固められたのでございましょうね。 結局、美津子様がお折れになるような形で、お二人の結婚が許されることになったのでございます。 ただ、華美な披露宴を開くことだけは、美津子様はお許しになられませんでした。それは、美津子様の最後の意地のようなものだったのかもしれませんわね。 美津子様のお許しをいただいてすぐに、ごくごく内輪の方々だけをお招きして、お二人は町の教会で結婚式をおあげになりました。披露宴も無い、本当に質素なお式ではございましたけれど、お二人は心の底からお幸せそうでございました。 役所に婚姻届をお出しになってから康夫様と岡谷さん――あら、若奥様と呼ばせていただくのが本当ですわね――がお屋敷に戻ってみると、先に帰ってらした奥様がダイニングルームでお待ちでした。そうしてお二人は、ダイニングルームの大きなテーブルの上にある可愛らしいデコレーションケーキに気づかれたのでございます。ケーキの上には、砂糖菓子でできているのでしょう、華やかな衣装を身に着けた男女のお人形が飾ってありました。よく見てみると、そのお人形は、花嫁と花婿さんでございました。 渋々ながらも結婚を認めた私の、それがせめてものお祝いよ――美津子様がおっしゃるその言葉を耳にされた途端、若奥様の両目から、大粒の涙がぼろぼろとこぼれ出したのでございます。康夫様も、お鼻の先を赤くしておいでのように見えました。 お二人はどちらからともなくお顔を見合わせて、何か覚悟を決めたように小さく頷かれました。そして康夫様が、少しばかり震えるようなお声でおっしゃったのでございます――ごめんよ、母さん。あれは嘘だったんだ。 美津子様は、康夫様が何をおっしゃっているのかおわかりにならないご様子で、きょとんとしてしまわれました。 そこへ、若奥様もおっしゃったのでございます――ごめんなさい、お義母様。私が妊娠したというのは嘘だったんです。ああ言えば私たちの結婚を認めてくださると思って、お芝居を……。 お芝居?――美津子様は体をがたがたと震わせて、信じられないように訊き返されました。 そうなんだ、母さん。こうでもしなきゃ結婚を認めてもらえないと思って、僕が言い出したんだ――康夫様は、若奥様の姿を美津子様の目からご自分のお背中で隠すようにされておっしゃいました。 美津子様のお顔からは、あまりのお怒りのためでしょう、いっさいの表情が消えておしまいでございました。 ここから、佐竹病院の物語が始まるのでございます。 「……許しません。私は、あなたたちの結婚を絶対に認めませんよ」 それが習性になっているのだろう、胸の中の怒りを感じさせない、むしろ穏やかな声で美津子は言った。 もう婚姻届も出したのだからと気を緩めていた康夫と舞江は、はっとしたように顔を見合わせた。 「けど、もう僕たちは法律的にも夫婦なんだし……」 あらためて美津子の方に向き直った康夫は、いくらかおどおどした口調で言葉を返した。 「法律ですって? いいかげんになさい、康夫。ここは、ずっと昔から続いた佐竹の屋敷です。そして、あなたのお父様が受け継ぎ、お父様が亡くなってからは私が精一杯守ってきた佐竹の屋敷です。この屋敷の中にいるかぎりは、法律など関係ありません」 能面のように表情のない顔のまま美津子は、自分よりも背の高い康夫を圧倒するようにきっぱりと、しかし怖いくらいに静かな声で断言した。 「じゃ、いいよ。母さんが認めてくれないなら仕方ない、この家を出るよ。それならいいんだろう?」 追い詰められたみたいな表情で、康夫は少しばかり不貞腐れたように言い返した。 「開き直るつもりですか? それならそれでかまいません。だけど、生活はどうするのです? ――研修期間も終えられずに佐竹総合病院を逃げ出した見習い医師と新米看護婦を雇ってくださる親切な病院がそうそうあるとも思えませんけれどね」 言い聞かせるように美津子が応じた。 「そんなこと……医者や看護婦にこだわらなきゃ、仕事はいくらだって……」 この家を出るならどこの病院にも勤められなくしますよ。それでもよろしいのね? 言外にそう言う美津子に、抵抗する気力もそがれそうになりながら、それでも康夫はかろうじて強がってみせた。 けれど、そんな康夫の言葉が終わるか終わらないかのうちに、舞江の弱々しい声が聞こえてきた。 「あの……私、お義母様のおっしゃるようにいたします。お義母様が認めてくださるまでは、夫婦めいた行動も控えます。差し出がましいことはいたしません。ですから、このお家に置いていただけませんか?」 舞江は、震える声で懇願した。 「舞江……?」 戸惑ったように、康夫は舞江の顔に目をやった。 「私の父も母も、私が幼い時に病気で亡くなりました。その後、私は遠縁の親類に引き取られて高校も卒業させてもらいました。――親類は大学への進学も勧めてくれたんですけど、父に続いて母が亡くなった時、幼い私は医療に携わる決心をしていたんです。でも、いくらなんでも、たくさんのお金がかかる医大へ行くとは言い出せませんでした。だから、せめて看護婦にと思って看護学校へ……」 舞江は不意に言葉を詰まらせた。康夫は気遣わしげに舞江の横顔に目をやった。 舞江は小さく頷くと、途切れがちに言葉を続けた。 「……そうして、やっと念願がかなったんです。看護婦として佐竹総合病院に勤めることができて、しかも、思ってもみなかったことに、佐竹という名門のお医者様の家族になれて……それなのに、今になってここを追い出されて、しかも看護婦としてお勤めすることもできなくなってしまうんじゃ、私……」 「あらまあ、妊娠のお芝居の後はお涙頂戴ですか? いいかげん懲りない人ですわね、舞江さんも」 少しだけ間を置いて、美津子は冷たく言い放った。 「母さん、いくらなんでも、そんな言い方は……」 思わず康夫は、声を荒げた。 「でも、そんな事情を知ってしまったからには、舞江さんにこの家から出て行ってもらうわけにはいかなくなりましたわね。何かの間違いで、私が追い出したとでもいうような噂をたてられでもしたら大変ですもの。そんなことになったら、病院の評判にもかかわります」 康夫の言葉など知らぬげに、美津子はまるで独り言のような口調で舞江に言った。 「それじゃ……」 舞江の顔が微かに輝いた。 「仕方ありません。舞江さんの気が済むまで、この家にいればいいでしょう」 美津子は溜め息をつくような仕草をしてみせた。それから、ふと思い出したみたいに言葉を続ける。 「但し、ルールは守っていただきますよ」 「ルール……?」 二人は要領を得ない顔で訊き返した。 「この家で暮らしていただくには、それなりのルールは必要ですからね。――たいして難しいことではありませんから、そんなに心配することはありません」 美津子は康夫と舞江の顔を交互に見比べた。そうして、静かに人差指を立てて言った。 「まず、康夫と舞江さんの寝室は別々にすること。私は、あんな姑息な嘘で結婚を認めさせようとしたあなたたちのことを認めていません。法律がどうあれ、この家で生活するからにはあなたたちは他人どうしです。――夫婦でもない殿方と妙齢の女性が一つ所で眠るなんて、とても許せることではありませんわよね?」 その言葉に咄嗟に反論しようとする康夫を、舞江がすがるようにしてなだめた。 「それから、舞江さんが自分の意志でこの家を出たいと申し出た場合には、もう私は引き止めません。せっかく私がこのお家に住まわせてあげようと言っているのに、私のその親切心に後ろ足で砂をかけるような行為ですからね、それは。もちろん、その時には正式に離婚届を提出していただきます。婚姻届さえ出していなければわざわざ離婚届を出す必要もないのに、本当に面倒なことですわね」 美津子は中指を立てて続けた。 「たったこれだけです。これだけのことを守っていただけるなら、舞江さんを佐竹家の大事なお客様として歓迎いたします。よろしくて?」 舞江には、力なく頷くことしかできなかった。 同居が始まった最初の日から、美津子の言ったとおり、舞江は康夫の妻として扱われることは全くなかった。 「あら。どうかしたの、舞江さん?」 同居を始めたその日の夕方、エプロンを身に着けてキッチンに入った舞江に向かって、先に流し台の前で包丁を動かしていた美津子は意外そうな表情を浮かべて声をかけた。 「え、あの……お夕食の用意をしようと思って来たんですけど……」 おどおどした口調で舞江が応えた。 「いやだわ、舞江さんたら。大事なお客様に夕食の用意をさせるだなんて、そんな不作法なことはできませんよ。用意ができたらお呼びするから、居間でテレビでもご覧になってらっしゃいな」 舞江の返事を聞いた美津子は、キャベツを刻む包丁を止めて気遣うように言った。 「でも、お義母様……」 「言った筈ですよ、私はあなたの義母ではありません。これまで通り、奥様と呼んでいただきます」 「……」 「もちろん、お掃除もお洗濯も、これまでと同様、私がいたします。二人だったのが三人分に増えたくらいなら、さして仕事が増えるわけでもありませんからね」 「だけど……」 「さ、お客様は台所から出て行ってくださいましな。お口に合うかどうかわかりませんけれど、夕食の用意は私がいたしますから」 そう言うと、美津子は再び包丁を動かし始めた。美津子の背中は、これ以上の会話を頑なに拒んでいた。 舞江は無言で頭を下げると、力ない足取りで台所を出て行った。 どことなく気まずい雰囲気の夕食が終わって、その後片づけをする時も、舞江は何もせずに済んだ。いや、何もさせてもらえなかったと言った方が正確かもしれない。 そうして、食後のお茶。 風呂場の掃除と湯張り。 ガスの元栓の確認と戸締まり。 何をするにしても、舞江の入り込む余地はなかった。そう、舞江は確かに『大事なお客様』としての扱いを受けていた。 けれどそれは、何もできないままにただ時間が流れるのをぼんやりと眺めるだけの生活は、舞江にとってはひどい苦痛だった。イヤミを言われてもいい、あからさまに罵られてもいい、康夫の世話をやくことができないなら、せめて自分の身の周りのことだけでもいいから、とにかく自分の手で何かをしたかった。さもないと、この家に自分の居場所が少しもないことを痛いほどに思い知らされてしまうのだから。 それに加えて、本来なら祝福されてもいい二人の最初の夜だというのに、就寝の時間になれば二人の間が否応なく別々の寝室に割かれてしまうのも、殊更に辛かった。 あのまま嘘をつき通すべきだったのかしら。でも……。 康夫さんと一緒にこのお屋敷を出た方がよかったのかもしれない。だけど……。 照明を消すと真っ暗になってしまう寝室で、堂々巡りの思いにとらわれてしまいがちになるり舞江は独り、悶々としてなかなか寝つけずにいた。 それでも日が変わる頃になって急に睡魔に襲われ、深い暗闇に引きずれこまれるように意識を失って、翌朝、舞江が目を覚ました時には、レースのカーテンを通して太陽の光が部屋中に差し込んでいた。 降り注ぐ眩しい光を避けようとして瞼の上に掌をもっていった時、すぐ傍らに人の気配があった。 「あ、お義母様。いえ、あの、奥様……」 舞江は、はっとしたように慌てて上半身を起こした。 「お目覚めですか?」 舞江の側にきちんと正座した美津子は、静かに声をかけた。 「あの、すみません。私ったら、こんな時間まで……」 枕元の目覚まし時計をちらと見て、舞江は小声で詫びた。 「気にすることはありませんわ。何度も言うようですけれど、舞江さんは大事なお客様ですからね」 美津子は静かな声で応じた。 舞江には、それがひどく皮肉めいて聞こえてしまう。 「それで、康夫さんは?」 急に思い出して、舞江は慌てて尋ねた。 「康夫はとっくに朝食を済ませて、空港に向かいましたよ。学会へは予定通り出席しなければいけませんからね」 「……」 舞江はぎゅっと唇を噛みしめた。 本当なら、今ごろは舞江は康夫と一緒の飛行機に乗っている筈だった。北海道で開かれる学会に同行して、康夫の用事が終わった後は一週間ほど観光旅行を楽しむ手筈になっていたのだ。それが、二人のささやかな新婚旅行になる筈だった。なのに、嘘を白状してしまったばかりに……。 「康夫は出かける前に、あなたのことを心配していました。舞江はいつまでも起きてこないけど、体調がすぐれないのかな――と。ですから私が様子をみにきたのです。でも、大丈夫のようですわね?」 「あ、はい……。体の方はなんともありません。ただ、どうしても目が覚めなかっただけで、あの、でも、普段はこんなことは……」 言い訳じみた口調で、舞江は再び口ごもってしまう。 「それじゃ、お布団をいただきましょうか? こんなに好いお天気ですもの、お布団を干さないと勿体ないですから」 「は、はい。すぐに……」 舞江は掛布団に手をかけた。 が、不意に何かに気づいたみたいに瞳をきょときょとさせると、なんとなくうろたえたような顔つきになって、その手を止めてしまう。 「どうしました?」 美津子は訝しげに尋ねた。 「あの……」 頬を微かに赤くして言い淀む舞江。 「何か不都合でも?」 「あの、あの……えと、私、これから着替えますから、それまで待っていただけないでしょうか?」 「ええ、それは結構ですよ」 「あの、ですから、少しの間、お部屋から出ていただいて……」 舞江は、心ここにあらずといった風情で顔を伏せたまま言った。 「どうしてですか? いいじゃありませんか、着替えを待つ間くらい、ここにいても。同じ女性どうしなんですし」 美津子は、舞江の真意を計りかねるように問い返した。 「だって、だって……」 駄々をこねる幼児のように、舞江は激しく首を横に振った。 「何かあったんですね?」 美津子はきらりと目を光らせると、言うが早いか、さっと両手を伸ばして舞江の掛布団を剥ぎ取った。 「いやぁ、だめだったらー!」 思わず甲高い叫び声をあげて、舞江は布団の端をぎゅっとつかもうとした。 しかし、その時にはもう、舞江の下半身を隠していた掛布団は殆ど剥ぎ取られた後だった。 鮮やかなレモン色をしたパジャマのズボンの股間からお尻にかけてが、大きなシミになっていた。そうして、舞江のお尻が載っている辺りを中心にして、敷布団のシーツもぐっしょり濡れている様子が美津子の目に飛びこんでくる。 「あ……」 舞江は声にならない叫びをあげると、美津子の目から逃げ出すみたいに顔を伏せた。その視線の先に、恥ずかしいシミが鮮やかに広がっていた。呆けたように大きく見開いた目を自分の下腹部に向けたまま、舞江は唇を震わせた。 そんな舞江とは対照的に、美津子はいたって平静な物腰で舞江の股間を覗きこんだ。 「だめぇ、見ちゃ駄目だってばー!」 金切り声で叫んだ舞江は、一度は剥ぎ取られた掛布団を再び引き寄せようとして細い腕を無闇に動かした。 その腕を払いのけたのは、五十歳を超えているとは思えないくらいに若々しい肌をした美津子の手だった。 「お待ちなさい」 威厳に充ちた静かな声で、美津子はぴしゃりと言った。 「これは、どういうことですか?」 「……わかりません。どうしてこんなことになったのか、私にもわからないんです……」 とうとう掛布団を全て剥ぎ取られてしまい、パジャマとシーツについた鮮やかなシミを美津子の目にさらした姿で、舞江は掌を唇に押し当てた。 「わかりませんではありませんでしょう? 色といい匂いといい、お小水にちがいないのですよ? それとも、何かの手違いでお茶をこぼしたとでも言い訳するおつもり?」 「……」 「黙っていてもわかりませんわね……」 わざとのように大きな溜め息をつくと、美津子は右手を敷布団の上に伸ばして、黄ばんだシーツの感触を確かめるように二度三度と掌を滑らせた。 「……もうすっかり冷たくなっているようです。たった今のことではないということですね?」 「……」 「康夫は知っているのですか? ――舞江さんに夜尿癖があることを」 美津子は、ねっとりした声で訊いた。 「そんな、夜尿癖だなんて……」 かっと顔を熱くして、舞江は美津子の言葉を弱々しく否定した。 「そうは言っても、現にこうして、舞江さんのお小水でお布団とパジャマが濡れているのですよ」 美津子は敷布団の上を滑らせた指先にちらと目をやって、念を押すみたいに言った。 「それは……そうです。でも、物心ついてからは一度も……」 「これまで、一度も粗相したことはないとおっしゃるのですね?」 「はい……」 「わかりました。今日のところはそういうことにしておきましょう。――そのままだと体に良くありませんから、早く着替えておしまいなさい。その間に私がお布団を干しておきましょう」 「え、お布団……」 「もちろんですとも。もともと干すつもりでしたし、それでなくても、こんなことになったのですから、少しでも早く乾かさないといけませんからね。裏庭の物干し場ではお日様が当たる時間が少し足りないかもしれませんから、南向きのこのお部屋のバルコニーがよろしいわね」 美津子は、さも当然のことのように平然とした顔つきで言った。 「あ、あの、お義母様――奥様。お布団を干すのは仕方ないかもしれませんけど、ここのバルコニーに干すのだけは……」 思わず、舞江は首を振ってしまう。 舞江たちが暮らしている屋敷は、病院と同じ敷地内に建っている。敷地の南側が五階建ての病院になっていて、そこから少し離れた北側が、二階建ての洋風の屋敷になっているのだ。医院と屋敷との間は生け垣で隔てられているが、南側の二階に位置する舞江の寝室のバルコニーは、病院から丸見えといってもいいような状態だった。そんな所に、大きなシミのついた布団を干されたりしたら……。 「仕方ありませんでしょう? お小水で濡れたお布団には、お日様の光がなによりですから。そうなると、南向きのこのお部屋のバルコニーが一番ですからね」 舞江の気持ちなど知らぬように、美津子はこともなげに言った。 「でも……」 「それに、今日だけのことですわ。お布団は毎日干すにしても、恥ずかしいシミになっているのは今日だけですもの。そうじゃありませんこと?」 「……」 そう言われてしまえば、返す言葉はなかった。 しかし、シミになった布団を寝室のバルコニーに干すのは、その日だけではなかった。翌日も、その翌日も、幼い子供のように恥ずかしい粗相を繰り返しては布団とパジャマを濡らす日は終わらなかった。 「どういうことでしょうね、舞江さん。やはり、あなたの夜尿は癖になっているんじゃなくて?」 三日も続いて舞江が汚した布団を前に、美津子は呆れたように言った。 「信じてください。本当なんです、本当に今まで、こんなこと……」 布団の上で肩を落とした舞江が悲痛な声で訴えた。 「それじゃ、この屋敷での生活が負担になって急に失敗するようになったとでもおっしゃるの? それとも、私との生活が重荷だとでも?」 背筋を伸ばして床に正座したまま、美津子は舞江の顔を見おろして言った。 「そ、そんな……」 「ま、よろしいでしょう。――谷口先生に連絡を入れておきますから、夕方にでも行って診ていただきなさい」 「あの……泌尿器科の谷口先生ですか?」 「そうです。佐竹医院で谷口というお医者様は、泌尿器科の谷口先生しかいらっしゃいません」 「それは……あの、診察を受けるのはもう少し待っていただけないでしょうか。もう少し様子をみてから……」 舞江は体を小さくして言った。つい一ケ月前までは自分が勤務していた病院だ。そこへ夜尿の診察を受けに行く決心が、美津子に言われたからといってすぐにできる筈もない。 「三日も続いたのですよ。様子をみるのはもう充分です」 美津子は舞江の言葉を言下に撥ねつけた。 「……せめて、他の病院へ行かせていただけないでしょうか。佐竹総合病院では、あまりに……」 「谷口先生では信頼できないとでもおっしゃるのですか?」 「いえ、そんなこと……ただ、顔見知りの先生に診ていただくのはあまりにも恥ずかしいと……」 「舞江さんも、つい最近までは医療の現場に立ってらした人でしょう? それも、小さな頃からの決心を崩さずに。そんなあなたが、診察を受けるのが恥ずかしいなどと言って駄々をこねるというのもいかがなものでしょうね? それに、少しでも早くその恥ずかしい癖を治しておかないと、康夫にも知られてしまいますよ。もうあと一週間ほどで学会から帰ってくるのですからね」 「……」 「夕方、外来の患者さんがいなくなった後、谷口先生に診ていただきなさい。よろしいですね?」 「……はい」 舞江は力なくうなだれた。 「けっこうです。それじゃ、体が冷えるといけないから手早く着替えておしまいなさい。お布団は私が干しておきましょう。――昨日や一昨日と同じように、そのバルコニーに」 舞江は布団の上に立ち上がって、のろのろと両手を動かし始めた。 「ね、舞江さん。あなた、いつもそんな下着を身に着けているの?」 ぐっしょり濡れて内腿に気味わるく貼り付くパジャマのズボンを舞江がずりおろすと、美津子が呆れたように言った。 「……?」 美津子が何を言おうとしているのかわからずに、舞江は、びしょびしょになった下着に掛けた手を止めた。舞江が穿いているのは、近所のスーパーで買った、どこにもあるようなスキャンティだ。美津子が訝しむ理由がわからない。 「なにもない時なら、そりゃ、それでもかまいません。どんな下着を身に着けようと、それは好みの問題ですから。でも、今のあなたは恥ずかしい失敗を繰り返している体なのですよ。そんな小さな下着だけではお尻も冷えて、治る病気も治らないんじゃありませんこと?」 「え、でも……」 やっとのことで、舞江も美津子が言っていることの意味がわかった。わかったけれど、かといって、舞江のタンスに入っているのは、どれも同じような下着ばかりだった。 「念のためにと思って、昨日のうちに私が買っておきました。これをお穿きなさい」 舞江の戸惑いを察したように、美津子は、背中の方に置いていた紙袋を体の前に動かした。 「……?」 スキャンティに手を掛けたまま、舞江は目だけを動かして紙袋を覗きこもうとした。 「これなら、少しはマシだと思いますよ」 舞江の視線を意識してか、美津子はゆっくりした動きで紙袋の中から何かをつかみ上げた。 美津子が紙袋から取り出して床の上に広げてみせたのは、コットン生地の下着だった。白いコットンにアニメのキャラクターがプリントしてあって、またがみの深い、全体にぶかぶかした感じのするその下着は、小学生の女の子が穿きそうな子供用のパンツだった。 舞江の頬がかっと赤く染まった。 「それに、これ。パンツの上にこれを重ねて穿けば、保温はまず大丈夫だと思いますよ」 美津子は再び紙袋に右手を差し入れた。 コットンのパンツの横に並んだのは、ゆったりした感じの下着だった。ベビーピンクのコットンで編みこんだブルマーのようなデザインで、お尻の方には飾りレースのフリルがあしらってあり、太腿の部分には少し太いゴムが縫い込んである。それは、幼稚園児や、せいぜいが小学生くらいの幼女がショーツの上に重ね穿きするオーバーパンツ(上穿きパンツ)にちがいなかった。 「これを、私が……?」 羞恥のあまり顔から火の出る思いでやっとのこと絞り出した舞江の声は今にも泣き出しそうだった。 「最近の子供は発育がよろしいのね。子供用だというのに、舞江さんに丁度いいサイズの下着が、こうしてすぐにみつかるくらいですもの」 美津子は感心するように言った。 待合室から人影がみえなくなった頃、分厚いドアが開いて、若い看護婦が姿を現した。 「どうぞ、岡谷さん」 山口享子と書かれた名札を白衣の胸元につけたその看護婦は、ドアのすぐ前で舞江を呼んだ。そして、じきに、しまったというような顔になって言い直す。 「すみません、今は岡谷さんじゃなかったんですよね。――どうぞ、若奥様。診察室にお入りください」 「いいわよ、舞江で。同期なんだし……」 若奥様と呼ばれて却っておどおどしてしまい、思い足取りで待合室のソファを離れながら、舞江は消え入りそうな声で言った。 「そうはいきませんよ。そりゃ、この病院に勤めた時には同期の看護婦だったけど、今は佐竹総合病院の次期院長夫人とヒラの看護婦の間柄ですもの。私も、立場はわきまえているつもりです」 舞江のためにドアを大きく開けて、享子が恭しく応じた。その声がひどく嫌味めいて聞こえたのは、舞江の気のせいだろうか。 「お待ちしておりました、若奥様。どうぞ、こちらへ」 享子に背中を押されるようにして診察室に足を踏み入れた舞江を待っていたのは、カルテから顔を上げてじっとドアの方をみつめていた谷口博美だった。 博美は三十歳を超えたばかりのまだ若い女医だが、学会発表を既に何度もこなし、出身大学からも研究室に戻ってこないかという申し出を幾度となく受けている新進気鋭の優秀な医師だ。彼女の父親も泌尿器科が専門で、何年か前まではこの佐竹総合病院の副院長を務めていたらしいことを、舞江も耳にしたことがある。 「よろしくお願いします、谷口先生」 舞江は体の前で両手の指を絡ませ、博美に向かって頭を下げた。 「承知しました。若奥様もご存じのように本当なら問診から始めるのですが、おおよそのことは大奥様から連絡をいただいていますので、早速ですけれど検診ということにしましょうか。――スカートと下着を脱いで、診察台に上がってください」 博美は手に持ったボールペンを指先で弄びながら言った。 「どうぞ、若奥様」 博美の言葉が聞こえるのと同時に、享子が舞江の側に脱衣篭を持ってきた。 舞江は覚悟したように深い溜め息をつくと、濃い紺色の巻きスカートに指をかけた。左手でウエストのあたりを押さえ、右手の親指と人差指でスナップを外してファスナーを引きおろすと、スカートがあっという間に一枚の布に変わる。 舞江は、一枚の大きな布になったスカートを脱衣篭の中にそっと置いた。  「わー、可愛いい下着ですこと。若奥様、とてもお似合いですよ」
「わー、可愛いい下着ですこと。若奥様、とてもお似合いですよ」スカートを脱いでしまい、上半身はざっくりしたトレーナー、下半身は下着だけという姿になった舞江の体をまじまじと眺めて、享子が歓声をあげた。 美津子から手渡された子供用の下着にお尻を包まれた舞江の頬がかっと赤く染まる。 「本当に可愛らしい下着ですこと。もともと、若奥様は同期の看護婦の中でも幼く見えましたから、そういう装いがお似合いですね」 博美も、いくぶん笑いを含んだような声で享子に同意してみせた。 「あの、これは……昼間でもお尻を冷さないようにとお義母様――奥様が買ってきてくださって……」 ますます顔を赤らめて、舞江は小さな声で呟いた。 「うふふ。言い訳なんてしなくてもよろしいのですよ。本当に若奥様は可愛らしくていらっしゃるわ。さ、下着も脱いでくださいな」 見る者の心をなごませる温かい笑顔で、けれど、ちっとも笑っていない目で舞江の顔をみつめて、博美が促した。 「は、はい……」 言われた舞江は、体を丸めて両手をもぞもぞ動かした。 ベビーピンクのオーバーパンツの下から、アニメキャラクターのパンツが現れた。 「それも大奥様が?」 博美は目を細めた。 「ええ、はい……」 舞江が腰をかがめて幼女用のパンツを大慌てで脱ぎ去ると、小柄で細っこい体に似合わない、豊かなアンダーヘアが見える。 「それでけっこうです。それじゃ、診察台の上で横になってください」 舞江を助けようとして、博美が腕を差し出した。 博美の腕を支えにして舞江が診察台に横たわると、彼女の胸元よりも少し下の方に享子がカーテンをおろした。泌尿器科や婦人科では両脚を大きく開いた姿勢で診察を受けることが多いため、診察中にひどい羞恥を感じる患者も少なくない。そこで、医師がどんな診察を行なっているのかを患者からは直接見えないようにして少しでも羞恥をやわらげるための配慮だった。 だが、一年間は現役の看護婦として医療の現場に立っていた舞江だ。泌尿器科でどのような恥ずかしい診察が行われるのか、知らないわけがない。だから、そのカーテンは気休めにもならなかった。 舞江は二度三度と深呼吸を繰り返してから、固く目を閉じた。そのすぐ後、誰かの手が舞江の手首に触れる感触があった。 細く目を開いた舞江が見たのは、診察台の肘置きの横に立っている享子の姿だった。 「なに、山口さん?」 そんな所で享子が何をしているのか不審に思った舞江は思わず声をかけた。 「あ、たいしたことじゃありません。ただ、不測の事故が起きるといけないので、ちょっと用意をしているだけです」 享子はこともなげに応えた。 同時に、右手の手首が肘置きに縛りつけられるような感覚。 その時になって、ようやく舞江は享子が何をしているのか気づいた。 「やめてよ、山口さん。診察中に暴れたりしないから、それはよしてちょうだい」 舞江はそう叫ぶと、体を起こしかけた。 が、もう遅かった。 既に享子は幅の広い革ベルトで舞江の右手首を固縛してしまっていたし、気がつくと、左手の方も博美がベルトを締めつけているところだった。 「先生、谷口先生。お願いだから、ベルトを外してください。私も看護婦です。だから、診察中に妙な動きをするようなことはしません。だから……」 完全に自由を失った両手を震わせて、舞江は博美に懇願した。 「だったら、尚さら、このベルトは外せません。医療関係者というのは意外に我儘な人が多くてね、医師にしても看護婦にしても、自分が診察や治療を受ける立場になると、それまでクランケに言っていたことも忘れて、泣き叫んだり暴れ出したりすることが多いんですよ。――自分が受けることになっている治療に伴う苦痛や診察中の恥ずかしさをよく知っているからそうなってしまうのかもしれませんね」 落ち着いた声でそう言うと、博美はカーテンの向こう側に姿を消した。そして、今度は舞江の足首を診察台に縛りつけながら言葉を続ける。 「泌尿器科の場合、非常にデリケートな部位を診察することが少なくありません。それに、特殊な器具を使うことも。そんな時にクランケが勝手に動いたりしたら、きちんとした診察をできる筈がありません。それだけならまだしも、最悪の場合、クランケの体に傷がつくことにもなりかねません。そうならないためにも、こうして体の動きを制限させていただくのです。わかっていただけますね、若奥様?」 わかっていただくも何もなかった。舞江の両手両足はもうすっかり診察台に固縛されて、体をよじることもできなくなってしまっているのだから。 「さ、始めましょうか。――山口さん、お願いします」 カーテンの向こうに隠れたまま、博美が享子に何かを指示した。 「はい、先生」 享子が事務的に応じる声だけが聞こえてくる。 |
|
|
|
|
|
| 目次に戻る | 本棚に戻る | ホームに戻る | 続き |