|
10 うつろいゆく心
「せっかくママがお外へ連れて来てくれたんだから、もう泣かないでね。ほら、からころ〜」
ひっくひっくとしゃくり上げながらまだ諦めきれない様子でガラス戸をみつめる早苗の耳元で遥香がガラガラを打ち鳴らした。
途端に早苗がびくんと体を震わせ、遥香の方に向き直って力なく首を振る。自分が置かれた惨めな状況に今にも大声で泣き喚きそうになるのを、通行人に泣き声を聞かれまいとして必死の思いで堪えているというのに、だだでさえ耳につきやすいガラガラの音が鳴り響いたりしたら、道路を行き交う通行人が何かと思ってこちらを見上げるに違いない。
(やめて、ガラガラなんて鳴らさないで。そんな音が下に聞こえたら……。お願い、もうやめて)
早苗は何度も弱々しく首を振り、心の中で哀願した。
けれど、いくら早苗が無言で訴えかけても遥香は気づかない。
「おかしいな、まだ泣きやまないなんて。お外はぽかぽかで気持ちいいし、おむつはさっき取り替えてあげたばかりなのに」
早苗の泣き顔をじっとみつめながら遥香は僅かに首をかしげて訝しげに呟いたが、すぐに何か思いついたのか顔をぱっと輝かせ、ガラガラと一緒にベランダへ持って出ていた哺乳壜をつかみ上げた。
「あ、そうだ。おっぱいの途中だったんだよね、早苗ちゃん。そっか、まだお腹が空いてて、それで泣いてるんだ。じゃ、これで泣きやんでくれるよね、きっと」
遥香は納得顔で言い、哺乳壜の乳首を早苗の唇に押し当てた。
(やだ、こん所で哺乳壜なんて)
早苗は反射的に口をつぐんだが、
「あれ? おっぱいが欲しいんじゃないかのかな? だったら、やっぱり、ガラガラであやしてあげた方がいいのかな」
という遥香の声を耳にすると、
(そうか、私が哺乳壜のミルクを飲んでいる間は早苗ちゃん、ガラガラを鳴らさないでいてくれるんだ。それだったら……)
と咄嗟に思い直し、唇に押し当てられたゴムの乳首をおずおず咥えた。
「あ、やっぱり、おっぱいが欲しくてぐずってたんだ。でも、これでご機嫌になってくれるかな。うふふ。哺乳壜のお乳を飲んでる早苗ちゃん、とっても可愛いんだ」
哺乳壜のミルクの表面にたつ無数の小さな泡と早苗の顔を見比べながら嬉しそうにそう言う遥香の笑顔は、春のお日様に負けないくらい眩しかった。
それからしばらくして哺乳壜のミルクを飲み干した後も、胸の内を満たす恥辱とは裏腹に、早苗は作り笑顔で『ご機嫌な赤ちゃんの早苗ちゃん』として振る舞わざるを得なかった。そうしなければ遥香が再びガラガラを打ち鳴らすに決まっているのだから。
*
「どう? 早苗ちゃんはいい子にしてた?」
真澄の声が聞こえたのは、二人きりのおままごとが三十分間ほど続き、遥香が早苗に膝枕をさせて優しくお腹を叩きながら子守唄を歌い聞かせている最中のことだった。
声が聞こえた途端、早苗は目を見開き、慌てて体を起こして、真澄の体にしがみついた。
「あらあら、早苗ちゃんたら甘えん坊さんだこと。ちょっとママがいないだけで寂しがっちゃうなんて」
真澄は洗濯物の入った籠をおろし、左手で早苗の体を抱き寄せ、右手で背中をとんとんと叩いた。
その様子を見ながら、遥香がお姉さんぶった様子で肩をひょいとすくめてみせる。
「本当に甘えん坊さんだね、早苗ちゃんたら。ずっと遥香ががあやしてあげてたのに、ママが戻ってきたらすぐに抱っこをせがむなんて」
「でも、仕方ないわよ。遥香は年長さんのお姉さんだけど、早苗ちゃんは赤ちゃんなんだから。それも、まだまだおむつ離れできない手間のかかる赤ちゃんなんだから。――ね、早苗ちゃん?」
真澄はおむつカバーの上から早苗のお尻をぽんと叩いた。
早苗が真澄の体にしがみついたのは、甘えたいからなどでは決してない。羞恥に満ちた自分の姿を誰かに見られかねないベランダにこれ以上放置されまいとして、ただ部屋の中に連れ戻してもらいたくて、それですがりついたのだ。真澄も、そんな早苗の胸の内はすっかりお見通しだ。お見通しのくせに、わざと早苗を甘えん坊の幼児扱いして面白がる真澄だった。
「あ、赤ちゃんじゃない。私、赤ちゃんなんかじゃ……う、うう……ひっ……ひっく、ひっく」
言い返そうとする早苗だが、ベランダに取り残されている間に胸いっぱいに溜め込んだ不安や怯えのせいで気持ちばかりが空回りしてきちんとした言葉が出てこず、再び涙をぽろぽろこぼしながらしゃくり上げてしまう。
「あ、また泣いちゃった。遥香がお乳を飲ませてあげてあやしてあげたら泣きやんだのに、ママの顔を見たら泣いちゃうなんて、本当に甘えん坊さんなんだから」
遥香が呆れたように言って、お姉さんぶった様子でもういちどひょいと肩をすくめてみせた。
「な、泣いてなんかない……私、泣いたりしない……」
遥香から「また泣いちゃった」と指摘されて、そのことを口実に再びベランダに放置されるのではないかという怯えに、早苗は涙をごまかすために真澄の胸元に顔をなすりつけた。
「やれやれ、本当に手のかかる子だこと。ママに甘えてくれるのは嬉しいけど、こんなにべったりだと用事もできないじゃない。でも、赤ちゃんなんだから仕方ないかな。いいわ、洗濯したおむつを干すのは後にして、お部屋に戻りましょう。いくら今日は暖かいといってもまだ三月で、いつ寒くなってもおかしくないし」
真澄はわざとらしい困り顔で言い、早苗の体を横抱きにして抱え上げた。
その拍子に早苗の顔が真澄の胸元から離れて、一瞬、二人の目が合う。
早苗は慌てて顔をそむけたが、傍目には、その様子はまるで小さな子供が人見知りをしているかのようだ。
「本当に可愛い赤ちゃんなんだから、早苗ちゃんは。こんなに可愛い赤ちゃんが本当は三年生なんだよって説明しても、誰も信じてくれないわよね」
真澄はくすっと笑って言った後、早苗の耳元でこんなふうに囁きかけた。
「本当は高校三年生なんだよって説明しても、誰も信じてくれないわよね? ね、早苗お・ね・え・ち・ゃ・ん?」
*
「じゃ、遥香は部屋の向こうの隅、そうそう、そこにいてね。それで、ママはこっち側に早苗ちゃんをおろすから、ガラガラで呼んであげて」
早苗を抱いたまま部屋に戻った真澄はそう言って遥香に居場所を指示し、反対側の隅に早苗をおろした。
「うん、いいよ。でも、何をするの?」
指図に従って部屋の隅に移った遥香だが、真澄がこれから何をしようとしているのかわからず、きょとんとした顔で尋ねた。
「早苗ちゃんに這い這いのお稽古をさせてあげるのよ。ねんねと抱っこばかりじゃ運動不足になっちゃうから」
真澄はそう答えながら早苗を四つん這いの姿勢にさせた。
ミトンに包まれた拳に体重がかかって早苗は呻き声をあげ、思わず床に座り込んでしまいそうになったが、真澄が下からお尻を支えるものだから、それもできない。
「さ、日向ぼっこの次は這い這いのお稽古よ。向こうで遥香お姉ちゃんがガラガラを振っているから、あそこまで這い這いするのよ」
部屋の向こう側でガラガラを大きく打ち振る遥香を指差して真澄は言い、少しだけ間を置いてこんなふうに付け加えた。
「それとも、お部屋の中でお稽古をするのは嫌かな? もしもお外でお稽古したいんだったらもういちどベランダへ連れて行ってあげてもいいわよ。どっちがいいのかな、早苗ちゃんは?」
「……お部屋……」
どちらがいいのかなと訊かれて、他に選びようなどあるわけがない。早苗は今にも消え入りそうな声で答えた。
「そう、お部屋がいいの。じゃ、始めようか。ほら、遥香お姉ちゃんの所へ這い這いしようね。――いい? 這い這いするのよ。早苗ちゃんはまだおむつも外れない赤ちゃんで、立っちなんてできないんだから」
真澄は念を押すように言い、早苗のお尻をぽんと叩いた。
その拍子に体が前のめりになってしまう。倒れまいとして、思わず早苗がとっとっとっと手足を繰り出す。
「そうそう、それでいいのよ。さ、その調子で遥香お姉ちゃんの所まで行くのよ」
真澄はもういちど早苗のお尻をぽんと叩いた。
同時に遥香がガラガラを更に大きな音で打ち鳴らす。
からころからころ。からころからころ。
かろやかな音色が響き渡る中、手と脚をぎこちなく動かして遥香のもとを目指す早苗の姿は、姉が鳴らすガラガラの音色に誘われるまま這い進む、ようやく這い這いができるようになったばかりの赤ん坊さながらだ。しかも、広げた掌を床につくのではなく拳で体重を支えているせいですぐに体のバランスを崩してしまい、そのたびに、ぷっくり膨らんだおむつカバーに包まれたお尻を左右に大きく揺らすものだから、その姿はますます赤ん坊めいて見えるのだった。
遥香がぱっと立ち上がり、早苗のすぐそばを擦り抜けて別の隅へ移動したのは、目指す場所までもう少しという所まで近づき、羞恥きわまりない『這い這いのお稽古』ももうすぐおしまいにできると早苗が胸の中で淡い期待を抱いた直後のことだった。
「ほら、今度はこっちよ。ここまでおいで」
早苗が首だけを巡らせて視線を移したその先で、遥香は今までと同じようにガラガラを振ってみせる。
「さ、頑張って遥香お姉ちゃんを追いかけるのよ。遥香お姉ちゃんをつかまえられたらお休みにしようね」
真澄が改めて早苗の体を遥香の方に向き直させて言った。
それを聞いた早苗の顔に絶望の色が浮かぶ。慣れない這い這いでいくら急いだとしても遥香にひらりと身をかわされてしまうのは火を見るより明らかだ。
早苗には弱々しく首を振った。
けれど真澄は容赦しない。早苗の腰を両手で持ち上げ、お尻をぽんと押しやった。
その勢いで早苗は再び、今にも倒れそうにしながら這い進む。
しかし、それも長くは続かなかった。
半分ほど進んだ所で早苗はお尻を床にぺたんとつけた恰好で座りこんでしまう。
「そんなことじゃ遥香お姉ちゃんをつかまえられないわよ。ほら、頑張って」
真澄が目の前に膝をついて、ぱんぱんと両手を打ち鳴らした。
だが早苗は弱々しく首を振って
「……もうやだ。手が痛くて、もう這い這いなんてできない」
と訴えかけるのが精一杯だった。
拳で体重を支えなければいけないのだから、すぐに手が痛くなってしまうのは事実だ。しかし、実は、早苗がぺたりと座り込んでしまったのには、もう一つの理由があった。
「そう、お手々が痛いの。お手々が痛くて這い這いができなくなっちゃったの。ふぅん、そうなんだ。――でも、這い這いができなくなった理由はそれだけかな?」
真澄はどこか意地悪な口調で確認するように尋ねた。
それに対して早苗は力なく視線を床に落とし、しばらく迷った後、躊躇いがちにこう答えた。
「……お、おしっこなの……」
そう。早苗が這い這いをやめてしまったのは、手の痛みのためというよりも、哺乳壜のミルクに混入した利尿剤によって再び誘発された尿意のせいだった。のろのろと這い進む早苗のお尻が左右に揺れるだけでなく時おり不自然にぶるっと震えるのを見て、真澄にはそれがありありとわかっていた。
「おしっこ、出ちゃったの?」
早苗の返事を聞いた真澄は重ねて訊いた。
「ま、まだ。……でも、出そうなの。おしっこが出そうだから、もう……」
早苗は上目遣いに真澄の顔をちらと見て小さな声で言った。
「そう。出ちゃいそうなのにちゃんと我慢してるなんて、お利口さんね、早苗ちゃんは。さっきはおっぱいの途中だったからトイレへ行かせてあげられなかったけど、今はそうじゃないからトイレへ行こうね。せっかくおしっこを教えてくれたんだもん、もうちょっと我慢して、トイレでおしっこしようね。そしたら、おむつの赤ちゃんじゃなくてパンツのお姉ちゃんになれるから」
真澄は意味ありげな笑みを浮かべて言い、早苗の腰に手をかけると、今度はドアの方に向き直させてぽんとお尻を叩いた。
「駄目! お尻を叩いちゃ駄目……そんなことしたら、そんなことしたら……」
改めて四つん這いの姿勢を強要された早苗は恨みがましい目で真澄の顔を見たが、利尿剤によって惹き起こされた尿意には耐え難く、続く言葉を飲み込むと、唇をぎゅっと噛みしめ、廊下に続くドアに向かって、おむつのお尻を大きく揺らしながらのろのろと這い進んだ。
本当は大急ぎでドアへ駈け寄りたいのだが、そんなことをすれば下腹部に余計な力が入ってしくじってしまうのは明かだ。
早苗は拳に痛みが走るのも構わず、下半身に力が入らないよう両手に体重を分散させてゆっくりドアまで這い寄った後、ドアに体重を預けて立ち上がろうとした。
けれど、眠っている間に着用させられたミトンが想像以上に滑りやすい素材でできていて、ドアにかけた手がすぐにつるっと滑ってしまい、体重を預けるどころか、上半身を起こす助けにもならない。しかも、痛みを堪えて這い進んだせいで腕の力がすっかり抜けてしまっていて、ドアのノブを廻すこともかなわない。
小刻みに震える両手を何度も何度もドアに押し当てて上半身を起こしかけるたびに四つん這いの姿勢に戻ってしまう早苗の様子は、伝い立ちに挑みながらも失敗して這い這いに戻る赤ん坊の姿そのものだった。
「……お願い、ドアを開けて。お願いだから、ドアを開けてよ、真澄お姉ちゃん」
伝い立ちに何度も失敗した後、床にぺたりと座りこんでしまった早苗は、声を震わせて真澄に訴えかけた。
「お姉ちゃん? 真澄お姉ちゃんですって? 今はおままごとの真っ最中なのよ。おままごとの中じゃ、早苗ちゃんのお姉ちゃんは遥香だけ。私はお姉ちゃんなんかじゃないわよ。――さ、私が誰なのか思い出して言い直してみようね」
真澄はすっと腰をかがめ、早苗の顔を見おろして面白そうに言った。
「……トイレへ行きたいの。お、おしっこが出ちゃいそうなの。だからお願い、ドアを開けて。お願いだから……マ、ママ……」
屈辱に顔を歪め、切羽詰まった声で早苗は真澄のことを『ママ』と呼び直して助けを求めた。
けれど、それだけで満足する真澄ではない。
「私のことをちゃんと『ママ』って呼べるようになって、お利口さんね、早苗ちゃんは。でも、本当にお利口さんだったら、もっと可愛らしくおねだりできるんじゃないかな。たとえば、自分のことを『私』って呼ぶのは、小学校くらいのお姉さんになってからじゃないのかな。年長さんの遥香お姉ちゃんでも自分のことを『遥香』って名前で呼んでるでしょ? だったら、それよりもずっと妹の早苗ちゃんが自分のことを『私』だなんて呼ぶのは変だよね。それに、小っちゃい子は上手に言葉を喋れないから『おしっこ』は『ちっち』になっちゃうんじゃないかな? ――ママの言うこと、わかるよね? わかったら、さ、もういちど言い直すのよ。這い這いのお稽古を始めたばかりの赤ちゃんにお似合いの可愛らしい言い方でおねだりをするのよ」
真澄は僅かに首をかしげて言った。
「……」
「どうしたの? ちっち、出ちゃいそうなんでしょ? トイレへ行きたいんでしょ? だったら、可愛らしくおねだりしなきゃ駄目じゃない。それとも、早苗ちゃんは赤ちゃんだから、おむつにちっちしちゃっても平気なのかな?」
屈辱にまみれた顔つきで唇を震わせるばかりの早苗に向かって、真澄は重ねて言った。
そうしている間にも尿意は容赦なく高まる。
「……さ、早苗……ち、ちっちなの。ちっち出ちゃいそうなの。トイレへ行きたいの。でも、早苗、ドアを開けられないの。だから、マ、ママ、お願い。ドアを開けて、お願い、ママ……」
しばらく逡巡した後、早苗は蚊の鳴くような声を絞り出して真澄に懇願した。そうするより他にできることなどないのは明らかだった。
「はい、よくできました。こんなに可愛らしくおねだりできるなんて、本当に早苗ちゃんはお利口さんだこと。お利口さんの早苗ちゃんのおねだりだもの、ママ、ちゃんときいてあげるわね」
早苗の羞恥に満ちた『おねだり』を耳にした真澄は相好を崩して言い、廊下に続くドアを押し開けた。
しかし、ドアが開いた後も早苗はまんじりともせず、ただ、目の前の廊下を睨みつけるばかりだ。
「どうしたの、早苗ちゃん? 早くしないとちっち出ちゃうんじゃないの?」
お尻を床にぺたんとつけたままなかなか体を動かそうとしない早苗に向かって真澄が言った。
「……連れて行って。早苗をトイレへ連れて行って、お願いだから、ママ……」
少し間があって、よく注意していないと聞き逃してしまいそうな小さな声が早苗の口から漏れ出た。
利尿剤によって惹き起こされた尿意がもう限界ぎりぎりのところまできていて僅かに体を動かすこともできなくなってしまっているのは、早苗の内腿がぴくぴく痙攣しているのを見れば明らかだ。
「あれ? 早苗ちゃんはドアを開けてっておねだりしたんじゃなかったっけ? だからママはドアを開けてあげたのよ。なのに、今になっておねだりの中身を変えちゃうの? でも、駄目よ。だって、ころころ変わるおねだりをそのたびにきいてあげていたら早苗ちゃんが我儘な子に育っちゃうもん。ママは早苗ちゃんにそんな身勝手な子には絶対なってほしくないの。だから、おねだりは一つだけよ。別のおねだりをする時は、最初のおねだりからもっと時間が経ってからにしようね」
真澄は両目をすっと細め、早苗の内腿が小刻みに震える様子を眺めながら軽く首を振った。
「そ、そんな……お願い、ママ。お願い、早苗をトイレへ連れて行ってよぉ。お願いだから、ママぁ」
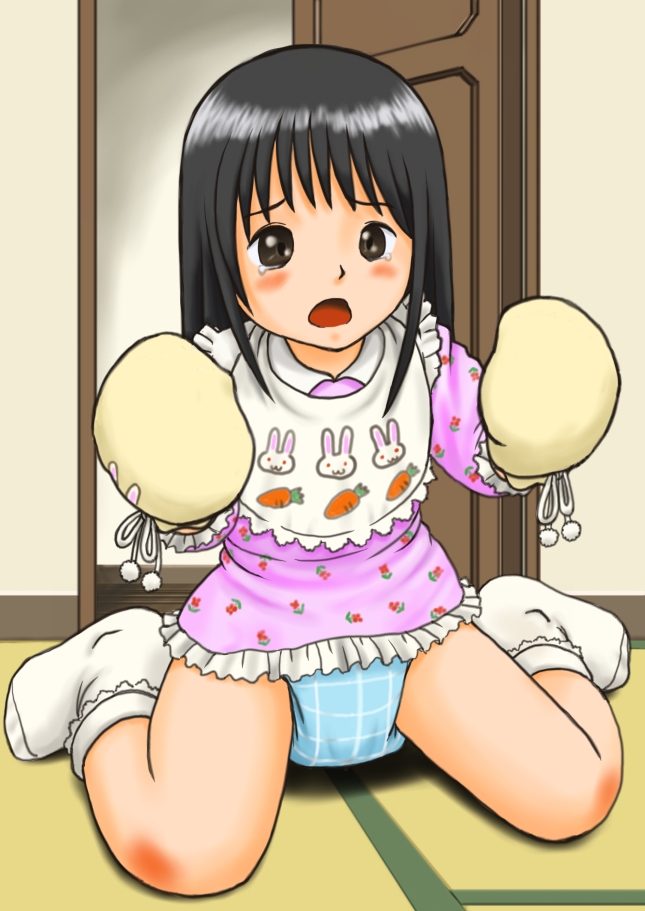
それまでそむけがちにしていた目を真澄の顔に向け、救いを求めて両手を前方に突き出して、早苗は涙声で訴えかけた。
「あらあら、今度は抱っこのおねだりなの? 本当に甘えん坊さんだこと。でも、仕方ないわよね。だって、早苗ちゃんはまだおむつの赤ちゃんだもん。いいわよ、抱っこのおねだりならきいてあげる。ママと赤ちゃんはスキンシップを欠かしちゃいけないもんね」
真澄の言う通り、胸元をよだれかけに覆われたベビー服めいたパジャマの裾からおむつカバーを半分ほどあらわにした状態で両脚を開きぎみにして、おむつで膨らんだお尻をぺたんと床につけて座り、両手を力なく前方に突き出す早苗の姿は、母親に抱っこを求める赤ん坊そのものだ。
真澄はその場で横座りになり、早苗の体を抱き寄せて膝の上に座らせ、
「さ、これでいいわね。じゃ、おむつにちっちしちゃおうか。自分でトイレへ行けないんだったらおむつにしちゃうしか仕方ないでしょ? ほら、ママが抱っこしていてあげるから安心してしちゃおうね」
と、早苗の下腹部をぽんぽんと叩きながら甘い声で囁きかけた。
が、早苗は弱々しく首を振り、今度は、廊下に向かって両手を伸ばす。もちろん、そこに誰か助けてくれる者がいる筈もない。ただ、トイレへ行きたいという思いがそうさせているのだ。
「ちっち出ちゃいそうなんでしょ? なのになかなか出ないなんて変ね。どうしちゃったのかな?」
真澄はわざと不思議そうな顔をして言ってから
「あ、そうか。ベランダへ連れて行ってあげる前は、おっぱいの途中でおむつを汚しちゃったんだったよね。ひょっとすると早苗ちゃん、おっぱいを吸いながらじゃないとちっちできないのかな。だったら、あの時と同じようにしてあげる。でも、もう哺乳壜は空っぽだから、今度はママのおっぱいよ。さ、ママのおっぱいをちゅぱちゅぱしながらちっちしちゃおうね。――ほら、早苗ちゃんの大好きなおっぱいよ」
と続けて言い、早苗が目を覚ました直後にそうしたように胸元をはだけると、張りのある乳房をあらわにして、ピンクの乳首を早苗の目の前に突き出した。
早苗は固く口を閉ざしたが、真澄は、ぴんと勃った乳首で唇を強引にこじ開ける。
早苗は諦めの表情を浮かべておずおずと乳首を口にふくんだ。真澄の執拗さに根負けしたというのもあるが、それよりも、一瞬でもいいから尿意を忘れさせてくれそうなものを求めて半ば自らの意志でそうしたという方が正しいかもしれない。
「それでいいのよ。さ、ママのおっぱいをちゅうちゅうしながらちっち出しちゃおうね」
見ようによってはひどく淫靡な笑みを浮かべて真澄は言い、おむつカバーの上から早苗の股間をまさぐった。
「あ……」
早苗は喘ぎ声をあげ、乳首を口にふくんだまま首をのけぞらせた。
だが、実は、喘ぎ声を漏らしたのは早苗だけではなかった。早苗の耳には届かなかったが、乳首を吸われた真澄もはしたなく喘いでいたのだ。
もう中学生の真澄だから、性欲も芽生えている。けれど、時おり胸の中に湧き起こる何やら得体のしれないもやもやした気持ちの揺らめきを性欲だときちんと認識できるまでには成育していない。それでも、本当は自分よりも四つも年上の早苗を逆に幼い妹扱いしているとわけもわからず気持ちが揺れ動き、浴室で早苗の体を抱え上げておしっこをさせている時などは、そのまま、年上なのに自分よりも小柄で華奢な従姉をぎゅっと抱きすくめたくて堪らなくなるほどの昂ぶりを覚えてならなかった。それに加えて、早苗が目を覚ました直後に自分の乳首を吸わせた時に感じた下腹部の疼き。そんな、これまでに経験したことのない妖しい情動に身をまかせるまま、今またこうして、ぴんと固く勃った乳首を早苗の口にふくませている真澄だった。それも今度は、下腹部がじんじん痺れるように疼くだけでなく、秘部からとろりと粘っこいお汁を溢れ出させつつ。
実を言うと、それさえも摩耶の企みの内だった。高校時代には姉のボーイフレンドを横取りし、実業団チームの選手だった時にも姉の交際相手を横から掠め取るだけでは飽きたらず結婚にまで至った摩耶だが、これまでに姉から奪い取った何人もの男性たちがいとも簡単に自分になびく様子に、逆に、不甲斐ない男どもに対する物足りなさを感じていたのも事実だ。いや、物足りなさというよりも、呆れるほどたやすく自分の手の内に堕ちる男どもに対して言いようのない侮蔑の念さえ抱いていた。そして、それは、夫が多忙を口実に摩耶と一緒にいることを疎ましがり、何かと言い訳めいた言葉と共に屡々家を空けるようになって、決定的になった。元はと言えば自分が姉から寝取った夫だから、そのような仕打ちを受けたとしても責めることなどできない筈だが、いささか身勝手なところのある摩耶にしてみれば、自身に非があるとは微塵にも思わず、ただ、若い頃はあんなに簡単に自分のものになった夫が今になって自分のもとから離れようとするのに対して不信の念と、侮蔑の念と、そして、少なからぬ憎悪を覚えるばかりだった。
そうして、その不信と侮蔑と憎悪の念を、娘である真澄もそっくりそのまま受け継いでいた。父親が家庭のことなどまるで顧みようともしないその原因が少なからず摩耶の方にあるなどとは露にも思わず、ただそれを父親の側にのみ非があるに違いないと思い込み(あるいは、摩耶によってそう思い込まされ)、ひいては男性全体への不信と侮蔑と憎悪の念を胸の中でふつふつとたぎらせて育ってきた真澄。真澄がバレーボールに打ち込むようになったのも、両親が揃ってプレイヤーだったという事情もあるが、それよりも、何かに夢中になっている間だけは父親や世間の男どもへの憎悪の念に幼い胸を焦がさずにすむからという理由によるものだった。
そのようにして、よく似た母と娘は殆ど母子家庭さながらの境遇に身を置いてこれまでを過ごしてきたのだが、そんな二人の前に現れたのが早苗だった。そして摩耶はたちどころにして不埒な企みを胸の中に思い描き、その企てに協力するよう真澄に耳打ちしたのだった。
だが、ここで一つだけ、摩耶を弁護できる点が無くもない。それは、不埒な企みの中にも娘に対する憐れみの念が見受けられるという一点だ。摩耶は、夫を含む男どもに対する憎悪と姉に対する妬みとが入り混じったどす黒い感情に衝き動かされるまま、実の姪である早苗を自分の娘の幼い妹に変貌させてしまうという猟奇的な計画を立て、それを今まさに実行しているところだが、その計画には、異性を愛する代わりに同性を愛する悦びを真澄に与えるという目的も含まれていた。
所属しているバレーボールチームにおいても真澄は女性コーチの指導には素直に従うものの、男性の監督やコーチに対しては敵愾心を剥き出しにするほどで、それが年ごろになったからといって収まるわけがないことは母親の目から見ても明らかだった。自身も男性に対する憎悪を胸の奥底に抱え持つ摩耶としては、それはそれで構わないという気持ちが強い。だが、年ごろになっても性欲の捌け口になる相手に恵まれないまま成長する娘のことが不憫でならないのもまた事実だった。そこで目をつけたのが、早苗だ。おそらくはまだ処女であろう早苗に、男の体を知らぬまま、真澄の性欲を満たす役割を与えてやろうと思いついたのだ。そのために、自分では何もできない、こちらの思うままにどうにでも扱える、真澄の幼い妹のような無力な存在に早苗を堕としてやろうと思いつき、真澄に手伝わせて、その不埒な企みを実行に移しているのだった。
今のように『おままごと』と称して早苗に自分の乳首を吸わせることで真澄の性欲が満たされるならそれはそれでいいし、また、これからいよいよ自分でもどうしていいのかわからず持て余してしまうほどに性欲が肥大化し、早苗だけでは飽き足らなくなった真澄が新たなパートナーを求めることがあったとしても、それはそれでいいと摩耶は思っている。ひょっとしたら、その新しいパートナーというのが、京子たちや、あるいは、更にひょっとしたら、遥香である可能性さえ無くはないが、それでも一向に構わない。
しかも、そうなった時には、おそらく新たなパートナーと共に真澄が新たな『おままごと』に打ち興じるのだろうという確信めいた予感も摩耶にはあった。男どもの体を頑として拒み、狂おしくも妖しい性欲にまかせて愛を交わしたところで、女性どうしでは子供が生まれることは決してない。一時の欲情を満たすだけならそれでもいいが、一生をそのまま暮らすとなると、それはそれで寂々とした生涯になるに違いない。そこで真澄が、生涯の伴侶となる同性のパートナーと共に、誰かの庇護のもとでなければ生きてゆけなくなってしまっている早苗を二人の『愛の結晶』とみなし、まやかしの『育児』を楽しみ、偽りの『親子水入らずの家庭』を築くことになるだろうという確たる予感が摩耶にはあった。
そう。摩耶は、異性を愛する悦びを幼くして放棄してしまった娘に、性欲の捌け口たる肉人形となり、また同時に、偽りの育児の悦びを満たしてくれる生きたミルク飲み人形ともなる早苗をプレゼントすることを企てたのだった。
そんな摩耶を非難することはたやすい。しかし、如何に歪んだ異形の心の動きであったとしても、それが血を分けた娘に対する愛情の発露であることを決して否めはしない。
その一点をもって摩耶を擁護することは、はたして、許されざる行為なのだろうか。
*
それから一時間弱が経過してまたもや尿意を訴えた時は、今度は真澄がドアを開けてやったおかげで早苗は部屋から出ることができた。しかし、休むことなく強要され続けた『這い這いのお稽古』のせいで腕だけでなく両脚の力もすっかり失っていたため、階段をおりることができず、二階の廊下でおむつを濡らしてしまった。
更に一時間ほど経って再びトイレへ連れて行ってくれるようせがまれた真澄は、今度は早苗を横抱きにして階段をおりたものの、半分ほどおりた所で足を止めると、その場に早苗をおろし、手摺りにつかまらせて途中の階段に立たせた。すると、手も脚もまるで力の入らない早苗はへなへなと座り込み、絶望の表情を浮かべておむつの中にしくじってしまった。
そして、それから更に一時間近くが経って早苗が涙声でトイレをせがんだ時は、今度こそ真澄は早苗を抱いて階段を最後までおり、一階の廊下で早苗を四つん這いにさせた。
「さ、トイレはこの奥よ。これまで失敗ぱかりだったけど、今度こそ頑張ってトイレまで這い這いしようね。早苗ちゃんも、パンツのお姉ちゃんになりたいでしょ?」
真澄は早苗の傍らに膝をついて廊下の奥を指差した。
そこには、先に階段をおりてトイレのドアの前でガラガラを振っている遥香の姿があった。
「ほら、こっちだよ、早苗ちゃん。ここまで這い這いできて一人でトイレへ行けたら、早苗ちゃんもパンツのお姉ちゃんだよ」
遥香は大声でそう言ってガラガラを打ち鳴らした。
「……連れて行って。お願いだから、トイレへ連れて行って。手も足も痛くて、もう這ってられないの……」
四つん這いの姿勢で手脚をぶるぶる震わせながら、早苗は涙に潤む目で真澄の顔を見上げて哀願した。
「駄目じゃない、そんなおねだりの仕方じゃ。手は『お手々』、足は『あんよ』、這うは『這い這い』って言うように教えてあげたのに、もう忘れちゃったの?」
涙声交じりの早苗の懇願に対して、真澄は教え諭すような口調で応じる。
「……お願いだからトイレへ連れて行って。早苗、お手々もあんよも痛くて、もう這い這いできないの。だからお願い、ママ……」
屈辱に顔を歪めながらも、早苗は真澄の顔から目をそらせることなく訴えかけた。どうやら、それほどまでに切羽詰まっているらしい。
「ママはいろいろ助けてあげた筈よ。ドアも開けてあげたし、抱っこして階段もおろしてあげたよね。ここまでしてあげたのに、まだ自分でトイレへ行けないの? そんなんじゃ、当分の間おむつ離れできないわね。パンツのお姉ちゃんになれるのは、自分でトイレへ行って誰にも手伝ってもらわずに便器にお座りして、ちゃんとちっちできる子だけなのよ。ママにトイレへ連れて行ってもらうような子はおむつの赤ちゃんのままなのよ。だから、さ、遥香お姉ちゃんの所まで這い這いして自分でトイレへ行きなさい」
真澄はぴしゃりと決めつけると、すっと立ち上がって早苗のそばを離れ、トイレの入り口の前でガラガラを振る遥香の傍らに移った。
「いや、置いてっちゃやだ。早苗も連れて行って。遥香お姉ちゃんの所へ早苗も連れて行ってよ、ママぁ」
自分のもとを離れる真澄に向かって早苗は四つん這いの姿勢のまま片手を差し延べた。
そのせいで、すんでのところで横向けに倒れそうになる。
それをかろうじてバランスを取り戻して、早苗は、真澄に向かって差し延べた手を廊下につき、じりっと体を進めた。
「頑張って、早苗ちゃん。ほら、ママとお姉ちゃんはこっちだよ」
じりじりと這い進む早苗に向かって遥香がいっそう大きくガラガラを振ってみせる。
「トイレ……トイレでおしっこするのよ……私、赤ちゃんなんかじゃない。おむつなんてもういや。だから、トイレで……」
いくらせがんでもトイレへ連れて行ってもらえそうにないことを思い知った早苗には、見ている方がもどかしくなるくらいのろのろと這い進むしかなかった。
だが、拳と膝頭の痛みに耐え、ようやく廊下を半分ほど這い進んだ所で、いよいよ尿意が限界に近づく。
ますます切羽詰まった表情の早苗は這うのをやめ、壁に手をついて体を起こした。表面を滑らかに処理してあるドアとは違って、クロス張りの壁はミトンに包まれた手でも簡単には滑ることなく体重を預けることがかろうじて可能で、やっとの思いで立ち上がることができた。
「トイレ……このままトイレへ……おむつなんていや。ちゃんとトイレでおしっこするんだから……」
今にもしゃがみこんでしまいそうにしながら覚束ない足取りでゆっくりゆっくりトイレへ歩み寄る早苗。
壁に手をつき、パジャマの裾からおむつカバーを覗かせ、ぶるぶる小刻みに震える脚をぎこちなく動かしてトイレ目指して進むその様子は、ようやく伝い歩きができるようになったばかりの赤ん坊が母親と姉の姿を求めてよちよち歩きをする姿さながらだ。
しかし、まだあんよが上手ではない赤ん坊そのまま、脚がもつれてその場に尻餅をついてしまう。
「あ! 早苗ちゃん、大丈夫!?」
トイレのドアまでもう少しという所で倒れてしまった早苗のもとに遥香が慌てて駈け寄り、気遣わしげな様子で声をかけた。
だが、早苗からの返事はない。廊下に尻餅をついたまま早苗は呆けたような表情で遥香の顔を見上げるばかりだ。
返事のない早苗に対してどう接すればいいのかわからず、遥香は手に持ったガラガラをころんと鳴らした。
と、うっすら潤んでいた早苗の目から大粒の涙がこぼれ出る。
「……ひ、ひっ……く。ひっく……早苗、赤ちゃんじゃない! 早苗、おむつの赤ちゃんなんかじゃない。早苗、パンツのお姉ちゃんだもん! 早苗、おむつの中に、ち、ちっちなんてしないもん……う、うわ〜ん」
最初は途切れがちにしゃくりあげていた早苗だが、感情の昂ぶりにまかせて金切り声をあげた後は、堰を切ったように涙をぼろぼろ流しながら手放しで泣きじゃくり始めた。
その様子を見れば、またもやトイレに間に合わずおむつを汚してしまったのは明らかだ。
*
玄関のドアが開いたのは、廊下に敷いたバスタオルの上に横たわる早苗のおむつカバーの前当てに遥香が指をかけた時のことだった。
ドアを開けて入ってきたのは、京子たち三人だ。
「どうしたの、早苗ちゃん? 外まで泣き声が聞こえてるよ」
廊下に上がるなり京子はそう言い、美咲や良美と一緒に早苗のそばに歩み寄った。
「あ、京子お姉さん。お別れ会、楽しかった?」
遥香は早苗のおむつカバーを開きかけていた手を止めて京子に言った。
「うん、とっても楽しかったよ。みんなでお菓子を持ち寄ってわいわい言って。自分でクッキーを焼いてきた子もいて、先生も喜んでくれてたよ。それで、私たちばかり楽しむのも悪いから、少しだけど、お土産にお菓子を分けてもらってきたの。はい、これは遥香ちゃんの分。それと、これが真澄お姉ちゃんの分」
お菓子を包んだティッシュを遥香と真澄に手渡した後、京子はポケットから別の包みを取り出した。
「それと、これは早苗ちゃんの分。だけど、早苗ちゃんにはお菓子じゃないんだ。今朝、お別れ会へ行く前にここへ寄った時、もう遥香ちゃんが来てて、『今日は早苗ちゃんを赤ちゃんにしておままごとをするんだ』って嬉しそうに言ってたでしょ? 赤ちゃんだったらまだお菓子は食べられないよね? それで、何がいいか三人で相談して、帰る途中、駅前のショッピングセンターに寄ってこれを買ってきたのよ。はい、遥香ちゃんから早苗ちゃんにあげてちょうだい」
そう言って京子が差し出した包みには、ベビー用品のチェーン店の名前が印刷してあった。
「よかったね、早苗ちゃん。京子お姉さんたちからお土産だって。何が入ってるか、楽しみだね」
遥香は受け取った包みをいそいそと開け、中に入っている物が何なのかわかるとぱっと顔を輝かせた。
「あ、オシャブリだ。ほら、お姉さんたちのお土産、オシャブリだよ」
遥香の言う通り、京子たちが早苗に買ってきたのは、幼児が好んで口に咥えるオシャブリだった。
「本当はもっといい物を買ってあげたかったんだけど、三人でお小遣いを出し合っても、これくらいしかお金がなかったから……」
美咲がはにかんだ様子で言った。
「何言ってるの、金額の問題じゃないわよ。今の早苗ちゃんが何を喜ぶか、それをちゃんと考えて買ってきてくれた、その気持ちが大事なのよ」
真澄は三人の顔を順番に見回して言い、くすっと笑って続けた。
「おままごとをしているうちに早苗ちゃんたらますます甘えん坊さんになっちゃって、遥香ちゃんに哺乳壜でミルクを飲ませてもらいたがってしようがなかったのよ。それに、哺乳壜が空っぽになった後もお口を寂しそうにちゅぱちゅぱ動かして。それで、仕方がないから私のおっぱいを吸わせてあげたりしてたの。でも、オシャブリを買ってきてくれたから、もうお口が寂しくなるなんてこともなくなるわね」
「ええ!? 真澄お姉ちゃん、早苗ちゃんにおっぱいを吸わせてあげたの!? 哺乳壜だけじゃなくて自分のおっぱいを?」
良美が驚いて聞き返す。
「そうよ、私のおっぱいを吸わせてあげたのよ。それで、早苗ちゃんたら、私のおっぱいを吸いながら何度もおむつを汚しちゃったのよ」
真澄は誇らしげな顔で答えた。
「じゃ、今も? 早苗ちゃん、今も真澄お姉ちゃんのおっぱいを吸いながらおむつにおしっこしちゃったの!? それで、遥香ちゃんにおむつを取り替えてもらうところだったの?」
驚いた顔で良美は重ねて訊いた。
「ううん、今のは違うのよ。目を覚ましてしばらくしてから早苗ちゃんには這い這いのお稽古をさせていたんだけど、お稽古の最中に何度もおしっこをしたくなってね。だけど、早苗ちゃんたらとっても甘えん坊さんで、私が抱っこしておっぱいを吸わせてあげながらじゃないとおしっこできなかったのよ。でも、今度のは、廊下で這い這いしている最中におしっこをしたくなって伝い立ちでトイレへ急いだんだけど、あんよが上手じゃなくて尻餅をついちゃって、その拍子に出ちゃったのよ。それで、お口が寂しくて大声で泣いちゃってるのかもしれないわね。そんな時にオシャブリを買ってきてくれたんだもの、本当に大助かりよ」
真澄はしれっとした顔で、京子たちが送別会に出かけていた間の出来事を虚実取り混ぜて説明した。
「おっぱいを吸いながらじゃないとおしっこできないとか、伝い立ちが上手にできなくて尻餅をついちゃうとか、なんだか早苗ちゃん、本当の赤ちゃんみたい。おままごとをしているうちに昨日までよりもずっと甘えん坊さんになっちゃったのかな」
真澄の説明に、美咲が興味深げな口調で言った。
「そうね、おままごとで私や遥香ちゃんに甘えているうちに、それが『ごっこ遊び』じゃなくなって、早苗ちゃんにとっては本当のことになっちゃったのかもしれないわね」
真澄は美咲に向かって軽く相槌を打ち、視線を早苗に転じた。
真澄や京子たちが見守る中、遥香は早苗の口にオシャブリ押し当てた。
おままごとと称して赤ん坊めいた恰好をしていても実際には高校三年生になる早苗だから、オシャブリを拒んで身をよじるのが本当だ。それも、自分よりも一回りほども年下の少女の手でそんなことをされるのだから尚更だ。
なのに、一瞬は躊躇いの表情を浮かべながらも、結局はおずおずとオシャブリを口にふくむ早苗だった。
涙をぼろぼろこぼしながらオシャブリを口にする早苗の姿に、真澄は胸の中でほくそ笑んだ。
這い這いの練習を強要されてすぐ早苗がトイレへ行きたいと訴えた時、真澄は早苗の体を抱きすくめ、自分の乳首を口にふくませた状態でおむつを汚させた。その次に早苗がトイレをせがんだ時、真澄はドアを開けて早苗が二階の廊下に出る手助けはしてやったものの、階段をおりることができずに身動き取れなくなった早苗に自分の乳首を咥えさせた状態でおむつを汚させた。それから更に早苗が尿意を覚えた時、真澄は早苗を抱いて階段をおりたが、最後までおりることはなく階段の途中で早苗の体をおろし、身をすくめる早苗を抱き寄せて乳首を口に押し当てた状態でおむつを汚させた。そして、京子たちが送別会から帰ってくる直前に早苗が尿意にお尻を震わせた時、真澄は早苗を横抱きにして階段を最後までおり、一階の廊下で四つん這いの姿勢にさせた。だが、その時にはもう尿意が限界に達している上、強要され続けた這い這いのせいで手も脚もまるで力が入らず、もうあと少しでトイレという所で、やはり早苗はおむつを汚してしまった。その時、真澄は、早苗が廊下に座りこんだままおむつにおしっこを出し終えるのを待って、これみよがしにトイレのドアを開け、純白の便器を指差して早苗の耳元に
「ほら、トイレはあんなに近くにあるのよ。なのに、早苗ちゃんはおむつを汚しちゃったのよ。こんなに近くにあるトイレに間に合わないんじゃ、とてもじゃないけど、当分おむつは外せないわね。いい? 早苗ちゃんはこれからずっとおむつの赤ちゃんよ。パンツのお姉ちゃんになるのはまだまだ先のことなのよ」
と甘ったるい声で囁きかけたのだった。
一昨日は何度もパンツを濡らし、昨日は紙おむつを何枚も汚してしまって、河野家へ来てからこちら家の中でも外出先でも早苗は一度もトイレへ行くことができないでいた。そして今日は、今度こそトイレへ行ける、今度こそトイレへ連れて行ってもらえるという淡い期待を繰り返し胸に抱きながらも、そのたびに一縷の望みを絶たれ、濡れた感触がはっきりわかる布おむつを汚し続けたのだ。最初から期待など抱いていないよりも、期待を抱いた直後に望みを絶たれる方が、却って絶望は深い。そんな計り知れない絶望を何度も味わううちに、「もう駄目だ。私の願いがかなうことはもう二度とないんだ」という諦めの気持ちが芽生え、その諦観の念がいつしか胸を満たしたとしても、なんら不思議なことはない。
まるで抵抗する気配もみせず、遥香が手にするオシャブリを早苗が口にしたのも、そんな心の隙を衝かれたからだ。抗おうとする気力は諦観の念によって心の片隅に押しやられ、、摩耶や真澄や遥香のなすがままにされるしかないことを早苗は身をもって思い知らされたのだった。
とはいえ、いつまでもそんな心の状態のままいる筈もない。やがて、一時的な精神の麻痺から覚めて早苗は自分を取り戻すことだろう。
しかし、急ぐ必要はない。時間はたっぷりあるのだ。同じような仕打ちを延々と繰り返し続ければ、いずれは――それこそが、摩耶と真澄の企みだった。
|