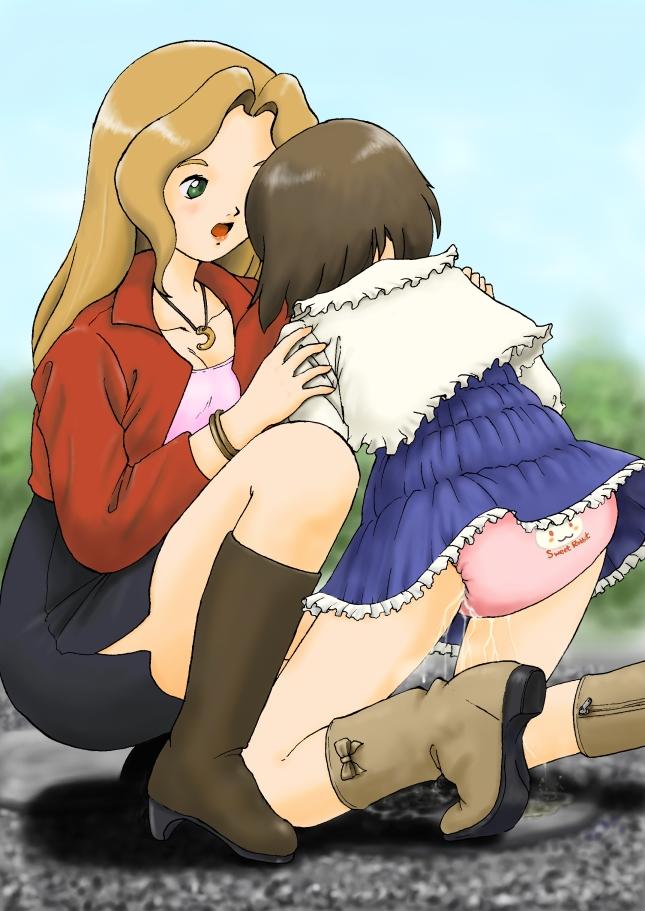|
《7 ようやくの帰宅。だけど……》
扉を開けて二人が外に出た時には、トイレの順番を待つ客が何人かいた。しかし、
「急なことでびっくりしちゃったけど、もう大丈夫よ。パンツは汚しちゃったけど、気にしちゃ駄目よ。もう処置も終わったし、平気なんだから」
と美幸が真衣に話しかける様子に、おそらく娘だろう若い方の女性に予定外の生理が訪れ経血で下着を汚してしまったのを、母親とおぼしき年長の女性が処置してやったのだろうと、自分や身近な者の経験を基に勝手に推測するものだから、不審げな表情を浮かべる者はいなかった。むしろ、いたわりの目で真衣の顔を覗い見る客が殆どだ。
だが、その視線が真衣には痛くてたまらない。『大きななりをしているくせにおもらしでパンツを汚しちゃって、お母さんにパンツを穿き替えさせてもらうだなんて、どんな子なのかしら』そんな目でじろじろ見られているように感じられてならない。しかも、汚物入れには、切れ目の入ったショーツと、高校生である真衣にはおよそ似つかわしくないお尻拭きが残されているのだ。後からトイレを使った客がそれを見たらどう思うだろう。そう考えると、一刻でも早くこの場から立ち去りたくて仕方なかった。
しかし、いざ、その場を抜け出してホテルのレストランに場所を移しても、気分が晴れることはなかった。三部袖のワンピースになっているスカートの下に、おむつ離れの練習さなかの赤ん坊と同じトレーニングパンツを着けていることを周囲の客たちに勘づかれるのではないかと気が気ではない。その上、普段のショーツは勿論のこと渋々ながらすっかり慣れてしまった紙おむつとも異なるトレーニングパンツの肌触りに絶えず下腹部を撫でさすられていようで、せっかくのランチコースもまるで味がわからないほどだった。
更に、帰り道のことを考えると、言葉では言い表されないほどの不安に胸を締めつけられる。大勢の客が乗り合わせる電車やバスの中、他の客の荷物がスカートの裾に引っかかったり、急ブレーキのせいで真衣自身が尻餅をついてスカートが捲れ上がってしまうかもしれない。そのせいでスカートの下に着けている恥ずかしい下着のことを周囲の乗客に知られでもしたら。しかも、次の駅なり停留所に着くまで、逃げる場所はないのだ。
そんな真衣の胸の内を見透かしたかのように美幸が口にしたのは
「荷物も増えたから帰りはタクシーにしましょうか」
という言葉だった。
思いがけないその提案を真衣が拒否するわけがなかった。
だが、美幸にしてみれば、帰り道にバスや電車ではなくタクシーを選んだのは、真衣のことを気遣ってのことでは決してない。それさえも、自分の企みを進めるための手段の一つにすぎなかったのだ。
タクシーに乗り込んだ美幸は佐藤家の住所とおよその場所を要領よく運転手に伝えた。間を置かず運転手からは、「まず国道××号線を辿って、途中から県道××号線、それから、広域道路の××号線に移ればいいですね」と確認を求める返答があったのだが、それに対して美幸は首を横に振り、「国道から県道に入った後、私が道順を指示するわ」と応じた。
言った通り、国道から県道に枝分かれした所で美幸は改めて道順を指示したのだが、それは、運転手が想定していたコースに比べるとかなりの遠回りだった。「本当にいいんですか?」と問いかける運転手に対して美幸は「いいのよ、この先に有名なケーキ屋さんがあるから寄って帰りたいの」と応じたのだが、それでようやく遠回りの意味を理解した運転手は謎が解けてほっとしたような表情を浮かべ、その後は、美幸が幾ら遠回りになりそうな道順を告げてもわざわざ聞き返すことなく指示通りに車を走らせることに専念するようになった。
実際、ケーキを買った後も美幸は、やれ「慣れない土地に赴任する優さんに持たせる胃腸薬を買い忘れていた」と言っては大通りから外れてドラッグストアに寄ってみたり、「新しいネクタイじゃないといけないかしら」と言っては全国チェーンの衣料品店に寄ってみたり、「ボタンが外れかけているカッターシャツがあったわね」と言っては手芸品店に寄ってみたりと、いろいろ理由をつけてはわざとのように遠回りの道を選んで運転手にあれこれとを指示を出し続けた。
だが、美幸が遠回りの道を選んでいるのは、『わざとのように』などではなく、『わざと』だった。その狙いは、帰宅するのに要する時間を長くして、その間に、真衣の尿意を我慢できなくなるほどに高めるところにあった。紙おむつが吸収したおねしょの量や、家を出てから家電量販店でのおもらしまでに経過した時間、これまでの問診の内容などから、真衣の膀胱の容量がどの程度なのか、そして、真衣がどれくらいなら尿意に耐えられるのかといったことについて、美幸には、およその見当がついていた。それを基に、タクシーに乗っている時間を調整して、真衣に車内でおもらしをさせるのが美幸の魂胆だったのだ。
今朝までに三度も美幸の手でおむつを取り替えられ、家電量販店ではトイレに入る前にショーツを濡らしてしまい、トイレで美幸によってトレーニングパンツに穿き替えさせられた真衣だから、もう既に美幸には頭が上がらない状態だった。その上、更に、タクシーの運転手という見ず知らずの他人の目がある前でパンツを汚すような事態になりでもしたら、これから先、真衣は美幸の言うことに僅かでも逆らうことができなくなるに違いない。
それこそが美幸の狙いだった。
そう。自分の言うことにいやでも従わざるを得なくなるような状況に真衣を追い込むことこそが、美幸の企みだったのだ。
見た目は優しそうな女医。だが、彼女の行動を律しているのは、理性などではなく、自分の子供を持つ夢を諦めたせいで奇妙に歪み肥大化してしまった異形の母性本能だった。尋常ならざる母性本能という糸によって絡め取られ気儘に動かされる狂おしく哀しい操り人形。それが、美幸の正体だった。
*
道が空いていればHホテルから佐藤家までは車なら四十五分ほどの距離だ。それが、美幸の指示する遠回りのせいで、途中に立ち寄った店での買い物に要した時間も合計すると、もうかれこれ二時間ほどになる時点で、ようやく最寄りのバス停の前に差し掛かかろうかというところだった。
美幸と並んで後部座席に座っている真衣の表情が微かに変わったのは、二十分ばかり前のことだった。それが今は、見るからにこわばった顔つきで、太腿の上に置いた掌をぎゅっと握りしめ、両腕を小刻みに震わせている。呼吸も浅い上に荒く、肩で息をするのがやっとといった風情だ。
「お嬢さん、大丈夫ですか? 気分がお悪いようですけど、もしも車酔いだったら、どこか木陰に車を停めましょうか?」
バックミラー越しに真衣の異変に気づいたのだろう、運転手が心配そうに言った。
「いえ、大丈夫です。もうすぐ家に着くから、車からおりてお布団で休ませた方がいいでしょう。このままお願いします」
美幸は軽くかぶりを振って応じ、はい承知しましたと運転手が応えるのを聞きながら、
「真衣ちゃん、大丈夫? 久しぶりの人混みで疲れちゃったのかな」
といかにも気遣わしげな様子で話しかけ、真衣の細い肩を抱き寄せた。
だが美幸は、真衣の異変の原因が疲れなどでないことを充分に承知している。ホテルでトイレを済ませ、タクシーに乗って、かれこれ二時間近い。もうそろそろ、我慢の限界も目の前に迫っている頃だ。
「だ、大丈夫……」
こわばった顔ながら気丈に応じる真衣。
しかし、大丈夫でないことは明かだ。美幸は、ついさっき真衣が妙な吐息を漏らすのを聞き逃さなかった。
「本当に大丈夫?」
美幸は体温を調べるふうを装って真衣の額に自分の額を押し当て、そのまま、真衣の体を自分の体でバックミラー越しの運転手の目から覆い隠すような姿勢を取ると、右手をスカートの中にもぐりこませた。
「大丈夫なの、おしっこは?」
ついさっきまでのよく通る声とは打って変わって、美幸は真衣の耳元に唇を寄せ、甘ったるい声で囁きかけて、スカートの中にしのばせた右手でトレーニングパンツの表面をなぞった。
「……大丈夫です……」
真衣は弱々しい声で繰り返し答えた。
「確かに大丈夫みたいね」
トレーニングパンツの表面が濡れていないのを確認した美幸はにこりと笑って言った。
「……大丈夫に決まって……」
真衣は顔をこわばらせつつも安堵の声を漏らしたが、それまで表面をなぞっていただけだった美幸の手が股ぐりを広げてトレーニングパンツの中に差し入れられる感触に、途中で言葉を失ってしまう。
「私が大丈夫って言ったのは、おしっこが表面までは沁み出していないってことよ。さすが、特別に作ってもらっただけあって、素材も縫製もしっかりしているトレーニングパンツだこと。でも、内側はびっしょりね。吸水パッドがこれだけ濡れているとすると、穿いているのが普通のパンツだったら、今ごろは座席もぐっしょりで運転手さんに迷惑をかけていたところね」
純白のバイアステープで縁取られた股ぐりを押し広げてトレーニングパンツの中に指を差し入れるや否や、美幸はさも呆れたように言った。
「でも、この様子なら、お家に着くまでは表に沁み出してこなさそうだし、匂いが漏れ出すこともなさそうね。もっとも、真衣ちゃんがこれ以上はおしっこを出しちゃわないならっていう条件付きだけど」
「……」
一瞬でもおもらしの事実をごまかしおおせるかもと期待した直後だけに、真衣の落胆は余計にひどかった。腕のみならず肩まで小刻みに震わせ、唇をぎゅっと噛みしめて屈辱に耐えるしかない。
「でも、気にすることはないのよ。そのためのトレーニングパンツなんだから。ね、わかったでしょ? おむつ離れのできない赤ちゃんの真衣ちゃんには、お出かけの時も、まだ普通のパンツは早いのよ。普通のパンツはおむつを外すお稽古を済ませてから。それまでは、ちょっとくらいちびっちゃっても平気なトレーニングパンツにしようね。念のために、業者さんにお願いしてたくさん作っておいてもらったから、いくら濡らしても大丈夫よ」
美幸は笑顔のまま言った。
そのわざとらしいにこやかな笑みが却って真衣の恥辱をこれでもかと煽る。
「真衣ちゃんはこれからずっと、おもらしとおねしょが治るまでは、お家にいる時はおむつ、お出かけの時はトレーニングパンツよ。わかったわね? 三度もおむつを取り替えてもらって、二度もパンツを濡らしちゃったんだから、わからないとは言わせないわよ。さ、わかったら、ちゃんとお返事しようね。いい子の真衣ちゃんは、上手にお返事できるよね」
そこまでは声をひそめて囁きかけていた美幸だが、真衣が押し黙ったままなのを見て取ると、トレーニングパンツの様子を探っていた手を元に戻し、真衣の体に覆い被さるような姿勢を取っていたのをきちんと座席に座り直して、運転手の耳にもはっきり届くよう
「じゃ、お家に帰ったらちゃんとしてあげる。もうすぐだから、それまで我慢するのよ」
と声を張り上げて言った。
お家に帰ったらちゃんとしあげる。それまでは我慢するのよ。運転手は、その言葉を『気分が悪いようだけど、お家で手当してあげるから、それまで頑張って我慢してね』という励ましの意味にとらえただろう。しかし、実のところ美幸は『お家に着いたらパンツを取り替えてあげるから、それまで、これ以上おしっこを出しちゃわないよう我慢してなさいよ』と言いつけていたのだ。
もちろん、真衣にも本当の意味はわかっている。わかった上で、運転手の手前、何も返事をしないわけにもゆかず、
「……うん、わかった。お家に着いたらちゃんとしてね」
と蚊の鳴くような声で応えるしかなかった。それが、『これからずっと、お家にいる時はおむつ、お出かけの時はトレーニングパンツ』と決めつける美幸の言葉に従いますと誓ったのと同じ意味合いを持つことを痛いほどわかりつつ。
運転手が時おりバックミラー越しにこちらの様子を覗う中、おしっこでトレーニングパンツの内側をびしょびしょにしてしまい、運転手に本当の意味を知られたわけでないとはいえ、美幸からの羞恥と屈辱に満ちた指示を受け容れると応えてしまった真衣。その時こそが、真衣が美幸の手に堕ちた瞬間であり、美幸が『娘』という名の生きた愛玩人形を手に入れた瞬間だった。それも、本人は気づいていないが、タクシーの運転手という証人を立ち会わせた上で。
*
ドアが開くと同時にシートベルトを外すのももどかしくタクシーをおりた真衣は、下腹部に余計な力を入れないよう注意しながら慌てて歩道を横切り、門扉の前に歩み寄った。
一方、美幸はからかうように
「ほらほら、真衣ちゃんたら、そんなに急いだりしたら、ころんしちゃうわよ。まだあんよが上手じゃないんだから、ママがお手々を引いてあげるのを待っていればいいのに」
と言いながらわざとゆっくり歩いてくるのだが、そんな言葉、もちろん真衣の耳には届いていない。。
真衣は大急ぎでポーチから取り出した鍵で門扉を開け、顔をひきつらせて玄関に向かった。
門扉から玄関までは僅か数メートルという距離だが、玉砂利を敷きつめた和風仕立ての通路になっているため、やや足場が悪い。そこを限界ぎりぎりの尿意をこらえつつ、そのくせ下腹部に余計な力を入れないよう注意しながら歩いて抜けなければならないのだから、なんでもない時からは想像もできないほどの苦痛だった。
「ほら、もう少しだから頑張って。おむつ離れのお稽古をする真衣ちゃんだもの、あんよのお稽古もちゃんとしなきゃ、姉ちゃんになれないのよ。ほら、あんよは上手」
それこそ、ようやく一人であんよができるようになったばかりの幼児がお尻を後ろに突き出しぎみにしてよちよちと歩いて行く姿そのまま、なんとも覚束ない足取りで玄関を目指す真衣の後ろを、つかず離れずの距離を保ってつき従いながら、美幸は両手を打ち鳴らして囃したてた。
そんな子供扱いは屈辱だが、今は尿意をこらえてトイレへ行くことに神経を集中するしかない。真衣は肩で息をしながら、玄関のドアを睨みつけて必死の形相で玉砂利を踏みしめた。
しかし、皮肉なもので、その必死さが仇になってしまう。玄関のドアばかり見ていて足元への注意が疎かになったせいで、普段は何気なく踏んで歩いている飛び石の存在にまるで意識がまわらなかったのだ。
周囲の玉砂利に比べて一段高くなっている飛び石に躓いた真衣は、体のバランスを崩して前のめりになる。それに気づいた美幸がたっと駆け出し、前方にまわりこんで、今にも倒れそうになっている真衣の体を受け止めた。そのおかげで、玉砂利の通路に倒れることもなく、膝を擦り剥くことも免れた真衣。
だが、全てが無事というわけではなかった。
倒れまいとして余計な力を入れてしまったのと、美幸に抱きすくめられた時の衝撃とで、それまで我慢に我慢を重ねていた尿意にとうとうこらえきれなくなって、堰を切ったようにおしっこを溢れ出させてしまったのだ。
それまでも或る程度の量のおしっこを吸収していたトレーニングパンツの内側は、それ以上のおしっこを吸い取ることはできなかった。しかも、我慢の限界を超えて溢れ出したおしっこは、『迸り出る』という表現がふさわしいほどの勢いで流れ出るために、吸水量にまだ余裕があったとしても吸い取る速度が追いつかず、結局は外に漏れ出していたに違いない。
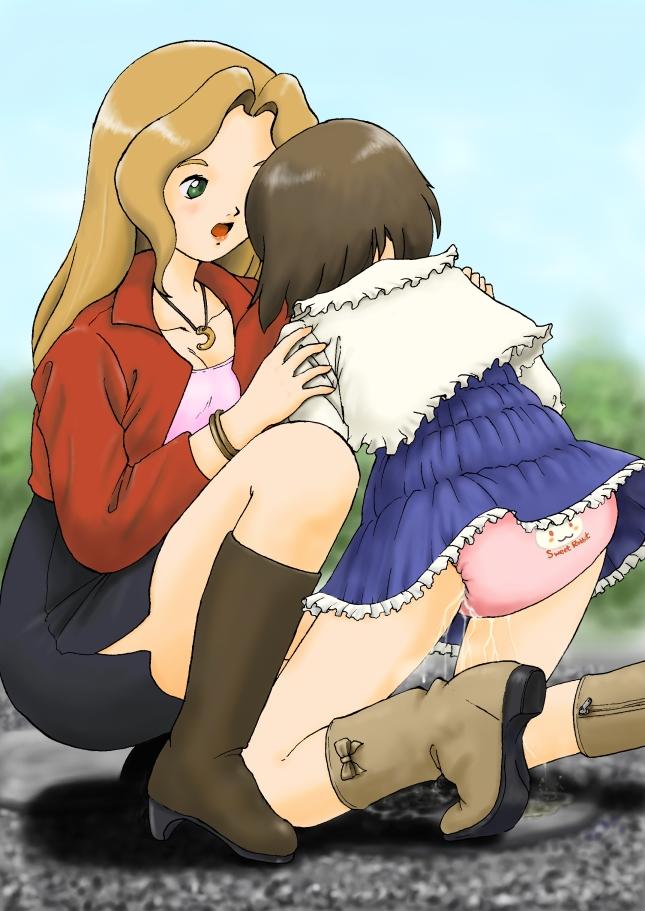
普通のショーツを穿いておもらしをした場合、おしっこはクロッチ部からほぼ真下へ滴り落ちるのだが、今の真衣が穿いているのは、表面が防水生地になっているトレーニングパンツだ。内側の吸水パッドに吸収されなかったおしっこは、表地に沁み出すこともできず、バイアステープで縁取りされた股ぐりと太腿の皮膚との間の僅かな隙間から漏れ出すしかなかった。そのため、おしっこは中央付近から滴り落ちるのではなく、太腿を濡らしながら、両脚の肌に沿って伝い落ち、膝といわずくるぶしといわず脚全体にまとわりつくようにして、最後はソックスを濡らしつつ、ブーツの内側に滴り落ちることになる。
おしっこが真下に落ちるだけなら、脚を開いて立っていれば、雫が地面に当たって周囲に飛び散る飛沫で足元が少し濡れるだけですむかもしれない。しかし、トレーニングパンツの股ぐりから漏れ出るおしっこは脚全体を濡らした上、ブーツの内側に溜まって爪先までびしょびしょにしてしまう。そのせいで真衣は、自分がおもらしをしてしまっている最中なのだということをより強く意識せざるを得なくなり、ますます美幸のいうことに従うしかないという意識を植え付けられてゆくのだった。
*
内側におしっこの溜まったブーツを美幸の手で脱がされ、玄関の上がり框に広げたバスタオルの上に立たされ、やはりこれも美幸の手によって五分袖のカーデガンと三分袖のワンピース、ぐっしょり濡れたソックスとトレーニングパンツを剥ぎ取られてブラスリップ一枚だけという姿に剥かれた真衣は、浴室へ追い立てられ、シャワーを浴びなさいと命じられた。しかも、おっこの雫が少しでも残らないよう下腹部は特に念入りに綺麗にしなさいよと付け加えられて。
それに逆らったりしたら、美幸の手で強引に浴室へ連れて行かれ、無理矢理体を洗われることになるのは明かだった。それも、自分では満足に体を洗うこともできないような小さな子供扱いされて、必要以上に入念に。
それを避けるために渋々ながら自ら浴室に足を運んだのだが、頭からシャワーを浴びているうちに力ない溜息を何度もついてしまうのをどうしても止められなかった。ひょっとしたら、頬から顎先を伝い流れて胸元に滴り落ちる湯の中には、悔し涙の雫も混ざっていたかもしれない。
美幸の言いつけに従ってたっぷり時間をかけてというよりも、いささか当てつけがましく半ば意地になって延々とシャワーを浴び続けた真衣が浴室のガラス戸を引き開けたのは、浴室に追い立てられてから小一時間も経ってからのことだった。
もういちど溜息をつき、浴室に隣接する脱衣場に足を踏み入れた真衣は、床に置いてある脱衣籠を見て僅かに首をかしげた。脱衣籠には、浴室へ入る前に脱いだブラスリップの代わりに、ナイティが入っていた。おそらく、真衣がシャワーを浴びている間に美幸が部屋の整理箪笥から持ってきたのだろう。勝手に部屋に入られていい気はしないものの、三度もおむつを取り替えられ、二度もおもらしの処置をされた今となっては、それを拒む気力もないし、抗議したとしても逆にあれやこれやと反論されて結局は美幸の言いなりになってしまうのは目に見えている。だから、それは仕方ないといえば仕方ないところだ。
真衣が訝しんだのは、そのことではなく、脱衣籠に入ってるのがナイティだということに対してだった。まだ日の高い午後四時。夜でもないのに、いくらなんでも、ナイティに着替えるにはまだ早い。
|