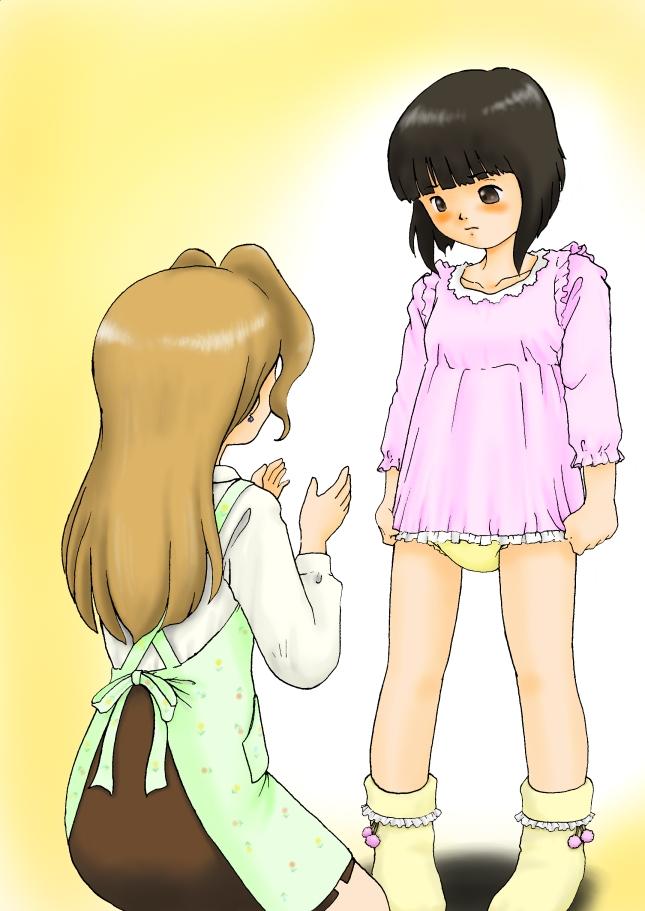ママは私だけの校医さん
|
《9 お家にいる時は》 「さ、できた。とっても可愛らしくなったわよ、真衣ちゃん。これなら赤ちゃん返りしちゃうのも当たり前かもね」 美幸は、診察室で顔を会わせた時の制服姿と比べてひどく幼く見える真衣の姿に満足げに頷いてから、さりげなく言った。 「ところで、おしっこは大丈夫なのかな? 玄関のおもらしから大分時間が経つけど、まだ我慢できるのかな?」 「……だ、大丈夫……」 美幸の方から問いかけられ、咄嗟にどうしようか迷ったものの、真衣は幾分うろたえぎみにそう応えた。本当はトイレへ行かせてくれるよう懇願したいところだが、なぜとはなしに躊躇われて、またもや言い出しそびれてしまう。 だが、それに対して美幸はくすっと笑うと、 「嘘おっしゃい」 と、真衣の返答を言下に否定した。 「え……?」 「そんな嘘をついてもすぐにわかっちゃうのよ。ちょっとした表情の変化とか些細な仕草から子供が何を求めているのかを直感するのが母親なんだから。真衣ちゃんが今なにをしたいのか、私にわからないわけないでしょう?」 「……」 「さ、真衣ちゃんは何をしたいの?」 「……ト、トイレ……」 美幸に促され、真衣は曖昧に答えた。 「そう、トイレに行きたいのね、真衣ちゃんは」 美幸はいかにも納得したといいたげに、にこやかな笑みを浮かべた。 そうして、笑顔のまま短く言い放つ。 「でも、駄目よ」 「……!?」 「トイレへ行っちゃ駄目って言ったのよ」 美幸は念を押すように繰り返し言った。 「……ど、どうして……?」 「だって、真衣ちゃんはおむつを着けているんでしょ? だったら、トイレなんて行かなくてもいいじゃない。おしっこはおむつの中にしちゃえばいいじゃない。現に、毎晩そうしているんだから」 美幸は妖しく瞳を輝かせて言った。 「で、でも……」 そう言ったきり二の句を継げない真衣。 「下の子ばかりに向けられる母親の愛情を取り戻すために赤ちゃん返りしちゃう上の子。そんな子の年齢は、普通は二歳とか三歳、大きくてもせいぜい五歳までってとこかしら。そのくらいの年の子だと、欲求をストレートに表現できるのよね。まだ理性なんてまるでないし、恥ずかしいという気持も殆ど持ち合わせていない。だから、下の子みたいに甘えたい、ママのおっぱいを飲ませてくれなきゃやだ、赤ちゃんみたいにおむつをあててほしい、そんな感情を何の遠慮もなくぶつけることができるの」 美幸は真衣の正面に立つと、手早くエプロンを脱ぎ去った。 「だけど、同じように赤ちゃん返りしちゃったのに、真衣ちゃんはそう簡単に欲求を表現できないでいる。ま、それも仕方ないわよね。いくら赤ちゃん返りしちゃったといっても、高校生なんだもの。理性とか恥ずかしさとかが先に立っちゃって、自分の感情を爆発させるなんてこと、そうそう簡単にできるもんじゃないわよね。――それに加えて、真衣ちゃんの場合は、下の子への嫉妬に起因する赤ちゃん返りじゃない。今はいないお母様の愛情を求めての赤ちゃん返り。欲求を表現しようにも、嫉妬の対象になる下の子がいるわけじゃなく、甘えの対象になるお母様もいない」 「……」 「下の子への嫉妬から赤ちゃん返りしちゃった上の子に対する一番いい対処方法は、思いきり甘えさせてあげることなのよ。その子の気がすむまで、その子の欲求通り、おっぱいを吸わせてあげたり、おむつをあててあげたりという赤ちゃん扱いも含めて、とにかく、存分に甘えさせてあげること。そうすることで、自分も母親に愛されているんだって実感させてあげること。そういうことを続けているうちに、その子の胸の内に溜まっていたもやもやが綺麗に消えちゃうの。つまり、心理学で言うところの『昇華』ってやつね。で、精神的な昇華を経験した子は、今度は逆に下の子のことを信じられないくらい可愛がるようになるのよ。それまでの嫉妬が、昇華というプロセスを経て愛情に変化するって言えばいいかしら」 美幸は、エプロンの下に着ているブラウスのボタンに指をかけた。 「これまで嫉妬の対象も甘えの対象もいない真衣ちゃんは、ずっと、中途半端な赤ちゃん返りの状態に置かれていた。下の子を苛めることもできず、お母様にすがりつくこともできないで。でも、今は私がいるのよ。私というママがいるのよ。ママに幾ら甘えてもいいのよ。ママは、赤ちゃんみたいに甘えてくれる真衣ちゃんのことが可愛くてたまらないんだから。甘えて甘えて、それで、胸の中のもやもやを消しちゃえばいいのよ」 美幸のはだけたブラウスの胸元からブラジャーが見えた。 「だけど、急にそんなこと言われても、簡単じゃないわよね。欲求の赴くまま赤ちゃんみたいに振る舞っていいのよって言われても、理性や恥ずかしさが邪魔しちゃうわよね。でも、それじゃ、いつまで経っても中途半端な赤ちゃん返りのままいなきゃいけないってことになっちゃうのよ。いつまでも精神的な昇華が訪れないの。――だから、私がきっかけを作ってあげる。真衣ちゃんがどんなに恥ずかしがっても、ママが真衣ちゃんを無理矢理にでも赤ちゃん扱いしてあげる。徹底的に赤ちゃん扱いして、思いきり甘えさせてあげる」 美幸が着けているのは、普通のブラジャーではなく、クロスオープンタイプの授乳用ブラだった。 「だから、おむつなのよ。これからずっと、真衣ちゃんは、お家の中にいる時はおむつの中におしっこをするのよ。おねむの時のおねしょだけじゃなく、おっきの時もおむつにおしっこなのよ。だって、真衣ちゃんは赤ちゃんだもの。まだ当分おむつ離れできない赤ちゃんだもの」 美幸は授乳用ブラの右側のカップを下にずらした。 「とはいっても、おねしょとは違って、おっきしている間におむつを汚すのって難しいわよね? おねしょだったら知らないうちに出ちゃうからいいけど、おっきしている時は出ちゃいそうなのがわかるから、ついつい我慢しちゃうわよね。いくら我慢しても最後はとうとう出ちゃうのがわかっていても、でも、我慢しちゃうよね。だけど、おしっこを我慢しすぎるのって体に毒なのよ。だから、いつまでも我慢してちゃいけないの。――真衣ちゃん、ママのおっぱいをちゅぱちゅぱしながらおねしょしちっゃたよね? だから、今もママのおっぱいを吸わせてあげる。ママのおっぱいを吸って気分が穏やかになったら体から余計な力も抜けておしっこが出やすくなるわよ。だから、さ」 美幸は、形のいい乳房を前に突き出すようにして両腕を広げた。 思わず後ずさる真衣。 だが、目の前に立ちはだかる美幸に気圧されて、それまでも知らず知らずのうちに僅かずつ身を退いていたのだろう、いつのまにか背後にはベッドがあった。 しかし、それにも気づかないまま更に後退する真衣。 と、ベッドの角が真衣の膝の内側に当たり、そのまま、へなへなとへたりこむようにしてベッドに端に腰をおろしてしまう。 その瞬間、真衣の唇が半開きになり、どこを見ているのか、目が虚ろに泳ぐ。 それを見逃す美幸ではなかった。 「お出かけの時みたいにちびっちゃった?」 右の乳房をあらわにしたまま美幸は真衣と並んでベッドに座り、さもそうするのが当たり前と言わんばかりの口調で問いかけた。 「……」 「わかっているわよ。お利口さんの真衣ちゃんは、おしっこがみんな出ちゃわないように、無理しておもらしを途中で止めたのよね? でも、そんなことばかりしてちゃ体によくないのよ。お出かけの時はパンツだったし、みんなに見られちゃうから途中で止めなきゃいけなかったけど、今はおむつだし、一緒にいるのはママだけ。だから、出しちゃっていいのよ。出しちゃっても、ベッドも床も平気なの。だって、おしっこが漏れちゃうパンツじゃなくて、今はおむつだもの。お家の中にいる時はおむつだもの」 美幸は、レモンイエローのオーバーパンツの上から真衣の股間をぽんと叩いてから、再び両腕を広げ、真衣の体を抱きすくめた。 「でも、出ちゃわないよう、ついつい我慢しちゃうのね。だから、ママのおっぱいをちゅぱちゅぱすればいいのよ。おねしょの時みたいに、ママのおっぱいを吸いながらおしっこを出しちゃえばいいのよ」 美幸の腕から逃れようと身をよじるたび体に余分な力が入って、却っておしっこが止められなくなってしまう。 遂に真衣は、美幸のなすがまま、豊かな髻に顔を埋め、ぴんと勃った乳首に唇を押し当てさせられてしまった。 「いいのよ、それで。さ、たっぷり吸いなさい。真衣ちゃんだけのおっぱいなんだから、遠慮なんてしなくていいのよ。下の子と取り合いなんてしなくていい、真衣ちゃんだけのママのおっぱいなんだから」 美幸は半ば強引に自分の乳首を咥えさせ、真衣の背中をとんとんと叩いた。 「んむ……」 豊かな乳房に鼻を押さえつけられ、ピンクの乳首を口にふくまされた真衣の唇が躊躇いがちに動き始める。 「ママのおっぱい、上手に吸えるかな。でも、最初は上手じゃなくてもいいのよ。何度も何度も、これからずっと吸っているうちに上手になるんだから。上手におっぱいを吸えるようになって、おっぱいを吸いながらおむつにおしっこをできるようになるんだから」 美幸は、真衣の背中を叩いていた手をそろりと下におろし、今度はオーバーパンツと紙おむつ越しにお尻をリズミカルに叩き始めた。 「今、真衣ちゃんのお尻を優しく包んでいるのは何かな? パンツ? それとも……」 「……お、おむつ。おむつだよ、ママ」 美幸の甘ったるい囁き声に、真衣は乳首を咥えたままのため少しくぐもった声でおずおずと応えた。 「そうね、おむつね。真衣ちゃんのお尻を包んでいるのはおむつなのよ。だって、真衣ちゃんは一人でトイレへ行けない赤ちゃんなんだもの。お出かけの時はお姉ちゃんぶってパンツを穿くけど、そのパンツもすぐおしっこで濡らしちゃう赤ちゃんだもの。パンツのお姉ちゃんになれるのはまだまだの、おむつの赤ちゃんだもの」 美幸は、お尻を叩くのをやめ、掌を真衣の股間にそっと押し当てた。 それまではなんとか途中で止めようとしていたのを、とうとう諦めたのだろう、職業柄きわめて敏感な美幸の指先の神経は、オーバーパンツと紙おむつ越しながら、真衣の恥ずかしい部分から迸り出て紙おむつの内側に広がってゆく生温かい液体の流れをはっきり感じ取った。 「それじゃ、念のために聞いておくわね。真衣ちゃん、お出かけの時は何を穿くのかな?」 紙おむつの内側に広がるおしっこの流れをオーバーパンツの上から指先でそっとなぞりながら、美幸は真衣の耳元に囁きかけた。 「お出かけの時はパンツ。真衣、お出かけの時はパンツだよ」 「そうね、お出かけの時はパンツね。でも、普通のパンツだとすぐにおしっこが漏れちゃうから、ママが用意してあげたトレーニングパンツを穿くのよ。お出かけの時はトレーニングパンツ。わかったわね? ――じゃ、お家いる時は?」 「……お家にいる時はおむつだよ。真衣、お家にいる時はおむつなの」 一瞬の間はあったものの、虚ろな瞳で真衣は答えた。 「そうよ、お家にいる時はおむつなのよ。真衣ちゃんはママのおっぱいを吸いながらおしっこをしちゃう赤ちゃんだもの。ずっとずっとおむつの外れない赤ちゃんだものね」 美幸は、右手でおしっこの様子を探りながら、左手で真衣の髪をそっと撫でつけた。 |
|
|
|
|
|
|
| 戻る | 目次に戻る | 本棚に戻る | ホームに戻る | 続き |