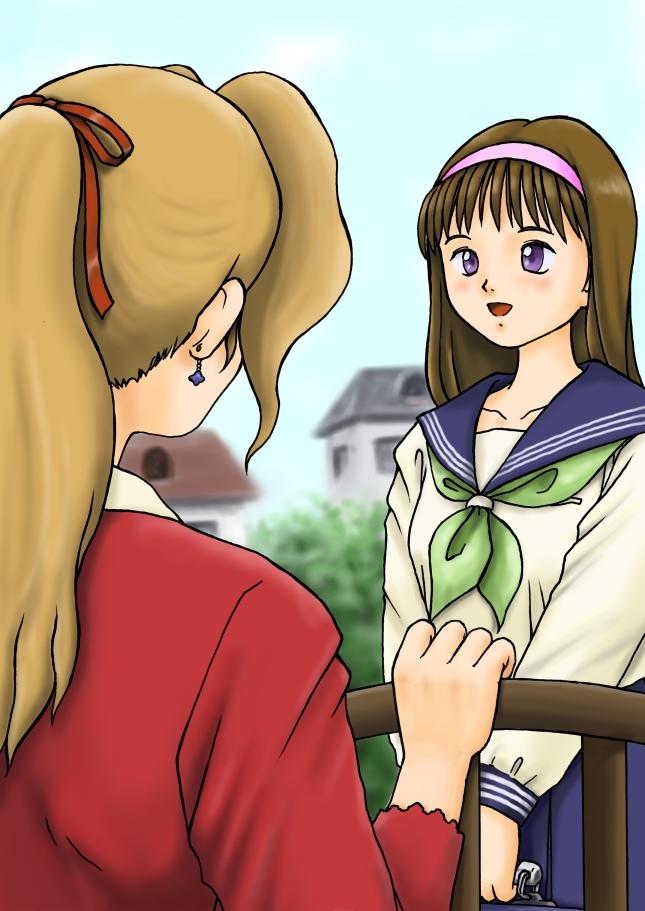ママは私だけの校医さん
|
《13 幼なじみ、親友、そして……》 「ありがとう。私のこと、そんなふうに思ってくれて、とても嬉しいわ。杉下さん、大学は医学部志望なの?」 美幸は、緊張のあまり声を震わて喋り続ける美沙の言葉をやんわり遮って優しく問いかけた。 「い、いいえ。私は小さな子供が好きだから、保育園か幼稚園の先生になりたいんです。ただ、お医者様にしても、幼稚園の先生にしても、お休みの日でもいざとなれば仕事場へ行かなきゃいけないこともあるし、厳しさと優しさを両立させなきゃやってけない仕事だし、共通するところが多いと思うんです。だから……」 「うふふ。そう言ってもらえると悪い気はしないわね。いいわ、真衣ちゃんのことも気になるでしょうし、お家の中でいろいろ話しましょう」 美幸は意味ありげに笑って言い、緊張しきりの美沙の手を取ると、背中を押して家の中に招き入れた。 それこそ生まれたての赤ん坊の頃から数え切れないほど訪れて慣れ親しみ、自分の家も同然の佐藤家。それでも、憧れの美幸と一緒だと思うと表情がこわばり、足の運びもぎこちなくなってしまう。 そんな美沙の緊張が解けたのは、リビングルームに敷いた布団の上で安らかな寝息をたてている真衣の寝顔を目にしてすぐのことだった。 「よかった、思っていたよりひどくないみたい。急な発熱で欠席って担任の先生から聞いた時はびっくりしちゃったけど、この様子だとあまり悪くないのかな。そうなんですよね、先生? 真衣、じきによくなりますよね?」 真衣の寝息が思ったよりも荒くないのに加え、さほど苦しそうな表情も浮かべていないことに安堵の溜息をつきながら、美沙は美幸に尋ねた。が、すぐにはっとしたような表情で言い直す。 「あ、すいません。真衣じゃなくて、真衣さんですよね。つい、いつもの呼び方が出ちゃって」 「いいわよ、そんなこと気にしなくても。私も学生の時は仲のいい友だちとは『さん』も『ちゃん』も付けないで名前を呼び合っていたんだから。それに、私なんかより杉下さんの方が真衣ちゃんとはずっとつき合いが長いんだから、私がいるからって気にしないで、呼び慣れた呼び方をしてちょうだい」 恐縮顔の美沙に、取りなすように美幸は言った。 「あ、はい、ありがとうございます。そう言ってもらえると助かります。これまでずっと『真衣』『美沙』ってお互いに呼んでいたのに、『真衣さん』なんて他人行儀で、私としても妙な気分で落ち着かないんです。じゃ、遠慮しないで名前だけで呼ばせてもらいますね」 美沙の顔がぱっと輝いた。 「ええ、どうぞ。ついでだから、私も、『ですます』調の堅苦しい話し方は遠慮させてもらうわよ。だから、美沙さんも、私のこと、昔からの知り合いだと思って気軽に接してくれないかな。すぐには無理かもしれないけど、私のこと、真衣ちゃんの本当のお母さんだと思ってくれると嬉しいんだけどな」 美幸は美沙の緊張を更にほぐすようにおだやかな笑顔で言った。 「え!? 憧れの鈴木先生のこと、そんな……ううん、でも、わかりました。先生の方からそんなふうに言ってもらえて、とっても嬉しいです。だから、先生の言う通りに頑張ってみます、私」 「ほらほら、言ってる端から『わかりました』とか『頑張ります』って堅苦しい言い方しちゃって。もっとリラックスしていいのよ、美沙ちゃん」 美幸は少し冗談めかして言った。 「あ――う、うん、わかった。じゃ、じゃ、真衣のお母さん、真衣、すぐによくなるよね? 熱なんてじきに下がるよね?」 美沙は、『杉下さん』ではなく『美沙ちゃん』と呼ばれたことに頬を赤く染めながら、それでも満更でもなさそうな顔をして再び美幸に尋ねた。 「うん、あまり時間はかからないわよ。三日間くらいは学校を欠席しなきゃいけないと思うけど、いったん熱が下がり始めたらすぐ平熱に戻ると思うから心配しないでちょうだい。一応、医師としての見立てだから間違いないわ」 美幸は、直腸検温の結果と、自分が投与した薬剤の効用を頭の中で思い浮かべながら軽く頷いてみせ、さりげない口調で美沙に訊き返した。 「ところで、二人はいつごろから名前だけで呼び合うようになったの? 幼稚園の頃から? それとも、最近になってから?」 「えーと、たしか、中学校に入る前くらいからだったかな。小さい頃は真衣が私のことを『美沙ちゃん』って呼んで、私は真衣のことを『真衣お姉ちゃん』って呼んでたんだけど、小学校の三年生くらいからお互いに『ちゃん』付けで呼ぶようになって、その後……あ、そうだ。小学校の高学年になって二人とも初めての生理が来て、それから、なんとなくお互いに名前だけで呼び合うようになったんだっけ。うん、そうよ、たしか、初めての生理がきっかけだったんだわ 美沙は、最初は考え考えしながら、けれど最後の方は自信たっぷりに答えた。 「ふぅん、そうなんだ。でも、三年生になるまで美沙ちゃんが真衣ちゃんのことを『真衣お姉ちゃん』って呼んでいたのはどうしてなの? 同じ学年の同い年なのに」 美幸はわざと不思議そうな顔をして重ねて訊いた。 「あ、そのことだったら、私たち、厳密に言うと同い年じゃないんだ。真衣は4月十日生まれで、私は翌年の三月二五日だから、学年は同じでも、丸一年近く誕生日が離れてるの。大きくなったら一年くらいの差はどうでもよくなるけど、小さい頃はそんなわけにもいかなくて、体も真衣の方がずっと大きかったから、ついつい真衣ったら私のことを妹扱いして、逆に私は真衣のことをお姉ちゃんみたいに思ってて、それで」 美沙は昔のことを懐かしむようにふっと目を細くして説明した。 「そうだったの。でも、三年生くらいになると両方とも『ちゃん』付けになったのよね?」 美幸は念を押すように言った。 「うん。生まれたのは真衣の方が早かったんだけど、その後の成長は私の方が早くて、小三の夏休み明けには身長も体重も負けないようになって、それで私が真衣のことを『真衣ちゃん』って呼ぶようになったの。それまでは冗談でも私がそんな呼び方をしたら真衣ったら嫌な顔をしてたんだけど、その時からは何も言わなくなって。あと、私に年の離れた妹ができたのもその頃で、それで私、なんとなく、お姉ちゃんとしての自覚みたいなものを感じるようになって、そのことも影響していたんだと思う。それに、うちは父も母も体が大きい方だから、私もその血をひいたのか、私の体の大きさが真衣に追いついてからは今度は逆に私の方がどんどん大きくなっちゃって、それで真衣もますます何も言えなくなったみたい」 美沙は僅かに首をかしげ応じた。 自分でも言うように、確かに美沙は体が大きい。身長は百七十センチを優に超えているのが一目でわかるほどだし、胸の発育ぶりも美幸と負けず劣らずだ。それに対して、真衣の身長は百五十センチあるかないかといったところだろうか。 「そうだったの。そういうことだったのね、美沙ちゃんと真衣ちゃんの仲は」 美幸は、寝息をたてている真衣の顔と美沙の顔とを交互に見比べて独り言のように呟くと、どこか探るような口調で言った。 「だったら、逆に真衣ちゃんから『美沙お姉ちゃん』って呼んでもらいたとか思ったことなかった? 特に、体の大きさが逆転してすぐの頃とか、それまでの反動でそんなふうに思う時期があったんじゃない?」 「それは……」 美沙は一瞬、困ったような顔になったが、目の前で眠っている真衣の年齢のわりにはあどけない寝顔をちらと見て、ぽつりと言った。 「あるよ。それまでいつも私が妹扱いで、でも、いつのまにか私の方が大きくなって、初めて生理が来たのだって私の方が半年ほど早くて、真衣に生理が来た時、相談に乗ってあげて――その時、なんだか真衣のことが妹みたいに思えて。そりゃ真衣の方が一年近く早く生まれたのは確かだけど、それでもって思ったことは何度かあるよ。そんなことを実際に言ったら、何バカなこと言ってるのよって嘲笑われそうだから、私のことを『美沙お姉ちゃん』って呼んでみてって口にしたことはないけど、でも、そんな言葉が喉まで出かかったことは何度かあるよ」 「やっぱりね。そんなふうに思うことってあるのよね、特に子供の頃は。真衣ちゃんが偉そうにしていたわけじゃなく、あれこれ煩わしく指図していたわけじゃなく。それに、美沙ちゃんが仕返しをしてやろうだなんて思うわけじゃなく。なのに、美沙ちゃんが真衣ちゃんのことを妹扱いしてみたくなったことがあるっていうのは私にもわかるわよ」 美沙の返答に美幸は納得顔で頷き、冗談とも本気ともつかない声で言った。 「だから、子供の頃にかなわなかったことを今やってみたらどうかな? 今から真衣ちゃんを妹扱いしてみたいと思わない?」 「え……?」 美沙はきょとんとした表情を浮かべて言葉に詰まった。 「あれ、何だと思う?」 美幸は部屋の一角を指差した。二人が並んで座っている場所からいうと、横になっている真衣の体のちょっと向こうあたりだ。 「脱衣籠だよね? それで、中に入っているのは……!」 美幸が指差す方を怪訝な顔で見た美沙は、そこにあるのが脱衣籠だと気づくと、脱衣籠に何が入っているのか確認するために目を凝らしたきり言葉を失い、見てはいけない物を見てしまったかのように慌てて顔をそむけた。 だが、完全に視線をそらしたわけではなく、顔はそっぽを向きながらも目だけを動かして、ちらちらと脱衣籠の中を窺い続けているのを美幸は見逃さない。 「中に入っているのは何だと思う? 体の大きな子だなっていう印象が強かったから、健康診断の時に会った美沙ちゃんのことはよく憶えているんだけど、視力も良かった筈よね」 美幸は微かに笑いを含んだ声で、脱衣籠に何が入っているか美沙にはわかっている筈だと確信しているのが明かな口調で言った。 「あ、あの……」 しかし、美沙は口ごもるばかりだ。 「じゃ、これを見ればわかるかな」 美幸は美沙の狼狽えぶりを面白そうに眺めながら、真衣の体にかかっている毛布をぱっと捲り取った。 「……!」 はっと息を飲み、顔をそむけることも忘れて大きく見開いた美沙の目が、真衣の下腹部に釘付けになった。 「お腹が冷えるといけないからオーバーパンツを穿かせてあげているのよ」 美幸は短く言ってから、改めて脱衣籠を指差した。 「あのバスケットに何枚も入っているのと同じオーバーパンツをね」 美沙はのろのろと視線を動かして脱衣籠を見、再び真衣の下腹部に目をやった。 「もちろん、オーバーパンツの下も、当然、あのバスケットに入っているのと同じ物よ。ほら、この通り」 美幸は、美沙が真衣の下腹部に目を向け直すのを待って、オーバーパンツを膝の上まで引きおろした。 それに対して美沙は無言のままだったが、脱衣籠に何枚か収めてあるのと同じニットのオーバーパンツを真衣が穿いているのを見て、その下に何を着用しているのかおよその見当がついていたのだろう、ついさっきのような驚いた様子はみせなかった。 「……真衣の具合、そんなに悪いの? 自分でトイレも行けないくらい容態がひどいの?」 しばらく沈黙が続いた後、何度か浅い呼吸を繰り返してから美沙が言った。 「そうね、急な発熱があって、なるべく苦しまないよう鎮静剤で眠らせているわけだから、自分でトイレへ行けないっていうのは本当ね。昨夜から今朝にかけては熱も高いままだったから、容態もあまりよくなかったと言っていいわね」 美幸は、膝のすぐ上まで引きおろした真衣のオーバーパンツを再び穿かせようともしないで言い、すぐ横に座っている美沙の方にゆっくり振り向いて続けた。 「でも、真衣ちゃんのおむつはそれよりもずっと前からなのよ。オーバーパンツは、お腹が冷えないようにって、私がこのお家に来てから穿かせてあげるようにしたんだけど、おむつは、私が来る前からなのよ――」 美幸はこれまでの経緯を全て説明した。入試が負担になって体調を崩したこと。それと同時におねしょが始まったこと。けれど、体調を崩したのは単なるきっかけで、おねしょの本当の原因は他にあったこと。その真の原因というのが、真衣の心の中にひそむ或る願望だったということ。そうして、その願望のせいで真衣が無意識のうちに赤ちゃん返りしてしまっていること。 自分が胸の中にひそませている妖しい欲望のことだけは巧みに隠しおおしつつ、真衣が一番の親友である美沙にさえ告げられないでいた諸々の事情を、時には偽りの事柄も取り混ぜつつ美幸は説明した。 「――というわけで、真衣ちゃんはすっかり赤ちゃんになっちゃってるの。だから、パンツじゃなくておむつだし、ほら、こんなことまでしちゃうのよ」 美沙が無言のままなのをいいことに話が自分に都合よく進むよう慎重に言葉を選んで経緯を説明し終わった美幸は、掛時計をちらと見上げて頃合いを図ると、真衣の横に寝そべって自分の胸元をはだけ、手慣れた様子でブラのカップをずりおろし、後頭部を右手の掌で包み込むようにして真衣の顔を抱き寄せた。 「……!?」 思ってもみなかった美幸の行動に、美沙が自分の口を両手で覆い、声にならない驚きの声をあげた。 が、美幸はそんなことまるで気にするふうもなく、あらわになった自分の乳首を真衣の唇に押し当てる。 美沙が体を固くして凝視する中、真衣の唇がおずおずと動き出したかと思うと、いつしか、空腹に耐えかねて母親の乳房にむしゃぶりつく赤ん坊さながら、美幸の豊かな乳房に顔を埋めて唇と頬を大きく膨らませてはすぼめるといった動きをリズミカルに繰り返すようになっていた。 「わかったでしょう? 真衣ちゃんはもうすっかり赤ちゃんなのよ。ママのおっぱいが恋しくてたまらない赤ちゃんなのよ」 真衣に乳首を吸わせたまま、美幸は、どこか勝ち誇ったようにも聞こえる口調で美沙に言った。 そうして、真衣の顔にとろんとした表情が浮かぶのを見て取ると、薄く笑って言葉を続ける。 「股ぐりから指を突っ込んで、おむつの中がどんなふうになっているか調べてごらんなさい。そうすれば、真衣ちゃんが赤ちゃんなっちゃったっていうのが本当のことだってわかる筈だから」 「え……? お、おむつの中に!?」 美沙はびくんと肩を震わせて聞き返した。 「そう、おむつの中の様子を調べるのよ。真衣ちゃんとは姉妹同然に育った美沙ちゃんだもの、できないわけないわよね」 美幸は医師としての威厳をいかんなく発揮し、有無を言わさぬ調子で決めつけた。 「あ、はい……」 憧れの的である美幸からそんなふうに言われて拒否できるわけがない。美沙は一瞬は躊躇いの表情を浮かべたものの、大きく息を吸い込むと、決意を固めたのが明かな顔つきになって、真衣の下腹部のそばへにじり寄った。 「そこでいいわ。そこから手を伸ばせばすぐだから」 真衣への『授乳』を続けながら横目で様子を窺っていた美幸は、そう言って美沙を促した。 美沙はもういちど息を吸ってから、おそるおそる右手を伸ばし、股ぐりのギャザーを押し広げるようにして人差し指と中指を紙おむつの中に差し入れた。 途端に 「ぬ、濡れてる。おむつの中、濡れちゃってる」 という、驚きの声が美沙の口を衝いて出た。しかし、言葉はそれだけではなかった。美沙は続けて 「あ、あの、まだ濡れ方がひどくなってる。最初はじっとりしてるだけだったのに、びしょびしょになってきて、あの……」 と戸惑いを隠せない表情で呻き、助けを求めるように美幸の顔を見つめた。 「そうよ、何度も言うけど、真衣ちゃんは赤ちゃんになっちゃったのよ。ママのおっぱいを吸いながらおしっこでおむつを汚しちゃう赤ちゃんになっちゃったのよ。だから、美沙ちゃんには真衣ちゃんのお姉ちゃんになってもらいたいの」 困惑の表情を浮かべる美沙とは対照的に、穏やかな笑顔で美幸は言ってのけた。 「ずっとというのは難しいでしょうけど、真衣ちゃんのお父様が帰ってくるまでの間だけでも真衣ちゃんのお姉ちゃんになってもらいたいの。このお家にやって来てまだ間のない私を助けてほしいのよ。小っちゃい頃から真衣ちゃんのことを知っていて、今も真衣ちゃんとは大の仲良しで、学校も同じクラスで、このお家のこともよく知っている美沙ちゃんの他に、こんなことを頼める人なんていないの。だから、お願い。赤ちゃん返りしちゃった真衣ちゃんのお姉ちゃんになってあげてちょうだい」 美沙は、指先から伝わるじっとり湿っぽい感触と共に美幸の言葉が自分の心の奥底にじわじわ染みこんでくるのを感じて、ぞくりと身を震わせずにはいられなかった。 |
|
|
|
|
|
|
| 戻る | 目次に戻る | 本棚に戻る | ホームに戻る | 続き |