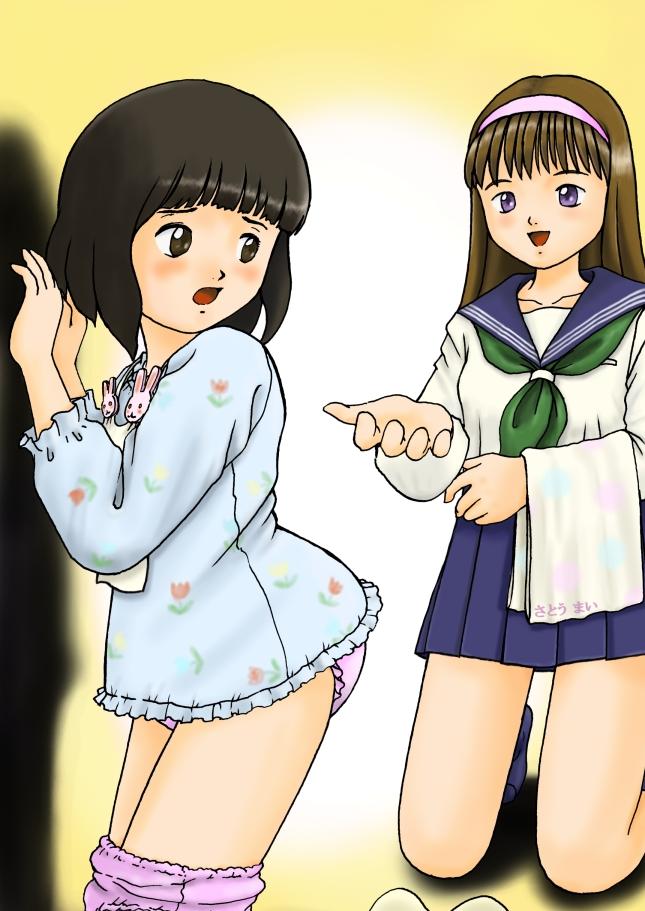|
《14 新たな家族》
美幸と美沙が見守る中、哺乳壜が殆ど空になり、それまで顔をこわばらせていた真衣の表情が緩んで、目つきがとろんとしてくる。
真衣の表情の変化に気づいた二人が互いに目配せを交わし合ったかと思うと、美沙が軽く頷いて、横抱きにされた真衣の体から滑り落ちそうになっている毛布を捲り取って部屋の隅に移し、オーバーパンツの股ぐりを押し広げて右手の指を紙おむつの中に差し入れた。真衣は弱々しく身をよじるのだが、まだ効き目の続いている薬剤のせいで手足の自由が戻っていない上、美幸に抱きすくめられているため、美沙の手から逃れることはできない。
「どう?」
美幸は、今やそれだけで二人の意志が通じるのだということを真衣に対して誇示するために、わざと短く美沙に訊いた。
「思った通りよ、ママ」
美沙の方も簡潔この上ない応え方をしたが、それが何を意味しているのか、二人だけでなく、真衣自身にも痛いほどわかっていた。美沙が口にした『思った通りよ』のあとに続くのは『おむつの中はぐっしょりだわ』という言葉しかない。
「おねむの間はママのおっぱいを吸いながらおねしょをしちゃうし、おっきの時は哺乳壜のミルクを飲みながらおもらしでおむつを汚しちゃうなんて、本当に赤ちゃんになっちゃったんだね、真衣ちゃんは」
おむつの中から引き抜いた指をウェットティッシュで拭きながら、美沙が呟いた。
「そうよ、真衣ちゃんは赤ちゃんになっちゃったのよ。それも、普通の赤ちゃんに比べれば、うんと体の大きな赤ちゃんに。こんなに大きな赤ちゃんのお世話、ママ一人じゃ大変だから、美沙もしっかり手伝ってね。だって、美沙は真衣ちゃんのしっかり者のお姉ちゃんなんだから」
美幸は、それまで自分の胸元まで抱え上げていた真衣の頭を太腿の上に戻し、哺乳壜の乳首を咥えさせたまま美沙に向かって軽く頷いてみせた後、真衣の顔を真上から見おろして言った。
「それじゃ、美沙お姉ちゃんにおむつを取り替えてもらいましょうね。美沙お姉ちゃん、真衣ちゃんがねんねしている間も何度もおむつを取り替えてくれたのよ。だから真衣ちゃんは何も心配しないで、みんなお姉ちゃんにまかせておけばいいの。おむつを取り替えてもらう間、お口が寂しいと可哀想だから、哺乳壜はこのままにしておいてあげる。哺乳壜をちゅうちゅうしている間におむつを取り替えてもらおうね」
「い、いや……美沙におむつを取り替えられるなんて、そんなの、いやぁ!」
自由にならない首を力なく振って真衣は訴えかけた。しかし、唇も喉も薬剤の効果で力が入らないため、叫んだり喚いたりすることはかなわない。
「何を言ってるの、真衣ちゃんたら。お姉ちゃんのことを『美沙』だなんて呼び方しちゃ駄目じゃない。それに、ほらほら、そんなに暴れるからミルクがこぼれちゃって。真衣ちゃんはずっとおねむだったから憶えてないでしょうけど、美沙お姉ちゃんには、二日前の夕方にお見舞いに来てくれた時から何度もおむつを取り替えてもらっているのよ。それに、哺乳壜でミルクを飲ませてもらったこともあるし。ママも忙しいから大助かりだったわ。それで、いろいろ相談して――」
力ない動作ながらも真衣が首を振ったせいで哺乳壜が口から離れ、僅かに残っていたミルクの雫が三つ四つ唇の下に滴り落ちる。その雫を簡易よだれかけの端で拭きながら美幸は、月曜日の夕方に美沙と交わしたやり取りの内容を手短に話して聞かせた。
「――ということで、早速その日のうちに美沙お姉ちゃんは自分のお母様と話し合って、真衣ちゃんのお父様が出張の間、このお家に泊まり込みでママのお手伝いをしてもいいわよっていうお許しをいただいてくれたのよ。ええ、話し合いがスムーズに進むよう、ママも美沙お姉ちゃんのお母様には電話でいろいろお願いしたわよ。啓明女学院の校医として、真衣ちゃんの主治医として、そして、真衣ちゃんの新しいママとして。だから、遠慮なんていらないの。美沙お姉ちゃんのことを本当のお姉ちゃんだと思って甘えればいいのよ。わかるでしょ? 真衣ちゃんには新しい家族ができたのよ。新しいママと、新しいお姉ちゃんが」
美幸は優しく言って聞かせるようにそう説明して、改めて美沙に向かって目配せをした。
「お母さん、美幸ママと私の話を聞いて、ちょっと迷ったみたい。でも、迷ったけど、結局は『美沙も真衣ちゃんのお世話をしてあげなさい。困ったことがあったら母さんも手伝ってあげるから、新しいママと一緒に真衣ちゃんの面倒をみてあげなさい。ただし、中途半端はいけないわよ。真衣ちゃんのお家にいる間は真衣ちゃんのことを本当の妹だと思って可愛がってあげなさい。それと、真衣ちゃんの新しいママのことも自分の本当のママだと思って言いつけを守りなさい』って言ってくれたの。それで、昨日、お家に帰ってすぐ荷物をまとめて宅配便でここに送っておいたの。教科書も教材も着替えも、なにもかも。だから、今日からここが私のお家なのよ。でもって、真衣ちゃんが私の小っちゃな妹で、美幸ママが真衣ちゃんと私のママ」
美沙は美幸に対して軽く頷いてから、美幸と同じように真衣の顔を見おろして言った。
「美沙お姉ちゃんは保育園か幼稚園の先生になりたいそうだし、学校じゃ家庭科クラブに入っているんだそうね。偶然とは言え、本当、赤ちゃんの面倒をみてもらうには打って付けだわ」
美沙の言葉を受けて、美幸がそんなふうに付け加えた。
しかし、美沙が真衣の『お姉ちゃん兼お世話係』を引き受けたのは、決して偶然のたまものなどではなかった。歪んだ母性本能に操られるまま育児の真似事を楽しむために真衣を自分の赤ん坊に変貌させてしまうという企みを実行に移すにあたって、美幸は、校医としての立場を存分に活用して、真衣の友人関係を慎重にに調べたのだが、そこで目をつけたのが美沙だった。むろん、企みをなるべく円滑に進めるための協力者に仕立てるためだ。そして、目をつけた美沙の性格と家庭環境、周囲の人間関係や真衣との幼い頃からの間柄などを更に徹底的に調べ上げた美幸は、真衣が体調を崩して学校を休みでもしたら美沙がその日のうちに見舞いに駆けつけるに違いないという確信を抱くに至り、その好機を逃さないよう入念に計画を練り、真衣の幼なじみであり一番の親友である美沙をまんまと自分の企みに引き入れることに成功したというわけだ。
だが、美沙にしてみれば、美幸の妖しい企みを手助けする立場に自分が置かれたという自覚はまるでない。幼い頃は姉ぶっていた真衣のことを今度は逆に小さな妹扱いしてみるのも面白いかなというちょっとした悪戯心がきっかけになって、気がつけば佐藤家に住み込んで真衣の面倒をみることになったものの、そんな状況についても、さほど奇異に感じることもなく、滅多に経験できないちょっと刺激的な遊びくらいにしか思っていない。それは、あまり細かいことを気にしない美沙の性格のためということもあるが、美幸の誘い込みがそれほどまでに巧みだったせいとも言える。
「さ、お話はこのくらいにして、美沙お姉ちゃんにおむつを取り替えてもらおうね。いつまでも濡れたおむつのままだとまた熱が出てくるかもしれないし、それに、おむつかぶれがひどくなっちゃうから」
美幸は、真衣の顔を覗き込んでいる美沙の横顔をちらと見て満足げに微笑み、わざと優しい声で言った。
「え? 真衣ちゃん、やっばり、おむつかぶれになっちゃったの?」
美幸に向かって美沙が確認するように聞き返した。驚いたような様子はまるでなく、『やっぱり』と、まるで、そうなることを予想していたような口ぶりだ。
「ええ、そうなのよ。二日前、美沙が初めておむつを取り替えてくれた時、真衣ちゃんのあそこ、うっすらと赤くなっていたわよね。それで、ひょっとしたらおむつかぶれになりかけているんじゃないかなって二人で話したけど、心配通りになっちゃって」
美幸はわざとらしく眉をひそめてそう応じた。その口調が少しばかり説明くさいのは真衣に聞かせるためだろう。
「ふぅん、そうなんだ」
それまで床に手をついて真衣の顔を覗き込んでいた美沙が、きちんと座り直して僅かに顔を曇らせた。
だが、すぐに思い直したようににこやかな笑みを浮かべて、リビングルームに入る時に入り口のすぐそばに通学鞄と一緒に置いた二つの大きな紙袋のうちの一つを手元に引き寄せて明るい声で言った。
「だったら、やっばり、これが役にたちそうだね。一昨日も昨日も、家に帰ってすぐミシンを独り占めにしてちゃんとしてきたんだよ。全部仕上がったのが昨夜の夜中だったから、他の荷物と一緒に宅配便で送れなくて、いったん学校まで持って行っちゃった」
「ああ、なんだか大きな紙袋を二つも持っているから何かと思っていたんだけど、そういうことだったの。でも、袋の中、誰かに見られなかった? もしも見られたりしたら、変に思われちゃうんじゃないの?」
美幸は、美沙が紙袋の中をまさぐる様子を眺めながら、どこか悪戯っぽく笑って言った。
「ううん、それは大丈夫。目立つ荷物だから同じクラスの子の何人かに見られたけど、家庭科クラブ恒例のボランティア行事に使うのって説明したら簡単に納得しちゃったから。うちの家庭科クラブ、毎年、春と秋に県内の介護施設とかに部員が作ったいろいろな物を寄付するのが恒例になってるんだけど、この春は児童養護施設と託児所が寄付先になっているの。そこへ贈る物だよって言ったら、みんな納得しちゃった。ま、そうだよね。こんな物、そんな理由でもなきゃわざわざ学校へ持って来る人なんていないよね」
美沙は軽くかぶりを振ると、紙袋の中に差し入れていた右手をそっと引き戻し、紙袋から取り出したばかりの『こんな物』を真衣の目の前でひらひら振ってみせた。
「あ……」
真衣は一瞬、それが何なのかわからなかった。だが、じきに、美沙が目の前で振っている布地の正体に気づき、大きく目を見張って唇を震わせた。
「ま、確かにそうかもね」
美幸がくすっと笑って肩をひょいとすくめてみせた。
「そういうこと。ただ、端っこの刺繍まで見られていたら私も説明のしようがなかったけど」
大きな瞳をくるりとさせて、美沙もくすりと笑った。
「そりゃそうよね。おむつに刺繍してある名前まで見られたりしたら、どう説明していいか、美沙じゃなくても困っちゃうわよね。でも、誰もそこまで気がつかなかったんでしょ? だったら、それでいいじゃない」
美幸は美沙から布地を受け取ると、それを両手で広げ、その端にピンクの糸で刺繍してある『さとうまい』という文字を真衣の目の前でわざとゆっくり指でなぞってみせた。
そう、美沙が紙袋にぎっしり詰め込んで持ってきたのは、水玉模様や動物柄の布おむつだった。それも、ご丁寧に真衣の名前の刺繍を施した布おむつ。
「ど、どうして……」
真衣は、自分の名前が平仮名で刺繍してある水玉模様の布おむつから目をそむけ、唇を噛んだ。
「真衣ちゃんのおむつかぶれがこれ以上ひどくならないようによ。そのためにわざわざ美沙お姉ちゃんが用意してくれたんだから」
呻き声をあげる真衣に向かって、美幸はしれっとした顔で言った。
「二日前、真衣ちゃんがおむつかぶれになりかけていることに気がついた私たちはいろいろ相談したんだけど、おしっこをしてなくても汗で蒸れることもあるから、こまめにおむつを取り替えてあげるのが一番だということになったの。でも、紙おむつだと、もともと吸水性がいいから、おしっこをしちゃっても少しの間くらいならいいかなって、ついそのままにしちゃう心配があるのよね。現に、私がこのお家に来るまでは、夜中におねしょで紙おむつを汚しちゃっても、真衣ちゃん自身がそれに気がつかなくて朝までぐっすりだったんだもの。それに比べて、布おむつだと、もともと蒸れやすいものだってわかっているから、こちらも気になって、結果として、なるべくこまめに取り替えてあげることになるんじゃないかなっていう結論になったのよ」
「うん、そういうこと。それに、嘘か本当か知らないけど、紙おむつよりも布おむつの方がおむつ離れが早いっていう話もよく聞くしね。だから、私が用意してあげることにしたの。私が赤ちゃんの頃に使っていたおむつは親戚の子にあげちゃったらしいけど、妹が赤ちゃんの時に使っていたのはまだ押し入れの奥にしまってあるのよっていつだったかお母さんが言っていたのを思い出したから、それを使えばいいかなって思って」
美沙が美幸の言葉を引き継いで言い、別の布おむつを紙袋から取り出して続けた。
「でも、妹のお下がりをそのまま使わせるんじゃ真衣ちゃんが可哀想かなと思ったから、私の愛情のシルシとして、おむつに一枚一枚、真衣ちゃんの名前を刺繍してあげることにしたのよ」
美沙はそう言って、美幸がついさっきしてみせたように、布おむつの端に刺繍した真衣の名前を指先でなぞった。
「妹さんは美沙とは十歳違いなんだそうね。だったら、妹さんが赤ちゃんの頃は美沙がおむつを取り替えてあげたこともあったの?」 美幸は、美沙の家族構成も、美沙が家族とどういう生活を送っているのかも熟知していながら、わざとらしい口調で尋ねた。
「うん、あるよ。私が赤ちゃんの時にはもう紙おむつが当たり前になっていたのに、うちのお母さん、布おむつの方が愛情がこもっているような気がするからって妙に意固地になっちゃって、私も妹も布おむつだったんだけど、お母さんがちょっと買い物に出た時とかに妹がおむつを汚しちゃったら、私が取り替えてあげてたの。最初は見様見真似だったけど、回数をこなすうちにどんどん上手になっていって、すぐお母さんに褒められるようになったんだから」
美沙はにこやかな笑顔で応えた。
「だったら、ますます、真衣ちゃんのお世話をまかせても大丈夫ね。それに、これからは、本当の妹さんにあててあげていた布おむつを使うことになるんだから尚更。ね、真衣ちゃんもそう思うでしょう?」
美幸は、簡易よだれかけで覆われた真衣の胸元をぽんぽんと叩いて言った。
その間に美沙の手がすっと伸びてオーバーパンツに指がかかる。
そのことに気づいた真衣が慌てて身をよじるが、なにほどの抵抗ができるものでもない。美沙はオーバーパンツを真衣の膝の上まで手早く引きおろして、あらわになった紙おむつに目をやった。
股間からお尻にかけての吸収帯がおしっこを吸ってぷっくり膨らんでいるのが一目でわかる。
「やだぁ!」
突然、真衣がそれまでになく悲痛な叫び声をあげ、体全体を強引に捻ったかと思うと、あらん限りの力で手足をばたつかせ、布団の上からフローリングの床に転がり出た。
幼なじみで一番の親友である美沙の手でおむつを取り替えられる屈辱に耐えかね、どうしようもなく感情が高ぶっているところへ、ちょうど、筋肉の力を弱める薬の効果が薄れてきたのだろう、それまでの弱々しい抵抗とはいささか異なり、今度こそようやく美幸の手から逃れることができた真衣。
しかし、それで完全に逃げおおせるわけではない。薄れてきたとはいっても薬剤の効果はまだまだ残っている上、体を殆ど動かしていない生活が三日間近くも続いたせいで、本来の手足の筋力も目に見えて落ちているものだから、床に手をついて上半身を起こすのが精一杯という状態だ。
それでも真衣は体を引きずるようにしてリビングルームの入り口へいざり寄ると、必死の思いで伸ばした手でドアのノブをつかみ、膝を床について、そのままじりじりと体を引き上げるようにして立ち上がった。
が、真衣にできるのはここまでだ。
壁に体をもたせかけるようにしておそるおそる足を踏み出したものの、ただでさえ力が入りにくいところに持ってきて、膝の上まで引きおろされたオーバーパンツに脚を絡め取られて、ぐじゅっという鈍い音と共にその場に尻餅をついてしまう。
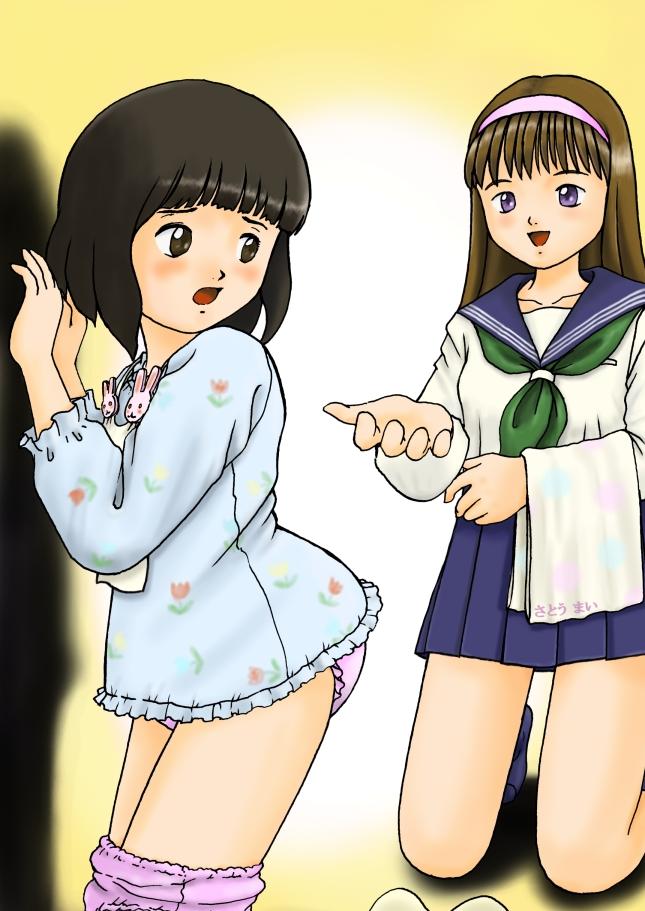
布おむつと違って、紙おむつの場合は、吸収帯の中に仕込んである高分子吸水材がおしっこをゼリー状に固めるため、いったん吸い取られたおしっこが沁み出す心配は少ない。とはいっても、全てのおしっこが吸収帯に吸い取られるわけではなく、幾らかは紙おむつの内側全体を構成する不織布に沁みこむため、或る程度の荷重をかけると、おしっこが逆流して沁み出すことも珍しくない。特に、尻餅をついたような急激な荷重のかけ方だと尚更だ。
真衣の場合も例外ではなかった。
不織布から沁み出たおしっこは、ギャザーからの横漏れになって腿の皮膚を伝い流れ、僅かながら、真衣の脚とフローリングの床をじとっと濡らしてしまう。
「い、いやぁ……」
さっきと比べれば随分と弱々しい悲鳴をあげながら、真衣は、床と腿から伝わってくるじとっと湿っぽい感覚から逃れようとしてお尻を浮かせた。だが、慌てたせいか今度はノブを上手くつかむことができなくて、そのまま前方にゆっくり倒れこみ、両手を床について四つん這いの姿勢になってしまう。
「駄目よ、真衣ちゃん。早く取り替えないとおむつかぶれがひどくなっちゃうってば」
「そうよ。お姉ちゃんがおむつを取り替えてあげるからおとなしくしてようね」
それまで真衣の行動を面白そうに眺めていた美幸と美沙だったが、そろそろいいかなとでもいうように互いに頷き合うと、二人揃って立ち上がり、四つん這いの姿勢でドアに体を擦りつけるようにして身をすくめる真衣に向かって足を踏み出した。
「ゃあ……」
迫ってくる美幸と美沙の手から逃れるため、真衣は、少しは自由に動かせるようになったもののまだまだ力の入らない手足を無理矢理動かし、四つん這いの姿勢のまま壁に沿って体を動かし始めた。
おしっこを吸ってぷっくり膨れた吸収帯の目立つ紙おむつに包まれたお尻を左右に振りながら手足をぎこちなく動かしてのろのろ這い進む真衣の姿は、ようやく這い這いができるようになった赤ん坊そのままだった。それも、おむつの交換を嫌がってオーバーパンツを両脚に絡ませたまま母親の手から逃れようとする聞きわけの悪い赤ん坊。
「待ちなさいったら、真衣ちゃん。ちょっと這い這いができるようになったらこれなんだから、お転婆にもほどがあるわ」
「本当にそうね。こら、待ちなさい、真衣ちゃんったら。這い這いで遊ぶのはおむつを取り替えてからよ」
のろのろとしか移動できない真衣が相手だから、捕まえようと思えばすぐにでも捕まえることはできる。だが、美幸と美沙は互いにしめしあわせて、わざとゆっくり真衣を追いかけた。そんなことをするのは、もちろん、おむつの交換を嫌がって逃げまわる赤ん坊さながらの真衣の姿をたっぷり眺めるのと同時に、ある意味、”狩り”の楽しみを味わうためだった。
けれど、真衣の方は、そんな二人の胸の内にはまるで気づかず、ただひたすら、自分を絡め取ろう迫ってくる四本の手から逃れるために自由にならない手足を動かし、床に落ちそうになるお尻を持ち上げて左右に振りつつ、息を切らせて部屋中を這い這いでうろうろするばかりだった。その姿に背後の二人が妖しい悦びに胸を満たしていようなどとはまるで思いもせずに。
*
「ほら、つかまえた。本当に真衣ちゃんは悪戯っ子なんだから。でも、もうここまでよ。おむつを取り替えたら一緒に遊んであげるから、それまではおとなしくしてなきゃ駄目よ」
およそ二十分間ほど追いかけまわした後、美幸は、とうとう力尽きて四つん這いの姿勢のまま動きを止めた真衣の腰を両手でつかまえた。
「いや……美沙におむつを取り替えられるなんて、そんなの絶対いやぁ!」
もう息も絶え絶えだというのに、美幸と並んで膝立ちになっている美沙の顔を見ないようにして、真衣は力なく首を振って声を震わせた。
「やれやれ、まだそんなことを言ってるんだ、真衣ちゃんたら。おねむの間に何度も美沙お姉ちゃんにおむつを取り替えてもらっているのに、今更なにを言っているのかしらね」
美幸はわざとおおげさに呆れてみせてから、美沙に向かって言った。
「いいわ、言ってもわからないみたいだから、このまま取り替えちゃいましょう。真衣ちゃんだって、新しいおむつに取り替えてもらったらお尻が気持ちよくなって、もうこれからは逃げまわらなくなるでしょうから。私が真衣ちゃんをつかまえているから、美沙は、お布団の上からあるおねしょシーツをここに持ってきて敷いてちょうだい。これだけ暴れまわった後だと、おむつのサイドステッチを破った途端おしっこが沁み出してきて床を濡らしちゃうかもしれないから」
「うん、わかった。ここに敷けばいいのね。――はい、いいわよ。ここにころんしてちょうだい、真衣ちゃん」
言われた美沙は身軽に立ち上がると、布団の上に敷いてあったパイル地のおねしょシーツを床に敷き直し、掌でぽんぽんと叩いてみせた。
「さ、いつまでも這い這いじゃ疲れちゃうから、ほら、ころんして」
美沙がおねしょシーツを敷き終わるのを待って、美幸は腰を両手で持ち上げるようにして真衣の体を移動させた。それから、おもむろに、おねしょシーツの真ん中にお尻が載るように位置を合わせて真衣の体を横たわらせる。
「いや、いやだってば……」
真衣は口では嫌がるものの、二人に追いかけまわされた結果、目を覚ました直後と比べても尚のこと抵抗する力は残っていなかった。
「ところで、ママ。ママが用意してくれることになっている物、どこにあるの?」
美沙は、真衣が仰向けに寝かされる様子を見守りながら、美幸に尋ねた。
「あ、そうだったわね。真衣ちゃんを追いかけるのに夢中になっちゃって忘れてたわ。美沙、これまで何度もこのお家に来ているんだったら、真衣ちゃんの部屋は知っているわよね? 真衣ちゃんのお部屋の隣が二つ空いているから、一つを美沙のお部屋、もう一つを真衣ちゃんの新しいお部屋に使うことにしたの。美沙のお部屋はこれまでの真衣ちゃんのお部屋に近い方で、真衣ちゃんの新しいお部屋は美沙のお部屋の隣にしたんだけど、その新しい方の真衣ちゃんのお部屋に置いておいたから持って来てちょうだい。ついでに、学校の鞄は自分のお部屋に置いてくるといいわ。――真衣ちゃんは、美沙お姉ちゃんが戻ってくるまでおとなしく待ってようね。はい、お口が寂しくないようにこれをちゅうちゅうして」
美幸は美沙に言ってから、改めて自分の太腿に真衣の頭を載せさせ、再び手にした哺乳壜の乳首を唇に押し当てた。
「うん、わかった。じゃ、ちょっと二階へ行ってくるね。お姉ちゃんが戻ってくるまで、真衣ちゃんはママと一緒に待っていてね。すぐに戻ってくるから寂しくなんかないよね」
美沙は、哺乳壜の乳首を強引に口にふくまされた真衣に向かって優しく微笑んでみせた後、足早にリビングルームをあとにした。
|