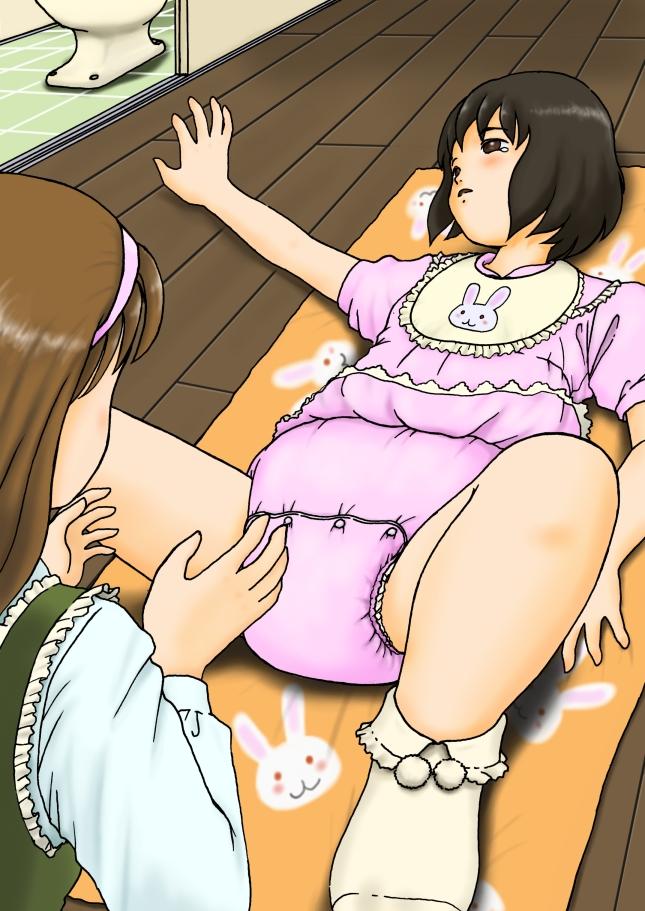|
《18 トイレはすぐそこなのに……》
シチューと離乳食を平らげた後、哺乳壜でミルクを飲まされている最中、不意に真衣の体がぶるっと震えた。
「あれ、寒いのかな、真衣ちゃん。でも、そんな筈ないよね。お姉ちゃんお手製のロンパースを着せてあげているんだから」
自分の食事もそこそこに、真衣に口移しでシチューと離乳食を食べさせてから、ミルクが半分ほど残っている哺乳壜を支え持ったまま、美沙が僅かに首をかしげて真衣の顔を覗き込んだ。だが、口では不思議そうに「あれ、寒いのかな」と言ったものの、実は、真衣が体を震わせた理由などとっくにお見通しなのは言うまでもない。
口移しという手間のかかる食べ方をさせたせいで、食事にはたっぷり時間をかける必要があった。しかも、その前には奪い取られたおしゃぶりを取り返すために美沙を追いかけ、そのあげく三十分近くも泣きじゃくっていたし、更にそれ以前には、おむつの交換を嫌がって美幸と美沙から逃げまわっていた真衣だ。意識を取り戻してすぐ哺乳壜のミルクを飲みながらおむつを汚してしまった時からだと、もうそろそろおしっこをしたくてたまらなくなっているのは明かだ。
それをわかっていながら美沙は哺乳壜を真衣の口から引き離すと、
「どうしたの、真衣ちゃん? ロンパースだけじゃ寒いんだったら、膝掛けの代わりにタオルケットをあんよに掛けてあげようか?」
と、わざと優しく尋ねた。
それに対して真衣はもういちどぶるっと体を震わせ、
「お、おし……」
と言いかけたが、出かかった言葉を途中で飲み込んで俯いてしまう。
「駄目よ、ちゃんと言わなきゃわからないでしょ? どうしたの? お姉ちゃんに何をしてもらいたいのかな、真衣ちゃんは?」
美沙は真衣の顎先に指をかけ、強引に顔を上げさせて訊いた。
「お、おしっこ……」
美幸と美沙を相手にこのまま黙りおおせるわけがないことは痛いほどわかっている。真衣は観念して、蚊の鳴くような声で言った。
「あ、おしっこだったの。大変、大変。早くおむつを取り替えてあげないとお尻が気持ちわるいわね。ちょっと待っててね。すぐに準備するから。ママ、大変よ、真衣ちゃんが……」
美沙は返答を聞くなり、さも真衣が哺乳壜のミルクを飲みながらおむつを汚してしまったと言わんばかりにわざとおおげさに騒ぎたてた。
「ち、違うの。出ちゃったんじゃないの。出ちゃいそうなの」
シンクに向かって洗い物をしている美幸に大声で叫ぶ美沙の言葉を遠慮がちに遮って、真衣は弱々しく首を振った。
「あ、出ちゃったんじゃなくて、出ちゃいそうなんだ。おしっこをちゃんと教えられるなんて、お利口さんね、真衣ちゃんは。このぶんだと、すぐにパンツのお姉ちゃんになれるかもよ」
真衣がおしっこを告げたことをおおげさにほめそやし、美沙は何度も真衣の頭を撫でた。
その間にも尿意はじわじわ高まってくる。
「ト、トイレ……トイレへ行ってもいいでしょ、お姉ちゃん」
真衣は、口の中に残っているミルクをごくりと飲み込み、助けを求めるように言った。美幸にそんなことを懇願しても一蹴されるのは目に見えている。しかし、相手が美沙なら。一縷の望みをかけて、真衣は美沙の顔をおずおず見上げた。
「いいわよ」
半ば拒まれることを予想して懇願した真衣だったが、美沙は意外にもあっさり願いを応諾した。
「……本当にいいの?」
あっけない返答に、どこか信じられない思いで真衣はおそるおそる聞き返した。
「いいに決まってるじゃない。せっかくおしっこを教えてくれた真衣ちゃんをトイレへ行かせないなんて、そんなことするわけないでしょう? さ、間に合わなくなったらいけないから、急ごうね」
美沙はこともなげに言って、真衣の太腿を座面に固定しているベルトを手早く外し、真衣の両脇に手を差し入れてベビーチェアから抱きおろして、ダイニングルームの床に立たせた。
が、薬の効果は切れているものの、三日間に渡って殆ど動かしていない真衣の両脚はすっかり弱体化していて、その場に立っているたけでも太腿からふくらはぎにかけてぷるぷる震え、今にも倒れそうになってしまう。
「ほら、ちゃんとおしっこを教えられたのに、いつまでも愚図愚図していると間に合わなくなっちゃうわよ」
言葉こそ優しいものの、美沙が笑い声で言っているのがわかる。
その時になって、ようやく真衣も、美沙が予想に反してあっさりと望みを聞き入れてくれた理由に思い至った。美沙は、真衣が自力でトイレまで行けるわけがないと高をくくっているに違いない。
「うう……」
真相に思い至った真衣は涙声で呻きながらも、まるで力の入らない両脚を必死の思いで動かし、ようやくのこと、最初の一歩を踏み出した。
途端に体のバランスが崩れて、そのまま前のめりに倒れそうになる。それを、こちらも自由にならない両腕を振り回して堪えたものの、両脚の踏ん張りがまるで利かず、結局は、フローリングの固い床に膝頭をしたたか打ち付けるようにして、膝立ちの姿勢を取るのが精一杯という有様だった。
真衣は、二メートルほど先にあるドアを睨みつけるようにして、尚も両脚に力を入れた。だが、その途端、下腹部に鈍い痛みを覚え、思わず身をすくめてしまう。
心理的な理由もあって、およそ一時間ごとに尿意を感じるというおしっこの近い体質の持ち主である真衣は、学校でも休憩時間のたびにトイレへ行くのが習い性になっている。それを、おねしょの治療という名目でトイレに行く回数をこれまでの半分に減らしなさいと美幸から指図され、事実、美幸が佐藤家にやって来てからはトイレを自由に使わせてもらえない日々の連続だった。しかも、尿意が限界寸前まで高まる頃合いを見計らって美幸の乳首を口にふくまされ、乳首を吸いながらおしっこをさせられるという生活が続いたものだから、気がつけば、美幸の乳首なり哺乳壜の乳首なりを咥えていなければ、どんなに尿意が高まっても、自分の意志では排尿もままならない体になってしまっていた。要するに真衣は、一時間ごとに感じる初期の尿意の段階では自分の意志でおしっこを出すことは可能だが、そうすることは美幸に許してもらえず、それ以上に我慢して尿意が我慢の限界ぎりぎりまで高まると、今度は、美幸の許しが出たとしても、乳首を思わせる何かを吸いながらではないとおしっこを出すことができないという厄介な習性を身に付けさせられてしまったというわけだ。
しかも、我慢の限界ぎりぎりまで尿意を堪え続けると、膀胱を中心として下腹部全体が時にはきりきりと鋭い、また、時にはずしんと重い痛みに襲われ、ますます体の自由が奪われてしまう。今、膝立ちになると同時に真衣が感じた鈍い痛みも、そんな症状の表れだった。もうこうなると、歩きまわることはおろか、その場に立ち上がることさえ難しい。
おそらく美沙は、筋力の弱体化のみならず、耐え難い尿意の高まるに伴う下腹部の痛みまで見越してトイレの使用を真衣に許したのだろう。そして、その背後に美幸の意志が働いているのは火を見るより明らかだった。
やがて、膝立ちでいるのも困難になってきたのか、真衣はそのまま崩れ落ちるようにして前のめりになって床に両手を床につき、おむつの交換を嫌がって逃げまわったり、美沙の手からおしゃぶりを取り返すために追いかけたりした時と同様、四つん這いになってしまった。こうすると、体重が下腹部に集中するのを幾らか防げるため、少しは痛みも和らぐ。
「どうしたの、真衣ちゃん? トイレへ行くんじゃなかったの?」
四つん這いになって肩で息をする真衣のかたわらに膝をついた美沙が、腰をかがめ、真衣と目の高さを合わせて言った。
だが、真衣には、無言で弱々しく首を振ることしかできない。
「あ、そうか。真衣ちゃん、まだあんよが上手じゃなかったんだっけ。だから、這い這いでトイレへ行くのね。あんよも上手じゃないのにおしっこを教えられるなんて、とってもお利口さんね、真衣ちゃんは」
美沙は澄ました顔でそう言い、膝立ちのまま真衣の前にまわりこむと、ジーンズのポケットから鍵の束を取り出した。
「ほら、これが何だかわかる? そうよ、便器の蓋の鍵よ。これがないと、せっかくトイレへ行っても便器を使えないから、お姉ちゃんも一緒についていってあげる。ついていって、便器の鍵を外してあげる」
美沙は、束の中でも特に小振りの鍵を真衣の目の前で振ってみせた。
「真衣ちゃんみたいな小っちゃい子が勝手に便器の蓋を開けて中を覗き込んだりしたら便器の中にころんしちゃうかもしれないって心配したママが、便器の蓋を勝手に開けられないようにしたんだってね。これが、それを開ける鍵よ。もちろん、ママも鍵を持っているけど、お姉ちゃんもスペアを預かっているの」
真衣は、美沙がこれみよがしに目の前で振る小さな鍵を求めて、僅かに体を前に進めた。
それに合わせて美沙がすっと身を退き、またしても、じゃらじゃら音を立てて鍵束を振ってみせる。
そんなことを繰り返し、リビングルームを出て廊下を這い進んだ真衣だが、下腹部の痛みを我慢しながらの上、筋力が戻っていない手足では美沙に追いつけるわけがない。
とうとう真衣は追いかけるのを諦め、廊下の真ん中にぺたんとお尻をつけて座り込んでしまった。
「どうしたの、真衣ちゃん? 鬼ごっこはもいいのかな? でも、ちょうどいいわ。ほら、追いかけっこをしているうちにトイレのすぐ近くまで来ちゃったから」
くすりと笑って美沙はそう言い、目の前のドアを押し開けた。
その向こうには、確かに、いかにも清潔そうな純白の便器があった。
美沙は真衣がじっとみつめる中、小振りの鍵を使ってロックを外し、便器の蓋を引き開けた。
「さ、いいわよ。ちゃんと蓋を開けてあげたから、トイレでおしっこをするといいわ」
美沙は再び廊下に膝をつき、真衣と目の高さを合わせて、蓋の開いた便器を視線で指ししめした。
「ト、トイレ……トイレでおしっこ……」
トイレの使用を許してもらうのは何日ぶりのことだろう。真衣は瞳を輝かせ、両手で自分の下腹部をまさぐり始めた。もちろん、美沙の手で着せられたロンパースの股間に並ぶボタンを外すためだ。
だが、次第に真衣の顔色が変わって呼吸が荒くなってくる。
「どうしたの? せっかくトイレまで来たのに、早くしないと間に合わなくなっちゃうんじゃないのかな?」
いつまでもロンパースの股間をまさぐっている真衣に向かって、美沙がわざと不思議そうな表情を浮かべて声をかけた。
「……外れないの。ボタンが外れないの……」
焦りの色を満面に浮かべて、真衣が涙声で言った。
「ロンパースのボタンが外れないの? 変ね、そんな筈ないんだけど」
美沙は訝るように言って、四つ並んでいるボタンの内の一つ人に指をかけ、一カ所に力を集めるようにして上下に引っ張った。
と、ぷつんと小さな音がして、スナップボタンの噛み合いが離れる。
「ね、簡単でしょ? どうして真衣ちゃんにはできないのかな? もういちど試してごらん」
美沙は、自分が外したスナップボタンを指差した後、再びぷつんという音とともに嵌め込んで閉じてしまった。
「あ、せっかく開いたのに……」
真衣は、そう叫び出しそうになるのを堪え、美沙の顔を恨みがましく睨みつけてから、改めてロンパースの股間に手を伸ばした。
だが、美沙の時とは違って、真衣がどんなふうにに指を動かしても、やはりロンパースのボタンが外れる気配はなかった。
実は、それには理由があった。もともと、スナップボタンは、金具部分の真球度のばらつきや僅かな歪みなどのせいで製造ロットごとに噛み合いの強さが異なる場合が少なくない。それをメーカーは或る程度の基準内にある物を商品として出荷しているのだが、保育園や幼稚園に通うような小さな子供に持たせる手提げ鞄等を母親が市販のスナップボタンを使って手作りした時など、母親の力では簡単に開けられるのに、小さな子供の力ではボタンを開けられないといったことがないわけではない。そんな時は噛み合いが緩めのスナップボタンに付け替えて対処する場合もあるが、付け替えが面倒な時は、スナップボタンの♂側に付いている金属球をペンチ等で僅かに変形させることで噛み合いの強さを調節することもできる。家庭科クラブに所属していて、そういった細かいテクニックにも通じている美沙は、手芸店でわざわざ噛み合いの強いスナップボタンを選んで買い求め、なおかつ、先の細いペンチで金属球に細工を施して、噛み合いを更に強くしておいたのだ。
美沙が指先に力を集めてやっと外すことのできる程度に噛み合いを強くしたスナップボタンを、もともと美沙よりも小柄で非力な真衣が、這い這いで力を使い果たした後で開けられるわけがない。それを見越した上で、美沙は真衣をわざわざトイレのすぐ近くまで連れて来たのだった。
「……外れない、外れないよぉ」
美沙がスナップボタンに細工を施したことにまるで気づいていない真衣は、尚もロンパースの股間をまさぐっていたが、やがて諦めの表情を浮かべると、おそるおそるといった様子で美沙の顔を見上げ、おずおずと言った。
「お、お願い、お姉ちゃん……ボタンを外して。真衣、自分じゃロンパースのボタンを外せないから、お姉ちゃんに外してほしいの。お願いだから、お姉ちゃん」
「いいわよ、じゃ、お姉ちゃんがロンパースのボタンを外してあげる」
よく注意していないと聞き逃してしまいそうになるほど弱々しい声ながら切羽詰まった調子で懇願する真衣に、美沙はわざとにこやかな笑みを浮かべて応じ、涙で潤む瞳を覗き込むようにして続けた。
「その代わり、自分が赤ちゃんだってことをもういちどよく思い出すのよ。もう二度とパンツのお姉ちゃんになりたいだなんて思わないこと。それが約束できるんだったら、お姉ちゃんがボタンを外してあげる」
「そ、そんな……」
思わず抗弁しかける真衣。
だが、すぐに思い直して、出かかった言葉を飲み込んでしまう。このままあと三十分もすれば、我慢の限界を通り越して膀胱の緊張が勝手に解け、口に何も咥えていなくてもおしっこが溢れ出すだろう。しかし、これまで、下腹部全体を包み込む痛みに耐えかねて、一度もそこまで我慢をし通すことのできなかった真衣だ。今回もこれ以上の我慢を続けられるわけがないことは自分自身がよく知っている。それに、もしも我慢し通すことができたとしても、我慢の限界を通り越して勝手におしっこが溢れ出したりしたら、おむつが吸い取れる量を超えて、オーバーパンツもロンパースもびしょびしょにした上、廊下に生温かい水溜まりをつくってしまう羽目になるのは目に見えている。
「……う、うん、わかった。真衣、パンツのお姉ちゃんになりたいだなんて言わない。真衣……おむつの赤ちゃんだから。ママと美沙お姉ちゃんがいないと何もできない小っちゃな赤ちゃんだから……」
美沙の顔を見ないようにしながら真衣はぽつりと言った。
「それでいいわ。お姉ちゃんがボタンを外してあげる。それと、試しにつくってあげたロンパース、真衣ちゃんの体にぴったりみたいだから、同じサイズでもっとたくさんつくってあげるね。一着だけじゃ、まんまを食べる時に汚しちゃったら着替えの分がないもの。それに、おっきの時とおねむの時に同じロンパースっていうのも変だし。だから、お家にいる時はいつもロンパースを着るのよ。そうしないと、お転婆の真衣ちゃんのことだから、お腹が出ちゃって、おもらしやおねしょが今よりもひどくなっちゃうものね。お家にいる時はおむつってママと約束したんでしょう? だったら、ロンパースがお似合いよね。あ、でも、ロンパースばかりだと可哀想だから、うんと可愛いワンピースやサンドレスもつくってあげなきゃいけないかな。あんよが上手じゃない真衣ちゃんに着せるワンピースだから、脚にまとわりつかないよう、スカートは短くしてあげないといけないわね。スカートの裾からぷっくり膨らんだおむつカバーをちょっとだけ見せてよちよち歩きする真衣ちゃん、可愛いでしょうね。それとも、おむつカバーが見えるのが恥ずかしいんだったら、ロンパースみたいに、お尻のところにボタンが並んだブルマーみたいなボトムスとセットにしてあげた方がいいかしら。うふふ、デザインを考えるのが今から楽しみだわ。あと、真衣ちゃんは大好きなおしゃぶりをずっと咥えているんだから、よだれかけもたくさんつくっていげないとね。とりあえず、三枚はつくっておいたけど、それだけじゃ、すぐにどれもよだれでべとべとになっちゃいそうだし。いつまでも赤ちゃんで、いつまで経ってもパンツのお姉ちゃんになれない真衣ちゃんに着せる物だもの、いくらたくさんつくっても足りないかしら」
「そ、そんな……」
「だって、真衣ちゃん、自分で言ったのよ。真衣はパンツのお姉ちゃんにならないって。そう約束したから、お姉ちゃんはロンパースのボタンを外してあげるのよ」
美沙は、何か言いたそうにする真衣の唇に自分の指先を押し当てて黙らせ、念を押すように言った。
そうして、真衣が視線を床に落として押し黙るのを見て取ると、やおら、自分が着ているトレーナーの裾を胸元まで捲り上げ、あらわになったブラジャーのカップを真衣の目の前に突きつけて、どことなく艶然とした笑い声で言葉を続けた。
「ほら、こっちを見てごらん。これ、昨日、ママがお姉ちゃんにプレゼントしてくれたのよ。これが何だか、真衣ちゃんにもわかるよね? だって、ママのおっぱいを何度も何度も吸ったことがあるんだから」
美沙の乳房を包み込んでいるのは、美幸が佐藤家にやって着てすぐ着用するようになったのと同じクロスオープンタイプの授乳用ブラジャーだった。
「……!」
そのことに気づいた真衣が驚きのあまりあっと声をあげそうになって、唇が半分ほど開いた。
美沙はそれを見逃さず、昨日から練習を重ねてきたのだろう、慣れた手つきで授乳用ブラのカップをさっと引きおろすと、半開きになった真衣の唇に自分の乳房を押し付けた。
「な、何を……こ、こんなことしてないで、ボタンを……早く、ボタンを……」
くぐもった呻き声をあげ、ロンパースのボタンを外してくれるよう懇願する真衣だが、その微かな声さえ、強引にふくまされた乳首のせいで途中で遮られてしまう。
「わかっているわよ。ロンパースのボタンを外してほしいのね? それに、おむつも外してほしいのね? いいわよ、真衣ちゃんのお願いはお姉ちゃんがきいてあげる」
真衣に自分の乳首を咥えさせた美沙は、頬を上気させ、甘ったるい声で言った。
「だけど、今すぐじゃないわよ。真衣ちゃんがおむつを汚しちゃった後でロンパースのボタンを外して、おむつも外してあげる。それでもボタンを外してあげることに違いはないんだから、約束を破ったことにはならないわよ。だから、真衣ちゃんも約束を守って、ずっとおむつの赤ちゃんでいるのよ。今まで我慢してきて辛かったでしょう? でも、もういいのよ。ママのおっぱいを吸いながらおむつを汚すのと一緒、お姉ちゃんのおっぱいを吸いながらおしっこをたくさん出すといいわ。おしっこを我慢しすぎてお腹が痛いんでしょう? おむつの中におしっこを出しちゃって楽になろうね。だから、さ、お姉ちゃんのおっぱいを思いきり吸ってちょうだい」
「や、やだ……こんな、こんなことされたら……」
廊下にお尻をぺたんとつけた格好のまま美沙に抱きすくめられ、身をひくこともできずに、真衣は、唇と乳房の僅かな隙間から息を吐き出すようにして、聞こえるか聞こえないかの声を絞り出した。
「こんなことされたらどうなっちゃうのかな、真衣ちゃんは?」
体を押し返そうとする真衣の手を軽く振り払って、美沙は更に強く乳房を押し付けながら言った。
「こんなことされたら……こんなことされたら、おしっこが……」
「こんなことされたら、おしっこが出ちゃうのね。でも、それでいいじゃない。真衣ちゃんは赤ちゃんなんだから、おむつをおしっこで汚しちゃってもちっとも変じゃないじゃない」
ますます上気した顔で美沙が言った。
おしっこを出して一時間くらい経ち、新たな尿意を覚えた時なら自然な排尿ができるが、それを通り越して我慢し、二時間くらいになると、美幸の乳首や、それを思わせる物を吸いながらでないと排尿できない体になってしまった真衣。それは、逆に言えば、限界ぎりぎりまで尿意を我慢している時に乳首を口にふくまされると、自分の意志とはまるで無関係におしっこを溢れ出させる体になってしまったということだ。そんな真衣に自分の乳房を与える美沙。その狙いが、自分が刺繍を施した布おむつを真衣におしっこで汚させるところにあるのは明かだった。
「さ、いつまでも我慢してちゃ体に毒だから、おしっこを出しちゃおうね。出しちゃっても平気なのよ。お姉ちゃんが真衣ちゃんのお名前を刺繍してあげたおむつがおしっこをちゃんと受け止めてくれるから。妹のお下がりのおむつが真衣ちゃんのおしっこをみんな吸い取ってくれるんだから」
美沙は左手を真衣の背中にまわしてこちらに引き寄せたまま、おむつでぷっくり膨れたお尻をロンパースの上からぽんぽんと叩いた。
「い、いや。美沙のおっぱいを吸いながらおしっこだなんて、そんなの、そんなの……」
それまで美幸の指図に従って『美沙お姉ちゃん』と呼んでいたのを、あまりの屈辱に耐えかねて『美沙』と呼び捨てにして、真衣は弱々しく首を振った。しかし、美沙の手で力いっぱい体を抱き寄せられ 豊かな乳房に顔を埋めたままだから、首の動きは殆どわからない。
「いいのよ、いつまでも強情を張って我慢しなくても。真衣ちゃんはママのおっぱいを吸いながらおもらしをするのが大好きなんでしょう? だったら、お姉ちゃんのおっぱいを吸いながらおむつを汚すのも大好きなんじゃないのかな」
美沙は真衣の耳元に唇を寄せて甘ったるく囁きかけた。
「やだ。やだってば……美沙のおっぱいを吸いながらおむつを汚すだなんて……そんなの、やなんだから」
何度も何度も『やだ』を繰り返しながらも、真衣の瞳が次第にとろんとしてくる。
「でも、真衣ちゃんは赤ちゃんなんでしょう? 赤ちゃんがおしっこでおむつを汚すのを嫌がるだなんて、その方が変だよ。赤ちゃんがおっぱいを嫌がるだなんて、そんなの変だよ。ママのおっぱいじゃなくてご機嫌斜めなのかもしれないけど、でも、お姉ちゃんのおっぱいもぷりぷりしてて気持ちいいでしょう? だから、ほら」
美沙は真衣の背中を優しく撫でさすった。
「だって、だって……」
とろんとしていた瞳が虚ろになって、真衣の頬にさっと朱が差した。
途端に、美沙の乳首に鋭い痛みが走る。
「つっ!」
思わず美沙は悲鳴をあげた。
だが、悲痛な声を漏らしたのはその一度きりで、あとは僅かな呻き声をあげることもなく、表情も変わらない。真衣に乳首を吸わせる悦びに上気した顔にどこかうっとりした表情を浮かべて、自分の乳首を盛んに吸う真衣の顔をいとおしげにみつめるばかりだ。
その表情が、異形の母性本能の表れなのか、あるいは、思春期の少女どうしの甘酸っぱくちょっと倒錯めいた恋心の発露なのか、それは判然としない。しかし、美沙の顔に浮かぶ悦びの色だけは本物だった。それに応えるかのように、真衣の顔を彩る表情もまた。
「あ……」
美沙の口を衝いて出た悲鳴を耳にするなり、真衣がはっとしたような顔になった。
だが美沙は
「いいのよ。真衣ちゃんが心配することなんて一つもないの。真衣ちゃんはただお姉ちゃんのおっぱいを吸いながらおしっこでおむつを濡らせばいいのよ」
と優しく言い聞かせるだけだ。
それは、真衣が美沙の乳首に歯を立てた理由を充分に理解しているからこそ口にできる言葉に他ならなかった。
それまで限界ぎりぎりまで尿意に耐えていたのを、乳首を口に含まされたせいでとうとう堪えきれなくなり、膀胱の緊張を解いてしまった瞬間。それこそが、意識しないまま真衣が美沙の乳首を噛んでしまった瞬間に違いない。そのことを直感したから、美沙は短い悲鳴をあげただけで、あとはひたすらいとおしげに真衣の髪を何度も撫でつけるのだった。
いったん出かかったおしっこを止めることはもうできない。それまでは美沙が真衣の体を抱き寄せていたのが、今度は逆に、真衣が美沙の背中に両腕をまわし、咥えた乳首を離すまいとしてすがりつく。そうなれば、美沙の両手は自由だ。
美沙は、廊下にお尻をぺたんとつけ両脚をだらしなく開いた真衣の股間に手を伸ばして、ロンパースのボタンに指をかけた。真衣があれほど苦労をし、結局は外すことを諦めざるを得なかったスナップボタンだが、美沙の巧みな指運びにかかれば、きつい噛み合わせを離すこともさほど難しくない。
ぷつんぷつんという微かな音が続けて聞こえ、美沙はボタンを四つとも手早く外してしまった。
そうして美沙は、ロンパースの股間の布地を大きく前後に開くと、乳首を真衣の口にふくませたまま、右手の人差し指と中指をおむつカバーの中にそろりと差し入れる。
指を差し入れた直後に感じたのは、汗によるじっとりした湿り気だけだったが、さほど時間が経たないうちに、布おむつがおしっこを吸ってぐっしょり濡れてゆく様子が指先から伝わってきた。
「そうよ、それでいいのよ。真衣ちゃんは赤ちゃんなんだから、お姉ちゃんのおっぱいを吸いながらおしっこでおむつを濡らしちゃっていいのよ」
美沙は、これまで何度も口にしたのと同じ言葉を今また真衣の耳元に囁きかけた。
「やだ、そんなこと言っちゃやだ……」
真衣は美沙の乳首を咥えたまま、どこか甘えるような仕草でかぶりを振った。
「やだじゃないわよ。お姉ちゃんは本当のことしか言ってないんだから」
美沙はくすりと笑って、自分の乳房をそっと支え持ち上げた。
*
それからしばらく経ち、真衣がおしっこを出しきった頃合いを見計らって美幸が美沙に声をかけた。
「バスケット、ここに置くわよ。それと、バスタオルも敷いておくわね」
言うと同時に、真衣が座り込んでいる場所のすぐそばに美幸は大振りのバスタオルを敷き広げ、リビングルームから運んできたバスケットを二つ、そっと置いた。
大きい方のバスケットには、美幸が業者に依頼して特別につくってもらった大きなおむつカバーと共に、紙袋から取り出し、一枚ずつ丁寧にたたんで重ねた状態で布おむつが何枚も収めてあった。そして、ひう一つの小さめのバスケットにも、赤ちゃん用の玩具やおむつかぶれの薬の容器といった小物類と一緒に、ロンパースと同じく美沙が試しにつくった三枚の大きなよだれかけの内の二枚が、きちんと重ねて収納してあった(ちなみに、既に真衣の胸元を覆っているのが、残りのもう一枚だ)。
「ありがとう、ママ。――じゃ、ママがちゃんと用意してくれたから、急いでおむつを取り替えようね。いつまでも濡れたおむつのままじゃお尻が気持ち悪いし、おむつかぶれがひどくなっちゃうもの」
美沙は、おしっこを出しきった後も乳首を咥えて離さない真衣に向かって、諭すように言った。
けれど、真衣が美沙の乳首から唇を離す気配はまるでない。それどころか、むしろますます強く美沙の乳房に顔を押し当ててくる。
「あらあら、まだお姉ちゃんのおっぱいがほしいの? 本当に真衣ちゃんは甘えん坊さんなんだから」
美沙は、真衣の頬を人差し指り先でつんとつついた。
しかし、それは決して美沙に甘えてのことなどではない。それこそ本当に乳離れできない赤ん坊そのまま乳首を口にふくんでおむつを汚してしまった羞恥に、二人と目を合わすまいとして美沙の豊かな乳房に顔を埋めているのだった。
美沙にしても、そんなことは充分に承知している。承知していながら真衣のことをこれでもかと赤ん坊扱いして楽しんでいる様子がありありだ。
「いつまでもそんなことしてちゃ駄目よ。ほら、もうおっぱいを離してちょうだい。おむつを取り替えたらまた吸わせてあげるから、ちょっとの間だけ我慢するのよ」
本当のところを言えば、美沙にしても、このままずっと真衣に乳首をふくませていたい。同じ年頃の女の子どうし、こんなことをしてちゃいけないかもという思いがちらと浮かぶが、姉妹同然に育った幼なじみであり一番の親友である真衣に乳首を吸われる倒錯的な悦びの前には、そんな思いさえもがほどよいスパイスにすぎなかった。それでも、美沙は一時の快楽に身をまかせることなく、それまで前のめりだった体を僅かに後ろにそらした。
それに抗して真衣が、美沙の背中にまわした両腕を離すまいとして、更に強くすがりつく。
そこへ横合いから飛んできたのは美幸の声だった。
「いいわよ、そんなに美沙お姉ちゃんのおっぱいを吸っていたいのなら、いつまでも吸っていればいいわ」
これまで同様、なにやら含むところのありそうな口調だった。
「でも、気をつけなきゃ駄目よ。真衣ちゃん、さっき、おしっこが出そうになった時、美沙お姉ちゃんのおっぱいを噛んじゃったでしょう? いくら真衣ちゃんがおむつの赤ちゃんだっていっても、本当の赤ちゃんと比べれば、大人の歯も生え揃っているし、顎の力も強いし、噛まれた美沙お姉ちゃんはとっても痛かったでしょうね」
美幸は、美沙の乳房と真衣の顔をちらと見比べて続けた。
「いつまでも吸ってたら、いつまた美沙お姉ちゃんのおっぱいを噛んじゃうかわからないわよね。長いこと吸い続けていれば続けているほど、噛んじゃう回数も増えちゃうわよね。そんなことになったら、美沙お姉ちゃんも堪らないんじゃないかな」
美幸は、目をすっと細めて真衣の顔を見おろした。
「でも、真衣ちゃんはいつまでも美沙お姉ちゃんのおっぱいを吸っていたい。ま、それならそれでいいわ。間違って真衣ちゃんが美沙お姉ちゃんのおっぱいを噛んじゃってもお姉ちゃんのおっぱいに傷がつかないようにしておいてあげればいいんだから。おっぱいを噛まれても美沙お姉ちゃんが痛がらないようにしておいてあげればいいんだからね」
そう言って艶然と微笑む美幸の様子に、真衣の背中がぞくっと震える。
「仕事柄、当たり前のことだけど、ママは歯医者さんともたくさんおつきあいがあるのよ。その中にはいろいろ新しい治療方法に挑戦しているお医者様もいてね。たとえば、ひどい歯周病のせいで歯をみんな抜いちゃわなきゃいけなくなった患者さんがいたとするじゃない? ま、そのあとは総入れ歯を使うとか、生活そのものには支障のないようケアするのは当然なんだけど、入れ歯だと、寝る時なんかに外すと、唇のあたりがぎゅっとすぼまって人相が変わっちゃうのよ。そんな寝顔を見られるのが嫌で旅行に出かけられない人も少なくないんだって。そんな人のために、歯をみんな抜いちゃったあとに別の素材を埋め込むことで人相が変わるのを防ぐ技術を研究しているお医者様もママの知り合いの中にはいるの。そのお医者様にお願いして、真衣ちゃんの歯をみんな抜いてもらって、そのあとに、ぷにぷにした柔らかい素材を埋め込んでもらうこともできるのよ。そんなふうにしてもらったら、間違ってママや美沙お姉ちゃんのおっぱいを噛んじゃっても、噛まれた方はちっとも痛くないし、おっぱいに傷がつくことも防げるわよ。そうしたら真衣ちゃんも遠慮なくママやお姉ちゃんのおっぱいを吸ってられるから、その先生にママからお願いしておいてあげようか?」
あながち冗談とも思えない口調でそう言って、美幸はもういちど真衣の顔をねめつけた。
「は、歯をみんな……」
どこまで本気か想像もつかない美幸の口調に、真衣はひきつった顔で息を飲んだ。
「だって、真衣ちゃんは美沙お姉ちゃんから口移しで食べさせてもらわないとまんまもちゃんと食べられない赤ちゃんなんでしょう? 口移しのまんまはとっても柔らかいから歯で噛む必要なんてないじゃない。それに、哺乳壜を吸うのも、歯の代わりに柔らかい素材で間に合うし。現に、まるで歯の生えていない赤ちゃんだって上手にミルクを飲んでるじゃない? だから、真衣ちゃんにも歯なんて要らないのよ」
美幸は、ぞくりとするような流し目をくれた。
「いや。歯をみんな抜いちゃうだなんて、そんなの……」
真衣は美幸と目を合わすまいとしてますます強く美沙の乳房に顔を埋めた。
だが、
「あれもいや、これもいや。いやいやばかりじゃ、どうしてほしいのかわからないでしょ? 歯を抜いてもらってこのままずっと美沙お姉ちゃんのおっぱいを吸っていたいの? それとも、おむつを取り替えてもらいたいの? 歯を抜いてもらいたいんだったら、すぐにでも先生に連絡してあげるわ。緊急用の往診セットを持って今から来てくださいって。麻酔や助手が必要なら私が手伝うし、私の診療キットのお薬を自由に使っていただいて結構です、だから今すぐ来てくださいって」
と迫られると、それ以上は何も言えなくなってしまう。
「……お、おむつを取り替えてもらう。取り替えてもらうから、歯を抜くのは……」
真衣は怯えきった表情で力なくかぶりを振り、美沙の乳首からおずおずと口を離した。
「おっぱいはあとにして、おむつを取り替えてもらいたいのね?」
「……うん」
「だったら、美沙お姉ちゃんにおねだりしなきゃ駄目でしょ? どんなふうにおねだりすればいいかは真衣ちゃんが自分で考えなさい」
嵩にかかって指図する美幸に、けれど真衣は従うしかない。
「お姉ちゃん……美沙お姉ちゃん。お……おむつ、汚しちゃったの。おむつ、おしっこでびしょびしょにしちゃったの。だから、取り替えてほしいんだけど……」
真衣は胸が張り裂けそうになる羞恥と屈辱にまみれながらも、乳首から口を離した後も二人と目を合わすまいとして俯いたまま、幼児めいた口調を真似て言った。
「そう、おむつを取り替えてもらいたいんだ。それで、誰のおむつを取り替えてもらいたいのかな?」
美沙が、豊かな乳房をブラのカップに収め、トレーナーの裾を引きおろしながら聞き返した。
「……ま、真衣の……真衣のおむつ。真衣、おしっこでおむつを汚しちゃったの。だから、真衣のおむつを……」
「ふうん、真衣ちゃんのおむつを取り替えてあげればいいのね。でも、取り替えてあげるのは今回だけでいいの?」
「あ、あの……これから、ずっと取り替えてほしいの。真衣、何回も何回もおしっこでおむつをびしょびしょにしちゃうから、そのたびに……」
「今回だけじゃなくて、真衣ちゃんがおもらしやおねしょしちゃうたびにおむつを取り替えてあげればいいのね。うん、わかった。真衣ちゃんは、いつになったらおむつ離れできるかわからない赤ちゃんだもんね。それで、ちょっと訊きたいんだけど、私の本当の妹と、真衣ちゃん、どっちがお姉ちゃんだと思う?」
「……妹。お姉ちゃんの妹の方が真衣よりもお姉ちゃん……」
「へーえ、ちゃんとわかってるんだ。真衣ちゃんは赤ちゃんだけど、私の妹は幼稚園の年長さん。真衣ちゃんの下着はおむつだけど、妹が穿いてるのはパンツ。だったら、私の妹の方がずっとずっとお姉ちゃんだよね。私の妹は誕生日が八月だから、まだ五歳。真衣ちゃんの誕生日はちょっと前に来たから、もう十六歳。でも、妹の方がお姉ちゃんなんだよね。だから、真衣ちゃんは私の妹からお下がりのおむつを貰えたんだよね」
「……」
「うん、わかった。つまり真衣ちゃんは、自分よりも年下のお姉ちゃんからお下がりで貰ったおむつをおしっこで汚しちゃったから取り替えてほしいのね? それも、今回だけじゃなくて、これからもずっと、おむつを汚しちゃうたびに取り替えてほしいのね? お姉ちゃんがお名前を刺繍してあげたおむつを」
美沙は執拗に何度も訊き返し、自分がおむつの赤ちゃんだということを真衣に改めて思い知らせてからようやく納得顔で頷くと、
「わかったから、おむつを取り替えてあげる。じゃ、ママが用意してくれたバスタオルの上にころんしようね。ころんして、おむつを取り替えようね」
とわざと優しく言って、真衣をバスタオルの上に横たわらせた。
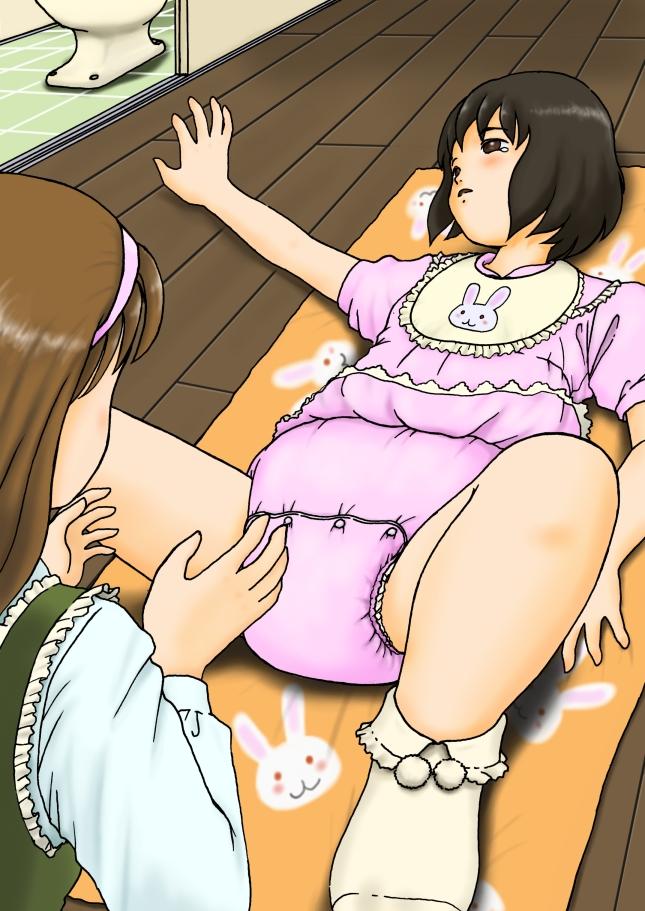
バスタオルに横たわると、頭がちょうどトイレの入り口と真正面から向き合う位置に来て、便座の蓋を開けたままになっている便器が丸見えになる。
(トイレ……トイレでおしっこ……)真衣は、諦めきれない表情で、意識しないまま、トイレの入り口に向かって力なく右手を差し伸べた。
「おしっこを教えてくれたからトイレへ連れてきてあげたけど、間に合わなかったね。でも、いいのよ。トイレに間に合わなくても大丈夫なようにおむつをあてているんだから。いつおしっこをおもらししちゃってもいいようにおむつをあてているんだから。だって、真衣ちゃんはまだあんよも上手にできない赤ちゃんなんだもの」
美沙が、真衣の胸の内を見透かしたかのように言った。
途端に、真衣の瞳がじわっと潤んだかと思うと、その直後、大粒の涙が次々にこぼれ出す。
すると美幸が
「あらあら。おむつを汚して泣いちゃうなんて本当に赤ちゃんだこと。赤ちゃんでも、おむつ離れが近い子は、おむつを汚しちゃうと『ママ、ちっち出たぁ』とか言って教えてくれるものなのに、それもできなくて泣くだけなんて、おむつが外れるのはまだまだ先のことみたいね。でも、そんな真衣ちゃんだから可愛いんだけど。――ほらほら、あまりむずがっちゃ駄目よ。真衣ちゃんの大好きな玩具を持たせてあげるから、ご機嫌をなおしてね。赤ちゃんは音の出る玩具が大好きだから、ほら、これを持って振ってごらん」
と、それこそ幼児をあやすように言って、感情の高ぶりに耐えられず遂に泣き出してしまった真衣の目の前で、小さい方のバスケットから取り出したガラガラを振ってみせた。
もちろん、そんなことで真衣が泣きやむわけがない。しかし、美幸にしても、それは承知の上だ。
からころ。からころ。
美幸が手を振るたびに、かろやかな音がガラガラから流れ出る。
美幸は自分で何度か振ってから、ガラガラを真衣の右手に持たせた。
が、そんな赤ん坊の玩具を真衣が自ら握ろうとする筈もなく、すぐに手を離してしまう。
「あらあら、おかしいわね。赤ちゃんが大好きな音の出る玩具なのに。ママの持たせ方が悪かったのかしら」
廊下に転がったガラガラを拾い上げながら美幸はわざと不思議そうに言い、拾い上げたガラガラをもういちど真衣の手に押し付けた。
だが、やはり真衣はガラガラの柄を握ろうとしない。かろやかな音をたててガラガラは再び廊下に転がってしまった。
「あら、また落としちゃった。ひょっとしたら、真衣ちゃん、まだお手々もちゃんと動かせないくらい小っちゃな赤ちゃんだったのかしら」
廊下に転がったガラガラを今度は拾い上げようとせず、美幸は、トイレの方に向かって差し伸べられた真衣の右手をじっと見て言った。
「ま、それならそれでいいわ。赤ちゃんはおねむの時、顔が痒かったら遠慮なしに自分の爪で掻いて柔らかい肌に傷を付けちゃうことが多いんだけど、お手々が自由に動かせないんだったら、その心配もないし。でも、中途半端に動かせると却って危ないから、どうせだったら、おいたができないようにちゃんとしておいてあげた方がいいわね」
真衣に聞こえるよう意識しつつ、けれど誰にともなく呟くふうを装って美幸はそう言い、バスケットやバスタオルと一緒にリビングルームから持ってきていた簡易診療キットの蓋を開けた。
胸騒ぎを覚えた真衣が体を起こそうとしたが、美幸に目配せされた美沙が肩をバスタオルの上に押さえつけてしまう。
その直後、消毒用のアルコールを染みこませたコットンを右腕の手首に押し付けられるひんやりした感触があり、続いて、ちくりとした痛みが走る。更に、同様の感触が左腕にも。
「……!」
「心配しなくてもいいわよ、怖いお薬じゃないから。発熱の治療のために鎮静剤と一緒に筋肉の力を弱める注射を打ってあげたことは話したわよね? それと同じ系統のお薬を、効き目を弱くして注射してあげただけなのよ。ま、同じ系統とはいっても、効き方はちょっと違うんだけどね」
わけのわからない注射を打たれ声にならない悲鳴をあげる真衣とは対照的に、澄ました顔で美幸は言った。
「鎮静剤と一緒に注射したのは、どちらかというと、筋肉を弛緩させるように効くお薬だったんだけど、今のお薬は筋肉を硬直させる効き目があるの。微妙なメスさばきが必要な手術の時なんかに、患者さんの体位を固定する目的で使うことがあるのよ。ただ、効果が及ぶ範囲は限定的で、今の真衣ちゃんみたいに手首を注射した場合だと、肘から先の筋肉は硬直するけど、肘から肩にかけては自由に動かせる筈よ」
美幸はそう説明した後、注射器をケースにしまってから、廊下に転がったままになっているガラガラを拾い上げ、力なく広げた真衣の掌の上に置くと、指を一本一本注意深く折り曲げた。
そうなると、もう真衣の意志では掌を開くことができなくなる。美幸の手で指を折り曲げられた形の通りガラガラの柄を握ったままになってしまうのだ。
「や、やだ、こんなの、やだ。真衣の手が……真衣の手なのに……」
意志に反してまるで指を開こうとしない自分の掌の様子に、真衣は再び両目から大粒の涙を溢れさせ、泣き声をあげて身をよじったた。
その反動で、肘から先が自由にならない右腕が勝手に動き、ガラガラを揺らしてしまう。
からころ。からころ。
美幸が比べた時と比べれば弱々しいものの、やはり変わらぬかろやかな音が流れ出て周りの空気を優しく震わせた。
「よかったわね、大好きなガラガラを振れるようになって。そうよ、その調子でどんどん振るといいわ」
美幸は、拳に握った真衣の掌を自分の掌ですっぽり覆うようにして強引にガラガラを振らせた。
「ち、違う。真衣が振ってるんじゃない。真衣がガラガラなんて……」
自分の意志とはまるで無関係にガラガラを振らされる屈辱に、真衣は金切り声をあげ、頬を涙に濡らしながら首を振った。だが、両腕とも肘から先の自由を奪われているため、美幸の手を振り払うこともできない。
「やれやれ、困った子だこと。大好きなガラガラを持てたのに、まだ泣きやまないなんて。美沙お姉ちゃんのおっぱいが吸えなくてお口が寂しいのかな。じゃ、おむつを取り替えてもらう間、これを咥えているといいわ」
まるで泣きやむ気配のない真衣の様子に、美幸は、困るどころか、むしろ満足そうに言って、バスケットからおしゃぶりをつまみ上げ、唇に押し当てた。
おしゃぶりに唇と舌を押さえつけられ、真衣の泣き声はそれまでよりも低くなったものの、やはり、まだ泣きやもうとはしない。
「まだ泣き止まないなんて変ね。あ、そうか。おむつが濡れているんだったわね。大好きなガラガラを持たせてもらっても、お気に入りのおしゃぶりを咥えさせてもらっても、おむつが濡れているんだったら、泣きまないのも仕方ないわね。まだお喋りのできない赤ちゃんは、そうするしか、おむつが濡れていることを知らせる方法はないんだから。――じゃ、あとは美沙、お願いね」
真衣が泣き続ける理由をわざと取り違えて美幸は白々しく頷き、改めて美沙に向かっておむつの交換を指示した。
*
インターフォンのチャイムが鳴ったのは、美沙が美幸に指図されるまま、真衣のおむつを取り替えるためにオーバーパンツを膝の上まで引き下ろし、おむつカバーの腰紐をほどいて、一番上のスナップボタンに指をかけた時のことだった。
「はい、どちら様でしょうか。――ええ、はい。あ、そうなんですか。はい、門扉は開いていますから、どうぞお入りください。玄関もすぐに開けますので」
ポケットから取り出したインターフォン用の受話器を耳に当て、最初は怪訝そうにしていた美幸だが、途中からはすっかり納得顔で頷いて、廊下を玄関に向かって歩き出した。
「誰か来たの、ママ?」
真衣のおむつカバーの前当てを開きながら美沙が尋ねた。
「新聞の集金よ」
美幸は振り向きもせずに短く応え、足早に玄関に向かう。
「い、いや。集金のおばさんを玄関に入れちゃ駄目!」
美幸の返答を聞くなり、真衣が、おしゃぶりを咥えているせいでくぐもりながらも悲痛な声で叫んだ。
「何を言ってるの、真衣ちゃんてば。もう日も暮れてお外は真っ暗なのよ。せっかく集金に来てくださったのに、そんな失礼なことできるわけないじゃない」
おむつカバーの横羽根を左右に開きながら美沙が教え諭すように言った。
「だって、だって……」
このままじゃ、おむつを取り替えられてるところを見られちゃう。涙声でそう言いかけた真衣だが、もうその時には美幸がドアを開け、中年の女性を玄関の中に招き入れていたため、喉まで出かかった言葉を飲み込むしかなかった。
「初めまして。数日前から同居している者です」
自分の方に注意を惹かぬよう言葉を飲み込み泣き声も押し殺す真衣の様子をちらと窺ってから、美幸は、集金の女性にお辞儀をした。
「先月の集金の時に、ご主人からお話はうかがっています。これからもご贔屓に、よろしくお願いいたします。こちらのお宅はご主人と学生の娘さんということで昼間はお留守のことが多いから夕方になってから集金にうかがわせているんです。もしも夕飯時でしたらご迷惑をおかけして申し訳ございません」
女性も恐縮ぎみに深々と頭を下げる。
「迷惑だなんて、とんでもありません。こちらこそ、うちの事情に合わせていただいてありがとうございます」
初対面の挨拶をかねた二人のとりとめのない会話はいつまでも続きそうで、廊下の真ん中に敷いたバスタオルに横たわっておむつを取り替えられている真衣としては、集金の女性の注意がいつこちらに向けられるかと気が気ではない。今はただ、少しでも体を動かさないよう気をつけ、息をひそめているしかない。
だが、真衣のそんな様子を面白そうに眺めていた美沙が、悪戯めいた笑みを浮かべたかと思うと
「あら、どうしたの。大好きなガラガラを持たせてもらったんだから、思いきり振っていいのよ。ほら、ころころ〜」
とわざと大きな声で言い、美幸を真似て真衣の掌を自分の掌で包み込んで、強引にガラガラを振らせた。
もうすっかり聞き慣れたかろやかな音が廊下に響き渡った。
途端に、それまでは初対面の美幸とのやり取りに夢中だった女性の注意が美沙たちの方に向けられる。
「あら、お嬢さんもいらっしゃったんですね。気がつきませんで、申し訳ありません。私がこちらに寄せていただいたおりに時々顔を会わせるお嬢さんとは違いますわね――あの、失礼なことを伺うようですけど、奥様の方のお嬢様ですか?」
美幸の肩越しに廊下の奥へ目を向けた女性は、美沙にの存在に気がつくと、少し慌てたような表情を浮かべつつも、いかにも興味津々といった様子で問いかけた。
「ええ、そうなんです。美沙といって、高校の一年生なんです。この子が対応に出た時もよろしくお願いします。――美沙、あなたからも御挨拶なさい」
美幸は、女性の誤解をいいことに、すっかり母親然とした様子で美沙に声をかけた。
「初めまして。あの、ちょっと手が離せないもんだから、こんな格好で失礼ですけど、これからよろしくお願いします」
美沙は、体は真衣の方に向けたまま、首だけを巡らせて女性の方に向き直り、ちょこんと頭を下げた。
「いいえ、そんな、お気になさらなくて結構です。見たところ、赤ちゃんのお世話にお忙しそうですから。こちらこそ、お取り込みの最中に伺ってごめんなさい。おむつを取り替えてあげている赤ちゃんは――妹さんかしら?」
廊下の真ん中あたりに美沙がいることに気づいた女性は、美沙の体のすぐそばにおいてあるバスケットに目をやると、少し考えてから言った。
玄関に入ってすぐの所に立っている女性からだと、バスケットの中が手に取るように見えるわけではない。それでも、大きい方のバスケットに重ねて収められているのが布おむつとおむつカバーだということはぱっと見ただけでわかるし、小さい方のバスケットに収納してある小物類が何なのかも、さほど目を凝らさなくても簡単に見て取れる筈だ。二つのバスケットに収められているおむつカバーの表地やよだれかけの生地の色合いから、それを使うのが女の子だと判断するのも難しいことではない。
「はい、そうです。妹で、名前は真衣っていいます。私と追いかけっこをして遊んでたんですけど、途中でおむつを汚しちゃったもんだから、ここで取り替えてあげているんです」
美沙の大きな体に遮られて、女性のいる位置からだと、真衣の姿は殆ど見えない。実際、真衣の方からも美沙の体しか見えず、集金の女性は声が聞こえるだけだ。それでも、赤ん坊そのままの格好をさせられて廊下の真ん中でおむつを取り替えられている場面に新聞店の顔馴染みの女性が現れたものだから、どうしていいかわからず、ただただ身をすくめるしかできないでいるところに、美沙が真衣の名前を告げたものだから、それこそ、わっと叫んでその場から逃げ出しそうになってしまう。
が、幸いなことに、いくら顔馴染みとはいっても、配達先の家族一人一人のことまで詳しく憶えているわけではなさそうで、『真衣』という名前を聞いても女性は興味をしめすことなく、
「そう、お名前は真衣ちゃんというの。しっかりお世話をしてあげてね。――面倒見のいいお嬢さんをお持ちで羨ましいですわ。うちの上の子なんて、下の面倒なんてちっともみないで遊びあるいてばっかりで」
と、再び美幸との会話に戻った。
しかし、自分への興味が薄れたと思って真衣が安堵の溜息をついたのも束の間。美沙がまたもや真衣の掌を持って強引にガラガラを振らせたものだから、その音につられて、女性の関心が改めて真衣の方に向けられる。
「それにしても、体の大きな赤ちゃんのようですね。いえ、上のお嬢さんの向こうにいるからよくは見えないんですけど、ガラガラを持っている右手だけは見えるものですから」
女性の言葉に、真衣の顔がこわばった。
便器に座ってのおしっこを最後まで諦めきれずにトイレに向かって右手を差し伸べ、その差し伸べた手にガラガラを握らされたものだから、右手だけは美沙の体に遮られることなく女性の視界に入っていてもおかしくない。赤ん坊の玩具であるガラガラに対して、それを持つ掌の異様に大きなことに女性が気づいても不思議ではない。それでも、まさか、時おり応対に出てくる少女が廊下の真ん中でおむつを取り替えられている赤ん坊と同一人物だなどとは想像もつかない女性にしてみれば、いささかの違和感を覚えつつも、随分と体の大きな赤ちゃんだなと思うのがせいぜいだった。
「でも、上のお嬢さんもまだ高校生のわりに体が大きくていらっしゃるし。将来はお二人とも宝塚のスターにでもなれるんじゃないかしら。――あら、もうこんな時間。明日も早いんだから、うちも急いで夕飯にしないと。では、こちらが領収書になります。すっかり長居をしてしまって申し訳ございません。どうぞ、これからもご贔屓に」
どこか釈然としない思いを抱きながらも、女性は無理矢理自分を納得させるように言ってお世辞笑いを浮かべ、ちらと腕時計に目をやると、少し慌てた様子で、そそくさと踵を返した。
「いいえ、こちらこそ」
「また来てくださいね。その時は真衣ちゃんの顔を見てやってください。――ほら、真衣ちゃんもお見送りするのよ」
玄関を出て行く女性の後ろ姿に向かって二人は揃って挨拶をし、美沙は真衣にガラガラを振らせた。
ガラガラがかろやかな音をたてる中、女性の姿が見えなくなるまでのほんの僅かな間が、真衣にとっては、いつ終わるともしれない長い長い時間に感じられてならなかった。
|