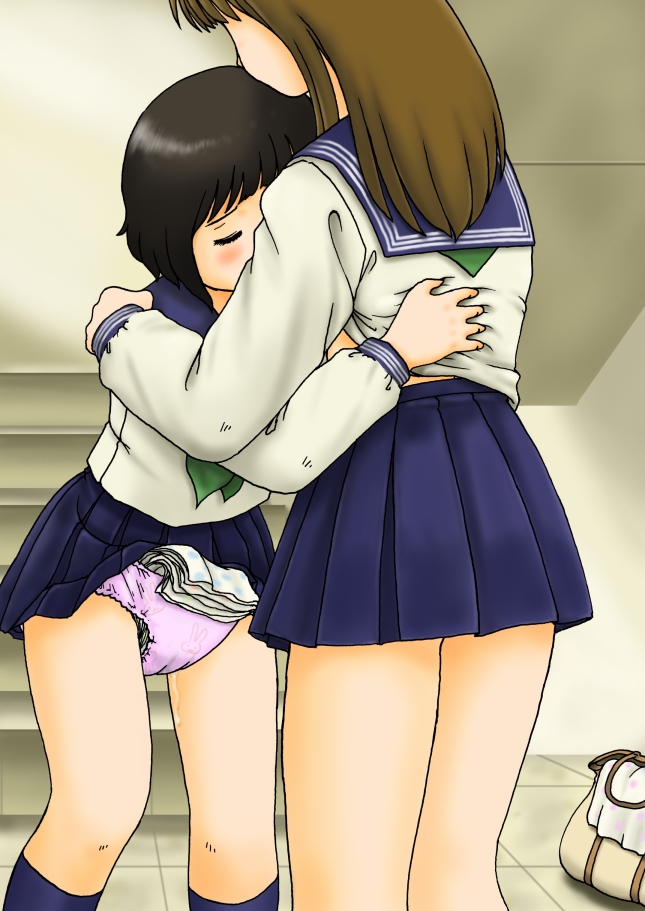|
《21 保健室にて》
美沙が真衣の異変に気づいたのは、一時間目の授業が始まって三十分ほど経った頃のことだった。
いや、正確にいうと、それまでも真衣が何かに耐えるように拳をぎゅっと握りしめたり、どこか辛そうに肩で息をするといった仕草を目にしていたものの、わざと無視していたというのが本当のところだ。だが、もうそろそろいいだろうと判断し、今更ながら気づいたかのように行動を起こすことにしたというわけだった。
「先生、ちょっとよろしいでしょうか」
美沙は、背中を丸めて唇を噛みしめている真衣の様子をちらちら窺いながら、さっと右手を挙げた。
「はい、どうかしましたか?」
それまで黒板に向かって板書をしていた教師がくるりと振り向き、美沙の顔を教壇から真っ直ぐ見て言った。
「あの、授業中に申し訳ないんですけど、佐藤さんの具合が悪いようなので保健室へ連れて行ってあげたいんです。許可していただけるでしょうか」
美沙は、いかにも級友の体調を案じる保健委員然とした殊勝な態度で応じた。
「あ、そうなんですか。私の方こそ気づいてあげられなくてごめんなさい。つい授業に夢中になっちゃって。もちろん、いいわよ。大変なことにならないうちに早く連れて行ってあげなさい」
教師は、机に突っ伏せんばかりにしている真衣を見て、少し慌てたような様子で美沙に指示した。しかし、どこか好奇に満ちた口調で『大変なことにならないうちに』と言ったことから察するに、この教師も真衣の『病状』がどんなものなのか美幸から聞かされているのは明かだ。
「わかりました。じゃ、佐藤さんを保健室へ連れて行きます。――さ、保健室へ行きましょう。鈴木先生に診てもらえば、すぐに具合もよくなるから」
美沙は教師に向かって恭しくお辞儀をしてから自分の席を離れ、真衣の傍らに立って優しく声をかけた。
が、真衣はなかなか椅子から立ち上がろうとしない。もともと弱気なところのある真衣だから、級友たちの視線を浴びながら教室をあとにするのが躊躇われるという理由もあるが、それ以上に、このまま、美幸が待つ保健室に連れて行かれてどんな目に遭わされるのかと思うと、美沙の言葉に易々と従うことはできない。
そんな真衣の態度に、美沙は腰をかがめ、真衣の耳元に唇を寄せてこんなふうに囁きかけた。
「いつまでも愚図愚図していると、真衣ちゃんがどんな病気で学校を欠席していたのか、みんなに話しちゃうわよ。ママ、先生方には本当のことを話したけど、今のところ、生徒には伝わってないみたいね。でも、真衣ちゃんがお姉ちゃんの言うことに逆らったりしたら、私からみんなに話すことにするわ。みんなに話して、真衣ちゃんのお世話を手伝ってもらうの。じゃないと、言いつけを守らない我儘な真衣ちゃんの面倒なんてみきれないもの」
その言葉に、一瞬だけ恨みがましい目で美沙の顔を睨みつけた真衣だが、結局は、のろのろと立ち上がり、悄然とした様子で自分の席を離れるしかなかった。
「すぐに保健室へ連れて行ってあげるから、心配しなくていいのよ」
ようやく立ち上がった真衣の肩を抱き寄せて、美沙は、いかにもしっかり者の保健委員という演技を崩さずに言った。真衣の肩を抱き寄せたのが、真衣のことを気遣ってのことなどではなく、真衣が逃げ出すのを防ぐためなのは言うまでもないところだ。
*
担任からの連絡事項が多くていつになくホームルームが長引き、ホームルームと一時間目の授業との間の休憩時間が殆ど取れなくなってしまったせいでトイレへ行きそびれ(もっとも、休憩時間がたっぷりあったとしても、トイレへ行くことは美沙に妨げられていたに違いないのだが)、限界近くまで高まった尿意のためにそれまでも覚束ない足取りだったのが、教室を出て廊下を進み、一階へおりる階段の途中にある踊り場で、とうとう真衣はそれ以上歩けなくなってしまった。
「どうしたの、真衣ちゃん? こんな所にいつまでもいたりしたら、恥ずかしい失敗をしちゃうんじゃないかな。保健室へ連れて行ってあげるっていうのは口実で、本当はトイレへ連れて行ってあげようとしてるんだってことは真衣ちゃんにもわかってるでしょ? だから、ほら、おしっこで階段を汚しちゃう前にさっさと歩かなきゃ」
真衣の足が止まってしまった理由を充分に承知していながら、美沙は僅かに首をかしげて言った。
しかし、真衣は息も絶え絶えだ。
「や、やだ……もう歩けない。お腹が痛くて、もう歩けないんだから」
一時間目の授業に遅れるのを覚悟の上で美沙の目を盗んででもトイレへ行っていればこんなことにならずに済んだかもしれないが、そんなことをして後でどんな仕打ちを受けるかしれたものではないという怯えが先にたって、次第に高まってきた尿意を堪えて授業に臨んだため、とうとう自分で尿意をコントロールできる範囲を超えてしまい、下腹部に痛みを覚えるまでになって、教室に戻ることもかなわず、トイレへ向かって歩き続けることもできないという惨めな状態に陥ってしまった真衣だった。
「そう。もう歩けないの。じゃ、仕方ないわね。ここで出しちゃいましょう」
真衣の力ない返答を耳にするなり、まるで逡巡するふうもなく美沙は言った。
「そ、そんな……」
「だって、仕方ないでしょ?」
「でも、でも、もうすぐ一時間目が終わって休憩時間になっちゃうんだよ。ここを通る誰かが階段が濡れてることに気づいたら……」
両脚の内腿を擦り合わせ、顔色を失って尿意を堪えながら、真衣は弱々しく首を振った。
それに対して美沙はこともなげに
「そうね、いくらトレーニングパンツとオーバーパンツを重ね穿きしているといっても、おむつじゃないんだから、外へ漏れ出しちゃうでしょうね。だったら、こうすればいいじゃない」
と言うと、教室を出る時から持ってきていた布製の手提げ袋を真衣の目の前に突き出した。
「え……?」
思いがけない美沙の行動に、真衣は内腿を擦り合わせながら要領を得ない表情を浮かべて美沙の顔を見上げた。
「替えのパンツを入れてきた袋なんだけど、念のために、こんなのも持ってきたのよ。よかったわ、無駄にならなくて」
きょとんとする真衣の目の前で、美沙は手提げ袋を左手で底から抱え上げるようにして口を広げ、無造作に右手を突っ込むと、水玉模様の布地をつかみ上げた。
布地の端には、『さとうまい』という名前がピンクの糸で刺繍してあった。
「……!」
「そうよ、昨夜から真衣ちゃんにあててあげている布おむつよ。お家じゃおむつの赤ちゃんだけど、お外じゃパンツのお姉ちゃんの真衣ちゃんだから要らないかなと思ったんだけど、念のために持ってきておいたの。でも、まさか、本当に役に立つことになるなんてね」
美沙は、手にした布おむつをこれみよがしに振ってみせてから手提げ袋を踊り場に置き、おむつをいったん袋に戻すと、真衣のすぐ目の前に歩み寄り、制服のスカートをぱっと捲り上げた。
「な、なに……!?」
慌ててスカートの裾を押さえた真衣だが、もう手遅れだった。トレーニングパンツの上に重ね穿きしたオーバーパンツが丸見えになってしまう。
「あまり大きな声を出すと、職員室に聞こえるわよ。そしたら、何があったのかと思って先生方が来ちゃうんじゃないかな」
美沙は、悲鳴をあげかける真衣をやんわりと制し、丸見えになったオーバーパンツのウエスト部分に両手の指をかけて、トレーニングパンツと共に膝の上までさっと引きおろした。
再び喚き出しそうになった真衣だが、悲鳴を聞きつけた教師が駆けつけ、恥ずかしい姿を見られたらと思うと、そこまで出かかった声を飲み込むしかなかった。
「それでいいのよ。いい子ね、真衣ちゃんは」
美沙はにまっと笑って、踊り場に置いた手提げ袋に改めて右手を突っ込み、今度は布おむつを六〜七枚まとめてつかみ上げたかと思うと、それを手早く広げて、膝のすぐ上まで引きおろしたトレーニングパンツの内側に重ね入れた。
「……!?」
真衣の口から声にならない悲鳴が漏れる。
美沙は、布おむつがトレーニングパンツの中で丸まってしまわないよう両側の端を軽く引っ張るようにしながら、オーバーパンツとトレーニングパンツをまとめて手早く引き上げた。
そうすると、再び真衣の下腹部はパンツに覆い隠されるのだが、トレーニングパンツのパット部分の厚みに布おむつの厚みも加わって、オーバーパンツがますます丸く膨らみ、それが普通の下着などでないことが一目でわかるようになってしまう。しかも、トレーニングパンツもオーバーパンツも股がみは浅くないのだが、美沙の重ね入れ加減のためだろう、布おむつの両端がオーバーパンツのウエスト部分からはみ出て名前の刺繍が見え隠れし、真衣の羞恥をこれでもかと煽りたてるのだった。
「さ、これで、おもらしをしちゃっても階段を濡らさずにすむわよ。トレーニングパンツもオーバーパンツもおむつカバーみたいに防水性の生地でできているわけじゃないけど、中にこれだけ布おむつを重ねておけば、そう簡単におしっこが沁み出してくることはない筈だもの」
美沙は、もこもこに膨らんだオーバーパンツの上から真衣のお尻をぽんと叩いてから、ようやく制服のスカートをおろした。
だが、これで済んだわけではない。
本当の恥辱はこれからだ。
「だから、安心して、さ、いらっしゃい」
美沙は自分のセーラー服のリボンをすっと緩め、手早く胸当てを外すと、胸元を大きくはだけ、美幸からプレゼントしてもらった授乳用ブラのカップをおもむろにずりおろした。
と、セーラー服の胸元から、張りのある乳房がいささか窮屈そうに現れ、ぴんと勃った乳首が丸見えになる。
「こ、こんな所で……!?」
真衣は思わず体を退いた。
だが、いつのまにか壁際に追い込まれていたようで、一歩も後ずさりできない。
「おしっこを我慢しすぎてお腹が痛いんでしょう? それで、もう、トイレまで歩くこともできないんでしょう? だから、私がちゃんとしてあげたんじゃない。ここでおしっこを出しちゃっても大丈夫なように、トレーニングパンツの中におむつを重ねてあげたんじゃない。だから、さ」
美沙は、怯えきった表情で弱々しく首を振ることしかできないでいる真衣の後頭部を右手の掌でそっと包み込み、大きくはだけた自分の胸元に引き寄せて、階段を一段だけ昇った。もともと真衣よりも頭一つ背の高い美沙がそうすると、美沙の胸元と真衣の顔とが殆ど同じ高さになる。
美沙は右手で真衣の頭を手前に引き寄せながら、左手を裾の方から自分の制服に差し入れて、あらわになった乳房を下から支え待ち、ぴんと勃った乳首を真衣の唇に押し当てた。
「いや! やだってば、こんな所で……」
首の動きを封じられ、唇をこじ開けるようにして美沙の乳首が入ってくるのを感じながら、真衣は喘ぐように言った。
「駄目、いつまでも駄々をこねてないで、おしっこをするのよ。早くしないと、授業が終わって、みんながここを通るのよ。みんなが見ている前でおむつとトレーニングパンツをおしっこで汚したいの?」
美沙は、自分の乳首を真衣の口にふくませ、真衣の耳元でねっとり絡みつくように囁きかけた。
「いや、そんなの、いや……」
真衣は、よく注意していないとわからないほど小さく首を振った。言われなくても、いつまでもそうしていられるわけがないことも痛いほどわかっている。わかってはいるのだけれど……。
「そうよね、そんなの、いやよね。だから、ほら」
美沙は、真衣に自分の乳首を咥えさせたまま軽く胸を反らせた。
一瞬だけ間があって、真衣の唇がおずおずと動き始める。
「そう、それでいいのよ。お姉ちゃんのおっぱいをたっぷり吸って、たくさんおしっこするといいわ。真衣ちゃんはママやお姉ちゃんのおっぱいを吸いながらじゃないとおしっこもできない甘えん坊さんなのよ。高校の制服を着ていても、赤ちゃんそのままオーバーパンツとトレーニングパンツと布おむつでお尻をくるんでいる甘えん坊さんなのよ。だから、お姉ちゃんがおっぱいをちゅうちゅうさせてあげている間におしっこを出しちゃおうね」
もう押さえつけていなくても大丈夫と判断した美沙は、真衣の後頭部から右手を離してそのままそっとおろし、背中を優しくとんとんと叩いて言った。
そうして、真衣が躊躇いつつも微かに頷くのを見て取ると、右手を更におろし、今度は、スカートの裾をそろりと掻き分けて、ぷっくり膨れたオーバーパンツの股間に掌をそっと押し当てた。
「あ……」
真衣の口からか細い喘ぎ声が漏れた。
けれど、美沙の乳首から口を離す気配はない。
「学校へ来る時はパンツのお姉ちゃん。それも、きちんと制服を着た女子高生。でも、結局、それは見た目だけだったわね。本当は真衣ちゃん、お家にいる時も、よそにお出かけする時も、学校へ行く時も、いつもいつも、おむつの赤ちゃんのままなのよ。だから、恥ずかしがらないでおしっこしちゃおうね。大丈夫よ、トレーニングパンツの中のおむつがちゃんと吸い取ってくれるから」
美沙は、それまで自分の乳房を支え持っていった左手を制服の裾から抜き、人差指と中指で真衣の喉を撫でた。
「やだ、そんなこと言っちゃ。いじわる、美沙お姉ちゃんのいじわる……」
拗ねたように、けれど聞きようによっては甘えてでもいるかのようにそう言う真衣の腰がびくんと震えた。
その直後、美沙の右手の掌に微かな感触が伝わってくる。
ニットのオーバーパンツ越しに伝わってくるそれは、生温かい液体が真衣の恥ずかしい部分から溢れ出して布おむつに吸い取られながらじわっと広がってゆく感触に他ならなかった。
「意地悪なんかじゃないわよ。本当のことしか言ってないんだから」
美沙はオーバーパンツから手を離し、もういちど真衣の背中を撫でさすって、微かに笑いを含んだ声で囁きかけた。
「だって、だって……」
真衣は、自分の方から体をすり寄せるようにして乳首を吸いながら、上目遣いに美沙の顔を見て言った。
「いいから、今はおしっこを出しちゃいなさい。授業が終わるまでに出しちゃって、パンツを替えに保健室へ行かなきゃいけないんだから。真衣ちゃん、こんな格好を誰かに見られるのはいやなんでしょう?」
美沙は、それまで指先で真衣の喉を撫でていた左手をそっと広げ、今度は真衣の頬を掌で包み込んで言い、それに対して真衣がいかにも恥ずかしそうに目をそらすのを見て、悪戯めいた口調で付け加えた。
「でも、お姉ちゃんはそれでもいいんだけどな。いいっていうより、こうしてるところ、誰かに見てほしいくらいなんだけどな。だって、そうしたら、お姉ちゃんと真衣ちゃんとの関係を誰にも遠慮せずにおおっぴらにできるんだもの」
「いじわる。お姉ちゃんてば、本当にいじわるなんだから……」
真衣は『いじわる』という言葉を繰り返し口にしつつも、美沙の乳首をちゅぱちゅぱ音をたてて吸うのはやめなかった。
もちろん、その間、おしっこもとめどなく溢れ出ておむつを濡らし続けている。
「また、そんなことを言う。でも、そんな真衣ちゃんが可愛くてたまんないんだけど」
美沙はくすっと笑って真衣の頬を指先でつんとつついた。
こつこつという硬い足音が階下から聞こえてきたのは、まさにその時だった。
はっとした様子で真衣は美沙の乳首から口を離そうとした。
しかし、美沙が
「駄目よ。まだおしっこを出しきっちゃってないでしょ?」
と、やんわり叱りつけるように言って却って強く体を抱き寄せるものだから、その場から逃れることはできない。
「や、やだ……」
真衣は乳首を咥えたままのくぐもった声で呻いた。
「平気よ。こうしておけば、真衣ちゃんが何をしているかわからなくなるから」
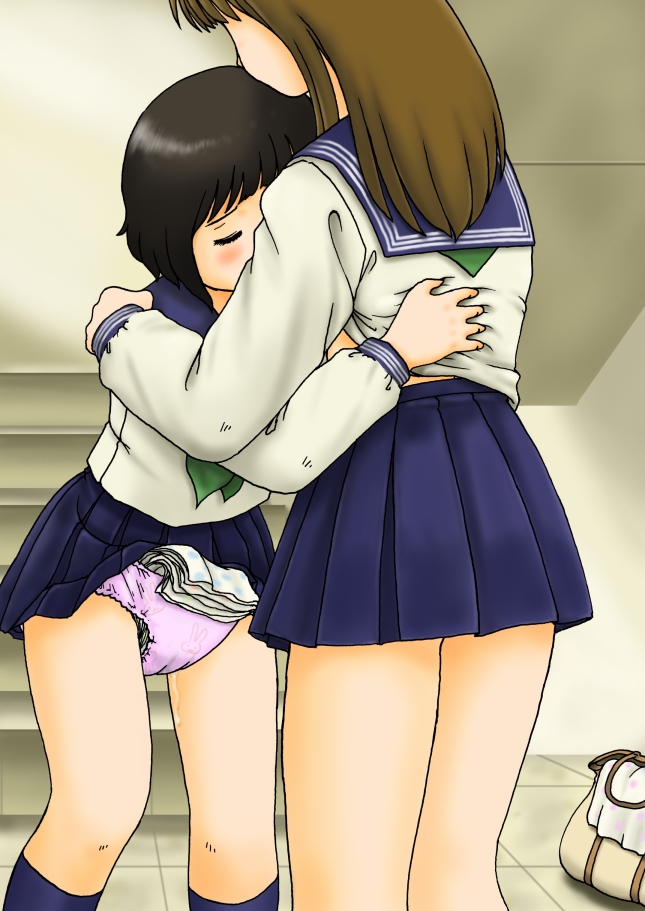
小刻みに肩と腰を震わせる真衣の体を抱きすくめたまま、美沙は微妙に立ち位置を変えた。こうすると、階段を昇ってきた者が二人に目を向けても、美沙の広い背中の陰になって、真衣が美沙の乳首を口にふくんでいるところまでは見えない。
「本当? 本当に平気?」
真衣はいかにも不安そうな面持ちで美沙の顔を見上げ、助けを求めるように頬を乳房に押し当てた。
それは、まるで、人見知りの激しい幼児が初めて訪れる場所で誰かが近づいて来る気配に怯え、母親の胸にすがりつくかのような仕草だった。
「大丈夫だから、お姉ちゃんにまかせておきなさい」
美沙は真衣の髪をそっと撫でつけた。
その間にも、足音は次第に大きくなってくる。
そうして、いよいよ。
「あら、こんな所で何をしているの?」
二人のすぐ近くでぴたっと足音が止まり、代わりに、訝しげな声が飛んできた。
声の主は担任の教師だった。
「はい、あの、佐藤さんが授業中に気分が悪くなったから、保健室へ連れて行く途中なんです。ただ、途中でますます具合が悪くなっちゃったらしく、歩くのもやっとみたいだから、介抱してあげているところなんです」
美沙はまるで慌てる様子もなく、わざとおおげさな身のこなしで真衣の背中をさすってやりながら、しれっとした顔で応じた。
「そうだったの。だったら、職員室に残っている先生方にお願いして、佐藤さんを保健室へ連れて行くのを手伝っていただくようにしましょうか? 少しでも人手があった方がいいでしょう?」
美沙の背中に阻まれて、真衣が実際は美沙の乳首を口にふくんで乳房に顔を埋めているところまでは見えない。窺い知ることができるのは、真衣が踊り場の壁にもたれかかるようにして顔を美沙の胸元に押し当てているらしいということくらいだ。担任は美沙の言葉を簡単に信じ込んで、いかにも心配そうに言った。
「あ、いいえ、大丈夫です。もうかなりましになってきたみたいですから。そうよね、真衣ち……佐藤さん?」
美沙は落ち着き払った物腰で応え、真衣の背中をとんとんと叩いた。
「だ、大丈夫です。お姉ち……杉下さんが介抱してくれたおかげで大分よくなりましたから。……杉下さんに保健室まで連れて行ってもらえば、もう平気です」
美沙に促されて、真衣は途切れ途切れに応えた。
「そう。なら、いいんだけど。じゃ、私は次の授業の準備で資料室へ行かなきゃいけないから、あとのことは杉下さん、お願いね」
真衣の声がくぐもっていたが、担任は、貧血ぎみになった真衣が倒れるのを防ぐために美沙の胸元に顔を押し当てているせいだろうと勝手に思い込み、まるで怪しむふうもなく、あっさり頷いた。
と、踊り場に置いたままになっている手提げ袋が担任の目に留まる。美沙が布オムツを取り出すために広げた口がそのままだから、手提げ袋の中は丸見えだ。
「これは……」
手提げ袋の中には、替えのトレーニングパンツや、美沙がつかみ上げた残りの布おむつが入っていた。それを目にした担任の口を困ったような声が衝いて出る。
その瞬間、担任に何を見られたのか、真衣にもおおよその見当がついた。
だが、担任は慌てて声を飲み込むと、僅かな間を置いて
「……それじゃ杉下さん、佐藤さんのことはくれぐれもよろしくね」
と言い残し、さっとその場を離れた。
「もういいかな。おしっこはもうみんな出ちゃったみたいね」
真衣と体を密着させていた美沙は、担任の姿が階上に消えるのとほぼ同時に真衣の腰がぶるっと震えるのを感じて、これ以上はないくらい優しい口調で念を押すように問いかけた。
そうして、美沙の乳首を咥えたまま喘ぐように熱い吐息を漏らしている唇をそっと押し離し、左手で真衣のスカートの裾をそっと捲り上げると同時に、右手の掌を両脚の間、普通のショーツならちょうどクロッチ部分にあたるところに押し当てた。
「あらあら、中に布おむつを重ねておいたから大丈夫かなと思っていたけど、おむつカバーと違って、トレーニングパンツじゃおしっこが沁み出すのを防ぐのは無理だったみたい。このままだとせっかくおむつが吸い取ってくれたおしっこが漏れてきちゃうから、早く保健室へ行ってママに取り替えてもらわないといけないわね」
掌を押し当ててすぐ、おしっこがオーバーパンツの表面まで沁み出しているのが感じ取れた。しかし美沙は何度も右手を離したり押し当てたりを繰り返し、わざと手間をかけてパンツの様子を探ってから言った。
が、じきに思い直したようにおおげさな仕草で首を振り、真衣の顔を見おろしてこう告げる。
「あ、でも、その前に真衣ちゃんにしてもらわなきゃいけないことがあったわね。お姉ちゃんが調べてあげただけじゃ思い違いってこともあるから、真衣ちゃん本人から教えてもらわなきゃいけないんだったわ。どう、真衣ちゃん? おしっこしちゃったの?」
だが、真衣は何も応えられない。学校の階段の踊り場で、そんなことを聞かれても応えられるわけがない。
しかし、美沙は澄ましたものだ。
「いいわよ、だんまりを続けたいなら続けていても。ただ、もうすぐ授業が終わって、みんながここを通るのよ。その頃には、おしっこがオーバーパンツの表面から雫になってぽたぽた滴り落ちているかもしれないわね。いいのね? おしっこを漏らしてるところを同級生や先輩たちに見られても」
と冷たく言い放つと、手の甲を腰に押し当てて真衣の目を見据える。
「い、いや……そんなの、いやっ」
美沙に言われて真衣は身をすくめた。
「じゃ、ちゃんと教えられるわね。あ、そうそう。どうやって教えればいいか、それもわかってるでしょうね? 夜のうちに何度も同じようにしてママやお姉ちゃんにおしっこを教えてくれたんだから、まさか忘れてないわよね?」
美沙は嵩にかかって言った。
「どうやっておしっこを教えればいいかって……」
一瞬、要領を得ない顔になる真衣。
だが、美幸にお腹を叩かれ子守唄を聴かされながら寝かしつけられた後、今朝になるまで何度もおむつを濡らすたびマイクを通して二人を呼ばされたあの屈辱に満ちた光景が脳裏にありありとよみがえってくる。
「忘れてなんかいないわよね?」
美沙は有無を言わさぬ調子で決めつけた。
「……」
為すすべなく押し黙ってしまう真衣。
「忘れてなんかいないわよね?」
美沙はしれっとした顔で、けれど執拗に繰り返した。
追い詰められて、とうとう真衣は微かに、それこそ、瞬きしている間に見落としてしまいそうになるほど僅かに頷いた。
そうして、弱々しく息を吸い込むと、
「……おぎゃあ……」
と、昨夜から今朝にかけて何度も繰り返しそうしたように、赤ん坊の鳴き真似をしてみせる。
「それでいいのよ。おしっこをちゃんと教えられるなんて、本当に真衣ちゃんはいい子だわ」
美沙は真衣の頭を何度も撫でながら、含み笑いを漏らして言った。
*
保健室の入り口に取り付けてあるインターフォンのボタンを押すと、少しだけ待って
『お待たせしました。クラスと氏名をお願いします』
という事務的な声がスピーカーから流れてきた。
それに対して
「一年三組の杉下美沙です。同じクラスの佐藤真衣さんが気分が悪いようなので連れてきました」
と、こちらも事務的に美沙が応じると、
『わかりました。入ってください』
という返答があって、ドアのあたりからカチャリという微かな機械音が聞こえた。
保健室の中では、様々な診察や相談、カウンセリングが行われる。時には、上半身のみならず下半身まで裸になることもあるし、他人には聞かせられないような深刻な相談が持ち込まれることもある。そういった生徒のプライバシーを守るため、啓明女学院では、担当教諭の許可がないと保健室に入室できないようになっていると共に、保健室内の話し声が外に漏れないよう、厳重な防音措置が施されているのだ。そのため、保健室に用がある者は、まずインターフォンで来意を告げ、中にいる教諭に遠隔操作式の電磁錠を開けてもらうという手順を踏む決まりになっている。
美沙が押し開いたドアから保健室の中に足を踏み入れた真衣が最初に見たのは、白衣をまとった美幸の姿だった。
「あら、まだ一時間目も終わってないのに、早速なの?」
おどおどした様子で入り口の近くに佇む真衣の姿を目にするなり、もう誰かに聞かれる心配もなくなったためだろう、インターフォン越しに聞こえた事務的な声とは打って変わって、くだけた口調で美幸は言った。いかにも呆れたような様子なのは、美沙が真衣を連れてきた理由をすっかりお見通しだからに違いない。
「そうなのよ。お家にいる時と同じ、学校でも二時間くらいが精一杯みたい」
こちらも廊下からインターフォン越しに話していた時の殊勝な様子はすっかりなりをひそめ、馴れ馴れしい調子で美沙が短く応じた。真衣がこれまでに数え切れないくらい何度も恥ずかしい粗相を繰り返したせいで、たったそれだけの説明で全てが通じてしまう。
「やれやれ、困った子だこと。それで、廊下や階段は濡らさなかったの?」
「それは大丈夫よ。ほら、こうしてあげたから」
美沙は、入り口の近くに立ちすくむ真衣のスカートをぱっと捲り上げた。
股間のあたりがじっとり濡れたオーバーパンツと、パンツの股がみから端だけが見えている布おむつがあらわになる。
「ああ、そういうことなのね。いいわ、じゃ、パンツからぽたぽた滴り落ちるようになる前に替えてあげましょう」
美幸は一目で事情を察し、にっと笑って頷いた。
「でも、困ったな。一応、替えのトレーニングパンツは持ってきたけど、久しぶりの登校早々トイレに間に合わなかったくらいだから、これからどうなるか心配で。授業中、私が気がつかないままだったら、教室の椅子に座ったままとうとう我慢できなくなってしくじっていたかもしれないのよ。そんなことになったら、トレーニングパンツとオーバーパンツじゃ、おしっこを吸い取れるわけがないし。今みたいにトレーニングパンツの中に布おむつを重ねるにしたって、あと一回分しか残ってないんだもの」
大きく頷く美幸に向かって、口では『困ったな』と言いながら実はまるで困った様子もみせずに美沙が言った。
それに対して、執務机の椅子に腰かけていた美幸がおもむろに立ち上がりながら言った。
「別に、困ることなんてないわよ。こっちへいらっしゃい。ちょうど乾燥も終わったところだから」
「え? 乾燥って?」
美沙が聞き返した。
だが、真衣に気づかれないよう互いに目配せを交し合ったところを見ると、美幸となにやら前もって打ち合わせを済ませているのは明かだ。
「ほら、こっちよ」
執務机から離れた美幸は足早に室内を横切り、奥まったところにある目立たないドアを引き開け、美沙に向かって目で合図を送った。
「ママは何をしたいのかしら。ほら、真衣ちゃんも一緒に見に行きましょう」
合図を受けた美沙は真衣の手首をつかんで、強引に奥のドアの前に連れて行った。
奥まったところにあるドアの先は、薬品棚や、健康診断の時に使う身長計や体重計、肺活量を測定する器具等を収納しておく器具庫になっていた。
だが、その一角に新品の洗濯機が置いてあるのがなんとも場違いな感じがして、美沙に促されて器具庫の中を覗き込んだ真衣は思わず首をかしげてしまう。
「授業が終わっても、ママは部活がみんな終わるまで保健室にいなきゃいけないの。特に運動部の生徒が練習中に怪我をすることがあるからね。それに、美沙お姉ちゃんも自分の部活があるから、真衣ちゃんをお家に連れて帰ってあげられない。だから、私たちがお家に帰るのは、どうしても七時前くらいになっちゃうの。でも、そうすると、朝に洗濯物をして干してきたりすると、お家に帰った頃はとっくにお日様も沈んでいるから、せっかく干してきた洗濯物がまた湿気を吸っちゃってるのよ。寝る前に出た洗濯物だったら全自動の洗濯機に放り込んでおけば朝になったら乾燥も終わってるけど、お出かけ前ぎりぎりに出た洗濯物はそうもいかないの。そのくらいのこと、真衣ちゃんにもわかるわよね?」
真衣の疑念を察した美幸はそう説明して、家にあるのと同じように乾燥機能の付いた真新しい洗濯機の前に歩み寄った。
そうして、真衣の顔を見据えて意味ありげに微笑み、こんなふうに問いかける。
「もちろん、お利口さんの真衣ちゃんだもの、朝のお出かけ前ぎりぎりに出る洗濯物っていうのが何なのか、それもわかるわよね?」
「あ……」
一瞬は怪訝な表情を浮かべた真衣だが、すぐに美幸が言わんとしていることに見当がついた。
「そうよ。だから、お家から持ってきて、学校でお洗濯をすることにしたの。ここに洗濯機を置かせてもらうことについては、前もって校長先生のお許しもいただいているから心配しなくて大丈夫よ」
美幸は改めてにっと笑い、洗濯機の扉を引き開けた。
洗濯機の中には、昨夜から今朝にかけて真衣が汚した布おむつの山ができていた。
「美沙お姉ちゃんの妹さんからお下がりのおむつを貰えたのはいいけど、枚数がぎりぎりなのよ。本当の赤ちゃんだったら一度にあてるのはせいぜい三枚くらいだけど、真衣ちゃんの場合は一度に十枚近くあてなきゃいけない上に、二時間に一度はおむつを汚しちゃうから、汚したらすぐ洗濯しておかないと、一日もつかどうかってところかな。だから、汚れたおむつをそのままお家に置いとけなくて、洗濯機を置かせてもらえるよう校長先生にお願いしたのよ」
真衣がおむつを汚すようになってしまったのは自分の企みのせいなのに、そんなことはまるでおくびにも出さず、美幸はどこか恩着せがましい口調で言った。
「よかったね、真衣ちゃん。この洗濯機なら、洗濯から乾燥まで二時間くらいで済んじゃうよ。これなら、学校でもパンツやおむつを幾ら汚しちゃっても大丈夫ね」
洗濯機の中から布おむつを何枚か取り出しながら、美沙が明るい声で言った。
そして、おむつの山の下の方に埋もれているカラフルな布地に気づくと、尚さら声を弾ませる。
「あ、おむつカバーも洗濯してたんだ。そうだよね、おむつカバーも汚れたらすぐ洗濯しとかないとシミになって取れなくなっちゃうもんね」
美沙は弾んだそう言うと、さっと広げた布おむつを自分の肘にかけ、改めて洗濯機に右手を突っ込んだ。
美沙が洗濯機から取り出したおむつカバーは二枚。一枚は、昨日の夕方から今朝まで真衣のお尻を包み込んでいた、横当てのおむつを使うタイプのおむつカバー。もう一枚は、真新しい股おむつ用のカバーだ。
「あれ? こっちも洗濯したの?」
美沙は、一枚目のおむつカバーを布おむつに重ねて肘にかけ、後から取り出した股おむつ用のカバーを両手で広げて美幸に尋ねた。
「そうよ。汚れていたのは昔ながらのおむつカバーだけなんだけど、股おむつ用の方も水通しをしておきたかったから。それに、洗濯をして乾燥すると生地によっては縮むことがあるから、そのへんがどうなのか確かめたかったっていうこともあるから。――でも、これなら大丈夫ね。さすが、しっかりした縫製だわ」
美幸は、美沙の手から股おむつ用のカバーを受け取り、サイズや生地のよれ具合を確認して満足そうに頷いた。
「あ、そういうことだったんだ」
美幸の説明に美沙も頷き返し、きらりと瞳を輝かせて言った。
「じゃ、どうせだから、そのおむつカバーを使って真衣ちゃんにはきちんとおむつをあててあげた方がいいんじゃないかしら。お出かけの時はパンツってことになってるけど、現に今だって、トレーニングパンツの中に重ねたおむつを汚しちゃってるんだし。だいいち、パンツだけだったら、私が気づかないうちに授業中にしくじって、おしっこが椅子や床をびしょびしょにしちゃうかもしれないじゃない? そんなことになったら教室中が大騒ぎになって、先生たちに迷惑をかけちゃうもの。トレーニングパンツの中におむつを重ねても、時間が経ったら結局おしっこが沁み出してきちゃうんだから、おむつカバーを使ってきちんとおむつをあててあげた方が真衣ちゃんのためになるんじゃないかしら」
「ま、待ってよ。そんな、学校でもおむつだなんて、そんな……」
「そうね、その方がいいかもしれないわね。パンツだったら、絶対に失敗しちゃいけないって精神的な負担になるけど、きちんとおむつをあてておいてあげれば、いつしくじってもいいやって気分が楽になって、却っておしっこを我慢できるかもしれないわね。実際しくじっちゃっても、保健室に来れば誰にも知られずに取り替えてあげられるんだし。どうせ洗濯機も用意したんだから、おむつを汚しても、そのたびに洗って乾かしてあげられるしね」
顔色を失って首を振る真衣の言葉を遮って美幸が同意した。
「じゃ、決まりね。昨日の夕方、ママ、説明してくれたよね。股おむつ用のカバーの方が少しは見た目がすっきりしているから、もしもお出かけの時におむつをあててあげるんだったら、こっちの方がいいのよって。だから、そっちにしましょう。昨夜のおむつカバーと見た目がどれくらい違うのか興味もあるし」
言葉を遮られてもまだ弱々しく首を振る真衣のことなどまるで眼中にないかのように美沙は決めつけると、いったん美幸に手渡した股おむつ用のカバーを再び手にして踵を返し、窓寄りの場所に二つ並んで据え付けてあるベッドに向かって歩き出した。
「さ、真衣ちゃんも行くのよ。いつまでも濡れたおむつとパンツのままじゃ体によくないわ」
美沙が歩き出すと同時に、美幸が真衣の背中をぽんと押した。
*
美沙が手前のベッドにおむつカバーを広げ、その上に洗濯したての布おむつを重ねる様子を窺い見ながら、美幸は、ベッドから少し離れた所に立たせた真衣のスカートに指をかけ、サイドファスナーをさっと引き下げた。
ウエストの締めつけがなくなったスカートはなんの抵抗もなくぱさっと床に落ち、今にもおしっこの雫が滴り落ちんばかりになっているオーバーパンツが丸見えになる。
「さ、美沙お姉ちゃんがおむつの用意をしてくれている間にママがパンツを脱ぎ脱ぎさせてあげるわね。あ、その前に靴を脱ぎ脱ぎさせてあげなきゃいけないんだっけ。――でも、こうしていると、先週のことを思い出しちゃうわね。お買い物に出かけた時とか、パパをお見送りに空港に行った時も、ママはこんなふうにして真衣ちゃんのパンツや紙おむつを脱がせてあげたんだったわよね」
美幸は膝を折ってその場にしゃがみこみ、ショッピングセンターや空港のトイレでの恥ずかしい場面を真衣に思い出させながら学校指定の革靴を右足、左足と順番に脱がせ、続いてオーバーパンツのウエスト部分に指をかけて、足首のすぐ上のところまで引きおろした。そうして、靴を脱がせたのと同じ順序で足を交互に上げさせ、ぐっしょり濡れた布おむつやトレーニングパンツごとオーバーパンツを脱がせてしまう。
その後、美幸は再び器具庫に向かい、洗濯機の横に置いておいたバケツの中に脱がせたばかりのパンツや布おむつを滑り込ませてから、ぐるりと壁際に沿って歩き、幾つか並んでいる収納棚の内の一つの前に立って、一番上の小振りの引出を開けると、家から持ってきておいたお尻拭きの容器と塗り薬の容器を取り出して、おむつの用意を終えたばかりの美沙に手渡した。
「まさか、学校でもこれを使うことになるなんて思ってもみなかったわね。でも、トイレまで我慢できなく階段の途中でおもらしをしちゃうような真衣ちゃんだもん、まだパンツのお姉ちゃんにはなれそうにないから仕方ないわね」
保健室のベッドの上に広げられた布おむつとおむつカバーを目の前にし、下半身を丸裸に剥かれて唇を噛みしめるばかりの真衣に向かって少しばかり皮肉めいた口調で言って、美沙は保健室の床に膝立ちになった。
「ん……」
もう数え切れないくらい繰り返し経験してきたのに、決して慣れることのないひんやりした感触が下腹部から伝わってきて、か細い喘ぎ声が真衣の口を衝いて出る。
それに続いて、ねっとりした塗り薬を二種類、恥ずかしい部分に丹念に塗り込まれる、羞恥きわまりないのに、どこかぞくぞくするような感触。
教室に比べ幾らか明るさを抑えた照明になっている保健室のの中で繰り広げられる一連の出来事。それが、どこか遠い世界の情景みたいに感じられて仕方ない。けれど、それは、紛うことなき自らの身の上に起こっている羞恥と屈辱に満ちた出来事に他ならない。
丹念に薬を塗り込まれた後、真衣は二人に体を抱え上げられるようにして、おむつの上にお尻をおろしてベッドに横たわらされた。
「や……」
こちらも決して慣れることのない、布おむつの想像以上に柔らかな肌触り。
「すぐに済むからおとなしくしててね、上はセーラー服だけど、下はおむつのおもらし赤ちゃん」
美沙は真衣の左右の足首を左手で一つにまとめてつかみ、高々と差し上げた。そうして、お尻の下に敷いてある布おむつを、わざと丁寧に一枚ずつ両脚の間を通して、その端をおヘソのすぐ下まで持ってゆき、じっくり時間をかけて真衣の下腹部を自分の妹からのお下がりの柔らかなおむつで包みこんでゆく。
と、布おむつを半分ほどあてたところで、壁に取り付けてある小振りのスピーカーから一時間目の終わりを告げるチャイムが聞こえ、それに続いて、おむつを全部あて終えて真衣の足をベッドにおろしたところで、今度はインターフォンの呼び出し音が鳴った。
「はい、どうしました?」
ふと手を止めた美沙の顔にちらと視線を走らせて、美幸が、執務机の上に置いてあるインターフォンに向かって話しかけた。
『一年三組の園田です。同じクラスの佐藤さんの容態を確認に伺いました』
美幸の問いかけに応じて返ってきたのは、真衣たちのクラスの委員長・園田茉莉の落ち着いた声だった。
「わかりました。すぐに鍵を開けるから、少しだけ待っていてください」
美幸も落ち着いた声でそう応え、美沙の方に振り返って目配せをした。
それに対して美沙も無言で頷き返し、持ち上げかけていたおむつカバーの横羽根をそのままにし、真衣のお腹の上に毛布をかけて下半身を隠してしまう。
その間に美幸は執務机から離れて器具庫のドアを閉め、そのすぐそばに落ちていた真衣のスカートを拾い上げると、ベッド脇に置いてある付き添い用の椅子の背もたれに掛けて、収納棚の引出がちゃんと閉まっていることを確認してから、遠隔操作式の鍵を開けるボタンを押した。
「いいですよ、入ってください」
カチャリという音が聞こえて鍵が開いたのを確認し、美幸は改めてインターフォンに向かって言った。
「失礼します」
待つほどもなくドアが開いて、縁の太い眼鏡に三つ編みのお下げ髪といういかにも優等生然とした茉莉が姿を見せ、美幸に向かって恭しくお辞儀をしてから、つかつかとベッドに近づき、横たわっている真衣の顔をそっと見おろして確認するように言った。
「熱があるんでしょうか。なんだか、佐藤さん、顔が赤いみたいですけど」
真衣の顔が赤いのは、学校の保健室のベッドでおむつをあてられるという想像もできないほどの羞恥に満ちた仕打ちのせいだ。しかも、かろうじて毛布一枚だけで隠されているとはいえ、おむつをあてられる途中の下腹部を級友の目にさらしているのだから尚更だった。が、茉莉が本当の理由に気づく由もない。真衣の体調を気遣って発したその言葉が、ますます真衣の恥辱を煽りたてる。
「ええ、少し熱が高くなったみたいね。私としては、もう少し、ここで様子を見た方がいいと思っているの」
美幸はさりげなく茉莉に話を合わせ、胸の中で舌を突き出しながら、事務的な口調で応えた。
「そうですか。じゃ、次の授業は体育なんですけど、見学も無理ですね。わかりました。体育の先生には、佐藤さんが欠席すること、私から伝えておきます」
眼鏡越しに尚も真衣の顔色を窺いつつ、茉莉が言った。
「ええ、そうしてあげて。一時間ゆっくり休めば元気になるでしょうから」
悠揚迫らぬ様子で美幸は頷き、ベッドの横に佇んでいる美沙の方に向き直って言った。「それじゃ、杉下さんも授業に戻ってください。佐藤さんのことは私にまかせてもらえばいいから」
「わかりました。体育の授業が終わったらすぐに着替えて、佐藤さんを迎えにきます」
本当は美幸と一緒にずっと真衣の世話をしていたくてたまらないが、必要以上に保健室に居残ったりすれば茉莉に怪しまれるかもしれない。咄嗟にそう判断した美沙は美幸の言葉に素直に応じることにした。お楽しみはこれからだ。今はまだ、三人の関係を誰にも気づかせるわけにはゆかない。
*
美沙と茉莉が出て行くのを待って、美幸は、保健室の窓にかかっているブラインドを開けた。
窓から見える校庭は、春盛りの太陽の光を浴びて眩いほどだ。が、保健室の方は、ブラインドを全て開け放っても方角の都合で直射日光が差し込まず、室内の明るさが幾らか増しただけだった。しかし、美幸がブラインドを開けたのは室内を明るくするためなどではなく、保健室から校庭をよく見渡せるようにするためだった。校舎と校庭とは木々の植え込みで隔てられているものの、季節柄まだ葉完全には生い茂っていないため、ブラインドを開けてしまえば意外に視界が開けるのだった。
だが、それは、逆に言えば、校庭から保健室の様子を窺い知ることができるというにもなる。
「閉めて、早くブラインドを閉めて……」
もう少しで美沙以外の級友にまでおむつ姿を見られるところだった恥辱にまだ頬を赤く染めながら、真衣はベッドの上で首を振った。
「だって、美沙お姉ちゃんが保健室からいなくなっちゃって寂しいでしょう? でも、次の授業は体育らしいから、こうしておけば、元気に走り回るお姉ちゃんの姿を見ていられるのよ。真衣ちゃんが寂しがらないようにお姉ちゃんの方からも手を振ってくれるかもしれないじゃない。だから、しばらくこうしておこうね」
ブラインドを開けるためにそれまで窓際に立って真衣に背中を向けていた美幸だが、視界を遮らないようベッドをはさんで窓と反対側に移動しながら、むずがる幼児をあやすように言った。
そうこうしているうちにも着替えを終えた級友たちが二人三人と校庭に姿を現し、最後に、美沙と茉莉が少し遅れて級友たちの輪に加わるのが、窓ガラス越しに見えた。
真衣がベッドの上で身をすくめると同時に、二時間目の始まりを告げるチャイムが鳴った。
体育を受け持つ教師が大きく右手を挙げてホイッスルを吹き鳴らし、それまで思い思いに体を動かしていた生徒たちが一斉に駆け出して校庭の真ん中に整列する。
「さ、体育の授業が始まったことだし、真衣ちゃんはおむつをあてちゃおうね。美沙お姉ちゃんが見えるから寂しくなんてないでしょう?」
美幸がわざと優しく微笑みかけて言い、真衣のお腹にかかっている毛布に手をかけた。
「だ、駄目。これを取っちゃ駄目。みんなにおむつを見られちゃう。だから取らないで。お願い、先生」
真衣は慌てて両手で毛布の端をつかんだ。保健室のベッドに横たわった状態で美幸のことを『ママ』と呼ぶのも躊躇われて、今にも泣き出しそうな声で懇願する。
「あら、また、私のことを『先生』だなんて呼んでる。たしかにここは学校だから、誰かがいる所じゃ『先生』って呼ばなきゃ変に思われるけど、私や美沙お姉ちゃんしかいない所じゃお家と同じ『ママ』と『お姉ちゃん』でいいのよ」
美幸は優しく教え諭すように言い、そのままの口調でこんなふうに続けた。
「おむつを見られちゃうから毛布を取っちゃ駄目ですって? でも、仕方ないじゃない。真衣ちゃんはセーラー服を着ていても、おしもはおむつの赤ちゃんなんだから、おむつを見られても仕方ないじゃない。それとも、もうすっかりパンツのお姉ちゃんになった気でいるのかな? じゃ、いいわよ。着替える時、たっぷりのおむつでぷっくり膨らんだおむつカバーをクラスのみんなに見られるのが恥ずかしいだろうなって思ったから、体調がまだ思わしくないからっていう口実で真衣ちゃんの体育は見学で済ませてもらえるよう先生方にお願いしたんだけど、パンツなら見られても恥ずかしくないわよね? だったら、クラスのみんなと一緒に着替えることもできるから、きちんと体育の授業を受けられるわね。いいわ、明日の朝の連絡会議で、体調も戻ってきたからもう体育の授業も大丈夫ですって伝えておくことにする。――トレーニングパンツとオーバーパンツもパンツには違いないんだから、見られても平気よね?」
「……」
これ以上の懇願と抵抗は無意味だということを痛いほど思い知らされ、真衣は返す言葉を失った。返す言葉を失って、のろのろと毛布から手を離すしかなかった。
「やっと聞き分けのいい真衣ちゃんに戻ってくれたみたいね。いいわ、やっぱり、当分は体育の授業は見学でお願いしますって先生方にもういちど言っておいてあげる。それでいいのね?」
それでいいのね? 念を押すように美沙が言った言葉に二つの意味が込められているのは明白だった。一つは、文字通り、体育の授業は見学でいいのね?という意味。そしてもう一つは、これからは学校でもパンツじゃなくておむつよ、それでいいのね?という意味に他ならない。
だが、なすすべなく毛布から手を離してしまった真衣には、二つの意味合いを同時に受け容れるしかなかった。
「じゃ、いつまたおもらししちゃってもいいように、おむつをちゃんとあてちゃおうね。おむつをあてておけば、授業中でも朝礼の途中でも、いつしくじっちゃっても大丈夫だから」
美幸は改めて真衣の体から毛布を矧ぎ取った。
その間に、春の体育大会に向けた準備の一環なのだろう、校庭では級友たちが幾つかのグループに分かれて互いに短距離走や走り幅跳び、ハードル走といった種目のタイムや距離を測り始めていた。
と、自分の計測までに間ができたのか、美沙が、体育の教師に気づかれないようさりげなく、こちらに向かって手を振ってみせた。
それに気づいて、真衣の胸がどきんと高鳴り、羞恥のあまり頬ががっと熱くなる。
「は、早くして……早くおむつをあてちゃって……」
頬を真っ赤に染めながら、真衣は窓からも美幸の顔からも視線をそらして弱々しく訴えかけた。
「あら、どうしたの? おむつなんて嫌じゃなかったの?」
真衣の胸の内などすっかりお見通しのくせに、美幸はわざと不思議そうに聞き返した。
「だって、だって……」
美沙を真似て他の級友たちもいつ何時こちらの様子を窺おうとするかもしれない。現に、真衣の具合を確認するために保健室にやって来た茉莉も、さりげくこちらに向かってちらちらと視線を走らせているのだ。級友たちは最初の集合場所よりも向こう側でタイムを測定し合っているから保健室からはかなり距離があり、真衣がおむつの上にお尻を載せた状態でベッドに横たわっていることを前もって知らなければ、今の光景も、美幸らしき人影が保健室の中で動いているみたいだなという程度にしか判別できないだろう。が、たとえば記録用紙が風に飛ばされ、それを追いかけて保健室の近くまで走ってきた級友がひょいと窓を覗き込むようなことがあったりしたら、美幸の手で真衣がおむつをあてられている場面を目の当たりにすることにもなりかねない。
今の真衣には、少しでも早くおむつをあて終えて再び体に毛布をかけてくれるよう美幸に哀願することしかできなかった。
だが、真衣のそんな思いをわざと取り違えてみせ、ようやく事情がわかったとでもいうようにぱっと顔を輝かせて美幸はこう言った。
「ふぅん、そうなんだ。真衣ちゃん、お家でも『早くおむつをあてて』って言ったことがあるし、やっぱり本当はおむつが大好きになっちゃったのね。でも、そうよね。おむつをあてていれば、お家だったらトイレに間に合わなくてもいいし、学校でも無理して休憩時間になるまでおしっこを我慢しなくていいんだから、おむつを好きになっちゃうのも当たり前よね。いいわ、わかった。じゃ、すぐにおむつをあててあげる。真衣ちゃんの大好きなおむつをね。その代わり、当分はパンツのお姉ちゃんにはなれないのよ。でも、それでいいよね。だって真衣ちゃんはおむつが大好きな、いつまでもおむつ離れできない赤ちゃんなんだから」
美幸は優しい声ながらも有無を言わさぬ調子で言い、あらためて真衣の下腹部を眺めて、こう決めつけた。
「うふふ。やっぱり、そうみたいね。もしもおむつが嫌だったら脚や体を動かして少しでもおむつをどけようとする筈なのに、真衣ちゃんのおむつ、美沙お姉ちゃんに途中まであててもらってから今まで、全然ずれたりしてないわよ。これって、柔らかくて優しいおむつの肌触りが気持ちいいからおとなしくしてたってことよね」
美幸はそう決めつけて妖しく微笑む。しかし、途中まであてられたおむつから真衣が逃れようとしなかったのは、体から毛布が滑り落ちるのを恐れてのことだった。変に体を動かして、そのせいで毛布が滑り落ちでもしたら、おむつに包まれた下腹部を茉莉の目にさらすことになってしまうのだ。だが、そう説明したところで、美幸は取り合おうともしないに違いない。
「早く、早くってば……お願いだから、ママ……」
おむつが好きになってしまったと決めつけられても、何も言い返せない。今の真衣には、一刻も早くおむつをあててくれるようせがむことしかできなかった。
|