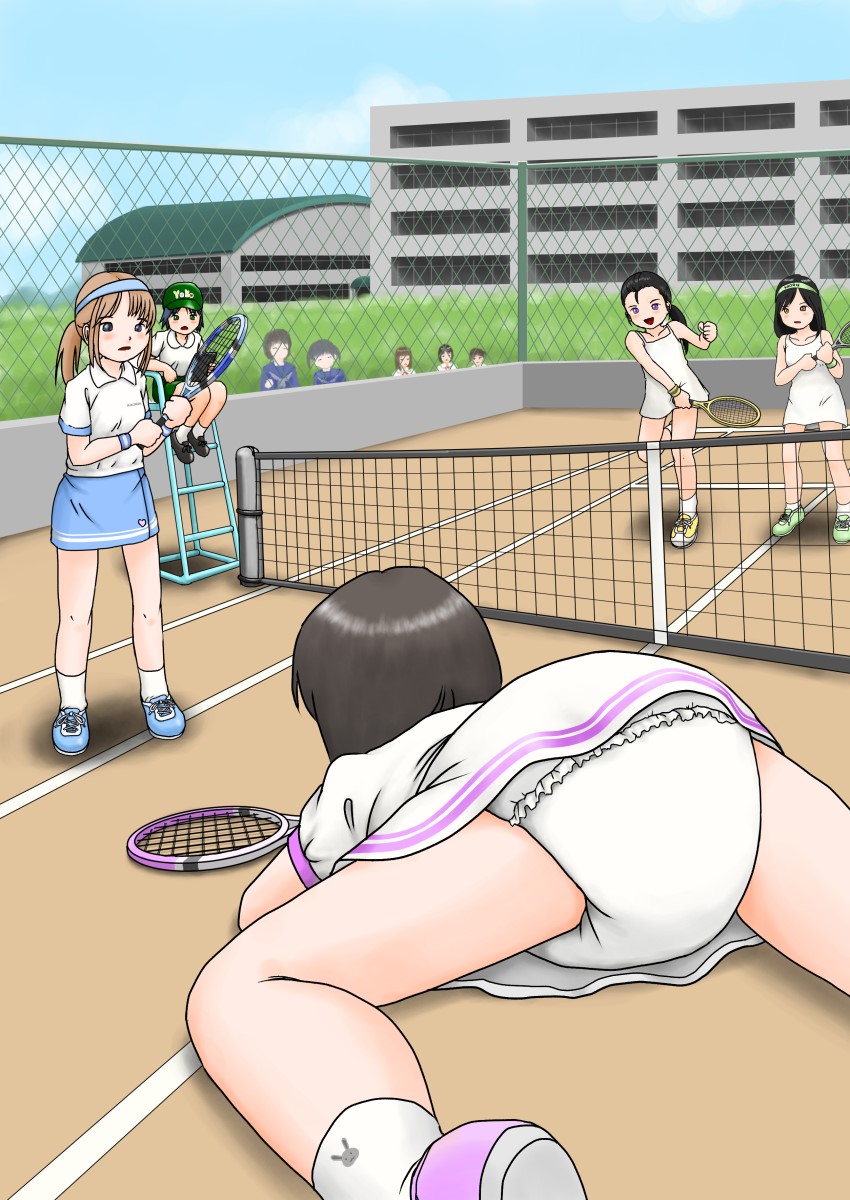|
その日以後も、ことあるごとに京子は美和と幸子のマンションを訪れ、おむつを取り替えてやったり、ガラガラで遊んでやったり、おしゃぶりを咥えさせてやったり、里美と一緒に這い這いをさせてみたりと、恵を存分に赤ちゃん扱いして悦に入っていた。恵が赤ちゃん扱いを拒むこともあったが、その時は
「あらあら、ママの言うことを聞けない悪い子なんだ、メグミちゃんは。だったら、メグミちゃんがお家じゃ赤ちゃんになっちゃうこと、クラスのみんなに話しちゃおうかな。そしたら、家庭科の保育の実習で、みんながメグミちゃんのおむつを取り替えてくれるかもしれないね。あ、でも、だったら、メグミちゃんが本当は男の子だってこともわかっちゃうかな。でも、いいよね。ママの言うことを聞けないメグミちゃんがいけないんだもん。ママのせいじゃないもんね」
と告げれば、恵はすぐに、とっても素直ないい子になってしまうのだった。
その様子を間近で見守っていた美和が胸の中で苦笑する。たまたま病院で出会い、この子は使えそうだと直感して、本人にそうと意識させないまま協力者に仕立てた京子が、今や手練手管を講じて恵をまんまと手懐けるまでになってしまっているのだから、内心舌を巻き、苦笑するしかなかった。
(ひょっとしたら、この子、私と同類なのかもしれないわね)
苦笑しながら、ふと美和は思った。病院の食堂で初めて出会った時の直感は、自分と同じ匂いを京子から嗅ぎ取ったからかもしれないと。
そんな或る日。
その日は行事の都合で学校が半日で終わり、夕方まで恵の面倒をみてやるためにマンションの幸子の部屋を恵と共に訪れたのだが、幸子は、胸元を大きくはだけて里美におっぱいをあげている最中だった。
里美を胸の高さで横抱きにしたまま幸子は
「ごめんね、こんな格好で。里美ったら、本当はもうとっくにおっぱいを卒業してなきゃいけないのに、いつまでもせがんで困っちゃうのよ。ま、せがまれるたびにあげちゃう私もいけないんだけど」
と溜息交じりに言ってから、面白半分に
「ついでだから、メグミちゃんにもおっぱいをあげちゃおうかな。どう、メグミちゃん?」
と、恵に向かってウィンクしてみせた。
だが、そのからかい半分の言葉に反応したのは、恵ではなく京子の方だった。なぜとはなしに幸子の言葉に対抗心を抱いた京子は
「メグミちゃんには私のおっぱいをあげるから、幸子ママのおっぱいは里美ちゃんにあげてください」
とややきつい声で言い、リビングルームのソファに座っている幸子の隣に腰をおろして制服のブレザーを脱ぎ捨て、ブラウスの胸元を大きくはだけて、小花の刺繍をあしらったジュニアブラの肩紐を少し乱暴に外した。
そんな行動を京子が取ったのは、メグミちゃんにもおっぱいをあげちゃおうかなと言われた恵がどことなく物欲しげな目を幸子の胸元に向けたことに気がついたからかもしれない。そう、おそらく、やっかみ半分の咄嗟の行為。だけど、そんな時にこそ本心が表われるものだ。
「さ、こっちへいらっしゃい、メグミちゃん。ここに座って、顔をこっちに向けるのよ」
京子は恵に向かって手招きし、自分の腿をぱんと叩いた。
「で、でも……」
恵は困惑しきりにかぶりを振るが、京子に
「じゃ、メグミちゃんがお家じゃ赤ちゃんで本当は男の子だってこと、クラスのみんなに言っていいのね?」
と迫られると、それ以上は抗えない。
恵は浅い呼吸を何度も繰り返してから、ソファに腰かけている京子の腿に自分のお尻をおそるおそる載せた。
スカート越しながら、京子の腿に、ぷっくり膨れたおむつカバーの感触が伝わってくる。
「それで、そのまま顔をママのおっぱいの方に向けるのよ」
京子は右手の掌で恵の後頭部を包むようにして、そのまま頭を上げさせた。
恵の吐息が乳首にかかって、下腹部がきゅんとなる。
「いいわよ。そのまま、もう少し顔をこっちに向けて」
京子は更に恵の頭を上げさせた。
そうして、空いている左手を乳房の下に添え、中学一年生の少女にしては豊かな乳房を支え上げるようにして乳首を恵の唇に押し当てる。
しばらく逡巡した後、綺麗なピンクの乳首を恵は口にふくんだ。
京子の下腹部がじんと痺れる。
「それでいいのよ。メグミちゃんはおっぱいを吸うのがお上手ね。里美ちゃんと同じくらいお上手かもしれないわね。でも、そうよね。里美ちゃんもメグミちゃんも、赤ちゃんだもの。赤ちゃんだったら、おっぱいを吸うのが上手で当り前よね」
京子は今にも喘ぎ出しそうになるのを我慢して、自分の乳房の乳首あたりを撫でさすった。
それは、我が子に与える母乳を絞り出そうとする母親の本能的な手の動きなのかもしれない。実際に母乳が出るわけがないことを知りながらも、それでも自分の体がつくり出す生命の雫を愛娘に飲ませたいと願う若い母親の。
ちゅぱ……ちゅぱちゅぱ……。
最初は躊躇いがちだったおっぱいを吸う音が次第次第に続いた音になって部屋の空気を震わせる。
その様子を見守っていた幸子が穏やかな笑みを浮かべ、里美の背中を優しく叩いて言った。
「ほら、里美もメグミちゃんに負けないようにたくさんおっぱいを飲もうね。たくさんおっぱいを飲んで早く大きくなって、ママたちと一緒にメグミちゃんのお世話をしてあげようね」
無心に幸子の乳首を吸う里美が小さくこくんと頷いたのは偶然のことだろうか。
しばらくの間、二人の赤ん坊が乳首を吸う音が部屋を満たしていたが、不意に恵の腰がぶるっと震えた。
「どうしたの、メグミちゃん。寒いんだったら、里美ちゃんの毛布を借りてあげようか?」
京子が優しく訊く。
けれど恵は何も答えない。何も答えずにもういちど腰をぶるっと震わせ、京子の乳首をきゅっと噛む。
「つっ……!」
京子の口から呻き声が漏れた。
「メグミちゃんのおむつを調べてあげるといいわ」
隣に腰かけている幸子が、意味ありげな視線を恵の下腹部に投げかけて京子に言った。
言われるまま、京子は恵のスカートの中に左手を這わせ、おむつカバーの股ぐりに指を差し入れた。
「どう?」
しばらく待って、幸子が尋ねる。
「濡れています。メグミちゃんのおむつ、ぐっしょりです」
京子は大きく目を見開いて幸子の顔を見た。
それから、頬をほんのり赤らめて京子の乳首を吸い続ける恵の顔を見おろし、
「おっぱいを飲みながらおむつを汚しちゃうなんて困った赤ちゃんだこと。本当に困った赤ちゃんね、メグミちゃんは」
と、困った困ったといいながらその実ちっとも困った様子など感じられない声で呟いた。
「でも、ママ、とっても嬉しいのよ。ママのおっぱいを飲みながらおむつを汚しちゃったメグミちゃんは、これで本当にママの赤ちゃんになったのよ。だからママ、とっても嬉しいの。嬉しくてたまらないの。さ、もっと吸ってちょうだい。可愛い赤ちゃんのメグミちゃんに噛まれたおっぱいなんてちっとも痛くないのよ。だから、もっともっと吸ってちょうだい」
恵のおしっこでぐっしょり濡れたおむつの感触を楽しむかのように、京子はおむつカバーの股ぐりに差し入れた指でおむつをまさぐり続けながら、熱い吐息と共に囁きかけた。
その時こそが、恵が京子の幼い娘になった瞬間だった。同時に、京子がメグミの若い母親になった瞬間。
その瞬間、恵は、自分が京子と決して離れられなくなってしまったことを実感する。京子がいなければ自分だけでは何もできない無力で頼りない存在に自分が墜ちてしまったことを知らざるを得なかった。自分よりも年下のママに躾けられ、ママの言いつけに従い、ママに頼りきる、素直でいい子になるしかないことを、心の底から痛感する恵の胸中を窺い知ることは難しい。けれど、頬をほんのり染めて京子の乳首を貪る恵の表情を見るかぎり、そのことを拒む様子はまるで見て取れない。
それから更に時が流れて、入学式からちょうど三週間が経った日の放課後。
どの部活を選ぶかまだ決めていない恵に、京子は、自分と同じ軟式テニス部に入るよう勧めた。京子が軟式テニス部を恵に勧めたのは、自分と同じ部活ならいつも一緒にいられるという理由の他に、一応は理にかなった理由もあってのことだった。まず、武道は真っ先に除外しなければならない。柔道や空手など、いくら相手が女子中学生であっても、筋肉がまるでない非力な恵が相手になるわけがない。次に、着用するユニフォームやコスチュームが体に密着して体のラインがあらわになる競技も、恵がおむつを着用していることが一目で知られるから除外することになる。これで、水着やレオタードの類を身に着ける競技はまとめて排除されてしまう。それから、バレーボールやバスケットボールといった、背の高さを求められる競技も駄目。野球やサッカーなどチームプレーを要求される競技も、引っ込み思案で常におどおどしている恵に向いているわけがない。そうなると結局、卓球かテニスしか残らないことになるのだが、卓球は女子選手でもハーフパンツなのでおむつカバーの膨らみが目立ってしまうから、最後に残るはテニスだけという結果になるわけだ。確かに女子テニスなら、おむつカバーの上に少し大きめのサイズのアンダースコートを重ね穿きして、少し丈の長いテニスウェアを着れば、おむつのことを知られずにすむかもしれない。
そんな理由もあって恵は部活として軟式テニスを選んだのだが、その選択が、二人のその後の人生を大きく変える出来事につながることになるとは、その時の二人には知る由もなかった。
ここで結論から先に言ってしまえば、軟式テニス部で恵はさんざんな成績しか残せなかった。下腹部を包むおむつのせいで恵は持ち前の敏捷性を発揮できなかったのだ。相手選手が打ったボールの軌跡を瞬時に判断して落下予想ポイントに向けてダッシュする際、敏捷性と柔軟性のおかげで出足の最初の一歩こそ鋭いのだが、下腹部にまとわりつくおむつのせいでその後が続かず、結局はボールに追いつくことができない。しかも時間が経つにつれて汗をかく量が増し、ただでさえ通気性が良くなくて蒸れやすいおむつが湿っぽくなり、ますます下腹部にまとわりつきやすくなって脚の動きを妨げるといったことに加え、テニスウェアの裾が大きく舞い上がって、おむつのせいで丸く膨らんだアンダースコートがあらわになるのが気になって思いきったダッシュを躊躇ってしまうといった理由も相まってボールに追いつけず、他校との対外試合どころか、部内の練習試合でも恵は惨憺たる結果しか残せずにいた。その上、悪いことに、軟式テニスにはシングルスの試合はなく、全ての試合がダブルスで行われる。言うまでもなく、恵とペアを組んでいるのは京子だ。京子は、戦力にならない恵の分まで自分の力で補おうとするのだが、相手ペアが執拗に恵を狙い撃ちするものだから、小学校時代から地元では知らぬ者のない優秀な競技者である京子にも、なす術がなかった。そんな状態で、六月に行われる新人戦にK女子中学校を代表して出場する選手のリストに恵と京子の名前が記載されるわけがなかった。
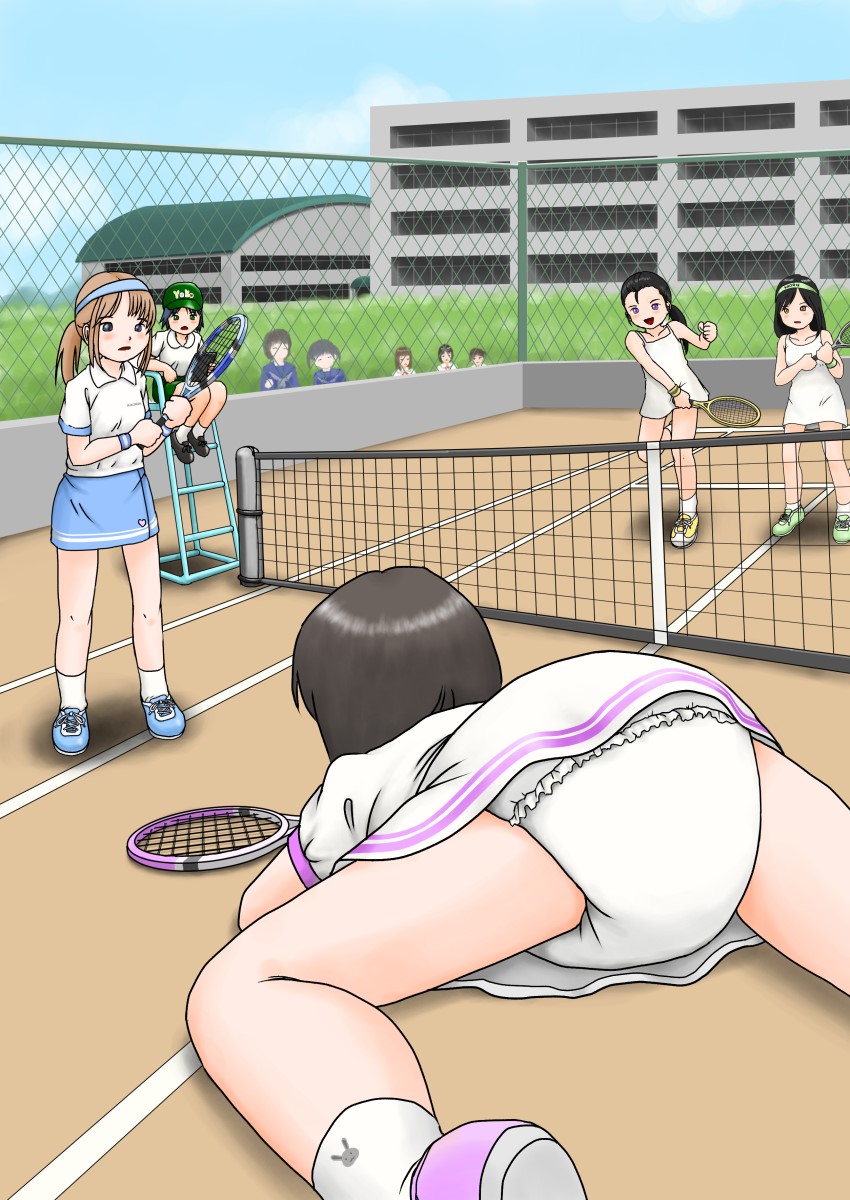
これがもしも硬式テニスだったらシングルスの試合に京子だけでも出場できたかもしれないのにと悔やむ恵の顔は沈痛だった。いや、軟式テニスでも、僕とのペアを解消して他のもっと上手な子と組めば、新人戦で優勝を狙うことだってできる筈なのに……。
「そんな暗い顔してどうしちゃったの、メグミちゃん? 可愛いメグミちゃんにそんな顔は似合わないわよ」
おむつの秘密を知られるのを避けるために他の部員が全員着替え終わるのを待って(ただ待つだけでは不審がられるので、もっと上手になりたいから走り込んできますと偽ってコートの周りを何周かランニングしてから)しんと静まり返った更衣室で着替える恵に、わざと明るい声で京子は言った。
「……わ、私のせいで今日の紅白戦もひどい成績だったよね。……このままじゃ京子ママがスポーツ特待生でいられなくなっちゃうよ。……だから、私とのペアを解消して……」
性別を偽るために自分のことを『私』と呼称しているのがいつしか習い性になってしまった恵が、顔を伏せて声を震わせる。
二人しかいない更衣室。最後まで言葉にできずに途切れてしまった恵の今にも消え入りそうな声が、遮音性の高い壁に吸い込まれてゆく。
「あらあら、変なことを言うのね、メグミちゃんたら。メグミちゃんは今までテニスをしたことなんてなかったんでしょう? それをわかった上でママはメグミちゃんを軟式テニス部に誘ったのよ。だから、どんな結果になっても、それはママのせい。メグミちゃんがくよくよすることなんてないのよ」
汗で濡れたテニスウェアのまま俯く恵の髪をそって撫でつけて、京子は優しく言い聞かせた。
「でも、だって……」
それ以上は何を言っていいのかわからなくなってしまう恵。けれど、自分はどうなっても仕方ないが、京子のことを考えると、このままでいいわけがない。
しばらく逡巡してから恵は、唇を噛みしめて顔を上げ、拳をぎゅっと握ってこう言った。
「……あ、あのね、ママ。私、ううん、ぼ、僕、男の子なんだよ。それも、今年で十七歳の、本当だったら高校生の男の子なんだよ。京子ママよりも四つも年上の男の子なんだよ。なのに、こんな格好をして。……気味が悪いでしょ? 十七歳の男の子なのに中学生の女の子の格好なんかして、おまけに、おむつまでしちゃって。こんな……こんな僕なんて、とっても気味が悪いよね。こんな気味の悪い僕と一緒になんていたくないよね? だ、だから、ペアを解消……」
恵が本当は男の子だということは、恵のおむつを取り替えることになった時に美和から告げられたから、京子も既に承知している。しかし、恵の本当の年齢はまだ京子に伝えていない。それを敢えて伝えることで、ペアを解消する理由にしようと恵は思いついたのだ。今にも泣き出しそうな声でその恥ずかしい事実を告げようとするのだが、やはり最後の方で言葉に詰まってしまう。
「あらあら、思い詰めた顔をして何を言い出すのかと思ったら、そんなことだったの。あのね、いいことを教えてあげようか? メグミちゃんの年が本当は幾つなのか、ママはちゃんと知っているのよ。高校の体操部の練習中に鉄棒から落ちて病院に運ばれたんだってことも知っているのよ、もうとっくに」
京子は自分の腰に手の甲を当て、悲痛な表情を浮かべる恵の顔を覗き込むようにして言った。
「え……?」
思わず恵の唇が半開きになる。
「メグミちゃんの退院が決まった日、美和ママが教えてくれたのよ。本当の年と怪我の原因を教えてくれた後、美和ママ、『たった今私が話したことを承知の上で、退院の日の朝も、メグミのおむつを取り替えてやってほしいの。おむつを取り替えながら、本当は高校生のメグミのお股を、おちんちんも含めて、じっくり見てほしいの。それで、でも京子ちゃんの気持ちが変わらないようなら――本当は男子高校生のメグミのお股を見てもいやな気分にならないようなら、いつかどこかでまた会った時もメグミのおむつを取り替えてやってほしいの。あの子には、全てをさらけ出して甘えられる相手が必要なの。もしも京子ちゃんがいやじゃなければ、あの子を思いきり甘えさせてやってほしいの。甘えさせて、恵からメグミに生まれ変わったあの子のママになってやってほしいの。――私が変なことをお願いしているってこと、自分でもよくわかっている。でも、どうしてもお願いしたいの、京子ちゃんに』って言ってた」
京子は軽く腰を曲げ、自分の顔を恵の顔に近づけた。
「入学式で挨拶の最中におもらししちゃったメグミちゃんを美和ママと一緒に私が保健室へ連れて行ってあげたこと、忘れてないよね? でもって、保健室で私がメグミちゃんのおむつを取り替えてあげたことも忘れてないよね? そうよ、その時も私が取り替えてあげたんだよ、メグミちゃんのおむつ。メグミちゃんが退院する時に美和ママと交わした約束を思い出しながら」
京子はますます顔を近づけ、自分の額を恵の額にそっと触れ合わせた。
「本当は男子高校生のメグミのお股を見てもいやな気分にならないようなら、いつかどこかでまた会った時もメグミのおむつを取り替えてやってほしいの。――美和ママとの約束を守って私はメグミちゃんのおむつを取り替えてあげた。そんな私に今さら何を言っているのかしらね、メグミちゃんは」
京子は、いったん触れ合わせた額を少し離し、こつんともういちど触れ合わせた。
「……」
恵の顔が歪んだ。けれど、その顔に浮かんでいるのは、さきほどまでの悲痛な表情ではなく、泣き笑いの表情だった。
「恵からメグミに生まれ変わったあの子のママになってやってほしいの。――私は約束を守ったよ。だから、メグミも頑張りなさい」 京子は恵のことを『メグミちゃん』ではなく『メグミ』と呼んで、それまでとは打って変わった真剣な声で言った。
「頑張る……?」
泣き笑いの表情で恵が聞き返す。
「そうよ、頑張るのよ。本当の意味で坂本恵から坂本メグミに生まれ変われるように頑張るの。辛い思い出は過去に置いてきちゃって、楽しい将来だけを見て生きてゆくために。私がメグミのこと、思いきり甘えさせてあげて、思いきり優しくしてあげて、思いきり泣かせてあげて、思いきり愛情を注ぎ込んであげる。でもって、きちんと躾けてあげる。私はそうやって、本気でメグミのママになる。本気でママになるって決めたから、もう『メグミちゃん』なんて呼び方はしない。自分の娘に対して、そんな他人行儀な呼び方なんてしない。だからメグミも頑張りなさい。辛い恵の過去なんてどこかに捨てちゃって、明るい将来への希望に目を輝かせるメグミに変れるよう、本気で頑張りなさい。本気で頑張れるよう、ママが励ましてあげる。メグミが本気じゃない時はママが思いきり叱って、変な方に行かないように躾けてあげる。だから、頑張りなさい」
京子は、触れ合わせた額を優しくぐりぐりと動かした。
「……そんなことしちゃ痛いよ、ママ。……痛くて涙が出ちゃうよ」
本当はちっとも痛くなんてない。京子は額を優しく動かしているから痛いわけがない。けれど、そうやって無理矢理にでも理由をつけなければ、泣き出すきっかけがつかめない。
「痛いよ、痛くて泣いちゃうよ、ぼく、……ううん、わたし」
本当は自分よりも四つ年下の京子。京子のためを思ってペアの解消を提案したけれど、それがどんなに薄っぺらな気持ちからの提案だったか、恵は思い知った。本当は四つ年下の京子の方が自分よりもずっと大人だということに気づかされ、少しばかりの屈辱と、そんなもの比べものにならないほどの心のぬくもりを抱いた恵。心のぬくもりが涙の粒になって、今にもこぼれ落ちそうになっている。だけど、そのまま涙を流すのはあまりにも気恥ずかしい。気恥ずかしさを隠すために、涙を流す理由が恵には必要だった。
「おでこが痛くて泣いちゃうよ、私」
もういちど言って、恵は正面から京子の体にすがりついた。
すがりついて
「ふ、ふぇ、ふぇ〜ん。ぅ、うぅ、ぅわ〜ん」
と誰憚ることなく泣き出してしまう。
「いいわよ、泣きなさい。涙が全部かれちゃうまで大声で泣きなさい」
京子は恵の背中に両手をまわして、華奢な体をそっと抱き寄せた。
そんなふうにされて恵の泣き声が大きくなる。
「こんな泣き虫の赤ちゃんのくせして、ママとのペアを解消したいですって? なにを生意気なこと言っちゃうのかしらね、赤ちゃんのメグミが。あ、ひょっとしたら、少し早い『いやいや期』なのかしら?」
京子は冗談めかして言い、抱き寄せた恵の背中を何度も撫でさする。
「だけど、変ね。いやいや期だとしても、おむつが外れてからが普通なのに。でも、ま、いいか。小っちゃい女の子がお姉ちゃんぶってみたくなるのは当たり前のことだしね。お姉ちゃんぶって生意気なこと言ってみたかっただけだよね、メグミは。おむつ離れなんてまだまだ先のメグミがいやいや期を迎えるのはまだまだ早いものね」
京子は恵の背中からお尻へ手を滑らせ、おむつカバーの上に重ね穿きしたアンダースコートの上からお尻を撫でた。
「いじわる。ママのいじわる」
手放しで泣きじゃくりながら、恵は涙でぐっしょりの自分の顔を京子の胸に押し当てた。ママのいじわると拗ねて言いつつも、その口調は京子に甘えているのがありありだ。
「そうよ、ママは意地悪なのよ。とっても意地悪なママなのよ。だから、メグミのお願いなんてかなえてあげない。メグミがどんなにママとのペアを解消してほしいってせがんでも、ママは聞いてあげない。生意気なメグミのそんな我儘なんて、絶対に聞いてあげない。いいわね、わかったわね?」
そう言って京子は再び両手を恵の背中にまわし、さっきよりも強く抱きしめた。
恵は京子の胸から顔を離して、こくんと頷いた。その顔はまだ泣き笑いだったけれど、何か胸につかえていたものが取れたかのように、晴れ晴れした表情が交じっていた。
が、次の瞬間、恵の顔が再び曇る。
それが何を意味するのか、京子はよく知っていた。
「出ちゃったの? それとも、出ちゃいそうなの?」
京子は短く尋ねた。
「……出ちゃいそう……」
両脚をもじもじ擦り合わせて恵が答える。
恵の返事を聞いた京子は、何日か前に幸子の部屋でそうしたように恵の後頭部を右手の掌で包むようにして引き寄せ、恵の顔を再び自分の胸元に押し当てさせて
「赤ちゃんはね、ママの心臓の音を聞くと安心するんだそうよ。さ、こうしていてあげるから、我慢しないで出しちゃいなさい」
と、穏やかな声で囁きかけた。
「……おむつに?」
甘えた口調の恵の声が京子の耳に届く。
「そうよ。メグミは赤ちゃんだもの」
京子は、聞く者の心をとろとろにしてしまいそうな甘ったるい声で囁きかけた。
恵の顔に、なんとも表現しようのない表情が浮かぶ。
たっぷりおしっこを溜め込んだ膀胱の緊張が解ける開放感からとも、京子の胸の鼓動を耳にしての安心感からとも、どちらとも取れる安堵の表情だった。
これまで京子にじわじわ手懐けられてきた恵が遂に身も心も全てを京子に委ねた瞬間の、屈服と安堵が入り交じった表情だった。
*
――遊鳥小学校に転校してきたばかりの愛くるしい『少女』の下着がショーツではなくおむつで、中学一年生の従姉のことを『ママ』と呼んでいるのは、こんな経緯があってのことだった。
けれどこれだけでは、K女子中学校から京子と共に遊鳥清廉学園へ転校したきた恵が小学校に編入することになった理由まではわからない。
続けて、そのあたりの事情についても振り返ってみることにしよう――。
*
恵と京子のペアがさんざんな成績しか残せない上、ペアを解消する様子もないことに業を煮やした理事長は、二人に二ヶ月間の部活動停止処分を申し伝えるようK女子中学校の校長に命じた。校長としては、本来は優秀なスポーツ特待生である京子については穏やかな処分で済ませたいというのが本音だったが、
「せっかく汚名返上の機会を与えてやったのに、こちらの温情を踏みにじり、しかも、ようやくスカウトできた有力テニスプレイヤーである井上京子の才能までも危うくする気か、あの莫迦な生徒は!」
と激しい怒りを理事長が恵に対して抱き、その恵とのペアを解消する意向を示さない京子に対しても理不尽な怒りを向けてしまっているという状況では、自分の一存で京子への処分を軽くすることができる筈も無かった。
部活動停止処分を受けたとなると、たとえ他校に転校したとしてもその処分記録がずっと付いて回り、転校した先の学校での部活動においても対外試合への出場の機会を与えられない等の不利益をこうむる恐れも強いのだが、そんな重い処分を言い渡されても、京子は平然としていた。
京子は確かに優れた競技者であるが、それは、努力を積み重ねてきたからではなく、持って生まれた天賦の才によるところが大きい。そして、そんな、いわゆる天才肌の競技者の場合、それまで一身に打ち込んできた競技に対する興味を突如として失い、その競技からあっさり身を退いてしまうということがままある。努力を積み重ねた末にようやく優れた競技結果をつかみ取るといったタイプの競技者だと、これまでの努力とトレーニングに費やした時間を無駄にすまいとして、多少の事情があっても競技を続けるために足掻くものだが、生まれつきの才能の結果として輝かしい栄冠を幾つも難なく手中に収めてきた者は、その点において、実に淡泊なことが少なくない。それを潔いと評価する声もあるし、他の競技者に対して失礼だとなじる声も聞こえるが、天才肌の競技者は、そんな声を気に留めることさえしない。
京子もそんな、才能の赴くままテニスを続けてきた競技者だった。だから、部活動停止処分を申し渡されても、ああ、そうなんだと無感情に受け取るだけで、感傷めいた心の動きは微塵もみせなかった。それどころか、これで授業が終わった後は心おきなくメグミの世話をやいてあげられると、むしろ清々しい気持ちさえ抱くほどだった。また、京子本人だけでなく、夫婦共に外資系のコンサルタント会社勤めで忙しい毎日を送っている両親も、京子の自主性を重んじていると言えば聞こえはいいが、要するに、育児放棄に近い状態で放任しているというのが実情で、そんな些細なことを気にかけることなどしなかった。
つまるところ、理事長が下した部活動停止処分というのは、京子にとってはいささかも『処分』の意味を持たない、滑稽な茶番でしかなかった。いや、意味をもたないどころか、テニスへの愛着を京子から奪ってしまったのだから、理事長が意図するところとは真逆の結果を招いたと言う他ないだろう。
処分期間に入って最初の土曜日。
本来なら休日もテニス部の練習に明け暮れているところだが、処分のおかげで土曜日も日曜日も平日の放課後も自由に時間を使えるようになったのだから皮肉なものだ。自由な時間が増えたとなると恵の面倒をみるために美和と幸子のマンションを訪れていると思われるかもしれないが、実はその日、京子が赴いたのは全く別の場所だった。
是非ともお会いしたいという連絡を受け、招待状に同封してあったチケットで新幹線のグリーン車に乗り、駅からは迎えの高級車で京子が訪れたのは、医療法人『慈恵会』の応用医療技術研究所。その中央棟の最上階に位置する理事長室だった。
理事長室の中は更に幾つかの部屋に別れており、京子が案内されたのは、質素で落ち着いた内装の応接室。
京子がソファに腰をおろして待つほどもなく分厚いドアが開き、中年の女性が姿を現した。女性から受け取った名刺に記されていたのは、『医療法人慈恵会 理事長 笹野美雪』の文字。
「どうぞ、遠慮なさらずに。飲みながら私の話を聞いていただければ結構です」
京子の向い側にすっと腰をおろした美雪が、京子の目の前の飲み物が手付かずのままなことに気がついて穏やかな表情で勧める。
「あ、はい……」
京子は小さく頷いたが、なぜとはなしにその場の雰囲気に気圧され、飲み物に手を伸ばそうとはしない。
「これからお話しする内容は、聞き慣れない述語も含まれますし、一般常識とは少し異なる概念に基づく論理展開も含まれますので、中学生くらいの年代の方に理解していただくのは少し難しいかと思います。ただ、私の手元にある情報から判断する限り、井上さんはとても聡明な方とお見受けしますので、中途半端に内容をぼかしたような説明ではなく、私どもが何を目的とし、どのような手法をもって目的を実現しようとしているのか、ありのままにお話しいたします。その点、ご承知おきください」
自分よりもずっと年下の来訪者を相手に、まるで対等な立場にある者どうしのような姿勢を崩さずに対応する美雪に対して少なからず好意を抱いた京子は、真剣な面持ちで頷いた。
「私ども医療法人・慈恵会は、様々な疾病に対処するため、最先端の治療手段を確立すべく努めています。それは、たとえば、人工臓器を用いた臓器移植であったり、人為的に合成したホルモン様化合物等といった特殊な薬剤を用いた治療であったりしますが、いずれにしても、これまでの既存の治療方法では対応しきれない症例に対しても著しい効果を示す、まさに次世代の治療手段であると自負しています」
美雪は京子の顔を正面から見据えた。
「そのような次世代型治療手段に関する研究を行う上で中核的な役割を担う、ここ、応用医療技術研究所において、私どもは新たなプロジェクトを立ち上げました。その内容を簡潔に申し上げると、経口薬を用いた内科的処置による人の記憶の人為的な操作ということになります。もう少し詳しく言うなら、脳細胞に薬剤を直接投与する施術に伴う危険を回避するために、より安全性の高い経口投薬によって患者の脳内における特定部位の細胞内に要因化合物を蓄積させるプロセスを通じて患者の記憶を人為的に操作し、それをもって患者の行動様式ならびに人格を最適化するといったところになるでしょうか」
美雪が最初に断ったように、確かに、ちょっと聞いたくらいでは理解が追いつかない単語や理念を織り交ぜての説明に、京子は戸惑うばかりだった。
しかし、美雪が口にした『対象者の記憶を人為的に操作し、そのことをもって対象者の行動様式ならびに人格を最適化する』という言葉を耳にした瞬間、いいしれぬ不安を覚えて
「あの、そんなことが本当にできるんですか? ……それに、なんていうか、記憶をいじらなきゃ治療できないような病気なんてあるんですか? 素人の私が説明の途中で口をはさんで申し訳ないんですけど、どうしても気になったものだから……」
と、おそるおそる尋ねてしまう。
「確かに、『記憶を人為的に操作する』という表現には穏やかならざる響きがありますね。しかし、身近なところで言えば、認知症という病気について井上さんはどのように考えられますか? 自分の記憶が日々失われてゆく恐怖におののく患者本人に対しても、患者を介護する周囲の人間に対しても肉体的かつ精神的に多大な負担をかける忌まわしい病気。認知症を予防する手段を見出すための研究は急を要します。そして同時に、既に認知症を発症してしまっている患者を救うための研究、つまり、失われた記憶を取り戻す手段を得るための研究もまた必要不可欠です。私どもは、そういった、記憶を取り戻すことも含めて、記憶の人為的な操作と称しています」
美雪は冷静な口調で答え、穏やかな表情を崩さぬまま続けて言う。
「加えて申し上げるなら、私どもの新しいプロジェクトが目指すところは、認知症の症状を緩和することにとどまりません。私どもが過去に迎え入れ、今はこの研究所に付属する病院の居住区画で心穏やかに生活している二人の患者の例を紹介しておきましょう。一人目の患者の名前は瀬田元哉。過去の震災で、彼は家族の悲惨な最期に立ち会いました。押し潰された寝室で、父親と母親と幼い妹がコンクリート片の下敷きになってしまい、そこに隣家からの延焼による火の手が迫ってきたということです。彼は、家族の体にのしかかるコンクリート片を自分の力では動かすことができず、結果として家族が自分の目の前で焼死してしまったことをひどく悔やみ、原因が自分にあると彼自身を責め続けました。そして、そうしているうちに、或る種の心理的な転化が発現しました。自身の無力を責め続ける彼の胸中において、自分というものに対する自己意識がきわめて不安定になってしまう中、助けることができなかった幼い妹の顔が思い出され、それが、彼の不安定な心の中で圧倒的な存在感をもって重みを増した結果、無力な自分のことを幼い妹とすり替えることで彼の精神は自我の崩壊を防ごうとするに至りました。つまり、自分のことを幼い妹だと思い込むことで、幼く非力な自分が家族を助け出せなかったのも仕方なかったのだと自分自身に対してエクスキューズしようとする心の動きがあったということです」
元哉という患者の身に起きた悲劇に衝撃を受け、まばたきをすることさえ忘れてしまったかのように京子がこちらを凝視して説明に聞き入っていることを確認して、美雪は言葉を続けた。
「私どもは、彼の望みを尊重することにしました。彼は、自分のことを地震で亡くなった妹だと思い込んでいました。正確に言うと、思い込もうとしていました。私どもは、それを手助けすることにしました。彼に対して形成外科手術とホルモン操作を実施することによって。手術の内容は、まず、手足の腱の切断。両手足の腱にメスを入れるものの、完全に歩けなくしてしまうわけではなく、幼児のようなよちよち歩きしかできない程度に四肢を弱体化する処置を行いました。その次に、声帯の整形。形そのものを変えるのではなく、声帯を形成する筋肉の一部を削ぎ取って薄くし、彼の声を幼い女の子のような甲高い声に変化させるための処置です。更に、頬と額をふっくらした感じにする簡単な整形手術を施して、もともと童顔だった彼の顔を幼い女の子の顔につくり変えました。そして最後に行った施術が、ペニスの短小化です。当初はペニスを切除して膣を形成する性転換手術を施すことも検討したのですが、いくら自分のことを幼い妹だと思い込んでいる(思い込もうとしている)彼であっても、いざ麻酔が切れて意識を取り戻した時にどのような反応をしめすか予想できなかったため、とりあえずは、海綿体の除去と外皮の切除によるペニスの短小化だけにとどめておきました」
そこまで説明して美雪が口を閉ざすと、応接室の空気がしんと静まり返る。
京子は美雪の説明に対してどう反応していいかわからず、大きく目を見開いて身を固くするばかりだった。
大きく見開いた京子の目をじっと覗き込んで、美雪は説明を続けた。
「もう一人は、須藤雅美という女性です。瀬田元哉とは異なる学校に通っていましたが、彼女も当時は高校生で、瀬田元哉と同様、建材の下敷きになった家族が絶命する場に立ち合っていました。しかし彼女の心の動きは、瀬田元哉の場合とは正反対でした。瀬田元哉のように現実に背を向けることはせず、むしろ現実と積極的に相対することを選んだと表現すればいいでしょうか、自らの無力を嘆くのではなく、自らが力をつけることを選んだのです。若く無力な自分を一日も早く成長させ、何事にも動じない大人になること。それが彼女の切なる願いになりました。けれど、彼女が選んだ途にも罠がひそんでいました。一日も早く一刻も早く大人になりたいと願う気持ちがあまりにも切実になりすぎ、それが原因になって精神に変調をきたしてしまったのです。願いと実際の成長の速度との間にはどうしても埋められない溝ができます。願ったからといってすぐにそうなれるわけがないのに、まるでそんな当たり前のことさえ忘れてしまうほどに強く激しい願いを彼女は抱いてしまったのでしょうね、願いとは裏腹にまるで成長しない自分の身体にひどい苛立ちを覚えて、自分の肉体を自らの手で傷つけるような行為を繰り返すように彼女はなってしまい、遂には、瀬田元哉と同じ慈恵会系列の病院の精神科病棟に収容され、自傷行為を繰り返さないようにと自由を奪われた生活を送ることを余儀なくされました。その後、この研究所の付属病院に彼女を迎え入れた私は、彼女を辛抱強く説得しました。あなたの願いは必ず私がかなえてあげる。だからもう自分の肉体を傷つけるようなことはしないでちょうだい。私は彼女に向かって何度も何度も語りかけ、訴えかけました。あなたの望み通りの大人の体にしてあげる。それに、もしもあなたが望むなら、地震で亡くなった妹さんのような、あなたがいなければ何もできない赤ちゃんも用意してあげる。妹さんの代わりの赤ちゃんの世話をやいていれば、自分が大人になったことを実感できる筈。だから、自分の体をもう二度と傷つけないでちょうだい。繰り返し繰り返しそう説得しながら、私は彼女が気づかないうちに或る種の処置を施しました。その処置というのは、彼女に定期的に服用させる精神安定剤や毎日の食事に特殊な合成ホルモン様化合物を混入して投与することでした。その合成ホルモン様化合物は女性の乳腺を刺激してその活動を高める効果を有しており、動物実験によって、マウスなどの小型哺乳類のみならず大型の霊長類にいたるまで例外なく顕著な効果をしめすことを事前に確認していました。その合成ホルモン様化合物を投与された雌は、出産経験のない個体であっても、投与から二週間程度で乳房が充分に成育し、三週目に入ると、乳首から母乳の分泌されるようになります。また、母乳の成分を慎重に分析した結果においても、ごく普通の妊娠出産期に分泌する母乳の成分と全く違わないとの結論を得ました。この合成ホルモン様化合物の投与によって彼女の乳房は短時間のうちに発育し、動物実験の結果そのまま、乳首の先から母乳を溢れ出させるまでになりました。加えて言うと、私は彼女に対して、その合成ホルモン様化合物だけでなく、同時に、筋肉増強効果を有する治験段階の薬剤も投与していました。二つの薬剤の効果によって彼女は短期間の内に、素晴らしく成育した体?と、出産経験がないにもかかわらず母乳を溢れ出させる豊かな乳房の持ち主に変貌しました」
美雪は一気にそこまで話してから、反応を窺うべく京子の顔をもういちど覗き込んだ。
明らかな驚愕の表情と共になにやら切なげな表情が入り交じって京子の顔に浮かんでいるのを美雪は見逃さなかった。
「二人は今、研究所付属病院の居住区画において、若い母親と幼い娘として心穏やかに暮らしています。いつか機会があれば井上さんを居住区画に案内して実際の生活ぶりをご覧いただいてもよろしいのですが、それはそれは仲睦まじい母娘ぶりですよ。幼い娘に三時間おきに授乳し、こまめにおむつを取り替えてやることを決して厭わぬ優しく若い母親と、母親に甘えて一時も離れようとせず、薬剤の効能によって優れた筋力を手に入れた母親の胸に軽々と抱かれて豊かな乳房にむしゃぶりつき、母乳を貪りながらおむつを汚してしまうのが常の幼い娘として」
淡々とした口調でそう言う美雪の言葉が終わって、応接室に再びの静寂が訪れた。
京子の顔に浮かぶ切なげな表情がますます鮮明になる。
静寂を破ったのは、やはり美雪だった。
「誤解しないでいただきたいのですが、そうなるように私どもが強引に仕向けたのではありません。二人の望みをかなえるために、私どもはささやかな手助けをしたに過ぎません。私どもは、二人の心の持ちようにふさわしい身体を二人に贈呈したに過ぎないのです。人は結局、そうありたいと願ったものにしかなれない。――井上さんは、坂本メグミさんの母親でありたいと願っておいでですよね? メグミさんの母親になりたいと常々望んでいらっしゃいますよね?」
美雪はテーブルの上で手を組み、少し間を開けて、決めつけるような口調で問いかけた。
「ど、どうして、そのことを……!?」
突然の問いかけに、京子は言葉を失ってしまう。
しかし、その反応は、美雪の問いかけを決して否定するものではなく、美雪がその事実を知っていることに対する驚愕の表われだった。
「私どもに情報を提供してくれる多くの人たちが随所にいます。河村宏子という看護師をご存じでしょう?」
美雪はすっと目を細くして言った。
「え? ええ、はい……」
思ってもみなかった人物の名前を告げられて、京子は言葉に詰まった。
かつて自分が入院していた時に世話になった看護師で、後に聞いたところによると美和と共謀して、男子高校生である恵を幼い少女めいた存在に変貌させた人物だ。
その名前をこんな所で耳にするなんて。
「彼女も協力者で、私どもの研究の対象者たり得る人物や、私たちが研究している治療手段以外では完治が難しい病状を抱える患者が身近に現れた際、その情報を速やかに私どものもとへ送ってくれる人たちの一人です。私どもは彼女の協力を得て、坂本メグミさん――坂本恵くんの身辺調査を慎重に実施し、彼を新たな研究の被験者とする決定をくだしました。それに伴って、坂本恵くんに関係する人々についても、極めて綿密な身辺調査をさせていただきました。もちろん、井上さんについても。ですから、坂本恵くんと井上さんの関係性等について私たちが詳細を把握しているのも、おかしなことではありません。いえ、その情報を外部に流出させることは決していたしませんので、その点はご心配に及びません」
美和は目を細めて穏やかな笑みを浮かべたまま言った。
「……それで、そこまで詳しく私たちのことを知った上で、私たちをどうしょうと……?」
京子は、どうしようもない不安を覚えつつ、そう言うのが精一杯だった。
「どうか、そんなに心配そうな顔をするのはおやめください。ついさきほど申し上げましたように、私どもは、井上さんが坂本恵くん――ああ、いいえ、この場合は坂本メグミさんとお呼びするのが適切でしょうか――メグミさんの母親になれるよう微力ながらお手伝いして差し上げたいだけです。そしてまた、坂本メグミさんが井上さんの可愛らしいお嬢ちゃまになれるよう助力して差し上げたいだけです。そう、瀬田元哉と須藤雅美のような仲睦まじい母娘にお二人がなれるよう尽力して差し上げたいだけです。他意は一切ありません」
京子の声が不安げに震えているのがおかしいのか、くすっと笑って美雪は言った。
「ただ、できることなら、その過程で私たちの研究にご協力いただきたく、その点をお願い申し上げる次第です。本日はそのお願いをいたしたく、お手数ながらこちらへおこしいただきました」
「研究に協力? 私が……?」
「ええ、その通りです。ちなみに、新たに立ち上げたプロジェクトが目的とする研究の内容は――」
元哉と雅美という貴重なサンプルのおかげで、心の在り方に適合するように肉体を変化させた場合に起こり得る心身の様々な変化に関する研究を進めることができた。つまり、自分を三歳の幼女だと思い込んでいる男子高校生の身体を手術によって三歳の幼女に近い容姿に変貌させると同時に身体能力も三歳の女児なみに抑制することで肉体と精神との間の齟齬を解消し、また、一刻も早く大人になりたいと願い続けていた女子高生に対しても望み通り大人の身体を与えて肉体と精神との間の齟齬を解消してやった上で、二人がその後、どのように精神と肉体との調和を図るのかを丹念に観察することができたというわけだ。
そうして得られた知見を元に、美雪は新たな研究に着手することにした。その新たな研究とは、精神と肉体の齟齬を解消する処置を受けた患者において、ゆっくり時間をかけて精神と肉体の調和がなされるプロセスに積極的に関与し、調和に要する時間を短縮することを目的とするものだった。そして、記憶の人為的な操作こそがそのための有効な手法になり得ると美雪は判断し、その手法を確立することを目的として、新たなプロジェクトを立ち上げたのだった。
「――といったところになります。実はこの研究を進めるに当たっては坂本メグミさんの心理状態を詳細に把握することが必要不可欠なのですが、そうするためには、坂本さんの保護者的な立場にいらっしゃる井上さんと梶田さんにご協力いただくことも必要と判断するに至りました。ちなみに、お二人の内、梶田さんには河村宏子を通じて先に連絡を済ませ、既にご了承いただいています。お二人揃ってご協力いただける旨の確約をいただいた後に当事者である坂本さんにお願いをする予定にしていますが、もしもここで井上さんの協力が得られないとなると、坂本さんに協力をお願いすることもできないまま研究が頓挫してしまいます。そのような残念な結果にならないよう前向きな返答をいただきたいというのが私どもの正直なところです」
美雪はそう説明した後、京子の胸の内を推し量るかのように押し黙り、少し間を置いて言葉を続けた。、
「それと。申し遅れましたが、ご協力いただける場合には、心ばかりのお礼をご用意いたします。たとえば坂本メグミさんには、生家に対する少なからぬ額の金銭的援助ならびに兄弟姉妹に対する就学の機会の保証を申し出る予定です。そして井上さんには……」
「本当ですか!? メグミちゃんのお家への援助と、メグミちゃんの兄弟姉妹が進学できるよう約束してくれるというのは、本当なんですね!?」
美雪の言葉を途中で遮って、京子が身を乗り出した。
「はい、医療法人・慈恵会の理事長の名においてそれは確約します」
美雪は静かに答えた。
それを聞いた京子はますますテーブルの上に身を乗り出して
「だったら、協力します。私が協力することでメグミちゃんの家族がみんな大丈夫になるんだったら、私、喜んで協力します」
と勢い込む。
「そうですか。お優しいんですね、井上さんは。ご自身のことよりもメグミさんのご家族への配慮を優先されるなんて、本当にメグミさんのことを大切に思っておいでなんですね。確かに、そんな井上さんだからこそ、メグミさんはあなたを慕って、あなたに頼りきりで、あなたに全てを委ねたいと思ったのでしょうね」
美雪は胸の中で満足そうにほくそ笑んだ。美雪が先ず恵への謝礼のことを話したのは計算尽くのことだった。恵が充分な謝礼を受け取れるとわかれば京子はプロジェクトへの協力を受諾するに違いない。そう見越してのことだった。
「いえ、あの、優しいだなんて、ただ、私、メグミちゃんのことがことが大好きで、だから、恵くんがメグミちゃんになっちゃって、その後、メグミちゃんの家族がどうなっちゃうのか心配なだけで、その……」
美雪の真意に気づくことなく、京子は照れくさそうにするばかり。ちょっと見には大人びている京子も、中身は中学一年生の少女でしかない。
「よろしいのですよ、そんなに照れたりなさらなくても。井上さんのような年代の方は、好きなものは好きというふうに真っ直ぐにしておられるのがお似合いなんですから。ただ、余計なことかもしれませんが、若い方は時として謝礼を受け取るという行為を何やら打算的な行為としてとらえがちですが、本当のところは、謝礼というものは、それを進呈する者の気持ちの素直な発露であることが大半なのですから、頑なに固辞する必要はありませんよと、敢えて申し上げます。いかがですか、私どもが井上さんのためにご用意した謝礼がどんなものなのか、せっかくですから、聞いてごらんになりませんか」
美雪は少しばかり勿体ぶった口調で、京子が自分への謝礼に興味をいだくよう仕向けた。
既にプロジェクトへの協力を受諾している京子だが、この謝礼の中身を知れば、その決心をますます固くするに違いない。
「それじゃ、そこまで言っていただけるのなら、これ以上の遠慮は却って失礼でしょうから、お願いします」
美雪の勧めに、京子は面映ゆそうに頷いた。
「承知しました。では、申し上げます。井上さんのためにご用意したのは、井上さんにメグミさんの本当の母親になっていただくための手段を当方が滞りなく講じることと、井上さんとメグミさんが一生にわたって二人で暮らすに必要な住居ならびに金銭を提供することです。いかがですか、これで」
「私とメグミちゃんが二人で暮らすためのお家……? それに、お金まで!? でも、そんなの、すごい金額になっちゃうんじゃ……」
思ってもみなかった飛びきりの条件を呈示された京子は、喜びに満ちた表情というよりも、狐につままれたようなきょとんとした面持ちになってしまう。
「井上さんが気になさる必要はありません。私どもは、医療の未来を切り拓くための研究を是非とも行いたい。研究のために必要だからこそ、井上さんに協力をお願いする。そんなふうにして研究が成就した時に私どもが手に入れることができるリターンの価値を考えれば、井上さんへは幾らお礼を差し上げても足りないくらいです。ですから、気になさる必要はまるでありません」
「そう言っていただけるなら、お言葉に甘えます。お言葉に甘えて、メグミちゃんと二人で楽しく暮らせる日が少しでも早く来るようお祈りしながら、研究に協力します。……ただ、でも、『井上さんにメグミさんの本当の母親になっていただくための手段を当方が滞りなく講じること』ともおっしゃいましたよね? それがどういう意味なのかまるでわからなくて、本当を言うと少し不安もあるんです。そのことについてわかりやすく話していただくことはできないでしょうか?」
京子は返答の冒頭では顔を輝かせたが、後半の言葉をを口にする時は首をひねりそうにしていた。
「そうですね、確かにその部分は少しばかり曖昧な表現になってしまいましたね。関係者どうしの間では短い文節で少しでも多くの情報を伝え合うことが習慣になっているものですから、つい、そのような話し方をしてしまいました。では、もう少し具体的に申し上げることにしましょう。実は、その部分の文節には二つの意味が含まれています。一つ目の意味は、血こそ繋がっていないものの、お二人を親子としてきちんと戸籍に記載するための手続きを私ども行って差し上げるという意味です。お二人を各々の生家の戸籍から解放して、母娘として新たな戸籍に移すための手続きを私どもが滞りなく進めます。もちろん、お二人がおいやでなければという前提のもとにですが」
「そ、そんなの、いやって言うわけありません。私がいやって言うわけ絶対にないし、メグミちゃんだって喜んでくれるに決まっています。……でも、そんなことができるんですか? できるんだったらとっても嬉しいけど、すごく難しいんじゃないんですか?」
京子は更衣室で抱きしめた恵の体の感触を思い出しながら声を弾ませつつも、少し懐疑的な様子で言った。
「確かに簡単なことではありません。けれど、私どもには確かな伝手があります。私の友人に、遊鳥清廉学園という学校法人の理事長がいるのですが、その友人と私が協力した結果、文部科学省と厚生労働省に少なからず顔が利く人脈を築くことができました。その人脈の中には、法務省や総務省に強い繋がりをお持ちの方も何人かいらっしゃいます。そういった方々にお願いすれば、到底無理だと思える事柄でも難なく実現してしまえることもあるんですよ。但し、そういった方々に力添えいただいたとしても、お二人を正式に親子として記載するのは、井上さんが成人年齢に達するまで待っていただく必要があります。それまでの間は、お二人が従姉妹どうしの間柄であるような架空の戸籍を作成することにいたします。その戸籍で住民票を取得することも可能なように手配しますのでご心配なく」
美雪は、悪戯っぽく笑ってみせた。
それから、わざとのような気がかりな表情で京子に
「それよりも、私どもとしては、井上さんのご両親がその点についてどう考えられるかというところを危惧しています。井上さんとしては、ご両親がどのように反応なさるとお思いですか?」
と問いかける。
「そのことでしたら、ご心配いただく必要はありません。私は両親に祝福されて生まれた子供ではありませんでした。むしろ、仕事の邪魔になるといって疎まれて育ちました。住み込みの家政婦さんがいなかったらどうなっていたんだろうと今も思うことがあります。だから、そんなこと心配していただかなくてもいいんです。もしも両親の承諾が必要だとしても、いとも簡単に書類にサインしてくれますよ、あの二人なら」
京子は、目の前に美雪がいるのも忘れてしまったかのように毒づいた。
そしてその瞬間、自分が恵に惹かれた理由に今更ながら思い至る。
京子と恵。まるで異なる事情で、けれど共に両親の愛情を受けることなく育った二人。初めて出会ったあの時、京子は、恵の瞳に自分とまるで同じ限りない寂寥の色が浮かんでいることに気がついたのではなかったか。そのことに気がついた途端、自分でも可笑しく思えるほど京子は恵をいとおしく感じられて仕方なかったのではなかったか。あの時以来、どんなことがあっても自分が恵を守ってやると心に決めたのではなかったか。
恵がその瞳にあの寂寥の色を浮かべずにすむようになるのなら、どんなことも厭わない。自身に向かって固くそう誓ったのではなかったか。
「お願いします。どんな協力でもします。だから、私とメグミちゃんを親子にしてください。私とメグミちゃんが二人きり、誰にも邪魔されずに親子水入らずで暮らせるようにしてください。どんなことでも協力します。だから、お願いです」
興奮のあまり京子は思わず美雪の顔を睨みつけるようして、これ以上はないくらい真剣な声で懇願した。
「承知しました。井上さんの希望は必ず実現します」
自分が事前に予想していた通りの反応を京子がしめしたことに満足しつつも、胸の内を気取られぬよう用心しながら美雪はわざと大きく頷いてみせる。
「さて、そうなると、『井上さんにメグミさんの本当の母親になっていただくための手段を当方が滞りなく講じること』の二つ目の意味がますます重要になってきますね。実は私どもは、須藤雅美に投与したのと同様の合成ホルモン様化合物を井上さんに対しても投与して、井上さんが自分の母乳でメグミさんに授乳できるようになるためのお手伝いしたいと考えています。それが、二つ目の意味です。ええ、そうです。ご自身の母乳をメグミさんに飲ませることで井上さんはメグミさんの本当の母親になることができる。そのためのお手伝いを私どもが実行するという意味です。――須藤雅美という先例もあって、合成ホルモン様化合物が井上さんの身体に不調を惹き起こすことはないと断言できます。しかし、まだ中学生の身でそのようなことになると過重な精神的負担に耐えられなくなるといった事態も予見されます。それを承知の上でお決めください。そのような処置を講じてもよろしいですか?」
京子が首を縦に振ることはわかっている。
それ以上はないくらい大きく首を縦に振ることはわかりきっている。
それでも美雪は、わざと気遣わしげな様子で尋ねた。
「精神的な負担ですか? そんなの、私が気にするわけありません。私とメグミちゃんの仲、もうすっかり知られちゃっているみたいだから隠さずに話しますけど、私、メグミちゃんが面倒をみてもらっているマンションに行くといつも、メグミちゃんにおっぱいをあげているんです。あ、いいえ、本当はおっぱいなんて出ませんよ。出ないから真似っこだけなんですけど、メグミちゃんに私のおっぱいを吸ってもらっているんです。吸ってもらっていると、なんだか体中が火照ってきちゃって、とっても気持ちよくなっちゃって、あの、恥ずかしいんですけど、ちょっぴりエッチな気分になっちゃって、それで、とにかく、気持ちが軽くなって、安らぐんです。だから、もしも精神的な負担とかいうのを感じたとしても、メグミちゃんにおっぱいをあげたら、そんなのすぐに吹き飛んじゃうに決まっています。だから、大丈夫です。心配することなんて、ちっともありません。だから、お願いです。私の体からおっぱいが出るようにしてください。私のおっぱいでメグミちゃんがお腹いっぱいになるようにしてください。私のおっぱいでべとべとになっちゃったメグミちゃんの口のまわりをよだれかけで綺麗に拭いてあげたいんです。だから、お願いです。お願いだから、おっぱいが出るようにしてください」
初めて訪れた研究所の雰囲気に気圧されて飲み物に口をつけることさえできなかったのが嘘のように、京子は口早に訴えかけた。
「承知しました。但し、井上さんの血液を採取して合成ホルモン様化合物との相性を確認したり、補助臓器を付与したりする事前検査および事前施術を実施する必要があります。そういった措置には相応の時間がかかりますが、もしも井上さんに同意していただいて今すぐに検査と施術を始めることができるなら、明日のお昼過ぎにはそういった措置を全て終えることができます。いかがでしょう、差し支えなければ、これからすぐに処置室へご案内しましょうか?」
美雪はわざと事務的な口調で言い、京子が目を期待に目を輝かせて何度も頷くのを確認してから、さりげなく付け加えて言った。
「なお、井上さんに投与する合成ホルモン様化合物の成分は、かつて須藤雅美に投与した化合物とは微妙に異なります。それと、須藤雅美に投与したものと同じ筋肉増強効果を有する薬剤に加え、もう一種類、井上さんの身体が様々なホルモンを分泌する機能の一部に干渉する作用を有する薬剤も投与いたします。その点、よろしいですか?」
ここに至って京子が拒むわけがない。いや、そもそも、自分の乳房から溢れ出る母乳を恵が貪り飲む様子を夢想することに夢中な京子の耳にその言葉が届いているどうかさえ定かではなかった。
それから時が流れ、京子が応用医療技術研究所を初めて訪れた日から三週目にあたる土曜日の昼過ぎ。
京子にしてみれば、(美雪に指示されるまま三週間前から服用している化合物や薬剤の効果を確認することを含む定期的な検査のため)週末ごとに通っていて、今回で四回目の来訪になるから研究所の雰囲気にもすっかり慣れ、ゆったりした気分で応接室のソファに腰かけることもできるようになっていた。しかし、京子に連れられて初めて訪れた恵は、かつての京子と同様に研究所独特の雰囲気に気圧されて、京子にぴったり体を押しつけてソファに座り、京子の手を握って離さず、おどおどした様子で応接室の内部をきょろきょろ見回すのをやめられずにいる。
しばらくしてドアが開き、ビジネススーツ姿の女性が応接室に姿を現した。
女性の顔を見るなり京子は
「あ、美和ママ、お久しぶり。今日の面談には美和ママも参加することを笹野先生から前もって教えてもらっていたから、ずっと楽しみに待っていたのよ」
と声を弾ませ、けれど年齢に似合わぬ落ち着いた物腰でソファから立ち上がり、顔をほこぼらせた。
京子から一瞬遅れ、それまでのおどおどした様子から一転、恵もぱっとソファから立ち上がって
「美和ママ! ずっと会いたかったんだよ!」
と嬉しそうに大声をあげ、たっと駆け出して女性に抱きついた。
そう、二人が名前を呼んだ通り、応接室に入ってきた女性は梶田美和だった。
実は美和は、恵と京子の処分が始まったその日にK女子中学校に退職届を提出し、恵を幸子に預けてマンションからも姿を消していた。そのため、恵と京子が美和と顔を会わせるは、およそ三週間ぶりということになる。
「私たち、随分心配したのよ。今まで何をしていたの!?」
恵に続いて京子も美和の側に歩み寄り、気遣わしげに声をかけた。
「ごめんなさいね、心配かけて。私がこれまでどうしていたかについては、この後、笹野先生から話してもらえるから楽しみに待っていて」
美和は意味ありげに微笑んでみせると、視線を恵の顔に移し、恵が着ている丈の短いワンピースの裾をさっと捲り上げてお尻をぽんと叩き、
「しばらく会わないうちにお転婆になっちゃったわね、メグミちゃんたら。でも、そんなに勢いよく走ったら、可愛いお洋服のスカートからおむつが見えちゃうわよ」
と言って、悪戯っぽい笑みを浮かべた。
「美和ママのエッチ!」
恵は頬をぱっと赤らめて美和の体から手を離し、慌ててスカートの裾を引っ張った。
本当は男子高校生の恵なのに、そうしていると女の子にしか見えない。それも、本来の年齢に見合う女子高生ではとてもなく、女子中学生というのも少し心許ない、小学校三〜四年生くらいの少女といったところだ。
「美和ママを叱ってよ、京子ママ。京子ママは、可愛い娘が美和ママにエッチなことされても平気なの!?」
そそくさとスカートの乱れを整えた恵は足早に美和のもとを離れ、今度は京子の体にしがみついて甘えるように言った。
(本当にすっかり女の子らしくなっちゃったわね、恵くん。それに、ますます京子ちゃんに懐いて甘えんぼうになっちゃって)
美和は、しっかり抱き合って京子の顔を振り仰ぎ見る恵と、恵の顔をいかにもいとおしげに見おろす京子の仲睦まじい様子を眺めながら胸の中で満足そうに呟いた。
が、ふと気づいたことがあって
「ひょっとして京子ちゃん、背が伸びた?」
と、不思議そうな面持ちで京子に問いかける。
「ええ、この三週間ほどで自分でもびっくりするくらい背が伸びたんです。小学校を卒業する半年くらい前に急に伸び出して中学校に入る頃には伸びなくなったから、それで第二次成長期は終わったんだろうなと思っていたのに、それが最近になってまた伸び出して。たぶん、笹野先生からいただいて毎日服用しているお薬が関係していると思うんだけど、ぐんぐん伸びるものだから、成長痛というのかな、体の節々が痛くて困っているんです」
恵とは逆の意味でとてものこと中学一年生の少女とは思えない落ち着いた様子で静かに京子は答えた。
二人の様子を眺めていて美和が気づいたのは、そのことだった。K女子中学校に入学した時点で京子は恵よりも背が高かったが、その差は十センチもなかった筈だ。それが今は、恵が京子の顔を見るには、首をうしろにそらせて振り仰がなければならないほどの身長差になっている。
そのことに気がつき、驚いて美和は訊いてみたのだが、「笹野先生からいただいて毎日服用しているお薬が関係していると思う」という京子の説明を聞いて、すぐに納得した。第二次成長期を過ぎた筈の京子の背が再び伸びだした、それも成長痛を伴うほど急激に伸びだしたのは、美雪に指示されて京子が合成ホルモン様化合物と共に毎日欠かさず服用している薬剤の筋肉増強効果に伴う副次反応によるものに違いない。そう思ってよく見てみれば、京子の体は身長だけでなく、豊かでたわわな乳房であろうことが容易に想像できる胸元と、きゅっとくびれた腰まわり、それに、張りのあるお尻の様子が着衣の上からもはっきり見て取れるし、全体的に(女の子というよりも、女性と表現するのがふさわしい)やや丸みを帯びてふくよかな印象と、決してぽっちゃりという感じではない、筋肉質で引き締まった印象とを併せ持つ、見事なまでに恵まれた体つきに変貌していた。
「でも、こんなに素敵な体になれたんだから、少しくらいのことは我慢しなきゃね。だって、こんなに立派な、こんなに大人びた、そう、こんなにもお母さんらしい体になれたんだから」
美和は京子の体つきを褒めそやした後、
「着ているスーツのせいもあるけど、どこの若奥様かと思っちゃうほど素敵よ、京子ちゃん。あ、いいえ、『京子ちゃん』なんて呼ぶのが失礼なほどのレディだわ。これからは『京子さん』と呼ばなきゃね」
と囃すように言って、優しく笑った。
美和の言うことは決して大袈裟ではなかった。ピンクベージュのジャケットとワンピースを組み合わせたセレモニースーツを着て、見る角度によって微妙に色を変える小粒の真珠を一粒だけアクセントに使った細めのチェーンネックレスを着けた京子を見て、実際の年齢を言い当てることは不可能だろう。
それに対して、ベビーピンクの丈の短いワンピースの上にオフホワイトのボレロを着て、ワンピースと同じ色合いの小振りのコサージュを胸に付けた恵。こちらも実際の年齢を言い当てることは不可能だ。
そんな二人を見ていると、念願だった私立のお嬢様小学校の入学式に臨む若い母親と新入生の娘が抱き合って記念撮影をしている最中の光景かと思えてくるほどだ。それがまさか、幼い娘の方が本当は十七歳の男子高校生で、凜とした母親の方が中学一年生の少女だと誰が想像できるだろうか。
「本当に二人ともよくお似合いだこと。まさか二人が中学一年生の同級生だなんて、誰も思わないでしょうね。ところで、誰の見立てなのかしら?」
本当は男子高校生と女子中学生の組み合わせだなんて誰も思わないでしょうねと胸の中でくすくす笑いながら、感心しきりに美和は尋ねた。
「見たてというか、実はこれ、幸子ママのお手製なの。初めてここへ来た時は何も考えずに普段着で来てしまったんだけど、来てみたらとても立派な建物だし、それに、笹野先生が実はすごくご高名なお医者様だということを後で知って、今度また来る時はそれなりの格好をしなきゃと思ったのはいいけど、どんな服装がふさわしいのかわからなくて幸子ママに相談したら、つくってあげようかって言ってもらえて。それに、事前検査を受けた後で笹野先生といろいろ話して、近いうちに私とメグミ、二人揃って最終面談に来てもらうからそのつもりでいなさいと言われたことも話したら、じゃ頑張って二人分つくらなきいけないわねって言ってもらえて。それで、こんなに素敵な洋服をつくってもらえたんです」
やはり静かな口調で答える京子。けれど美和に褒めてもらえたのがよほど嬉しいのだろう、頬に朱が差していた。
その後、京子は少し間を置いて僅かに首をかしげ、
「ただ、私としては何かお礼をしたくてたまらないのに、幸子ママったら、『里美が大きくなって小学校に入る年になったら自分の分と里美の分を手作りするつもりでいたんだけど、その練習になったから私の方も助かっているのよ。だから気にしないで。それよりも、なかなかおむつ離れできない手のかかる娘を持つママ友どうし、これからも何かあったら遠慮しないで相談してちょうだい』って言うばかりで、なかなかお礼ができなくてちょっと困っているんです」
と思案げな様子で続けて言った。
それに対して美和は
「あらあら、あの幸子ママがそんな殊勝なこと言っちゃうんだ。ちょっと意外かも」
と、悪戯っぽく笑ってみせる。
(あの幸子さんがそんなことを言うだなんてね。私と二人で恵くんを小っちゃな女の子扱いして面白がって興奮して、その後は決まって私の体を求めてきたあの幸子さんが、そんな殊勝なことをね)
美和は胸の中でさも可笑しそうにくすっと笑った。
そして、これまでの一連の出来事を何気なく思い出し、やはり心の中で
(そういえば、幸子さんだけじゃないわね。宏子にしても、京子ちゃんにしても、この私にしても、恵くんと一緒にいる時間が長くなれば長くなるほど、恵くんの世話をやきたくて仕方なくなっている。華奢で体の小さな恵くんに女の子の格好を強要して恥ずかしそうに体を震わせる様子を堪能して、飽きたら捨てちゃうつもりだった私が、いろんな事情があってのこととはいえ、恵くんの将来のことを案じて、こうしてこんな所にまで出向いて来るくらいになっちゃうなんて)
と呟いて、ふっと溜息をつく。
そこに恵が再び近づいて
「幸子ママにつくってもらったお洋服、可愛いでしょ? メグミに似合ってるよって京子ママが褒めてくれるから、すっごく嬉しいんだ」
と声を弾ませ、ワンピースの裾を両手で軽くつまんで左右に広げるような仕草をしてみせた。

「うん、とってもお似合いよ。そうしていると、さっきのお転婆ぶりが嘘みたいにおしとやかで、このまま、有名な附属小学校の入学式に出てもおかしくないくらいだわ」
本当に、いつのまにこんなに女の子らしくなってしまったんだろう。男子高校生だった頃の面影なんてちっとも見当たらないじゃないの。たった三週間ほど会わなかっただけなのに、その間の恵の変貌ぶりに驚きというよりも戸惑いを覚えて、美和は知らず知らずのうちに恵の顔をじっとみつめていた。
と、恵の瞳が不規則に揺れ動いていることに気がつく。
自分自身なり自分の着衣なりを褒めてほしいのなら、相手の顔に視線を向けたまま、(直接的な表現ではないにせよ)褒めてほしいという意思表示をするのが普通だ。幼児が玩具の片付けを終えて親の機嫌を窺う際の様子がその典型だろう、いわゆる「どや顔」で、ほら、きちんとできたよと自慢げに親の顔を見据え、親が大げさに褒めてくれるのを心待ちにするものだ。なのに恵は、口でこそ「幸子ママにつくってもらったお洋服、可愛いでしょ?」と自慢げにアピールするものの、その瞳は、おずおずと美和の顔を見たかと思うと次の瞬間にはあらぬ方に視線を向け、よそを向いた筈の視線が再びおそるおそる美和の顔に戻ってくるといった具合に、どこに目を向ければいいのかわからないかのように不安げにきょときょと動き、細かく震え続けていた。
それが何を意味するのか、スクールカウンセラーを兼ねた養護教諭として多くの生徒の様々な心の問題と向き合ってきた美和が理解するのに、さほど時間はかからなかった。
(この子は、女の子らしくなったんじゃない。精一杯、女の子らしく見えるように振る舞っているんだ。本当は男の子だということを誰にも気づかれまいとして、自分が心の中にイメージする女の子の姿を真似て。女の子を演じて、もしも実は男の子だと知られた時には「どう、僕の演技、なかなかのものでしょ? ちょっとした悪戯だけど、僕の女装姿、なかなか似合ってるでしょ? 今度はもっと上手に演技するから、その時を楽しみにしていてよ」とでも言っておどけてみせるために。そんなふうに、女の子の格好をしているのをちょっとした冗談として済ませることで、本当のことを気取られぬように)
だからこそ。演技だからこそ、見た目は本当の女の子よりも女の子らしくなってしまう。男の子としての要素を微塵も見せまいとして、おそらく誰も気づくことのないであろう僅かな男の子の要素をも覆い隠そうとするあまり、過剰なほどに女の子の要素を振りまいて。たとえ一瞬でも疑いの眼差しを向けられまいとして、大げさなくらいに女の子らしく振る舞って。ひょっとしたら誰かに本当のことを知られてしまっているかもしれないという不安で胸が締めつけられそうになるのを必死で我慢しようとするあまり、必要以上に可愛らしく幼い少女を演じて。おどおどした様子をみせて周りから怪しまれまいとするあまり、快活で元気いっぱいの少女を真似て。
K女子中学校の他の生徒の前で常に女の子のふりをしているのが習い性になって、つい美和たちの前でもそうしてしまうのだろうう。
以前の美和なら、そんな恵を妖しい欲望の餌食にしていただろう。いやらしい言葉で執拗に嬲り、ぞっとするような笑い声を漏らしながら、ねっとり絡みつく不埒な想いで搦め取っていたことだろう。
けれど、恵の胸の内を見透かし、恵の心の奥底から聞こえる忍び泣く声を聴き取ってしまった美和には、恵の振る舞いが痛々しく思えてならなかった。努めて明るく女の子を演じようとする恵の姿が哀れでならなかった。
「あのね、メグミちゃん……」
何かを恵に言おうとして、けれど何も言えないまま押し黙ってしまう美和。
|